(1)旅行業の状況
旅行業者等は、業務の範囲により、第一種旅行業者(海外を含むパック旅行及び乗車船券等の販売等)、第二種旅行業者(国内のみのパック旅行及び乗車船券等の販売等)、第三種旅行業者(乗車船券等の販売等)、旅行業者代理業者(特定の旅行業者を代理した旅行商品の販売)に区分される。旅行業者数は表4-2-1のとおりである。
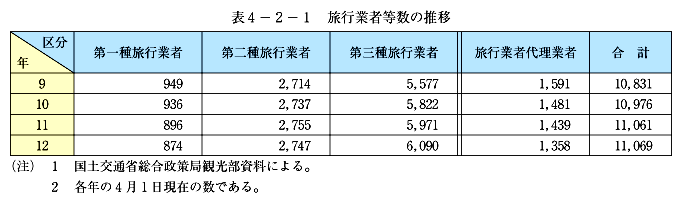
旅行業者の取扱高については、主要50社の12年の実績は第1章表1-2-4に記述したとおりであり、11年に比べ国内旅行の取扱いは0.2%の増、海外旅行の取扱いは3.7%の増、全体では1.7%の増となった。なお、11年における第一種旅行業者の取扱実績は6兆6,626億円である(表4-2-2)。
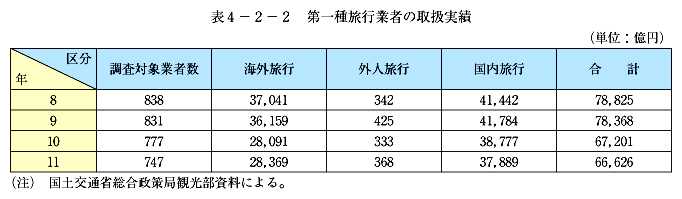
(2)旅行商品の電子商取引の拡大にあわせた環境整備
![]() インターネットを利用した旅行取引に関するガイドラインの策定等
インターネットを利用した旅行取引に関するガイドラインの策定等
インターネットによる旅行取引が急速に拡大しているが、インターネット取引の適正化を図るため、12年6月に旅行業協会において「インターネットを利用した旅行取引に関するガイドライン」を策定し、旅行業者等が遵守すべき基本的方針を定めた。また、このガイドラインを遵守しているホームページに対し、旅行業協会が適正マーク(e-TBTマーク)を交付している(13年4月現在64社に対して交付)。
また、13年2月には旅行業者のインターネット上の広告について、適正な表示が行われているか法令遵守状況を点検するインターネット・サーフデイを実施した。
![]() 書面交付規定に係る旅行業法改正
書面交付規定に係る旅行業法改正
インターネットによる旅行取引の拡大に対応し、旅行契約の締結に際し義務付けている書面の交付について、電磁的方法によってもできるようにするため、旅行業法の改正を行った(13年4月施行)。今回の法改正により、携帯電話ではこれまで旅行商品の紹介や予約にとどまっていたものが、携帯電話のみで契約締結まで行うことが出来るようになった。
(3)より便利で安心な旅行取引へ
![]() 旅行商品を取り扱える場所の拡大等
旅行商品を取り扱える場所の拡大等
9年6月よりコンビニエンスストアを使用した主催旅行商品等の販売が行われているが、旅行者の利便の向上のため12年4月より委員会等における検討を踏まえ、旅行商品を取り扱える場所の拡大、旅行代金のコンビニエンスストアでの収受、航空券の宅配サービス等を認めた。
![]() 登録の有効期間の延長にあわせた施策
登録の有効期間の延長にあわせた施策
9年12月から旅行業の登録及び更新の登録の有効期間が3年から5年に延長されたことに伴い、消費者保護措置として、財産的基礎等についての立入検査及び報告徴収の強化等の措置を行っている。
(4)旅行業等における公正な競争の確保
旅行業等における公正な競争を確保し、一般消費者の適正な商品選択に資するため、「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景品表示法」という。)に基づいて、次のような施策を行った。
![]() 旅行業に関する施策
旅行業に関する施策
- ア.公正競争規約
- 旅行業公正取引協議会に対し、「旅行業における景品類等の提供の制限に関する公正競争規約」及び「主催旅行の表示に関する公正競争規約」が適正に運用されるよう引き続き指導を行った。
- イ.適正な情報提供
- 旅行業公正取引協議会は、一般消費者の意見を協議会活動にいかすため、消費者モニター制度の検討を行い、その効果的導入について積極的な取組みを行った。
-
 観光土産品に関する施策
観光土産品に関する施策
ア.景品表示法 - 桜皮細工の原産国等について、中華人民共和国で製造されたにもかかわらず、あたかも秋田県の伝統工芸品であるかのように表示していた2社に対し、不当表示であるとして、警告を行った。
- イ.公正競争規約
- 全国観光土産品公正取引協議会に対し、「観光土産品の表示に関する公正競争規約」が適正に運用されるよう引き続き指導を行った。
- ウ.試買検査会等
- 観光土産品における消費者の意見を把握するため、試買検査会を実施するとともに、全国観光土産品公正取引協議会において、各地方協議会ごとに審査会等を開催し、適正な表示及び包装がなされている観光土産品に対し、認定マークを交付した。
(1)ニーズに対応した新たな宿泊旅行
近年の我が国社会の構造変化等に対応して国民の旅行ニーズが多様化している中で、こうした変化に対応して新しい形態のサービス提供の動きがみられる。
具体的には、
なお、従業員の慰安、社内の親睦・融和を図るとともに勤労意欲の向上等を目的とする全従業員を対象とした会社主催の4泊5日以内の従業員レクリエーション旅行(金銭との選択が可能でないもの)については、その旅行に参加した従業員等の受ける経済的利益について、少額不追求の趣旨を逸脱しないものに限り課税されないこととされており、日数や旅行先の選択の幅の広い多様な旅行を楽しむことができるようになっている。
(2)ネットワークを活用した鉄道輸送サービスの向上
| 鉄道事業においては、12年3月に施行された改正鉄道事業法により、従来一定の要件の下で、上限の範囲内であれば運賃等の設定変更ができたものを、更に自由に設定変更できるようにされた。 鉄道事業者は、観光地等と連携し、海外からの観光客を対象にした運賃等の割引商品の発売や、各鉄道事業者間の共通乗車カードシステムを活用して、当該システムの加盟事業者の路線間を乗り放題でき、沿線観光施設の割引を受けられるカードの発売等、積極的に旅客の誘致を図っている。サービス面においては、インターネット等により各駅の運賃・料金、時刻表をはじめ、沿線の観光案内等の情報を提供するとともに、携帯端末で特急券の予約及び購入ができるようにする等、情報システムを活用したサービスの向上が図られている。 |
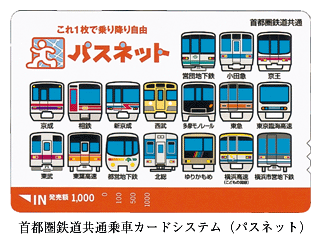 |
(3)運賃の多様化等航空輸送サービスの向上
国内航空運賃については、平成12年2月より施行された改正航空法において、認可制から事前届出・変更命令制へ移行したことにより、航空会社の経営判断による自由な運賃・料金の設定・変更が可能となった。これを受け航空各社は、12年4月以降、往復割引運賃等の各種割引運賃を設定するなど、運賃・料金の更なる多様化・低廉化の動きが進んでいる。
なお、11年6月より、有識者による「航空輸送サービス懇談会」を開催し、利用者が自らの判断により自由かつ的確な選択を行うことを可能とするために運輸省(当時)及び航空会社が行うべき情報公開の在り方や、差別的な運賃・料金等に対する変更命令の発出に係るガイドラインについて検討を行い、11年10月に検討結果の取りまとめを行った。それに基づき、12年9月より、運輸省(当時)のホームページ上などにおいて、航空輸送サービスに係る情報公開を行っている。
(1)観光情報提供の高度化
一方、近年、パソコン等による情報ネットワークの充実、情報通信機器の発達等情報提供システムの高度化が進められており、このような高度情報社会の進展に対応した観光情報システムを充実していくことが重要な課題となっている。このため、次のような施策を実施した。
![]() 観光情報サービスの充実
観光情報サービスの充実
(社)日本観光協会は、12年12月に「全国地域観光情報センター」(http://www.nihon-kankou.or.jp)をオープンし、インターネット上でリアルタイムに全国の観光情報を提供している。
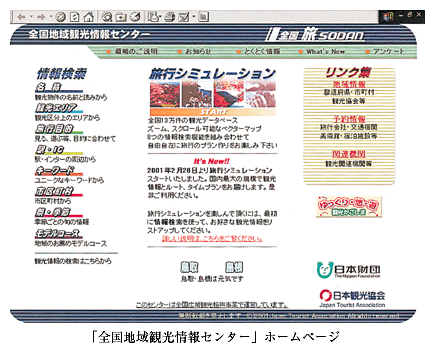
![]() 海洋情報
海洋情報
海水浴、釣、潮干狩、ヨット、サーフィン等のマリンレジャー等に関する海洋情報についての問い合わせ等に対応するため、海上保安庁水路部及び各管区海上保安本部に設けられた「海の相談室」では、各地域の特性に応じたきめ細かな情報提供を行っている。
![]() 林野森林情報
林野森林情報
レクリエーションや登山等に関する情報を提供するため、国有林野事業では、全国の森林管理局・署等において、国有林野内の保護林、レクリエーションの森、林道・歩道の位置、針葉樹林・広葉樹林の別等が示されている国有林野施業実施計画図等の提供を行っている。
また、林野庁の森林センターにおいて、知床半島等の生きた森林の状況をインターネットで広く国民に提供する森林環境情報システムの整備を行った。
森林とのふれあいを通じた様々な体験活動の場、都市と山村との交流の場、森林浴による健康づくりの場などの広く国民に開かれた森林について、森林総合利用ホームページ等による情報提供を実施した。
![]() 郵便局ネットワーク
郵便局ネットワーク
地域の観光・イベント等の地方公共団体(全国215団体)が発信する情報を、郵便局ネットワークを通じて、都会等で生活する人々に提供する「活き活き情報交流サービス」を引き続き実施し地域の観光・産業情報等の交流促進に努めた。
![]() ふるさと情報
ふるさと情報
都市と農山漁村との交流に資するため、インターネット、ふるさとプラザ等を通じた都市住民のニーズ調査を行い、地域のイベントや特産品、体験活動のふるさと情報の効果的な発信方策を検討した。
![]() テレトピア構想
テレトピア構想
地域の情報化を促進し、地域社会の活性化を図ることを目的としてテレトピア構想を推進している。(平成13年3月末で189地域指定)本構想指定地域では、インターネットやCATV、コミュニティ放送等の情報通信メディアを活用して、観光情報システム等を構築し、各々の地域情報を内外に発信している。
![]() コミュニティ放送
コミュニティ放送
4年12月に全国で初めて北海道函館市においてコミュニティ放送局が開局し、12年12月末現在、全国137局が開局している。
![]() 地域映像情報の発信
地域映像情報の発信
地域衛星通信ネットワーク整備構想の一環として、衛星通信を利用して地方公共団体等から全国に向けて地域のイベント等の情報を発信する地域映像情報発信事業について、情報提供等の充実を図り、地域の活性化に努めた。
(2)観光産業等における情報化
![]() 旅客輸送業における情報化
旅客輸送業における情報化
旅客輸送業においては、座席予約システム、移動体情報システム、安全性確保のためのシステム等各種情報システムを活用して、予約の容易化・総合化、移動時間の有効活用、観光旅行者の安全性の確保等が図られている。
- ア.予約の容易化・総合化
- 旅客輸送業においては、オンライン座席予約・発券システムの整備等の情報化が進められ、観光旅行、出張の容易化等が図られており、近年では、インターネット、パソコン等を通じて、空席状況等を確認しながら座席予約が行えるようになってきている。
航空会社のCRS(コンピューター予約システム)を利用することにより、航空機の座席の予約・発券等に加え、総合的なサービスを受けることができ、また、自社のCRSを他社のCRSと接続することにより、広範なサービスの提供がなされるようになっている。さらに、国内線においては、電話やインターネットによる予約のみで航空券が購入できるチケットレスサービスが導入され、また、一部の航空会社においては、コンビニエンスストアを活用するなど、さらなる手続の簡素化が図られている。
さらに、JR各社は従来の鉄道乗車券中心の発券システムに旅行業対応機能を付加した旅行業システムを運用しており、旅館・ホテルの宿泊券の予約・発券が容易となり、イベント商品等の内容も充実するなど、予約の容易化・総合化が図られている。 - イ.移動時間の有効活用
- 旅客輸送業においては、移動体情報システムの導入が着実に進展しており、観光旅行者の移動時間の有効活用が図られるようになってきている。鉄道分野では、新幹線において、漏洩同軸ケーブルのデジタル化による容量拡大により公衆電話が大幅に増設されている。また、航空分野においても、国内線だけでなく国際線においても機内から地上への公衆電話サービスが行われている。
-
 効率的な情報化
効率的な情報化
現在までの観光分野における情報化は、それぞれの事業者が独自に進めている状況にあり、一部を除き事業者のシステム相互間に互換性がないため、複数の他社の端末機への重複入力等(いわゆる「多端末現象」)が発生しており、事業の効率化を阻害する要因となっている。
このような状況に対応し、各事業者間のシステムの交換性を図り各種予約業務の利便性の一層の向上、事業の効率化によるコストダウン等を通じて観光の振興に資すため、旅行EDI研究会を中心として、観光分野へのEDI(異なる企業間で、見積、注文、支払等の取引データを広く合意した規約に基づき、電子データとしてコンピュータ間で交換する仕組み)の導入を推進するとともに、近年、普及しているインターネット等を利用した取引等を推進するため、EDIの開発動向把握、我が国旅行分野における情報交換の現状把握、国際機関への意見具申等の活動を行っている。
(1)施設の整備
- ア.交通バリアフリー法(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律)
- 12年5月、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進することを目的とする交通バリアフリー法が公布され、同年11月に施行された。
同法は、交通事業者に対し、交通施設を新たに整備・導入する際にバリアフリー化を義務付けるとともに、鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に即して、旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等の重点的・一体的なバリアフリー化を進める制度を導入することを内容としている。 - イ.公共交通機関のバリアフリー化
- 高齢者、身体障害者等の移動制約者が安全かつ身体的負担の少ない方法で公共交通機関を利用できるようにするために、鉄道駅における障害者対応型エレベーター・エスカレーター等バリアフリー施設の整備、ノンステップバス、低床式路面電車等の導入等に対して国と地方公共団体が協調して補助を行うとともに、税制上の特例措置を講じた。また、鉄道駅、旅客船・空港ターミナルにおけるエレベーター・エスカレーター等の施設整備について日本政策投資銀行等による融資を行うなどの支援策を講じた。
- ウ.歩行空間のバリアフリー化
- 幅の広い歩道等の整備や歩道の段差、傾斜、勾配の改善、電線類の地中化、視覚障害者誘導用ブロックの整備、障害者の利便を考慮した信号機の整備等を進め、誰もが安心して歩ける歩行空間のバリアフリー化を推進した。さらに、積雪や凍結等による冬期特有のバリアを軽減するため、消雪施設、流雪溝、堆雪幅の整備等や歩道除雪の充実を図る冬期バリアフリーを進めた。
また、鉄道駅等の周辺の道路等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するため、交通バリアフリー法及びこれに基づく道路構造基準を制定するとともに、標識令を改正した。 - エ.道路交通環境の整備
- 見やすく分かりやすい道路標識、標示の設置、ゆずりあい車線、一般道路の休憩施設(「道の駅」)等の整備を進めるとともに、交通情報提供装置の整備、道路情報提供装置やそれを支える情報・通信基盤の整備促進等により、運転者が安心してかつ安全に運転できる道路交通環境の整備を行った。高速道路のサービスエリア、パーキングエリア、「道の駅」などの休憩施設においては、障害者用トイレや駐車ます等の整備を行った。
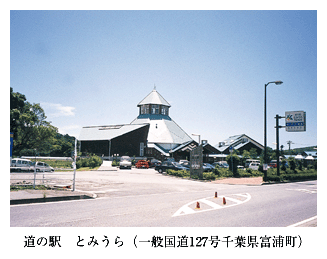
- オ.観光地のバリアフリー化
- 高齢者等に対する充実した余暇を過ごす機会の提供と観光振興の拡大の観点から平成12年度補正予算において「観光地バリアフリー化整備事業」を行った。

- カ.地域福祉施策との連携
- 高齢者、障害者をはじめ、女性や子供、外国人等すべての人にやさしいまちづくりを推進する観点から、地方公共団体が地方単独事業により歩道の段差切り下げ、歩道の整備と一体的に行う障害物の除去など公共施設等の改良を体系的・一体的に実施する場合に、「共生のまち推進事業」により財政支援措置を講じた。
- キ.宿泊施設
- ホテル・旅館については、高齢者・障害者の利用に配慮した施設整備に対し、中小企業金融公庫等による特利融資制度により支援を図ったほか、8年3月に策定された「高齢者・障害者の利用に対応する宿泊施設のモデルガイドライン」について、関係団体を通じて、宿泊施設に周知した。
-
 文化施設等
文化施設等
国立の文化施設(国立博物館・美術館、国立劇場等)においては、障害者用トイレ、スロープ、エレベータ等の設置や車椅子の配慮等の施設の整備、入場料金の軽減措置等を行っており、高齢者・障害者も安心して観覧できる環境をつくるよう配慮した。
また、視聴覚障害者等が公共施設を利用する際の安全確保の見地から、地方公共団体が必要な火災情報や避難情報を視聴覚障害者等に有効に伝達することのできるシステムを導入するための改良工事を行った場合には、財政支援措置を講じた。
さらに、観光地における高齢者、障害者の利便を考慮した信号機(視覚障害者用信号機、高齢者等感応式信号機等)、道路標識、道路標示等の交通安全施設等の整備を推進した。 都市公園
都市公園
都市公園においては、活力ある長寿・福祉社会の形成に資するため、公園施設のバリアフリー化や、公園を福祉施設と一体的に整備することにより、すべての利用者の生きがいの創出や、健康づくりに資する公園(いきいきふれあい公園)等の整備を実施した。 水辺空間
水辺空間
河川等の水辺空間は、障害者等にとって憩いと交流の場を確保するための重要な要素となっている。このため、河川改修及び砂防事業等を通じて、障害者等にも配慮した堤防坂路のスロープ化、休憩施設の設置等の河川の整備等を実施した。(2)運賃等の割引等
 公共交通機関
公共交通機関
鉄道等各公共交通機関では、身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者及び療育手帳の交付を受けた知的障害者の運賃割引を実施している。 有料道路と国営公園
有料道路と国営公園
有料道路においては、身体障害者手帳の交付を受けたすべての身体障害者が自ら運転する場合や、重度の身体障害者又は療育手帳の交付を受けた重度の知的障害者の介護者が運転する場合に、通行料金の割引措置を実施している。また、国営公園においては、身体障害者等の入園料等の免除を実施している。 自動車
自動車
歩行困難な身体障害者が自動車を利用しやすいように、身体障害者の使用する車両に対し駐車禁止除外指定車標章を交付しており、一つの都道府県公安委員会から駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた車両については、その他の都道府県においても駐車禁止規制の適用除外とする措置を講じている。
定期開設局(富士山頂、上高地等8か所)又は移動郵便車等による臨時出張所(各地の高原、名所、旧跡等)を開設して、郵便切手類の販売、郵便物の引受け、風景入通信日付印の押印等を行った。
また、地方色豊かな風物等を題材とする「ふるさと切手」、過疎地域の代表的な風物等を題材とした図画等を印刷した「ふるさと絵葉書」(50円)等の発行を通じて全国にふるさとを紹介し、それぞれの地域における観光・文化の振興に努めた。
さらに、各地の名所、史跡等をデザインした風景入通信日付印を全国約10,000の郵便局で郵便物の消印に使用し、旅行及び観光促進の一助となるように努めた。