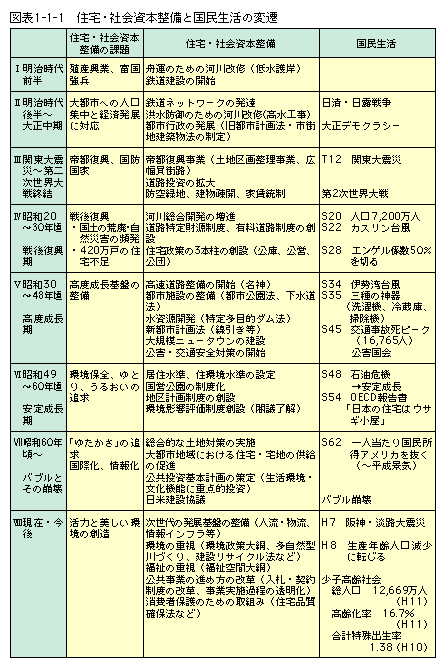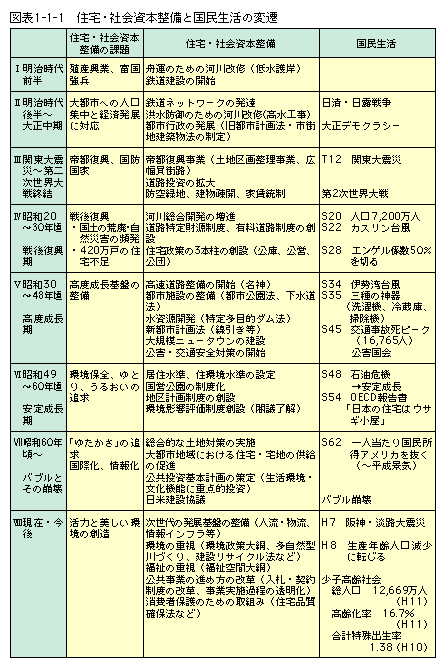(住宅・社会資本整備の歴史)
まず、明治以降の我が国の社会資本整備の歴史を年表にして大まかに振り返ってみよう(図表1-1-1)。時代を大きく区分すると、それぞれの時代における住宅・社会資本整備に対する諸課題とそれらに対する対応の歴史が明らかになる。
明治時代の前半に、殖産興業・富国強兵といった国家的な課題に対応するために、早くも鉄道建設が開始され、産業界と軍部の需要に支えられて鉄道への重点投資は第二次世界大戦までおおむね一貫して行われた。これと並んで、河川の舟運を目的とした河川の低水工事が行われた。この時期には、治水・砂防工事の技術を日本に残したオランダ人技師デ・レイケを始めとする政府雇用外国人により欧米の優れた技術が導入され、日本人技術者を育てていった。また、明治24年の濃尾地震を契機に、在来木造建築構造が見直され、鉄骨・鉄筋コンクリート構造による我が国独自の耐震技術開発が始まった。
明治時代後半から大正中期には、我が国の急速な近代化に伴う大都市への人口の集中と経済発展に対応するため、旧都市計画法の制定などが行われた。鉄道ネットワークも発達し、河川改修も、洪水防御のための高水工事が中心となった。
大正12年の関東大震災後には、帝都復興計画に基づいた帝都復興事業が開始され、土地区画整理事業により大規模な既成市街地が整備された。また、同時に近代的な舗装や街路樹による緑化が施された広幅員の街路や、公園、コンクリート造による不燃建築の小学校、さらには景観設計の隅田川六大橋の整備などが進み、首都の本質的な復興・改造をもたらした。また、同時期に大阪市においても、初めての都市計画事業が受益者負担金を活用(道路、地下鉄等)して行われ、御堂筋など今日に残るまちの基礎がつくられた。
また、第2次世界大戦期には防空緑地の整備や建物疎開など国防国家の形成が行われた。一方、自動車交通の開始を受け、大正末期以来、道路の近代舗装が街路を中心に進められた。昭和14年に策定された東京緑地計画による「グリーンベルト構想」は、初めて欧米各国と共通の思想に立った都市における緑地(Open Space)を目指したものであり、その構想自体は完全には実現していないものの、その精神は現在においても受け継がれている。
昭和20年代の戦後復興期には、国土の荒廃と昭和22年関東地方を襲ったカスリン台風を始め自然災害の頻発に対応するため、特定地域総合開発事業という形で洪水調節、水資源開発等の河川総合開発が行われた。また、戦後の420万戸の住宅不足に対応するために「公庫・公団・公営住宅」のいわゆる住宅政策の3本柱が昭和30年までには整えられたほか、緊急かつ計画的に道路整備を進める必要性等から、受益者負担の考え方に基づいた道路特定財源制度や有料道路制度も創設された。この時代には、プレストレスト・コンクリート(予め外力を与えることにより抵抗力を強化したコンクリート)をはじめとする海外の技術が導入され、これらの事業を支えてきた。
昭和30年代に高度経済成長が始まると、住宅・社会資本整備は「欧米水準に追いつき追い越す」ことと「国土の均衡ある発展」を目標に一貫して進められてきた。急速な都市化への対応と経済成長を確保する基盤の整備のため、中京地域と京阪地域を結ぶ名神高速道路をはじめとする高速道路網の整備や公園・下水道などの都市施設の整備や水資源開発が精力的に推進された。これには、シールド工法、アーチ式ダム等のダム技術、長大橋梁など難度の高い技術が導入された。一方、昭和34年の伊勢湾台風は、死者・行方不明者5,000人超という甚大な被害をもたらしたが、これを契機に、昭和36年に災害対策基本法が制定されて国、地方を通じ一貫した防災行政の推進が図られた。また、昭和40年代には、急激な都市化に対応するため、都市計画法の制定や建築基準法の集団規定の全面改正が行われ、今日まで続く都市計画の新たな法体系が確立した。
昭和48年に石油危機が起きたが、その前後から我が国は安定成長期に入り、それまでの急速な成長拡大のもたらした公害問題等様々な問題点に対する反省から、環境保全やゆとりとうるおいの追求が求められるようになった。住宅・社会資本整備の分野においても、昭和45年のいわゆる公害国会において、下水道法の目的として公共用水域の水質保全が加えられ、また、昭和48年には全ての都道府県において一世帯一住宅を達成したことを受けて、第三次住宅建設五箇年計画(昭和51年)において居住水準目標が、第四次住宅建設五箇年計画(昭和56年)において住環境水準目標が設定され、ゆとりの住生活の実現や住環境の着実な改善が求められる一方、環境影響評価制度が創設され、公共事業における環境保全が大きなテーマとなった。また、昭和55年には都市計画法及び建築基準法の改正により地区計画制度が創設され、国民の多様化するニーズに応えて住民参加による「まちづくり」への道を拓いた。
昭和60年以降の、いわゆるバブルの発生とその崩壊に至るまでは、平成景気が続く時期を迎え、地価高騰に対する総合的な土地対策の実施や、大都市地域における住宅・宅地の供給の促進、真の「ゆたかさ」を実現するための公共投資基本計画の策定などが行われている。