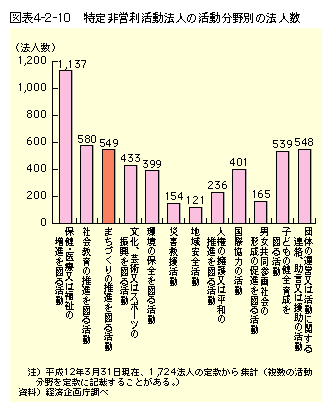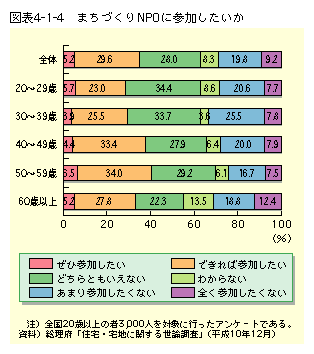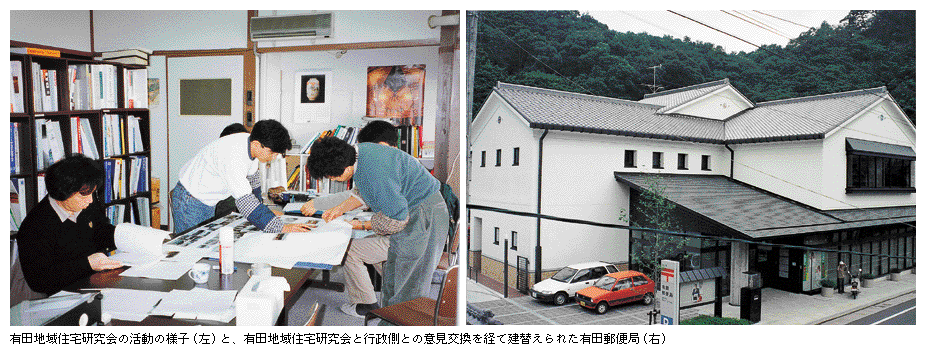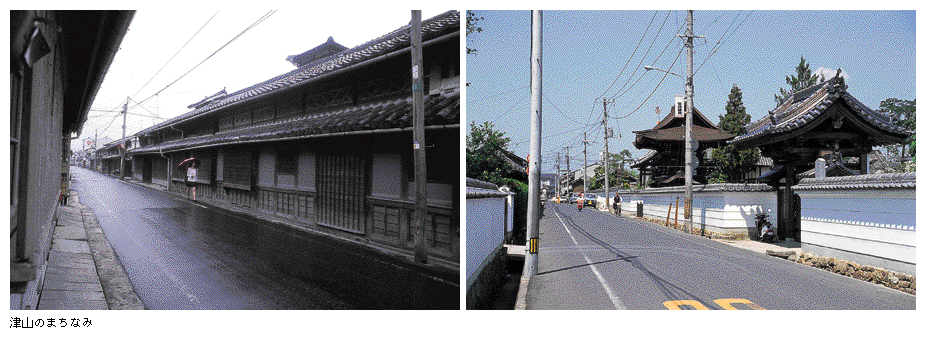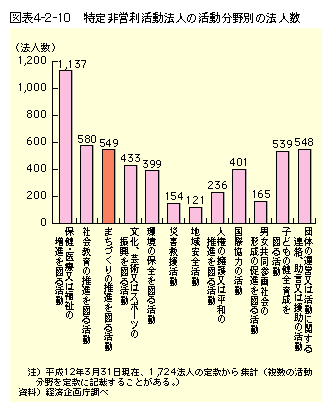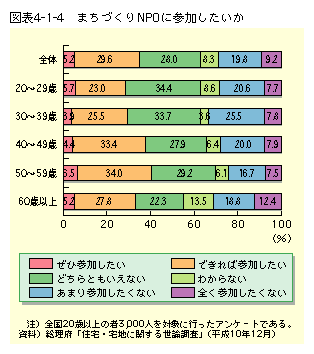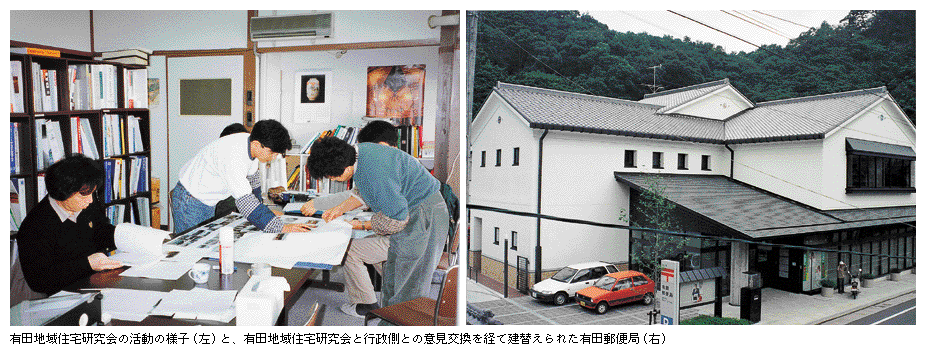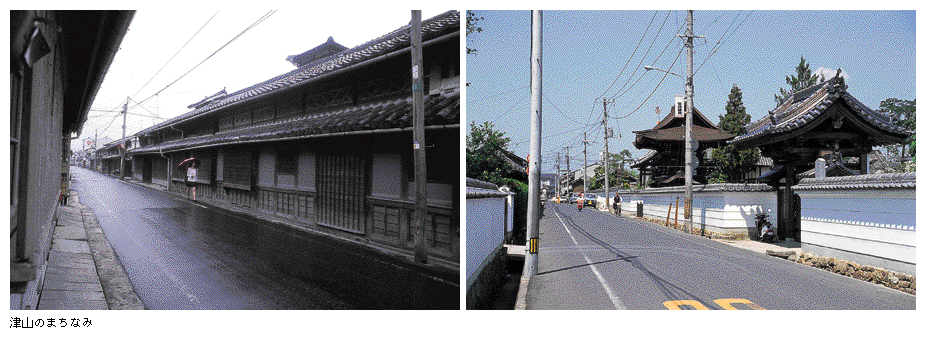(NPO(民間非営利団体)の活動)
平成10年12月に特定非営利活動促進法(NPO法)が施行されて以来、NPO元年ともいわれる近年においては、NPOの活動が注目を浴び、職場での仕事等とは異なる「生きがい」を感じられる場、退職後にも活躍できる場等として、国民の生活スタイルにも取り込まれてきている。NPOはこれまで希薄であった「行政に頼らず、自分たちのできることは自分たちの責任においてやる」という発想を強く根付かせる契機となるであろう。
まちづくりにおいても、行政のみならず、住民が参加するための母体としてのNPOの役割が期待されている。
NPO法に基づく認証(都道府県知事及び経済企画庁長官)を受けた特定非営利活動法人(NPO法人)を見てみると(図表4-2-10)、1,724法人のうち549法人(全体の31.8%)が「まちづくりの推進を図る活動」を行うこととしている(平成12年3月31日現在、経済企画庁調べ)。活動内容としては、安全パトロール等犯罪防止に関する事業、中心市街地の活性化に関する事業、伝統的祭事・地域おこしの行事・イベントに関する事業、環境との共生を図るまちづくり事業等多岐にわたっている。
また、総理府の世論調査「住宅・宅地に関する世論調査(平成10年12月)」によると、「あなたは景観の改善や地域の住環境の向上など、住民主体のまちづくり活動などを行うまちづくりNPOに参加してみたいと思いますか」との問いに対し、年齢別に見ると(図表4-1-4)、より参加への意向が強いのは、50〜64歳と比較的高年齢の層に多く、今後、退職後の高齢者層が実社会での知識・経験を地域の活動のために活かしてくれることを期待すると同時に、より若い主体が積極的にまちづくりに関わるように促すことが課題となってくる。
〈有田地域住宅研究会〉
佐賀県有田町は日本の陶磁器発祥の地であり、現在でも有田町の全産業のうち6割が有田焼に関わっている焼き物の町として、焼き物と関連のある古くからのまちなみが焼き物の伝統とともに現代に伝わっている。
有田町では、昭和58年度から有田町地域住宅計画(HOPE計画)を策定したことを機に、有田らしい住まいづくり、まちづくりを考えるために地域の設計事務所・工務店を中心としたネットワークを作り、有田地域住宅研究会が発足した。有田地域住宅研究会では、伝統的な民家を調査し、有田焼創業期から伝わるまちなみに調和した新たな建築物の設計など、古いまちなみ・景観の保存と居住性を両立させる住まいづくりの提案を行い、有田焼を育むまちの持つ雰囲気を伝えた「有田らしい」住宅をつくるための景観カタログを作成するなどの活動を行っている。
*HOPE計画
地方公共団体の策定する「住宅マスタープラン」のうちの一つで、地域の持つ自然、伝統、文化等を踏まえ、その特性を活かしながら、個性ある地域文化を創造する住まいづくり、地域開発等と連携した人口の定住促進のための住宅整備、大都市地域における勤労者世帯向けの住宅供給等地域の課題に対応し、良好な住宅市街地の形成、地域の住文化の育成、地域住宅生産の振興等を図るための計画である。
〈津山まるごと博物館研究会〉
津山市は岡山県の北に位置し、周囲を中国山地に囲まれた、人口9万人の都市である。約400年にわたって伝わる城下町として発達し、豊かな自然と田園景観に囲まれ、津山市の西に位置する城西・田町地区は、現代にも城跡、武家屋敷、町家、寺町の姿を残している。また、大正時代に建てられた銀行、病院等の近代建築が点在し、歴史が重層したまちなみを形成している。地区では昔ながらの職人の手仕事を生業とする店(和菓子、畳、竹細工、ちょうちん、鋸の目立て等)も多い。
「津山まるごと博物館研究会」は、平成8年に津山市を中心に活動する市民グループ「津山まちづくり市民会議」のメンバーと地元の有志により発足し、地区のまちなみや暮らし全体を一つの「博物館」として紹介する「エコ・ミュージアム」構想の実現を目標としている。このため、手仕事をキーワードにしたイベントや地域の歴史、暮らしの調査、地区内の伝統産業を続ける仕事場や寺を「ミニ博物館」と見立ててのネットワークづくりを行うほか、インターネット等による全国への情報発信を行うなどの活動を展開している。