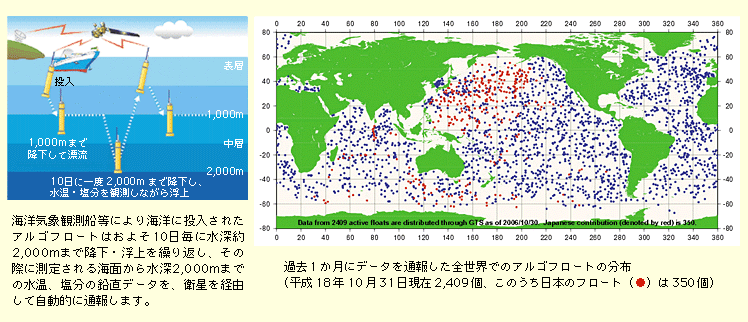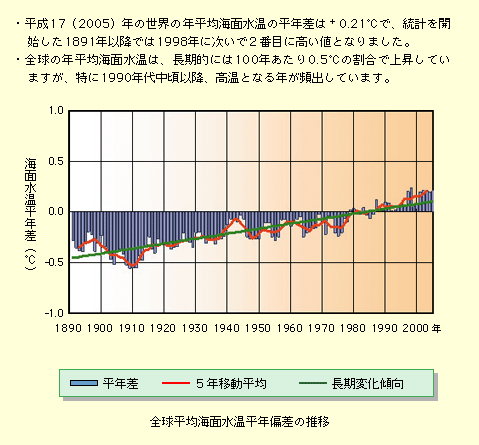(2)海洋の観測・監視
海洋は、温室効果ガスであるCO2を吸収し、熱を貯えることによって、地球温暖化を緩やかにしている。また、海洋変動は、台風の発生・発達や異常気象等、気象にも深く関わっている。このため、地球環境問題への対応には、海洋の状況を的確に把握することが重要である。
地球全体の海洋変動を即時的に監視・把握するために、国土交通省は関係省庁等と連携して、世界気象機関(WMO)等による国際協力の下、海洋の内部を自動的に観測する装置(アルゴフロート)を全世界の海洋に展開するアルゴ計画を推進している。
図表II-7-7-1 アルゴ計画における観測の概要
気象庁では、観測船、アルゴフロート、衛星等による様々な観測データを収集・分析し、地球環境に関連した海洋変動の現状と今後の見通し等を総合的に診断する「海洋の健康診断表」を、ホームページを通じて提供している。
図表II-7-7-2 気象庁ホームページで公開している「海洋の健康診断表」の例
海上保安庁では、アルゴフロートのデータを補完するシステムとして、伊豆諸島周辺海域における黒潮変動を海洋短波レーダーにより常時監視・把握し、インターネットにより公開するとともに、我が国の海洋調査機関によって得られた海洋データを収集・管理し、関係機関及び一般国民へ提供している。