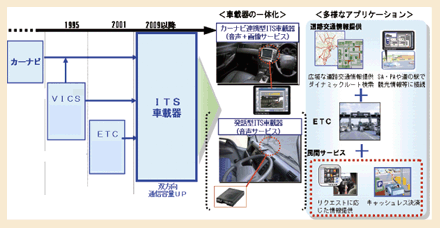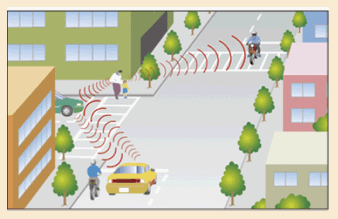1 交通分野のICT化
(1)公共交通分野のICT化
地方の中小公共交通事業者の生産性やサービスを向上させていくために、ICTを活用することが重要である。現在、大都市圏の公共交通機関を中心に導入が進んでいるIC乗車券システムについて、地方の公共交通機関へ導入していくには費用面等の課題があることから、地方の中小公共交通事業者にも導入が容易となる低廉なIC乗車券システムの実現に向けた開発の支援を行っている。
(2)ITSの推進
最先端のICTを活用して人・道路・車を一体のシステムとして構築する高度道路交通システム(ITS)は、高度な道路利用、ドライバーや歩行者の安全性、輸送効率及び快適性の飛躍的向上の実現、また交通事故や渋滞、環境問題、エネルギー問題等の様々な社会問題の解決を図り、自動車産業、情報通信産業等の関連分野における新たな市場形成の創出につながっている。
1)社会に浸透したITSとその効果
(ア)ETCの普及促進と効果
ETCは、今や日本全国の有料道路で利用可能であり、車載器の新規セットアップ累計台数は平成22年2月時点で約3,008万台で、全国の高速道路での利用率は約83.9%となっている。これにより高速道路の渋滞原因の約3割を占めていた料金所渋滞がほぼ解消され、CO2排出削減等、環境負荷の軽減にも寄与している。さらに、ETC専用ICであるスマートICの導入や、ETC車両を対象とした料金割引等、ETCを活用した施策が実施されるとともに、有料道路以外においても駐車場での決済やフェリー乗船手続等への応用利用も可能となるなど、ETCを活用したサービスは広がりと多様化を見せている。
(イ)道路交通情報提供の充実と効果
走行経路案内の高度化を目指した道路交通情報通信システム(VICS)対応の車載器は、平成21年12月末現在で約2,600万台が出荷されている。VICSにより旅行時間や渋滞状況、交通規制等の道路交通情報がリアルタイムに提供されることで、ドライバーの利便性が向上し、走行燃費の改善がCO2排出削減等環境負荷の軽減に寄与している。
2)新たなITSサービスの技術開発・実証実験
(ア)ITS車載器の普及
次世代のITSを見据えた官民共同研究により、カーナビ、VICS、ETCなどこれまで個別の車載器で提供されていたサービスを1つの車載器(ITS車載器)で提供可能とする新たなITSシステムの技術仕様を開発した。このシステムは、国際標準化された5.8GHz帯DSRC(スポット通信)(注1)をベースとし、高速・大容量での双方向通信による多様なサービスが実現可能となった。具体的なサービスとしては、広域な道路交通情報の提供、ドライバーへの注意喚起となる画像や音声を用いた前方障害物、前方状況に関する安全運転支援情報の提供などが挙げられ、将来的にはサービスエリア・パーキングエリアにおける地域・観光情報への接続や、駐車場等での料金決済などの多様なサービスも可能となる。平成19年3月に、JEITA規格としてITS車載器標準仕様書が発行された後、公道実験結果を踏まえ、20年7月には、実用化を見据えた同規格の改訂がなされており、21年の秋には民間側で車載器の販売が開始された。