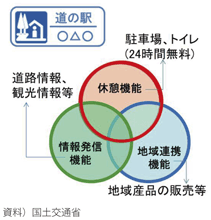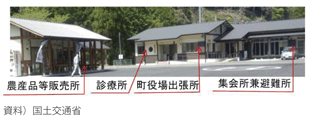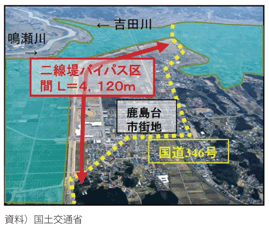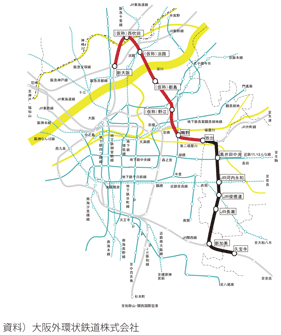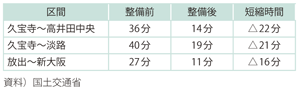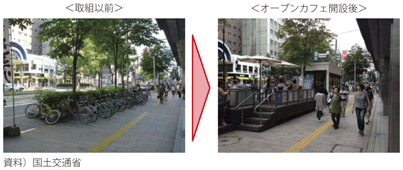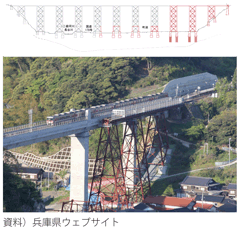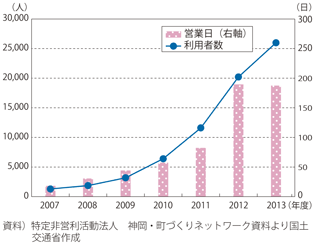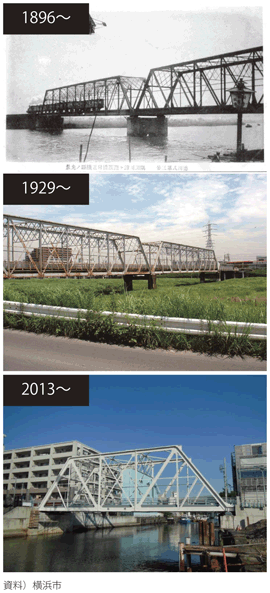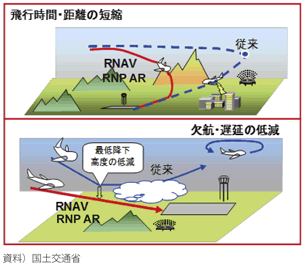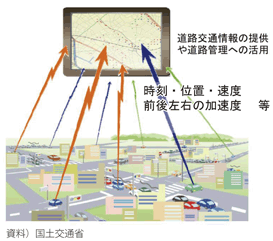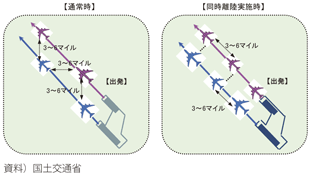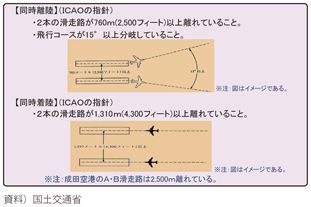◯2 使い方の工夫による既存ストックの活用
財政制約に直面している我が国では、社会インフラを新規整備する際にはこれまで以上に効率的・効果的に進めていくことが求められるが、既に整備された社会インフラのなかには、経済社会の変化に伴い、必ずしも効率的に利用されていないものもある。このため、既存の社会インフラの使い方を見直すことで、追加的なコストをかけずに従来以上に利用者の便益を増大させていくための工夫をこらすことが求められる。ここでは、使い方を工夫し既存の社会インフラを有効に活用している事例を見ていく。
(1)社会インフラの多面的活用
一定程度の利用がある社会インフラでも、従来の用途だけでなく、他の用途としても用いれば、社会インフラの便益の及ぶ範囲が広まる。また、既存の社会インフラを使いつつ、その空間を有効活用すれば、社会インフラの価値は更に高まる。以下ではその具体的事例を見ていく。
■様々な可能性を持つ「道の駅」
「道の駅」は、道路利用者の休憩、情報提供、地域連携の場として、1993年の制度発足から約20年、全国各地に広がり、2014年3月現在1014の施設が登録されている。全国年間売上額は約2100億円、全国年間購買客数は約2.2億人(ともに2011年時点)の規模となっている。
図表2-1-17 「道の駅」の機能
当初は、通過する道路利用者へのサービスが中心であったが、近年は、農業・観光・福祉・防災等、地域の個性、魅力を活かした様々な取組みがなされている。
農林水産業については、地元農水産品の直売、さらに商品開発・加工・販売まで行う6次産業化の拠点となるなど、地域の農林水産業を支えている。例えば、福岡県宗像市の道の駅「むなかた」では、2012年の販売額の99.9%は地元産品が占めるなど地元でとれた新鮮な魚や野菜の直売に力を入れており、地元産業の活性化に貢献している。また、栃木県茂木町の道の駅「もてぎ」では、地元農産物を道の駅で加工し、18種類の新商品を開発、販売している。
観光業については、宿泊農業体験や地域独自の旅行ツアーの実施、地元ならではの見どころ情報の提供等、観光振興に寄与している。北海道長沼町の道の駅「マオイの丘公園」では「道の駅」での対面販売をきっかけに、地元農家が宿泊農業体験を行っており、2012年の年間の体験者は約4000人にのぼる。また、島根県飯南町の道の駅「赤来高原(あかぎこうげん)」では「道の駅」が旅行業資格を取得し、森林セラピーを売りにしたツアー等を自ら企画・販売している。このように「道の駅」は農林水産業、観光業を通じた地域活性化に一役買っている。
また、道の駅は、地域活性化だけでなく地域住民の安心な暮らしも支えている。和歌山県古座川(こざがわ)町の道の駅「瀧之拝太郎(たきのはいたろう)」では、診療所や町役場出張所が設けられており、地域住民に医療や行政サービスを提供する場となっている(図表2-1-18)ほか、島根県川本町の道の駅「インフォメーションセンターかわもと」では宅配サービスを提供しており、町内の高齢者世帯の約1割が同サービスを利用するなど、道の駅は地域の住民には欠かすことのできない存在になりつつある。
図表2-1-18 瀧之拝太郎(和歌山県古座川町)
また、災害時の対応拠点としても道の駅は大きな役割を担っており、東日本大震災の際には自衛隊の活動の拠点になるなど、復旧支援活動の拠点となった。また、岩手県下閉伊(しもへい)郡山田町の道の駅「やまだ」では、流通経路が寸断されるなか、地元農家の出荷等により、速やかに販売を再開し、被災者を支援した。
このように「道の駅」は、当初の主目的であった「通過する道路利用者へのサービス提供の場」から、地域の暮らしを支え、「地域の課題を解決する場」に成長している。
今後は「地域の拠点機能の強化」と「ネットワーク化」を重視し、移動中で立ち寄る場所としてではなく、「道の駅」に行くこと自体が目的となるよう更なる取組みを進めることとしている。具体的には、「道の駅」相互、設置自治体、駅長等の関係者間の連携強化、「道の駅」の質を高める取組み、各省庁と連携した、既存の「道の駅」への再投資、個性ある取組みへの重点的な支援等を進めていく予定である(図表2-1-19)。
図表2-1-19 「道の駅」の多様な機能の強化
■社会インフラにおける防災・減災機能の付加
前述の道の駅の事例で見たように、社会インフラは災害時の拠点として機能を発揮することが期待されているが、社会インフラにわずかな改良や運用の改善を図ることで、防災・減災の機能を付加することも可能である。
宮城県は国土交通省と共同して、国道346号のバイパスと二線堤(万一洪水で河川が氾濫した場合、氾濫水による被害を最小限にとどめるために、従来の河川堤防と並んでつくられる第二の堤防)の両方の機能を有する道路を、高さ5mの盛土構造で合併施工し、2013年5月に供用を開始した(図表2-1-20)。これにより、国道346号における交通安全確保や渋滞緩和が図られるだけでなく、周辺を流れる鳴瀬川、吉田川が氾濫したとしても鹿島台総合支所や総合病院等を含む二線堤内の家屋約860戸と浸水面積約230haの浸水が緩和されることが期待できる。
図表2-1-20 二線堤及び国道346号鹿島台バイパス(宮城県大崎市)
また、兵庫県は、姫路市にある高架道路、高架橋梁を津波避難地として指定し、その情報をホームページに掲載したり、自主防災会が作成する地域防災マップに掲載したりして周辺住民に周知することで、災害時において、道路や橋梁の防災・減災機能が発揮できるようにしている。
このように、整備の際の工夫や運用の工夫により、社会インフラに本来の用途に加えて防災・減災の面からの機能を付加することも可能である。今後は社会インフラの本来の用途に加えて、防災・減災といった観点からも社会インフラの活用を考えていくことが求められる。
■貨物専用線の旅客線化
かつて我が国の陸上貨物輸送の大半は鉄道が担っており、臨海工業地帯等では貨物列車のみが運行する貨物専用線が敷設された。その後、大都市圏では人口の増加に伴って、こうした貨物専用線の沿線にも人々の居住地域は拡大してきた。このような背景から、既存ストックを有効活用して効率的に沿線地域の通勤・通学輸送の確保や都市機能の向上・活性化を図るため、貨物専用線を複線化、複々線化して、貨物線と旅客線の両方で利用する「貨物専用線の旅客線化」が行われている。
大阪外環状鉄道(おおさか東線)は、大阪都心外延部の城東貨物線を複線・電化し旅客線化を進めている。この路線の整備により、大阪東部地域において、都心から放射状に広がるJR、私鉄、地下鉄の各路線とのネットワークが形成され、大阪市中心部までのアクセス時間が大幅に短縮されるなど利便性が大きく向上することが期待されている。(図表2-1-21、図表2-1-22)
図表2-1-21 おおさか東線の路線図
図表2-1-22 整備効果
2008年に久宝寺〜放出(はなてん)間が開業しており、放出〜新大阪間は現在旅客線化に向けた工事が進められているところであり2018年春に開業予定である注29。
■公共施設等におけるソーラーパネルの設置
太陽光発電は、太陽電池等を用い、太陽光を直接電力に変換する発電方式であり、全国の発電量はこの10年間で約8倍になるなど急速に増えている。また、近年は住宅用太陽光発電システム以外に、産業用や公共施設等で導入が進んでいる。
例えば、新関西国際空港株式会社とSFソーラーパワー株式会社注30は、関西国際空港内にアジアの空港としては最大級の規模となる大規模太陽光発電施設(KIXメガソーラー)を建設し、2014年2月から供用を開始している(図表2-1-23)。
図表2-1-23 KIXメガソーラー
このKIXメガソーラーは、事業主であるSF関西メガソーラー株式会社が、B滑走路南側誘導路拡張予定地沿いの土地(約96,700平方メートル)及び貨物上屋等の屋根(約23,000平方メートル)を借り上げ、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用して発電事業を行うもので、初年度の予定年間電力量は約1,200万kWhとなり、関西国際空港での使用電力のうち約7%に相当する。
また、全国41箇所の下水道施設において、上部空間等を利用して太陽光発電を導入している。例えば、東京都江戸川区に位置する葛西水再生センターは、2010年4月より3836枚から成る太陽光パネルを設置し、年間約62万kWh(2012年度)を発電している(図表2-1-24)。これは、昼間時における使用電力量の約5%に相当する。
図表2-1-24 葛西水再生センター太陽光発電設備
このように既存の施設の上部スペースを利用し太陽光パネルを設置することが今後期待される。
■公的空間のオープン化
街ににぎわいをもたらしたり、道路等の維持管理費を捻出したりするために、道路空間、河川空間を活用している地方公共団体もある。
道路空間については、都市再生整備計画の区域内において道路管理者が指定した区域で余地要件注31等の基準が緩和され、オープンカフェ、広告板等を設置、運営できるようになっている。例えば、北海道札幌市大通地区では、これまでの社会実験の結果を踏まえ、2013年度よりオープンカフェ・広告板事業を実施し、オープンカフェ等の収入を道路維持管理、地域イベント等のまちづくりに還元している(図表2-1-25)。また、2013年4月、大阪府大阪市に開業したグランフロント大阪の一部を形成する「けやき並木」は、幅員11メートルで自然石の舗装が施された歩道空間であるが、その沿道にオープンカフェを開設し、通りのにぎわいを演出している(図表2-1-26)。
図表2-1-25 札幌市大通地区における例(2013年8月オープンカフェ開設)
図表2-1-26 グランフロント大阪における例(2013年4月オープンカフェ開設)
さらに、2014年度より、国家戦略特別区域法が施行されたことにより、国家戦略特別区域内において余地要件の基準が緩和され、都市再生整備計画の区域内と同様にオープンカフェ、広告板等を設置できるようになった。
河川空間についても、かつてのにぎわいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性を創造していくため、水辺に対する社会の関心を高め、様々な立場からの参画を得るための取組みを推進しており、2011年度より河川管理者が指定した区域で、民間事業者が河川敷にイベント施設やオープンカフェ等を設置することが可能になっている。例えば、名古屋市堀川、大阪市道頓堀川、広島市京橋川等ではオープンカフェの設置やイベントの開催等により、にぎわいを創出している(図表2-1-27)。
図表2-1-27 河川空間を活用したにぎわい創出の事例
(2)低利用インフラの用途転換等
人口減少社会への移行等の経済社会情勢の変化によって、利用状況が低下するインフラも出てきており、今後はますます増加していくことが予想される。こうしたインフラについて、用途を転換することで有効活用を図ることが必要である。団地の建替に伴って地域の医療・福祉拠点を設置したり、廃校となった小学校を老人福祉施設に転用するといったハコモノの用途転換が代表的な事例としてあげられるが、ここでは橋梁や鉄道施設といったインフラの用途転換事例について紹介する。
(観光施設としての活用)
■余部鉄橋「空の駅」展望施設
兵庫県美方(みかた)郡香美(かみ)町にある旧余部(あまるべ)鉄橋は、1912年(明治45年)に建設された東洋随一の鋼トレッスル橋で、我が国有数の橋梁として親しまれてきたが、1986年の列車転落事故を契機に、架け替えに向けた取組みがなされ、2010年にコンクリート製の新橋である余部橋梁が完成した。
一方、約100年間山陰本線の運行を支えてきた旧余部鉄橋の歴史と近代土木遺産としての土木技術の素晴らしさを後世に継承すべく、保存・利活用に向けた検討が進められ、余部鉄橋の一部(3橋脚3スパン)を展望施設として整備することが決まり、2013年5月に余部鉄橋「空の駅」展望施設がオープンした(図表2-1-28)。施設へのアプローチ部と施設先端部は列車走行時そのままのレール、枕木を残すなど、既存の姿を極力残すようデザインし、在りし日の姿の復元に配慮されている(図表2-1-29)。
図表2-1-28 余部鉄橋「空の駅」展望施設
図表2-1-29 旧余部鉄橋の現地保存箇所(赤色部分)
展望施設はJR山陰本線餘部駅のホームに隣接しており、地上40メートルの高さから日本海を望むことができる。このほか、展望施設の下部、道の駅「あまるべ」に隣接する場所に公園施設が整備され、歴史的構造物を活用した地域活性化の取組みが行われている。
■廃線後の線路の利活用〜レールマウンテンバイク「Gattan Go!!」
岐阜県飛騨市神岡町では、2006年に廃線となった神岡鉄道の資産を利活用するために地域の有志を中心に検討が進められ、「レールマウンテンバイク」が考案された。レールマウンテンバイクとは、市販のマウンテンバイク2台を鉄道のレール幅に合わせた特製のフレームで固定し、マウンテンバイクを2人で漕ぐことで前進するという、全国で類を見ない乗り物である注32(図表2-1-30)。鉄道レールの上を自転車が走るため、レールの継ぎ目での「ガタンゴトン」という鉄道ならではの音と振動を感じることができる。また、廃線当時の軌道・トンネル・高架等をそのままコースとして利用しており、鉄道が走っていた風景を楽しむことができることが魅力となっている。
図表2-1-30 レールマウンテンバイクの様子
2007年度の創業当初から2010年度までは連休のイベント的な運行のみであったが、2011年度からはシーズン(4〜11月)中の毎週土日、2012年度からは同期間中の平日を含めた運行を開始し、年間の利用客数は2万人を超え、単体の事業としても黒字を確保しているだけでなく、飛騨地域での宿泊客が増加するなど、周辺の観光地にも大きな経済波及効果を生み出している(図表2-1-31)。この事業は当初は観光協会によって運営され、2011年に町内の非営利活動法人である神岡・町づくりネットワークに事業移管され現在に至っている。今後の展望として、現在の旧神岡鉄道全延長の15%(2.9km)に留まっている運行区間を延長して全延長(19.9km)を利活用したいとしている。
図表2-1-31 利用者数の推移
鉱山の町を支え続けたシンボルともいえる旧神岡鉄道をその形を変えずに残したいという地域の思いが原点となって新たな観光資源を創出した事例として、全国各地の廃線を抱えた地方公共団体や団体からの視察も多く、注目を浴びている。
(移設による有効活用)
横浜市の新山下運河に架かる霞橋は、老朽化による架替工事が行われ、2013年3月に新たな霞橋として開通した。その架替工事で使われたのは、常磐線の隅田川橋梁として1896年(明治29年)に建設され、その後、1929年(昭和4年)に鶴見区の旧江ヶ崎跨線橋に移設され再利用されていたプラットトラス注33であった(図表2-1-32)。
図表2-1-32 トラス橋の変遷
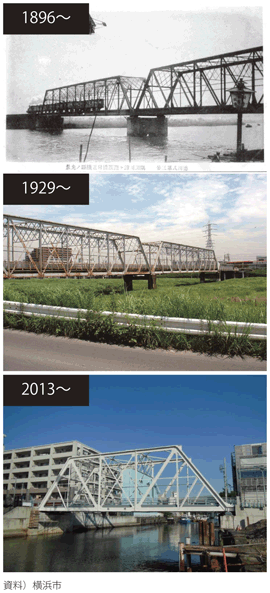
1896年の架橋時、複線式のプラットトラスは我が国初であり、広く外国会社に競争設計され、英国のHandyside社製が採用された。当時最大級の規模、鋼鉄道橋の採用、当時の様式と異なるデザイン等、先進的な橋梁であった。
架橋から32年後の1928年に、機関車の荷重増加に伴い撤去されたが、新鶴見操車場開業により分断される地域を結ぶ橋として移設され、旧江ヶ崎跨線橋として1929年に竣工した。その後、老朽化が進み、道路幅員も狭いことから、2005年に架替えが決定し、2009年に撤去された。
このプラットトラスは、「かながわの橋100選」「鉄の橋100選」「日本の近代土木遺産」に選定されるなど、近代土木遺産として歴史的価値が高いとされていたことから、時期を同じくして架替え予定であった霞橋へその損傷の少ない部材を再利用して転用されることとなった注34。
この事例に見るように、役目を終えるはずであったインフラであっても、貴重な土木遺産を後世に継承しつつ、インフラを再利用することができる。
当初の役割を終えたインフラでも、その構造物自体は引き続き利用可能というケースは今後も出てくることが想定される。将来的な再利用や転用のしやすさという視点を持って社会インフラの整備を行っていくことが重要となる。
(3)イノベーションによる有効活用
社会インフラの運用を効率化させる方法の一つとしてイノベーションがある。イノベーションというと新しい技術の活用というイメージが強いが、ここでは、技術革新に限らず、経済・社会にインパクトを与える新しい取組み等を含めた広義の意味で捉えることとする注35。
既存の社会インフラを有効に活用するイノベーションとしては、IT等の新技術やソフトな手法が考えられる。前者については、新技術を導入することによって、混雑等の非効率性の原因を特定したり、運用を効率化したりするものである。後者については、ハードの整備だけでなく、ソフト面の工夫を行うことで、社会インフラの運用を効率的に改善するものである。
以下ではこれらの具体的な事例について見ていく。
(新技術の導入による効率化)
■広域航法(RNAV、RNP AR)の導入
航空機の運航にあたって、従来の航法では、無線施設等の地上施設からの電波を受信しながら飛行するという受動的な飛行を行っていた。したがって、運航ルートは地上施設の設置場所に依存していた。
しかし、航空機側の航法技術の進歩により、現在、無線施設の他GPS等からの信号をもとに飛行コースを柔軟に設定できる飛行経路が順次導入されている(RNAV、RNP AR)(図表2-1-33)。これにより、地上施設の設置場所の制約を受けず、自立的な飛行が可能になり、就航率の向上、経路の短縮、燃料の削減やCO2の削減等の効果を生んでいる。
図表2-1-33 広域航法(RNAV、RNP AR)の導入
例えば、秋田県にある大館能代空港のRNP AR進入方式注36では、従来の航法と比べ約50km経路が短縮されている。また、滑走路に進入するにあたっては、当該地点で滑走路が見えなければ着陸を行うことができない高度(進入限界高度)が定められているが、従来の航法では、944フィート(約288m)の高度で着陸できるかが決まるのに対し、RNAV、RNP ARでは300フィート(約90m)の高度で着陸できるかが決まり、より視界が悪い天候の場合でも飛行することが可能となっている。
■プローブ情報の活用
プローブ情報とは、個々の車両が走行した位置や速度、前後左右の加速度等の情報であり、各車両からのプローブ情報を収集することにより、きめ細やかな道路交通情報の把握・提供が可能となり、渋滞対策、交通安全、災害対応等に利用されている(図表2-1-34)。
図表2-1-34 プローブ情報の収集
例えば、三重県にある四日市IC付近を先頭とする渋滞について、当初はICからの合流がその原因ではないかと考えられていたが、プローブ情報を利用して渋滞の状況を正確に把握したところ、IC分岐手前のサグ(下り坂から上り坂にさしかかる凹部)が、渋滞発生の大きな要因となっていることが新たに判明した。今後は、こうした分析結果を踏まえ、きめ細やかな対策を行うことで、交通の円滑化を促進していくことが期待されている。
(ソフトな手法による利用の効率化)
■成田空港における同時離着陸方式の導入
航空機の発着にあたっては、安全性を確保するため、1機ごとに、周囲の航空機と一定の間隔を取ることとなっている(現在の国際基準では、3〜6マイル(5〜11km)程度)(図表2-1-35)。このため、以前の成田空港では、例えば出発が連続する場合は、A滑走路から出発した航空機がある程度離れるまでB滑走路からの出発機は待機させるという、制限的な運用を行っていたが、増大する航空需要に対応するため、A、Bの両滑走路から同時に離着陸するという独立運用を可能とする同時離着陸方式の検討を行ってきた。
図表2-1-35 同時離陸のイメージ(北風時の例)
同時離着陸方式を導入するには、国際ルール(ICAOの指針)が定められており、成田空港は同時着陸の指針注37については満たしているものの、離陸直後に15度以上分岐するという同時離陸の指針については、飛行ルートを分岐させると騒音影響区域が広がるため、満たすことができていなかった(図表2-1-36)。
図表2-1-36 同時離着陸の国際ルール
この指針は各国の航空当局が安全性を検証することにより特例を定めることが可能であるとされていることから、国土交通省において安全性検証を行い、成田空港において必要なリスク低減策(離陸後の経路逸脱を監視するための管制席の設置等)をとることで同時離陸が可能と判断し、2011年10月に導入に至った。
同時離着陸方式の導入の結果、成田空港の年間発着枠は2010年10月時点の22万回から23.5万回に増加した。このように、従来の離着陸の運用を見直すことで、滑走路等の整備を行わずとも離着陸を効率化することが可能となるケースもある。なお、その後、誘導路新設や駐機場増設等の施設面の整備等により、2013年3月には27万回に増加している。
以上のようにITをはじめとした新技術の活用により、既存の社会インフラをより効率的に活用することが可能となる。また、ハードの整備等を伴わなくても、従来の運用を見直すことに既存の社会インフラをより効率的に使うためのヒントが隠されていることもある。今後は、社会インフラに関しても、積極的なイノベーションを実現し、社会インフラをより賢く使うことが求められる。
注29 この事業においては、地元公共団体とJR西日本の出資により設立した第三セクターの大阪外環状鉄道株式会社が旅客線の建設及び施設を保有し、JR西日本が運行を行う上下分離方式が採用されている。
注30 ソーラーフロンティア株式会社と株式会社日本政策投資銀行が設立した共同投資会社。
注31 道路の敷地外に余地がないためにやむをえない占用であることという要件。
注32 基本的には2人乗りであるが、様々なタイプの補助席を取り付けることで大人数や幅広い年齢層に対応できるようにしている。
注33 3本の部材を三角形に連結した構造をトラスといい、これを連続して組み合わせて橋としたものをトラス橋という。
注34 霞橋は土木学会平成25年度田中賞作品部門を受賞している。
注35 例えばシュンペーターは、イノベーションを1)新しい製品の生産、2)新しい生産方法の導入、3)新しい販路の開拓、4)新しい供給源の開拓、5)新しい組織の実現導入の5つに分類している。
注36 2013年12月現在、11空港にRNP AR進入方式を導入している。
注37 成田空港のA、B滑走路は2,500m離れているため、1,310m以上離れていることというICAOの指針は満たしている。