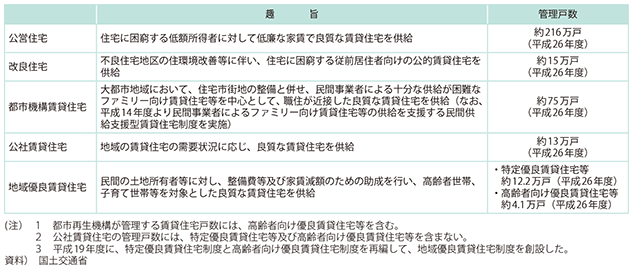第5章 心地よい生活空間の創生
第1節 豊かな住生活の実現
■1 住生活の安定の確保及び向上の促進
本格的な少子高齢社会の到来、人口・世帯数の減少、厳しい雇用・所得環境等の社会経済情勢の変化や、住生活を支えるサービスに対するニーズ等を踏まえ、平成23年3月に閣議決定した、23年度から32年度を計画年度とする新たな住生活基本計画(全国計画)に基づき、1)安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築、2)住宅の適正な管理及び再生、3)多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備、4)住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保という4つの目標の達成に向け、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を推進している。
(1)安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築
安全・安心な住宅及び居住環境の整備を図るため、大規模な地震等に備え、住宅・建築物の耐震改修等を促進するとともに、高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世帯が交流し、安心して健康に暮らすことができる「スマートウェルネス住宅・シティ」の実現に向けた取組みを推進することとしている。また、低炭素社会の実現に向けて、住宅の省エネルギー性能の向上、地域材の利用の促進等を図っている。
さらに、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、住宅及び住宅市街地における高齢者等の生活の利便性の向上を図るとともに、住生活にゆとりと豊かさをもたらす、美しい街並みや景観の維持及び形成を図っている。
(2)住宅の適正な管理及び再生
マンションのストック戸数は約613万戸(平成26年末現在)に達し、国民の重要な居住形態となっているが、適切な維持管理や再生を推進していく上で、高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足、管理費滞納等による管理不全等の様々な課題への対応が必要となっている。
このため、外部の専門家の活用、管理費滞納に対する措置、管理状況等の情報開示を内容とする「マンション標準管理規約」を平成28年3月に改正した。
また、老朽化マンションの再生が円滑に行われるよう、マンション敷地売却制度の創設、容積率の緩和特例の創設等を内容とする「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」が26年6月に成立し、同年12月に施行された。
さらに、住宅団地の再生のための「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を平成28年2月に閣議決定し、国会に提出した。
(3)多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備
1)既存住宅が円滑に活用される市場の整備
「中古住宅・リフォームトータルプラン」(平成24年3月)及び「中古住宅の流通促進・活用に関する研究報告書」(25年6月)に基づき、既存住宅が円滑に活用される市場の整備として、(ア)及び(イ)の取組みを推進した。
また、既存住宅の建物評価手法の改善に取り組むとともに、その取組みを既存住宅市場及び住宅金融市場に定着させるため、25年9月より「中古住宅市場活性化ラウンドテーブル」を開催し、既存住宅流通に携わる民間事業者等と金融機関等との間で意見交換を行い、27年3月、「中古住宅市場活性化ラウンドテーブル報告書」を取りまとめた。
加えて、26年度税制改正において、既存住宅の取得後に耐震改修工事を行う場合についても住宅ローン減税等各種特例措置の適用対象とすることとした。また、26年度税制改正において、既存住宅・リフォーム市場拡大の起爆剤となりうる買取再販事業で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置を創設し、28年度税制改正において、適用期限を2年間延長した。さらに、27年度税制改正において新たに、買取再販事業者に課される不動産取得税を軽減する措置を創設した。
(ア)消費者が安心してリフォームができる市場環境の整備
住宅リフォームを検討する消費者は、費用や事業者選びに関して不安を有しており、これを取り除くことが住宅リフォーム市場の拡大には必要である。
このため、「住まいるダイヤル」((公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)における電話相談業務及び具体的な見積書についての相談を受ける「リフォーム無料見積チェックサービス」、各地の弁護士会における「専門家相談制度」等の取組みを進めている。平成27年度はリフォームに関する電話相談が9,836件、リフォーム見積チェックが820件、リフォームに関する専門家相談が899件となっている。
また、消費者が安心してリフォームができるよう、施工中の検査と欠陥への保証がセットになったリフォーム瑕疵保険制度の27年度の加入申込件数は3,421件、マンション大規模修繕工事を対象とした大規模修繕工事瑕疵保険制度の同年度の加入申込件数は955棟となっている。
なお、事業者が保険に加入するには、建設業許可の有無や実績等の条件を満たした上で、住宅瑕疵担保責任保険法人に事業者登録をする必要があり、登録された事業者は(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会のウェブサイトで公開されるため、消費者は事業者選びの参考とすることができる。
さらに、「住宅リフォーム事業者団体登録制度」において、住宅リフォーム事業者の業務の適正な運営の確保及び消費者への情報提供等を行うなど、一定の要件を満たす住宅リフォーム事業者の団体を国が登録することにより、住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備を図っている。
(イ)消費者が安心して既存住宅を取得できる市場環境の整備
既存住宅購入を検討する消費者は、その品質や性能に不安を有しており、これを取り除き、安心して既存住宅を購入できるような環境を整備することが既存住宅流通市場の拡大には必要である。
このため、消費者が既存住宅の状態を把握するための現況検査に係る指針である「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(平成25年6月策定)に添った、適正なインスペクションの普及促進を図っている。
また、検査と欠陥への保証がセットになった既存住宅売買瑕疵保険制度については、25年度において保険期間が短く比較的安価な保険商品が新たに開発されるなど、保険商品のバリエーションが広がっているところであり、27年度の加入申込件数は、9,309件と、徐々に利用件数が増加している。
なお、消費者は、リフォーム瑕疵保険と同様に登録事業者をウェブサイトで検索し、事業者選びの参考とすることができる。
2)将来にわたり活用される良質なストックの形成
(ア)住宅の品質確保
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、新築住宅の基本構造部分に係る10年間の瑕疵担保責任を義務付けるとともに、新築住宅及び既存住宅に対し、耐震性、省エネ対策、劣化対策等、住宅の基本的な性能を客観的に評価し、表示する住宅性能表示制度を実施している。平成27年度の実績は、設計図書の段階で評価した設計住宅性能評価書の交付が200,050戸、現場検査を経て評価した建設住宅性能評価書(新築住宅)の交付が168,514戸、建設住宅性能評価書(既存住宅)の交付が388戸となっている。
建設住宅性能評価を受けた住宅に係る紛争については、指定住宅紛争処理機関である全国各地の弁護士会が裁判によらず迅速かつ適正な処理を図ることとしており、住宅紛争処理支援センターがその支援業務を行っている。同センターは、住宅に関する様々な相談も受け付けている。27年度の実績は、指定住宅紛争処理機関における建設住宅性能評価書が交付された住宅に係る紛争処理の申請受付件数31件、同センターの建設住宅性能評価書が交付された住宅に係る電話相談受付件数900件となっている。
(イ)住宅の長寿命化への取組み
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、住宅の構造や設備について、一定以上の耐久性、維持管理容易性等の性能を備えた住宅(「長期優良住宅」)の普及を図っている(平成27年度認定戸数:104,633戸)。
また、既存住宅の長寿命化に資するリフォームの先進的な取組み等に対する支援を行っている。
(ウ)木造住宅の振興
7割を超える国民が木造住宅を志向する注1など、国民の木造住宅に対するニーズを踏まえ、良質な木造住宅ストックの形成を図るため、地域材等資材供給から設計・施工に至るまでの関連事業者からなるグループによる、長期優良住宅や認定低炭素住宅、ゼロエネルギー住宅の建設に対する支援を行っているほか、木造住宅の建設等に係る人材育成に対する支援を行っている。
また、平成28年度早期を目途に、CLTを用いた建築物の一般的な設計法を策定するため、実大実験等の技術的検討を行っている。
3)多様な居住ニーズに応じた住宅の確保と需給の不適合の解消
(ア)住宅金融
民間金融機関による相対的に低利な長期・固定金利住宅ローンの供給を支援するため、(独)住宅金融支援機構では証券化支援業務を行っている。当業務には、民間金融機関の住宅ローン債権を集約し証券化するフラット35(買取型)と民間金融機関自らがオリジネーター注2となって行う証券化を支援するフラット35(保証型)があり、フラット35(買取型)における平成28年3月末までの実績は、買取申請件数1,067,575件、買取件数750,537件で、331の金融機関が参加している。また、フラット35(保証型)における28年3月末までの実績は、付保申請件数20,148件、付保件数12,416件で、5金融機関が参加している。
証券化支援業務の対象となる住宅については、耐久性等の技術基準を定め、物件検査を行うことで住宅の質の確保を図るとともに、証券化支援業務の枠組みを活用し、耐震性、省エネルギー性、バリアフリー性及び耐久性・可変性の4つの性能のうち、いずれかの基準を満たした住宅の取得に係る当初5年間(長期優良住宅等については当初10年間)の融資金利を引き下げるフラット35Sを実施している。
また、同機構は、災害復興住宅融資やサービス付き高齢者向け賃貸住宅融資等、政策的に重要でかつ民間金融機関では対応が困難な分野について、直接融資業務を行っている。
(イ)住宅税制
平成28年度税制改正において、空き家が放置され、それが周辺の生活環境へ悪影響を及ぼすことを未然に防ぐ観点から、相続により生じた古い空き家(耐震性のあるものに限る。)又はそれを除却した後の敷地を譲渡した場合の譲渡所得について3,000万円を特別控除する制度を創設した。また、世代間の助け合いによる子育てしやすい環境整備を図る観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度を創設した。さらに、住宅取得者の初期負担を軽減し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図る観点から、新築住宅に係る固定資産税を減額する措置の適用期限を平成30年3月31日まで2年延長した。
また、29年4月の消費税率10%引上げ後の反動減等に対応する観点から、住宅ローン減税の大幅拡充に加え、すまい給付金の拡充(最大給付額30万円→50万円等)、贈与税の非課税措置の拡充(最大限度額1,500万円→3,000万円)を措置することとしている。こうした措置により、若い世代の住宅取得が促進されるとともに、住宅取得等を検討している人々の予見性が高まり、住宅市場の安定に資することが期待される。
(ウ)賃貸住宅市場の整備
賃貸住宅市場においては、戸建て住宅、マンション等の持家ストックの賃貸化等を通じたストックの質の向上を図るため、定期借家制度の普及、DIY型賃貸借注3の指針整備等の環境整備に取り組んでいる。
(エ)空き家対策の推進
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月に全面施行された。市区町村が地域の実情に応じて、空家等対策計画を促進するとともに、空き家や空き建築物等の活用・除却等を推進している。
(4)住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
1)公的賃貸住宅の供給
住宅に困窮する低額所得者に対し地方公共団体が供給する公営住宅に対し的確に支援するとともに、各地域における居住の安定に特に配慮が必要な高齢者等の世帯を対象とした良質な賃貸住宅の供給を促進するため、公営住宅を補完する制度として地域優良賃貸住宅制度を位置付けており、これらを含む公的賃貸住宅の整備や家賃の減額に要する費用等に対して助成を行っている。
また、解雇等により住居の退去を余儀なくされる者に対する住宅セーフティネットを確保するため、本来の入居対象者以外の離職者に公営住宅等の空家を利用させる場合の手続の簡素化等、離職者の居住安定確保に向けた対策を講じてきたところである。