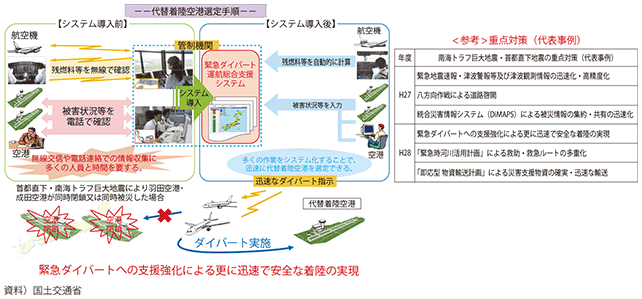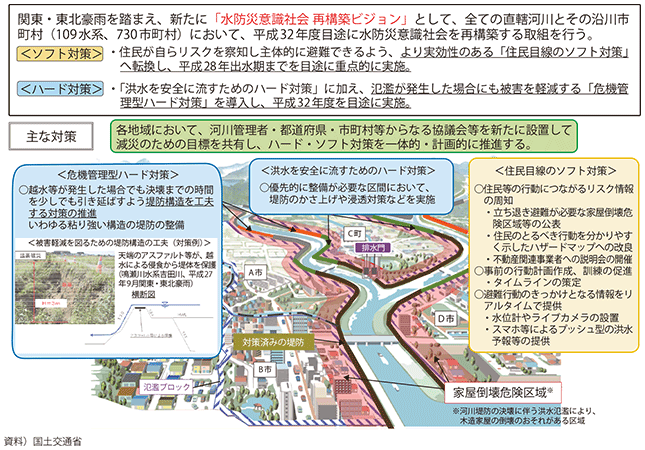■1 激甚化する気象災害、切迫する巨大地震への対応
(1)新たなステージに対応した防災・減災のあり方
近年、時間雨量50mmを超える雨が頻発するなど、雨の降り方が、局地化・集中化・激甚化している。また、平成26年9月には御嶽山の噴火も発生し、大規模な火山噴火がいつ起きてもおかしくない状況となっている。それらの状況を「新たなステージ」として捉え、それに対応した今後の検討の方向性について27年1月に取りまとめた。
「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」では、比較的発生頻度の高い降雨等に対しては、施設で守ることを基本とし、それを超える降雨等に対しては、「少なくとも命を守り、社会経済に壊滅的な被害が発生しない」ことを目標として、ソフト対策に重点を置いて対応するという考え方を示した。具体的には、1)「命を守る」ためには、避難勧告が出たら逃げるという「指示待ち」型避難だけでなく、住民自らが雨量等の「状況情報」に基づき「主体的行動」型避難ができるようにすることが必要、2)「社会経済の壊滅的な被害を回避する」ためには、最悪の事態を想定し、国、地方公共団体、事業者等の関係者が危機感を共有して、社会全体で対応することが必要という考え方であり、この考え方を踏まえ様々な取組みが進められている。
(2)水災害に関する防災・減災への対応
我が国における平成25 年の伊豆大島をはじめとする災害、米国における24 年のハリケーン・サンディによる高潮被害等、台風等に伴う大規模な水災害が頻発化・激甚化している。こうした状況を踏まえ、26年1月に国土交通大臣を本部長とする「国土交通省 水災害に関する防災・減災対策本部」、同本部の下に「地下街・地下鉄等ワーキンググループ」、「防災行動計画ワーキンググループ」を設置し、検討を進めている。
「地下街・地下鉄等ワーキンググループ」においては、地下空間の課題への対応を取りまとめ、関係機関に周知した。これも踏まえ、三大都市圏等において、地下街・地下鉄及び接続ビルが連携した浸水対策が進められている。
「防災行動計画ワーキンググループ」においては、市町村長が避難勧告等を適切なタイミングで発令できるよう支援する、全国の直轄河川を対象とする避難勧告等の発令に着目したタイムラインの策定や、荒川下流域において、自治体、鉄道、電力、通信、福祉施設など20機関、37部局もの多数の関係者が連携したタイムラインを策定した。これを踏まえ、石狩川(北海道)、球磨川(熊本県)をはじめ、全国各ブロックで協議会を設置し、多数の関係者が連携したタイムラインの検討を開始した。
27年8月には、「第3回 国土交通省 水災害に関する防災・減災対策本部」を開催し、「壊滅的被害回避ワーキンググループ」の設置や、企業等と連携した取組みを検討するため、地方整備局が中心となって企業等へのヒアリングを実施することを決定した。本ワーキンググループは、同年1月に公表された「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」において、「少なくとも命を守り、社会経済に対して壊滅的な被害が発生しない」ことを目標とし、危機感を共有して社会全体で対応することが必要であるという方向性が示されたことを踏まえ、社会経済の壊滅的な被害を回避するための対策の検討を目的に、「国土交通省 水災害に関する防災・減災対策本部」の下に設置されたものである。関東、中部、近畿の各地方整備局においては、地域ごとにそれぞれ協議会等を設置し、企業へのヒアリングや被害想定の検討等が進められている。
(3)気候変動への対応
地球温暖化に伴う気候変動により水害(洪水、内水、高潮)、土砂災害、渇水被害の頻発化、激甚化が懸念されている。平成27年8月には、社会資本整備審議会より「水災害分野における気候変動適応策のあり方について〜災害リスク情報と危機感を共有し、減災に取り組む社会へ〜」が答申された。
激化する災害に対処するため、比較的発生頻度の高い外力に対し、施設により災害の発生を防止し、施設の整備等を着実に進めることが適応策としても重要である。さらに、施設の能力を上回る外力に対しては、施設の運用、構造、整備手順等の工夫を図る等、施策を総動員してできる限り被害を軽減する施策に取り組む必要がある。施設の能力を大幅に上回る外力に対しては、ソフト対策を重点に壊滅的被害を回避するための施策を推進していく必要がある。
また、沿岸部の適応策については「沿岸部(港湾、海岸)における気候変動の影響及び適応の方向性検討委員会」において検討を行い、27年6月に港湾、同年7月に海岸における取組みの方向性を取りまとめた。
上記の検討成果も踏まえ、政府全体の計画として、「気候変動の影響への適応計画」が27年11月に閣議決定されるとともに、国土交通省においては「国土交通省気候変動適応計画」を取りまとめた。今後、これら計画を踏まえ、気候変動の影響への適応策に取り組む。
(4)南海トラフ巨大地震、首都直下地震への対応
南海トラフ巨大地震が発生した場合、関東から九州までの太平洋側の広範囲において、震度6から震度7の強い揺れが発生し、巨大な津波が短時間で、広範囲にわたる太平洋側沿岸域に襲来することが想定されている。死者は最大で約32万人にのぼり、交通インフラの途絶や沿岸の都市機能の麻痺等の深刻な事態が発生し、我が国全体の国民生活・経済活動に極めて深刻な影響が生じることが想定されている。
また、首都直下地震が発生した場合、首都圏の広域において震度6から震度7の強い揺れが発生することが想定されており、首都圏は、他の地域と比べ人口や建築物、経済活動が極めて高度に集積していることから、人的・物的被害や経済被害が甚大なものになると予想される。さらに、首都圏には政治・行政・経済の首都中枢機能も集積しているため、国全体の経済活動等への影響や海外への波及も懸念されている。
これらの国家的な危機に備えるべく、多くの社会資本の整備・管理や交通政策、海上における人命・財産の保護等を所管し、また全国に多数の地方支分部局を持つ国土交通省では、平成25年に「国土交通省南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策本部」及び「対策計画策定ワーキンググループ」を設置し、省の総力をあげて取り組むべきリアリティのある対策を「国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画」及び「国土交通省首都直下地震対策計画」として、26年4月1日に策定した。南海トラフ巨大地震については、本対策計画の策定とあわせて、地方ブロックごとに、より具体的かつ実践的な「地域対策計画」を策定した。同年7月及び27年8月には「南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策本部」において、両対策計画のこれまでの実施状況をフォローアップしたうえで重点対策を決定した。
28年度の重点対策の具体事例としては、昨年度策定した「首都直下地震道路啓開計画」、いわゆる「八方向作戦」の充実や、発災直後の輸送体制を確保するため、1)河川も活用し、輸送ルートを多重化する「緊急時河川活用計画」の策定、2)陸海空の輸送ルートをフル活用して、災害支援物資を迅速かつ確実に輸送する「即応型災害支援物資輸送計画」の策定、3)地震によって閉鎖された空港へ向かう飛行機の代替空港への着陸(ダイバート)を迅速に行うための、最適な代替空港を即時選定する「緊急ダイバート運航総合支援システム」の本格運用等を決定した。