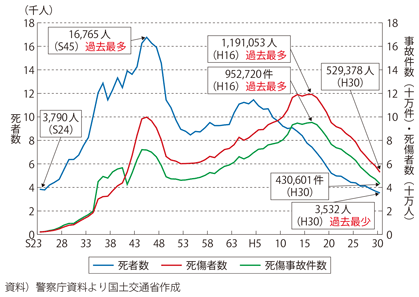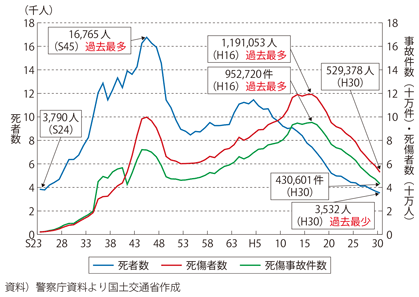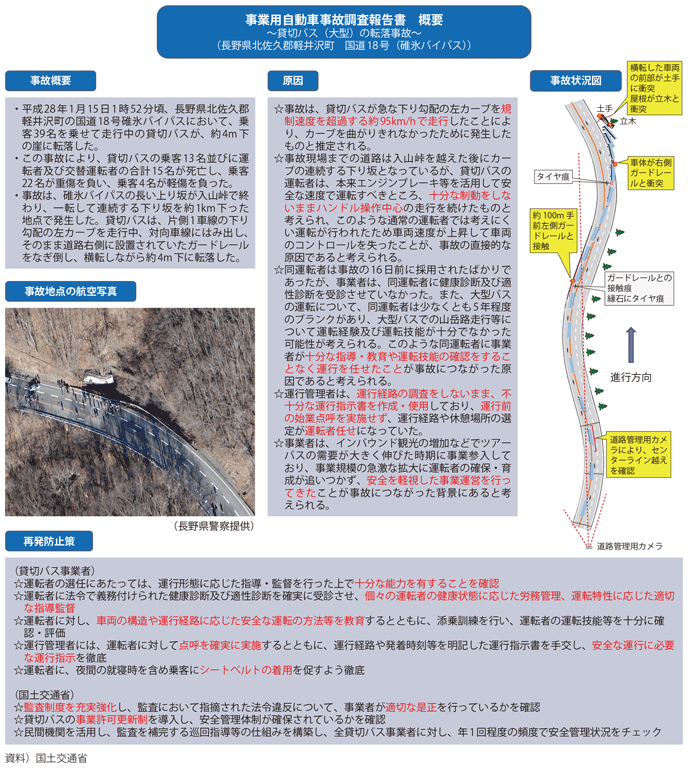7)運転者の体調急変に伴う事故防止対策の推進
平成26年4月に改訂した、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」で推奨している、睡眠呼吸障害、脳疾患、心疾患等の主要疾病の早期発見に寄与する各種スクリーニング検査をより効果的なものとして普及させるため、27年9月に、「事業用自動車健康起因事故対策協議会」を立ち上げ、普及に向けた課題を整理するための事業者へのアンケート調査等を行った。また、事業者による運転者の脳検診受診等を促進するため、30年2月に「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」を策定した。
8)国際海上コンテナの陸上運送の安全対策
国際海上コンテナの陸上運送の安全対策を充実させるため、平成25年6月に新たな「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」等を策定し、地方での関係者会議や関係業界による講習会等を通じ、ガイドライン等の浸透や関係者と連携した実効性の確保に取り組んでいる。
(6)自動車の総合的な安全対策
1)今後の車両安全対策の検討
平成28年6月に取りまとめられた交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会の報告を踏まえ、子供・高齢者の安全対策、歩行者・自転車乗員の安全対策、大型車がからむ重大事故対策、自動走行など新技術への対応を中心に車両安全対策の推進に取り組んでいる。また、高齢運転者による事故防止対策として、29年3月の関係省庁副大臣等会議における中間取りまとめに基づき、衝突被害軽減ブレーキについて、国連の場において国際基準の策定に向けた検討を行うとともに、基準の策定に先立ち、国による性能認定制度を創設するなど、「安全運転サポート車(サポカーS)」の普及啓発・導入促進に取り組んだ。
2)安全基準等の拡充・強化
自動車の安全性の向上を図るため、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において策定した国際基準を国内に導入することを通じ、シートベルト非装着警報装置の義務付け対象座席を拡大するなど、保安基準の拡充・強化を図った。また、公道を走行するカートについては、他の交通からの視認性の向上及びシートベルトの設置等の安全確保策について検討を行った。
3)先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及の促進
産学官の連携により、衝突被害軽減ブレーキなど実用化されたASV技術の本格的な普及を促進するとともに、平成28年度より開始した第6期ASV推進計画において、路肩退避型等発展型ドライバー異常時対応システムの技術的要件等の検討に取り組んだ。
4)自動車アセスメントによる安全情報の提供
安全な自動車及びチャイルドシートの開発やユーザーによる選択を促すため、これらの安全性能を評価し結果を公表している。平成30年度より、ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の評価を新たに開始した。
5)自動運転の実現に向けた取組み
WP29において、自動運転に係る基準等について検討を行う各分科会等の共同議長又は副議長として議論を主導している。自動運転の主要技術である自動ハンドルについて、平成30年10月には車線変更に関する基準を発効し、手放しの状態での車線維持等に関する基準策定に向けて検討を開始するなど、着実に国際基準の策定を進めている。また、国内においても、30年4月に策定された自動運転に係る制度整備大綱を踏まえ検討を実施し、31年1月にとりまとめた、自動運転車等の設計・製造過程から使用過程にわたる総合的な安全確保に必要な制度のあり方に係る交通政策審議会報告書に基づき、「道路運送車両法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出する等、必要な制度整備に取り組んでいく。
6)自動車型式指定制度
複数の自動車メーカーにおける、型式指定車の完成検査における不適切な取扱いを受け、平成30年3月にとりまとめられた「適切な完成検査を確保するためのタスクフォース」の中間とりまとめ等を踏まえ、30年10月に道路運送車両法に基づく省令の一部改正等を行い、これまで通達において規定されていた完成検査員の選任に係るルールを省令等に規定した他、完成検査の記録を書き換えできなくする措置や、型式指定制度の適正な運用の確保のための勧告制度に係る規定を新設した。また、完成検査における不適切な取扱いを行っている自動車メーカーに対する是正措置命令の創設等を行うための「道路運送車両法の一部を改正する法律案」を31年3月に国会に提出した。
7)リコールの迅速かつ着実な実施・ユーザー等への注意喚起
自動車のリコールの迅速かつ確実な実施のため、自動車メーカー等及びユーザーからの情報収集に努め、自動車メーカー等のリコール業務について監査等の際に確認・指導するとともに、安全・環境性に疑義のある自動車については、(独)自動車技術総合機構交通安全環境研究所において技術的検証を行っている。また、リコール改修を促進するため、ウェブサイトやソーシャル・メディアを通じたユーザーへの情報発信を強化した。さらに、自動車不具合情報の収集を強化するため、「自動車不具合情報ホットライン」(
www.mlit.go.jp/RJ/)について周知活動を積極的に行っている。
また、国土交通省に寄せられた不具合情報や事故・火災情報等を公表し、ユーザーへの注意喚起が必要な事案や適切な使用及び保守管理、不具合発生時の適切な対応について、ユーザーへの情報提供を実施している。特に、「衝突被害軽減ブレーキは万能ではありません!」について報道発表等を通じ、ユーザー等への注意喚起を行った。
なお、平成30年度のリコール届出は、自動車は408件で対象台数は822万台、チャイルドシートは1件でその対象は5,022台であった。
8)自動車検査の高度化
不正な二次架装
注の防止やリコールにつながる車両不具合の早期抽出等に資するため、情報通信技術の活用による自動車検査の高度化を進めている。
(7)被害者支援
1)自動車損害賠償保障制度による被害者保護
自動車損害賠償保障制度は、クルマ社会の支え合いの考えに基づき、自賠責保険の保険金支払い、ひき逃げ・無保険車事故による被害者の救済(政府保障事業)を行うほか、重度後遺障害者への介護料の支給や療護施設の設置等の自動車事故対策事業を実施するものであり、交通事故被害者の保護に大きな役割を担っている。
2)交通事故相談活動の推進
地方公共団体に設置されている交通事故相談所等の活動を推進するため、研修や実務必携の発刊を通じて相談員の対応能力の向上を図るとともに、関係者間での連絡調整・情報共有のための会議やホームページでの相談活動の周知を行うなど、地域における相談活動を支援している。これにより、交通事故被害者等の福祉の向上に寄与している。
(8)機械式立体駐車場の安全対策
機械式駐車装置の安全性に関する基準について、国際的な機械安全の考え方に基づく質的向上と多様な機械式駐車装置に適用するための標準化を図るため、平成29年5月にJIS規格を制定した。
また、同年12月に社会資本整備審議会「都市計画基本問題小委員会都市施設ワーキンググループ」で、今後の機械式駐車装置の安全確保に向けた施策の具体的方向性についてとりまとめ、平成30年7月には、このとりまとめに基づく「設置後の点検等による安全確保」の推進に向けて、「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」を策定した。