|
1 運営状況
わが国の国際航空事業は,昭和29隼2月,日本航空(株)が戦後はじめての国際線として,東京-ホノルル-サンフランシスコ線および東京-沖縄線を開設して以来,すでに10年の歳月をへ,現在では 〔III−8表〕のとおり,全日本空輸(株)が鹿児島-沖縄線を運営しているほかは,日本航空(株)がもつぱらその運営に当つている。
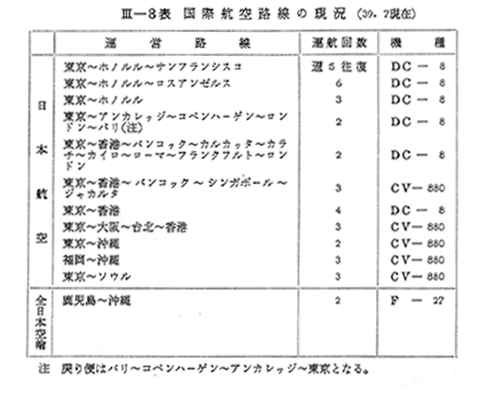
これらの国際航空路線のうち,昭和38年度中に新規開設された路線はないが,既設路線においては,4月に東京-ホノルル-ロスアンゼルス線を1便増便したほか,7月から,沖縄線の使用機材をDC-6BからCV-880に,10月から,南回り欧州線の使用機材をCV-880からDC-8へ切り変え,また,同じく10月から,CV-880による東京-香港直航便を2便再開する等輸送力増強,国際競争力の強化を図つて来た。
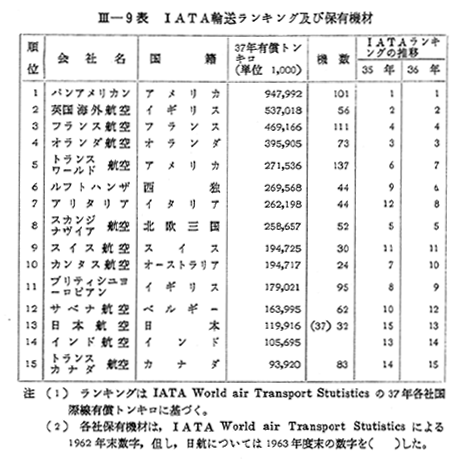
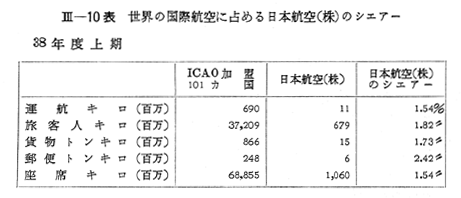
イ 概要
まず,運航キロは,2164万9000キロで,昭和37年度に比較して14%の増加であるが,昭和37年度の対前年度比19.1%に比較すると多少鈍化している。
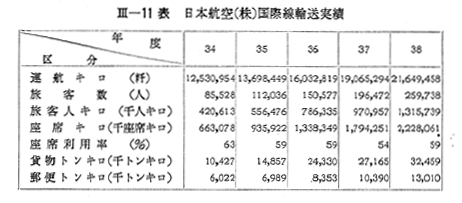
これは,主として,南回り欧州線の平年度化,太平洋線の増便および香港直行便の開設による増加があつた反面,DC-7Fによる貨物専用便を運休したことおよび大阪空港のジェット寄港が不可能なたあ,大阪〜沖縄線を減便したこと等によるものである。
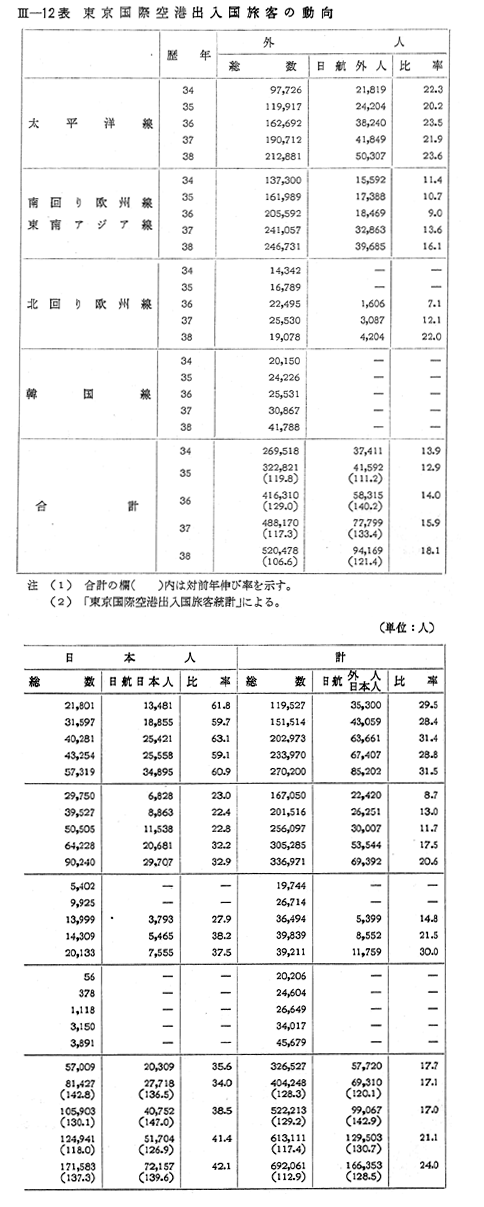
すなわち 〔III−12表〕にみるとおり,昭和38年度において日本人旅客ば,対前年度比37%増であるのに対し,外人旅客は,7%増と従来の増加率からすれば,非常に悪く航空国際収支上大きな問題となつている。
ロ 旅客
まず,太平洋線においては,ロスアンゼルス線の増便等により,座席キロが対前年度比19%増の12億3508万2000座席キロに増加したのに対し,旅客人キロが27%増の7億4535万8000人キロと大幅に上回つたため,座席利用率は,昭和37年度の57%から,昭和38年度は,60%と向上している。 旅客人キロが増加したのは,主として,ロスアンゼルス線およびホノルル線の増加によるものであり,それぞれ対面年度比50%増の4億3464万人キロおよび43%増の3087万8000人キロとなつている。なおロスアンゼルス線における座席利用率も63%とサンフランシスコ線(59%)に比較して高く,太平洋線におけるロスアンゼルス線の重要性が注目される。 また 〔III−12表〕のとおり,太平洋線における日本人の日本航空利用率は,昭和38年61%と他の路線と比較してかなり高く,また,外人の積取比率も24%となつている。これは,一つには,同路線の便数が多く,運航密度が高く利用しやすいことによるものと思われる。 日本航空(株)の国際線輸送に占める太平洋線の地位を座席キロおよび旅客人キロの路線別構成比にみると 〔III−15表〕のとおりであつて,これによれば南回り欧州線,北回り欧州線が整備されるにしたがつて,太平洋線の相対的地位は低下していることがわかるが,昭和38年度においても,旅客人キロにおいて56.6%,座席キロにおいて55.5%が太平洋線であつて,依然として,日本航空(株)の経営の中心であることに変りはない。 北回り欧州線は,昭和37年度と比較して,座席キロがほぼ横這いであつたにもかかわらず,旅客人キロが41%増と著しい伸びを示したため,座席利用率も昭和37年度の40%から一躍56%と改善された。 また南回り欧州線では,同路線が昭和37年10月から開設されたため,昭和38年度が非常に大きな伸びを示したようにみられるが,実際は,平年度化したものである。しかしながら,この路線においても,座席キロの伸び率よりも旅客人キロの伸び率の方が著しく,座席利用率は,昭和37年度の36%から,45%と向上している。 東南アジア線は,10月に東京-香港直航便を運航したこと等のため,座席キロが対前年度比12%増となつたが,旅客人キロが他の路線ほど伸びずに15%増にとどまつたため,座席利用率の改善はほとんどみられなかつた。しかしながら,東南アジア線における座席利用率は,昭和37年度65%,昭和38年度66%と,他の路線よりもはるかに高い水準にある。 先にみたように,日本航空(株)の国際線に占める東南アジア線のウエイトは,座席キロ,旅客人キロとも毎年低下する傾向にあるが,昭和38年度では,前者が16.6%後者が186%であつて,太平洋線についで日本航空(株)の主要路線である。 また,沖縄線は,海外渡航の自由化に伴つて,沖縄の渡航地としての魅力も失なわれてきた事情もあつて漸次需要の減少する傾向にあり,すでに昭和38年度においては,前年度と比較して,座席キロで,10%減,旅客人キロで2%減となり,その相対的地位も次第に下つてきている。 しかしながら,旅客人キロが座席キロの減少ほど落ち込まなかつたため,座席利用率は,逆に向上し,昭和38年度において61%となつている。
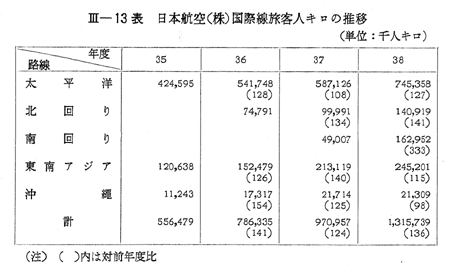
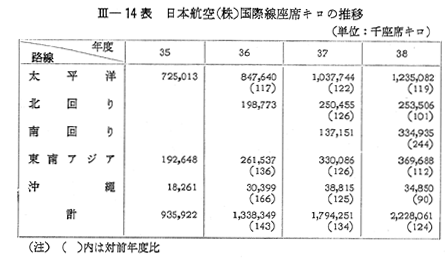

ハ 貨物 |