|
4 国際観光地および国際観光ルートに関する問題点
わが国を訪れた外客の観光地別滞在状況を全国の主要ホテル,旅館において調査した昭和37年の外客の宿泊延人員からみると 〔IV-23図〕にみられるように,東京が54.1%と過半数を占め,続いて京都,大阪,横浜の順になつている。次に,同じく昭和37年度に運輸省で訪日観光団証明書を受給した観光団について,その訪れた観光地をみると,東京,京都をほとんどの観光団が訪れており,また,東海道沿線の鎌倉,箱根,熱海,沼津,名古屋等や東海道から枝状に発生した日光,奈良,伊勢,志摩へ行くものも少なくない。また,外客の流れを旅行あつ旋業者の売る旅行からみていくと,(東京-日光-)東京-鎌倉-箱根-京都-奈良-大阪-東京(-日光-東京)というルートで旅行するものが最も多い。これらのことは,多くの外客が東京では滞在期間が長く,観光客の大きな流れが東京と京都を中心に動いていることを示している。

ルートの総合的形成を図るため,観光基盤施設および旅行関係施設の総合的整備等について,国が必要な施策を講ずべきこととしている。
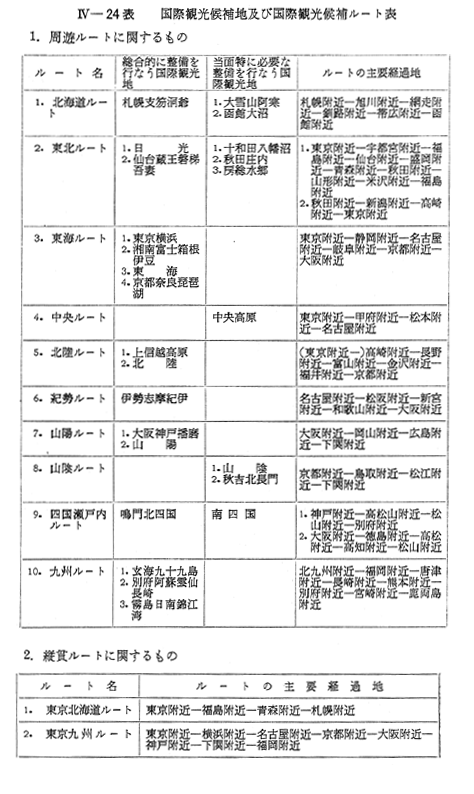
これに基づき,昭和39年9月21日に観光対策連絡会議において国際観光地および国際観光ルートについて 〔IV-24表〕のように決定をみ,政府は国際観光候補地,国際観光候補ルートおよびその整備方針案につき,観光政策審議会の意見をきくことになつた。
|