|
3 乗員養成の問題点
前述のようにわが国における乗員養成には種々の問題があるが,なかでも急務とされている路線の機長クラスの養成に焦点を絞つて問題を列挙すると次のとおりである。
(1) 訓練機
各社とも訓練機は路線に就航している航空機を,定期運航に支障のない範囲で割愛して使用しているため計画的訓練の実施が困難となつているので,なるべく専用の訓練機を確保し,充実した訓練ができるよう対策を講じる必要がある。
(2) 訓練用飛行場
国内においては,大型機(特にジェット機)の訓練に適した飛行場はごく限られている。その上,使用可能な規模はあつても著しく交通量が多いとか,米軍あるいは防衛庁の所管下の飛行場で,その使用について種々の制約を受けて,計器飛行等の高度な訓練は事実上不可能な状態にある等の理由により,国内における訓練用飛行場は皆無に近い状態である。そのため,各航空会社は遠く米国まで訓練生
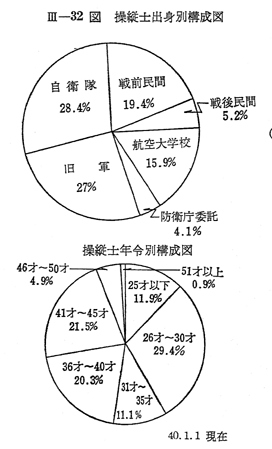
を派遣して訓練を行なつている実情であり,そのための支出は各航空会社の経理上,大きな負担となつている。このような現状を打破し,計画的な乗員訓練を実施するためには,訓練専用の飛行場の確保を図ることがぜひとも必要である。
(3) 操縦教官要員の不足
自社養成のための操縦教官を専属に配備しているところは極めて少なく,殆んど定期路線の機長クラスの中堅操縦士のうちから,定期運航に支障のない範囲で操作充当している現状であつて,教官要員の不足も隘路の一つとなつている。
(4) 乗員養成に対する助成
各社の自社養成は,その能力と乗員の需要状況に応じ独自に実施しているが,膨大な養成経費は会社の経理面を大きく圧迫している現況にかんがみ,航空事業育成のため積極的な助成策が必要とされている。
(5) 乗員養成体制の確立
前述のように現在航空大学校の直轄養成・防衛庁における依託養成および自社養成の三本だてで一応新人養成の体系はできあがつているが,ますます大型化・高性能化されつつある航空機の操縦士養成については,より高度の技術を修得させるため,現在の航空大学校のメンター(単発)・ビーチ(双発)機課程に,少なくともローカル線主力機種であるYS-11型機課程およびヘリコプター課程も加え,教育内容の充実強化をはかり,民間操縦士の一元的な養成機関として,体制を整えることが急務とされている。
|