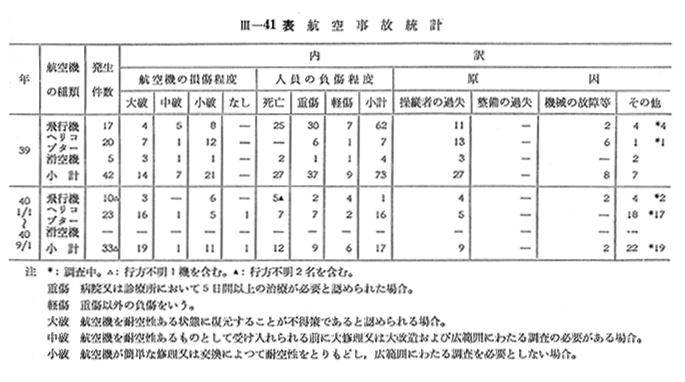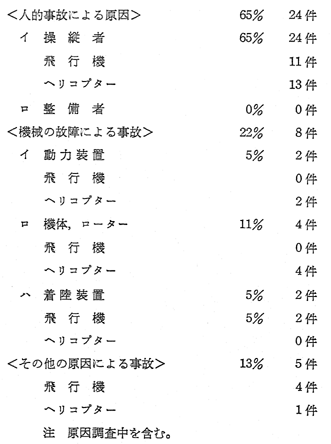|
2 最近の航空事故
(1) 事故の発生状況と分類
昭和39年1月から本年9月1日までの間における民間航空機の事故発生の状況は 〔III−41表〕に示すとおりである。
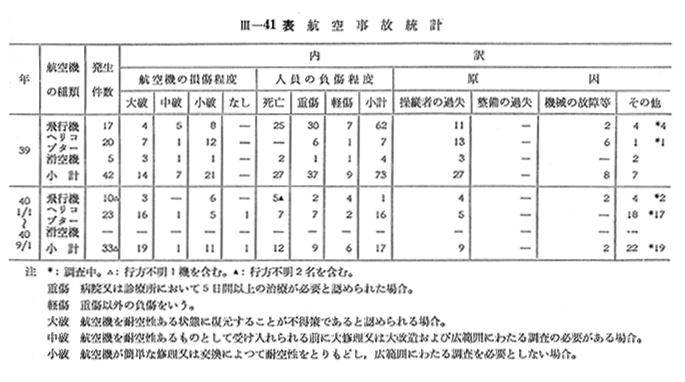
39年の事故件数は,前年の事故発生件数に比較して総件数において14件,25%の減を示し,このうち飛行機は13件42%,ヘリコプターは4件,7%の減であつた。
同年の事故を運般形態別にみると,地上-飛行機1件,地上滑走中-飛行機2件,離陸時-飛行機4件,ヘリコプター3件,航路上-飛行機2件,へリコプター15件(農薬散布件業時8件),進入着陸時-飛行機8件,ヘリコプター2件である。
この分類において事故発生の最も多い場合は,飛行機にあつては着陸時であり,これは飛行機事故件数の47%を占め,昨年より増加した。ヘリコプターにあつては航路上の事故,とくに農薬散布時のものが目立ち,ヘリコプター事故の40%を占めている。
(2) 事故の原因
昭和39年の航空事故(滑空機を除く)の原因は,つぎのごとく類別される。
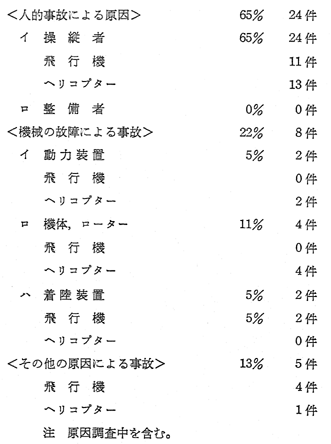
以上の分類からみると事故の主な原因は,従前と同様に操縦者の操作の誤り,判断の不良等の人的なものである。なお,ヘリコプターにあつては,飛行機に比較し機械の故障に原因している事故も多い。
(3) 事故防止対策
昭和39年度においては,臨時民間航空事故防止専門調査団の報告に基づく航空審議会の答申に応じて,操縦者の過失,技倆未熟による事故の対策としてつぎのような方法が講じられた。
イ 新たな操縦者の操縦適性の把握
航空大学校の入学予定者に対し,入学時において航空機を使用して操縦適性検査を実施し,適格者のみを入学せしめた。
ロ 航空運送事業に従事している操縦者に対し,操縦する航空機の高速,複雑性に対応した身体の健康管理を強化した。
ハ 操縦者の操縦操作の適確を期するため,航空機の構造,機能に関する教育を強化した。
ニ 航空運送事業に従事する航空機乗組員の訓練の内容を,使用航空機の性能と使用飛行場の規模,航路,気象条件に見合うような適切なものとするよう事業者を指導した。
またヘリコプターの薬剤散布,低空飛行時の事故を防止する技術の開発を推進するため39年度予算に特別研究促進調整費1,149万3,000円を計上し,運輸省,農林省のほか農林水産航空協会,航空安全推進協議会,事業会社,製作会社からなる委員会を39年12月1日設置して,回転翼機発動機回転速度定速回転自動制御装置の試作研究,高々度農薬散布装置の試作研究を実施した。
|