|
3 東海道新幹線の影響
新幹線は,39年10月に開業して以来,車両の増備,スピードアップ等により逐次輸送力が増強され,41年10月の時刻改正では,列車設定本数は60.5往復となり,車両数も600両となつた。輸送人員は 〔1−1−13表〕に示すとおり急激に増加し,42年7月13日には開業以来1億人を突破した。特に「こだま」利用客の急増が目立ち,1人平均乗車キロはしだいに短くなつている。
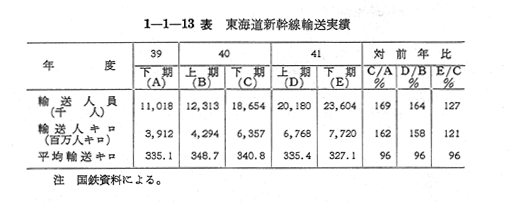
新幹線による時間距離の短縮は,1日の行動範囲を拡大し,特に用務旅行を著しく便利にした。41年2〜3月に行なわれた実態調査によれば,新幹線開通後出張回数が増加した反面,1回当りの出張期間は短くなつている。この時間距離の短縮は用務旅客のみでなく,観光客にも影響を与え,関東の観光客が関西の観光地を,また関西の観光客が関東の観光地を訪れやすくした。このように新幹線は潜在していた輸送需要を誘発し,新幹線が開通したことによつて増加したとみられる輸送人員は 〔1−1−14図〕に示すとおり,東京・大阪間は39年度下期15%,40年度上期14%,同下期28%であり,東京・名古屋間は39年度下期24%,40年度上期23%,同下期43%である。もちろんこれは駅の利用範囲が変つたこともあるが,新幹線のこのような成功は鉄道による長距離旅客輸送の方向を示唆したものといえよう。しかし平行輸送機関に与えた影響は大きく, 〔1−1−15表〕に示すとおり,新幹線が開通した39年度下期の東京・大阪間の航空旅客は,前年同期より19%減少し,40年度下期には新幹線の輸送力増強と運転時間の短縮があり,これに航空事故が重なつて,前年同期よりさらに14%減少した。41年度下期には上期に比べてやや回復したものの新幹線開通前の38年度下期の61,3%に過ぎない。東京・名古屋間の航空旅客に与えた影響はさらに大きく,41年度下期の輸送人員は38年度下期の6.2%となつた。
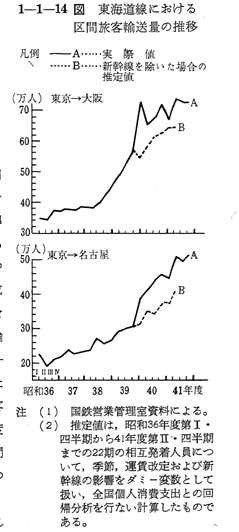
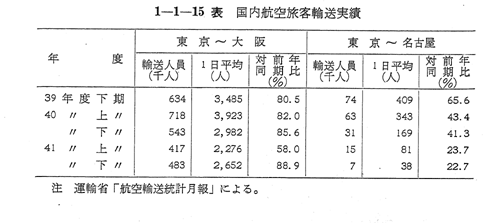
|