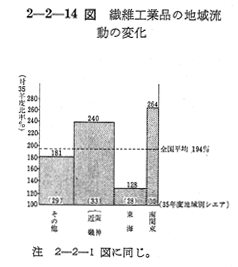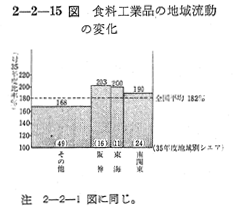|
3 食料工業品
わが国の食品工業は国民の所得水準の向上による食料消費内容の多様化と高度化によつて飛躍的な発展をとげ,35年度対比で事業所数(従業員30名以上)25%増,出荷額73%増となつている。
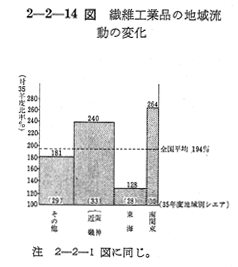
これらの食品工業のうち装置工業的性格をもつ製粉業,製糖業,ビール製造業についてみると,いずれも巨大な消費人口と関連産業のある四大消費地帯に集中しているが,原料のほとんどを海外資源にあおいでいる製粉業,製糖業では輸送土臨海部に立地しているものが多い。
(イ) 小麦粉
小麦粉生産量は35年度対比で21%増となつているが,原料輸入の関係から南関東,北関東,東海,阪神等主要輸入港を持つた地域で全国生産量の約7割が生産されている。
消費もこれら4地域で約7割を占めているので域内流動率が高く,自動車輸送が約70%を占めている。
新しい動向としては輸送,荷役の合理化のため,原料,一次加工,二次加工,飼料その他関連産業を有機的に組み合せた食品コンビナートの構想が各地で具体化しつつある。
(ロ) 砂糖
砂糖の生産量は35年度対比で28%増となつているが,この期間にてん菜糖が伸びなやみのほかは地域別には大きな変化がなく,京浜,阪神,山口・九州,北海道の4地区で全国生産量の約9割を占めている。これに対する消費量は南関東,東海,阪神等主要消費地で約6割を占めている。
輸送機関別には自動車の伸びが高いが,最近ではバラ積輸送の専用車,小型コンテナ,増加しつつある液糖用のタンクローリーなどが利用されつつある。
他方,企業のグループ化の進展に伴つて適正な工場配置とブランド統一による交錯輸送の減少がうかがわれる。
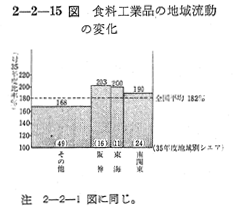
(ハ) ビール
ビールの消費は人口集中の大都市が中心であるが,近年は全国的な所得水準の向上により農村地帯における伸びが大きい。
旺盛な需要に対して工場の新設,生産能力の増設等があり,生産量は35年度対比で約2.2倍となつたが,地域別には大きな変化はなかつた。輸送機関別には,自動車輸送が70〜80%を占めているが,輸送の計画化によつて鉄道輸送の増加が見込まれている。
食料工業品全体としての輸送量は 〔2−2−15図〕に示すように35年度対比で82%の伸びである。地域別には南関東,東海,阪神の三大消費地で全国の約半分を占めている。品物の性格と流通機構の複雑性もあつて,域内流動率は高く90%に及び,そのうち自動車が94%を占めている。域間輸送では内航海運の伸びが高い。
|