|
1 列車運転管理システム
輸送の安全確保は,輸送機関の基本的使命であり,一本の列車の運転についてみても適正な列車ダイヤの作成に始まつて,車両,線路,電気系統など施設の安全の確認等,多くの配慮が必要である。ことに,列車運転の神経ともいうべき信号系統,運行指令など運行情報の迅速かつ正確な伝達・処理は,その中枢をなすものであるともいえよう。 鉄道においては,その創設以来,列車の運転に当つては,駅務員や運転士などの人間的能力を前提として運転の安全が考えられてきたが,近年輸送需要増にともなう列車の増発・稠密運転,列車の高速化にともなつて,人間の能力に頼りつつ安全な運転を確保することは限界に近づきつつあり,ATC(Automatic Train Control――自動列車制御装置)の導入により一部自動化したり,列車の運転状況,信号系統,電力系統等の情報を1ヵ所で集中的に監視し,運行の指令を行なうCTC(CentraIized Traffic Control)の開発が行なわれる一方,列車ダイヤの作成に始まる運転管理の総合的システム化(OPERUN――Operation Plan-ning&Execution System for Railway Unifed Network)が進められている。
本システムは,列車基本計画システム(ダイヤの自動作成等),要員,車両基本計画システム(乗務員・車両の運用計画の作成),運転計画伝達システム(運転実施計画の伝達の正確化と迅速化を図る),列車運転システム(進路の制御等,自動運転を考えたシステム)など,多岐,広範囲にわたるものである。このため,まず緊急度の高い運転計画伝達システムから43年度以降開発を進め,45年度中に試験段階に入り,47年度より実用化されることとなつている。
新幹線は最高時速210kmの高速運転であるため,運転士が在来線のように平均1kmごとに設置されている地上の信号機をいちいち確認して運転することが非常に困難である。
CTCは初期においては単線区間の運行の安全,省力化を中心として導入され,この適用区間は伊東線をはじめとして860余キロ(新幹線を除く)に及んでいる。しかし,ATCとともにCTCの機能がフルに生かされているのは東海道新幹線においてである。新幹線は,全線515kmの間に常時数十本の列車が高速かつ高密度で運転されており,これらの列車群を能率的に,また安全に運転調整を行なう必要があるわけである。
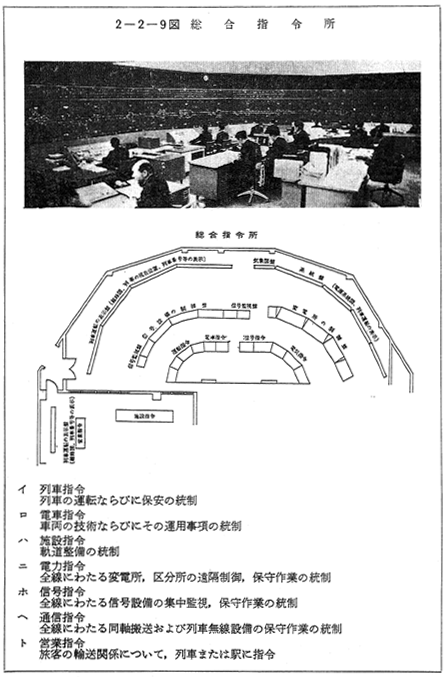
表示盤の手前には,信号設備の制御盤があり,全駅のポイントや信号機はすべてこの制御盤にあるてこで遠隔制御される。
|