|
1 航空運送事業
ア 日本航空(株)
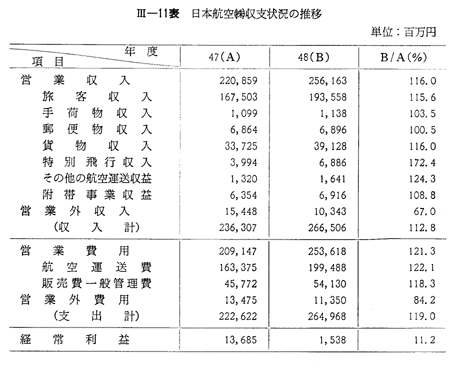
48年度の営業収入をみると,国際線については,48年11月以降,海外空港の多くにおいて実施された給油制限の影響による不定期便の抑制,定期便の運休,減便等更には政府の総需要抑制策による観光旅行宣伝の自粛等の措置にもかかわらず,旅客人員及び旅客人キロがそれぞれ前年度比13.0%,16.7%の増加となり,旅客収入の伸びは同15.0%増となっている。また,貨物については,貨物トンキロ及び貨物収入がそれぞれ同22.3%,13.1%の増加となっている。国内線については,需要が前年度に引き続き増大したが,騒音対策上あるいは空港処理能力上の見地からの東京及び大阪両国際空港の発着制限に加えて,石油危機に対処するため49年1月以降毎月減便を余儀なくされ,その結果,旅客収入及び貨物収入は,前年度に比べて,それぞれ16.6%,35.2%増にとどまった。
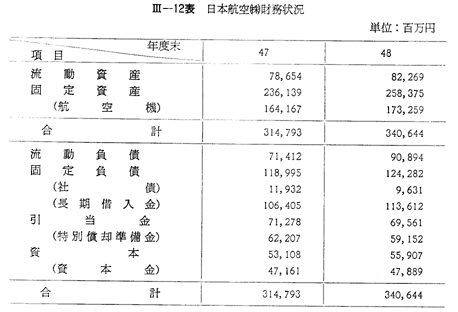
政府としても,従来から同社に対し,出資を行っているほか 〔III−13表〕のように債務保証,政府保有株の後配当等の助成措置を講じている。
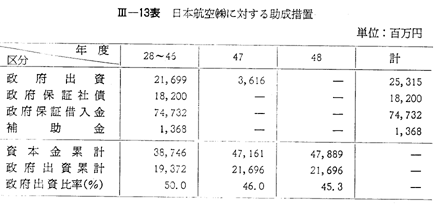
イ その他の定期航空会社
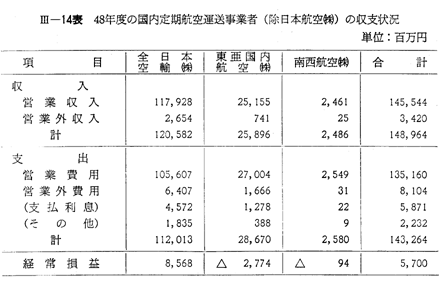
国内定期航空運送事業の最近5年間の利益率の推移は 〔III−15図〕のとおりであり,43年度までは急速に収益性が高まりつつあったが,44年度から低下の兆しがみえ,48年度は売上高営業利益率,売上高経常利益率はそれぞれ7.7%,5.5%となった。
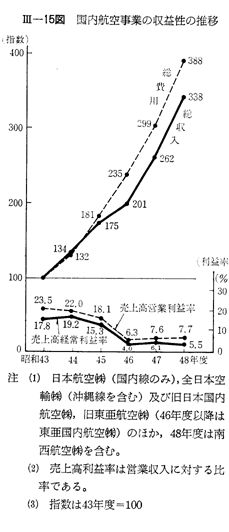
従来,日本の航空企業が米国から輸入する航空機の購入資金については,購入価格の80%相当分を米国金融機関からの借款によりまかなってきた(購入価格の40%については米国輸出入銀行,40%については米国市中銀行)。この借款の債務保証は,主として日本開発銀行が行ってきた(日本航空(株)が購入する国際線用機材の米国輸出入銀行からの借款部分については,43年度から政府保証が認められた。)。
日本航空(株),全日本空輸(株),東亜国内航空(株)については,47年7月に旅客運賃を平均9.5%,貨物運賃を平均8.6%増とする改定を行ったが,航空機燃料税の増徴,諸経費の増大などを理由に,48年8月改定申請があった。その後,48年10月以降の石油危機による航空用燃料費の急激な増大,諸物価の高騰による諸経費の増大などのため,企業努力では,吸収が困難であるとして,49年4月旅客運賃を平均39.6%,貨物運賃を平均38.7%改定したい旨の再申請が行われ,また,沖縄県内離島路線を運航する南西航空(株)からも,上記3社と同様の事由により旅客運賃を平均70.0%,貨物運賃を平均29.4%改定したい旨の申請が行われた。これらの申請に基づき,南西航空(株)を除く3社については,旅客運賃を平均29.3%(幹線27.0%,ローカル線32.4%),貨物運賃を平均27.2%(幹線26.0%,ローカル線31.0%),南西航空(株)については,旅客運賃を平均49.0%,貨物運賃を平均19.0%増とする改定をそれぞれ認め,49年9月10日から実施することとなった。
|