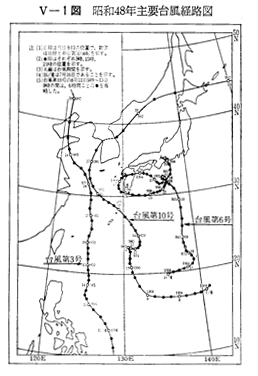|
第1節 気象
昭和48年度の顕著な天気現象として,夏期のほぼ全国的な干ばつと異常高温,晩秋から冬期に起きた太平洋側の異常乾燥と北日本の豪雪,台風の発生が少なかったこと等があげられる。
台風第1号は7月に,ようやく発生し,総数は21個で47年の31個に比べて少なく,また,日本に上陸した台風は7月に1個のみであった。他に影響のあった台風は 〔V−1図〕のとおりである。
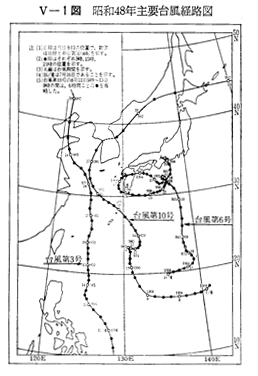
そのほか主な異常気象を発生順に見ると,5月8日朝,日本海西部の低気圧と前線の影響で,長崎市から諌早市にかけての狭い範囲を中心に,九州北部で100〜200mmの大雨が降った。長崎では6時までの3時間に146mmの豪雨を記録,総雨量は206mmに達した。このため死者,行方不明10名,建物の全半壊や浸水家屋等の被害が出た。
5月10日から13日と20日から24日には,バイカル湖方面の寒気が南下して本州の各地は異常低温となった。このため12日と24日の朝には,岐阜県,長野県と関東,甲信の山沿い地方に晩霜がおり,農作物や果樹に被害が出た。一方,5月は北海道西部,東北北部と東部,山陰,四国等の各地で少雨傾向が目立ち,梅雨期も前線活動が不活発で降雨はほぼ全国的に少なかった。梅雨末期に起こる大雨もほとんど無く,梅雨は平年より早く終り,7月上旬には本州付近は太平洋高気圧に覆われ,中旬末まで高温晴天が続き干ばつは決定的となった。下旬から8月7日頃までは,日本付近は大きな前線帯の中に入り,台風6号や前線上に発生した低気圧群により,各地に局地的な大雨が降り,北海道や東北北部の干ばつはかなり解消したが,8月7日頃から23日頃まで再び夏型の気圧配置が続き,各地で記録的な高温が観測され,中国,四国北部,近畿,北陸,関東,東北南部の干ばつは著しくなった。その後,8月24日頃の四国沖の低気圧による降雨から天気は周期的に変化した。
8月末から9月上旬にかけて低気圧が次々と東進し,上記各地の干ばつは次第に解消するに至った。
この間の6月26日には済州島付近に進んできた低気圧に刺激され梅雨前線が急速に北上し,九州北部から山口県にかけて100〜300mmの大雨が降り,死者,行方不明3名が出た。また,7月30日午前,黄海に現れた低気圧が31日昼に日本海東部に入り,中心からのびる前線が九州北部を通過した。このため福岡県春日市を中心とした地方で150〜200mmの大雨が降り,春日市で1時間115mmの豪雨を記録,総雨量は232mmに達し,死者,行方不明30名,家屋の被害140棟,浸水家屋4,200余棟等,48年最大の災害が起こった。
9月22日,本州の南海上を東北東進した低気圧と,寒気流入による大気成層の不安定化のため,新潟県糸魚川市付近,青森県下北半島,北海道南部の渡島,檜山地方を中心に23日から24日にかけて200〜400mmの大雨が降り,死者,行方不明23名,建物被害210余棟等が出た。
11月9日から10日にかけて,低気圧が本州南岸沿いに進み,10日午前には紀伊半島から関東北部までの地方で雷を伴った大雨が降り,特に神奈川県下では150mmを越す大雨となり,死者2名が出たほか若干の被害があった。
11月17日に日本海を北東進した強い低気圧の後面に大陸からの寒波が襲来し,山陰以北の日本海側や北日本に初雪が降った後,次々と寒波が襲い,北日本を中心に,49年2月中旬まで記録的な豪雪となり,秋田県横手で2月14日に259cm,山形県肘折で470cm等,秋田,山形県方面では積雪の深さが観測所開設以来の記録を更新した所が多く,大雪の被害が甚大で日常生活に大きな影響を与えた。また,2月7日から9日朝には太平洋岸を北東進した低気圧により東北地方の太平洋岸にも大雪が降った。一方,太平洋側の地方では,11月中旬から49年1月中旬まで無降水日が続き記録的な異常乾燥となった。
|