|
第1節 国内貨物輸送昭和49年度の国内貨物輸送量は,50億8,500万トン,3,758億トンキロで,前年度に比べトン数は,11.0%減(48年度2.7%減)トンキロは7.7%減(48年度4.6%増)と近年にない落込みを示した。前年度に引き続き2年連続して減少した輸送トン数は,45年度の水準を下回るまで後退し,またトンキロでも47年度の水準を下回つた。 〔1−3−1表〕 〔1−3−2図〕
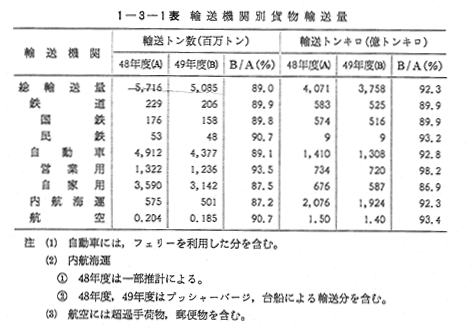
最近における国内貨物輸送(トンキロ)の動きは,48年4〜6月期をピークとして,総需要抑制策に伴う公共投資の減少とともに下降に転じ,石油危機を契機とする景気の後退が始まった49年1〜3月期以降は生産出荷の著しい低下により,輸送量は一段と減少し始め,49年度中は回復することなく推移している。
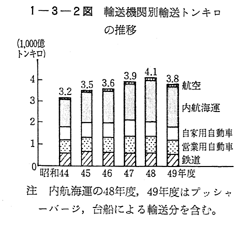
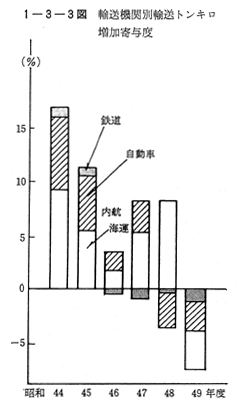
自動車による輸送は,前年度に比べトン数で10.9%減(48年度5.6%減),トンキロで7.2%減(48年度8.2%減)と2年連続の減少となり,今回の不況によりもっとも大きな影響を受けた。この輸送量は45年度の水準を下回るものである。これは,自動車輸送の大宗貨物である農畜水産品(トン数で18.7%減),林産品(同19.7%減),砂利・砂・石材(同9.5%減),機械(同23.0%減),及び軽・雑工業品(同19.6%減)がすべて大幅に減少したことによる。これを営業用,自家宙別にみると,営業用がトン数で前年度比6.5%減(48年度1.3%増)トンキロで1.8%減(同4.1%減)であったのに対し,自家用がトン数で12.5%減(同7.9%減),トンキロで13.1%減(同12.3%減)と自家用の大幅な落込みが目立っている。品目別にみて営業尾自動車の比重が比較的大きいものは鉄鋼,機械,石油,食料工業品等の工業製品であるが,これら品目の自動車輸送量は全体として大幅に減少したにもかかわらず,鉄鋼のように逆に営業用自動車輸送量が増加したものがみられるなど,営業用自動車の輸送量は底堅い動きを示しており,これらの品目では自家用自動車が,景気の動向に影響される性格を有していることがうかがわれる。また,自家用自動車の比重が大きい砂利・砂・石材,木材などの輸送量がいずれも減少となったことも,自家用自動車輸送の不振の一因となっていお 〔1−3−4図〕。
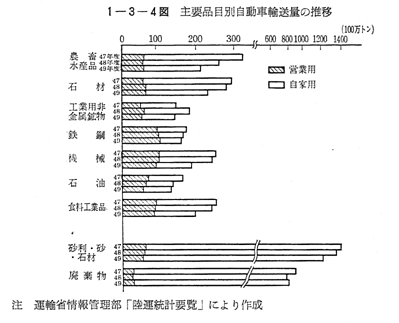
内航海運は,トン数が前年度に比べ12.8%減(48年度32.4%増),トンキロが7.7%減(48年度18.1%増)と前年度に大幅な伸びを示したこともあってトン数の落込みは大きかったが,トンキロの落込みは比較的小さかった。内航貨物の主要品目についてみると,一般貨物の串で最も大きな比重を占める鉄鋼は下半期の落込みが大幅となり,前年度に比べ9.9%の減少となった。石炭は前年度比4.2%の減少にとどまった。また,公共事業関連物資であるセメントは総需要抑制の影響を受けて,89%の減少となり石灰石も44%の減少となった。
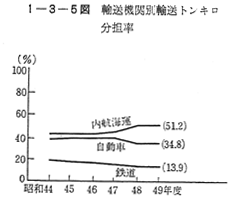
次に,49年度の主要品目の輸送動向をトン数でみると 〔1−3−6表〕 〔1−3−7図〕のとおりで,不況による荷動きの減退を反映して第2次産品が大きく落込んでおり,また景気の動画と関連のないと思われる野菜果物も含め,林産品,鉱産品が大幅に減少したのをはじめ,他の第1次産品も軒並みに減少した。
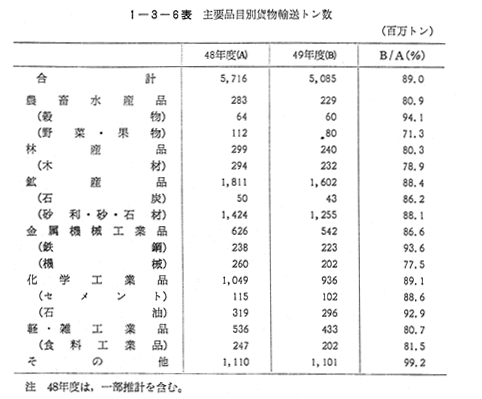
まず農畜水産品は,前年度比19,1減であった。林産品は,民間住宅投資の不振から荷動きが停滞し,前年度比19.7%減と大幅な落込みとなった。総輸送量の30%強を占める鉱産品は前年度比11.6%減であったが,そのなかで約80%を占める砂利・砂・石材が民間の建築着工の減少,公共事業のくり延べにより前年度比11.9%減となった。

|