|
1 労働力の現状昭和49年の労働力人口は5,274万人で,前年と比較して25万人減少した。労働力人口が対前年比で減少したのは戦後初めてのことである。このうち,就業者数の産業別内訳は第一次産業673万人,第二次産業1,890万人,第三次産業2,638万人であり,過去,第一次産業から第二次及び第三次産業へ就業者が移行する傾向が続いているが,第一次産業の減少及び第二次,第三次産業の増加は近年鈍化している。 このなかにあって,運輸業就業者数は35年には169万人であったのが47年には251万人に増加し,労働力人口の伸びを大幅に上回ったが,第三次産業就業者に占める割合はおよそ10%で一定している。これを業種別に見ると,航空が5.3倍と最も高く,次いで道路貨物及び道路旅客運送業がそれぞれ2.5倍,1.9倍という高い伸びを示した。海運,鉄道は横ばいであるが,物的労働生産性の上昇傾向が著しく,これは,合理化等により,輸送需要の増大に対応してきたことを示している。 一方,49年のわが国経済はインフレ下のマイナス成長という異常な状況にあり,このため,有効求人倍率は49年10〜12月期には0.84倍と1を割り,さらに50年1〜3月期には0.72倍となり,また,48年には254万人であった求人数が49年には145万人となり,労働力需給は緩和した。この傾向は運輸部門においても例外ではなく,運輸通信業における求人数は48年に15万人であったのが,49年には11万人と大幅に減少した。 なかでも,船員にあっては,外航部門におけるタンカー船腹の過剰,中小型船の国際競争力の低下,内航部門における荷動きの停滞,また,漁船部門における漁業の国際規制の強化は,その雇用不安をもたらしている。すなわち,49年度の船員の新規求人は前年度比12.0%減に対し,新規求職は前年度比9.9%増となった。さらに,50年6月の新規求人は前年同月比67.3%減,新規求職は前年同月比36.9%増で,有効求人倍率は0.3倍となり50年度に入り雇用情勢は一段と悪化しており,船員職業安定機能の充実,船員再教育,技能訓練の充実等の総合的な船員雇用安定対策を講ずる必要が強まっている。 また,運輸業は他産業と比較して中高年齢労働者の占める比率が高く,特に国鉄においてこの傾向が著しい。従って,これら高年齢層の一斉退職に伴う労働力の補充が今後大きな問題となろう。 49年の賃金は,大幅なインフレ等を背景として近年比類のない大幅な上昇率を示し,運輸部門もその例外ではなかった。月平均現金給与総額の推移は 〔2−3−1表〕のとおりである。一方,賃金水準をみると,運輸業賃金の水準は他産業に比べて高く,49年については全産業平均賃金の1.12倍となっている。業種別では航空,海運業が全産業平均に比べてそれぞれ2.36倍,1.52倍と非常に高水準にある。これは 〔2−3−2表〕のとおり,所定外労働時間の長いこと,他産業に比して雇用者の平均年齢が高いこと,専門的技能を必要とする運輸業の特殊性,労働環境の特殊性等の理由によるものである。
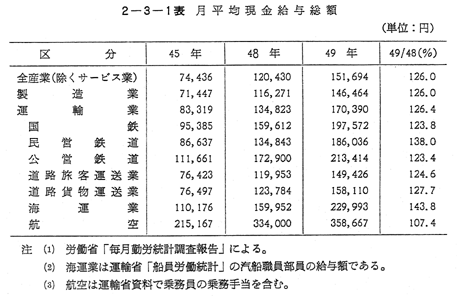
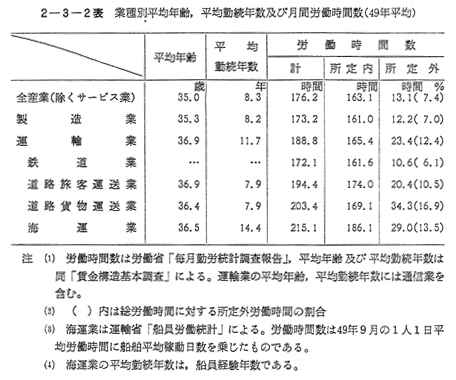
次に,従業員1人当たりの付加価値額と労働装備率を見ると 〔2−3−3図〕のとおりであり,これによれば,海運は,付加価値額,労働装備率ともにずばぬけて高く,航空も比較的高い。運輸業の中でも労働葉約的で省力化等が困難な道路運送業においては,付加価値額,労働装備率ともに低く,また,鉄道業においては労働装備率は高いが付加価値額が低い。これは,国鉄の場合,現行の運賃水準では大幅な赤字を余儀なくされており,民鉄においても程度の差こそあれ同様な状態にあるためである。
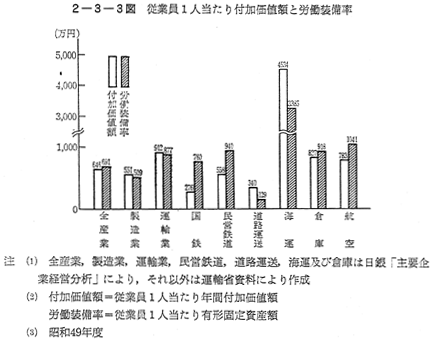
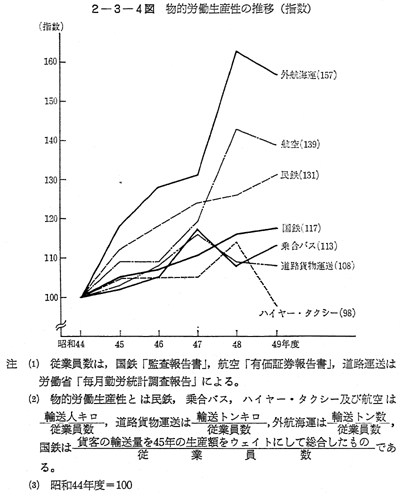
|