|
2 エネルギーの現状昭和30年代以降の我が国経済は,高度成長により,規模を大きく拡大した。この間,石油を中心としたエネルギー価格が安定的であり,かつ,供給面の制約がなかったため,我が国の産業構造はエネルギー多消費型の発展をとげ,エネルギー消費量は35年度の844兆Kcalから48年度は3,540兆Kca1へと急速に増大した。 こうしたなかにあって運輸部門のエネルギー消費量が全消費量に占める割合はほぼ一定した推移を示し48年度では全体の12.9%に当たる457兆Kcalであった。また,49年度のエネルギー消費量を輸送機関別にみると 〔2−3−5表〕のとおりである。 エネルギー種類別の消費構造は 〔2−3−6図〕のとおりであり,ガソリンの98.3%,軽油の64.3%を運輸部門で消費しており,かつ,原油から精製される各油種の比率がほぼ一定しているうえ,他のエネルギーによる代替は短期的には不可能であるため,石油の供給がひっ迫した場合には,運輸部門はその影響を受けやすい状況にあるといえよう。 以上のように急速に拡大してきたエネルギー需要を賄ってきた一次エネルギー供給については石油の割合が年々ふえており,48年度における石油の割合は,77.6%と,米国の47.2%,西欧の63.8%に比べ高くなっているうえ,石油供給の99.7%までを輸入に依存している。ところが,48年10月の石油危機を境にして,世界の石油エネルギーひっ迫状況が表面化し,供給面の量的制約等が生ずるとともに, 〔2−3−7図〕にみられるようにエネルギー価格は急上昇した。 このため,営業費用に占めるエネルギー費の割合が上昇し,特に航空,外航海運においては非常に高い比率を占めるに至った。 〔2−3−8図〕
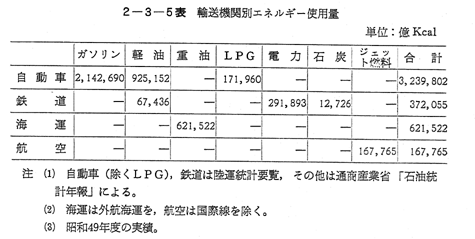
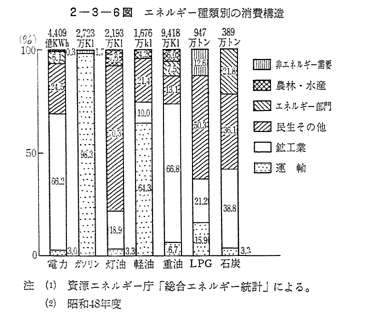
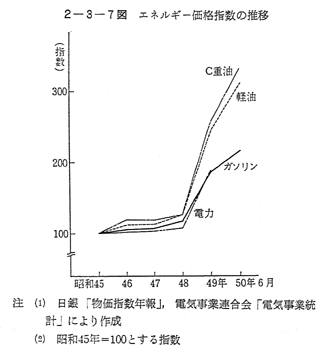
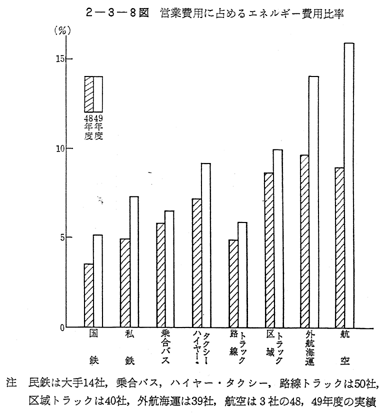
次に,輸送機関別のエネルギー効率を比較すると 〔2−3−9図〕のとおりであり,旅客輸送については鉄道,バスはエネルギー効率が良く,乗用車,航空はエネルギー効率が悪い。また,貨物輸送については鉄道,海運がエネルギー効率が良く,自家用トラックはエネルギー効率が悪い。
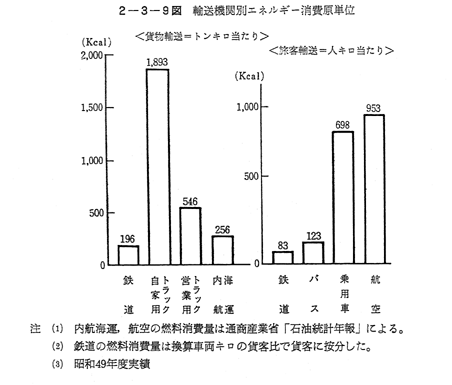
また,積載効率を100%として,航空機とタンカーの単位輸送量あたりのエネルギー消費量を試算してみると,航空機ではB747-SR(定員498人)はB727-200(定員178人)の2分の1強であり,一方,載貨重量23万トンのタンカーは2万トンのタンカーの5分の1であり,これらの輸送機関においては大型化によりエネルギー効率が向上するという傾向がみられる。
|