|
3 交通空間の確保難と環境保全輸送隘路の解消,交通混雑の緩和あるいはサービスの改善等を図るため,運輸交通施設の整備を進めてゆく必要があるが,このための交通空間の確保が緊要な課題となっている。 国土が狭あいでしかも山岳部の多い我が国にあっては,交通空間は需要の点からも,施設整備における地形的制約の点からも平野部に求められるのは当然である。その結果アメリカ,西独等先進諸外国と比較して,我が国の場合,道路等の交通空間の可住地面積に占める比率が高い。この傾向は都市部においてより顕著であり,昭和47年における全国の可住地面積に占める道路等用地は5.3%であるが,東京都の場合は11.6%となっている。 次に,平野部に交通施設を求めることは,人口密集地にそれを求めることを意味し,利害関係者が多数にのぼることとなる。また,都市部においては宅地の占める比率が高く,新たな交通空間を確保するためには宅地を転用せざるを得ない場合が多いが,六大都市における宅地価格は過去10年間に3倍に上昇している。 その上,環境保全の要請に応えて交通空間のため直接必要な用地のほか,周辺対策のための用地の確保を必要とする場合も生ずるようになり,取得すべき用地面積も増大することとなる。 これらに加えて施設の建設段階における騒音,振動,地盤沈下等,また,運用段階における騒音,振動,日照妨害,排出ガス,水質汚濁等の公害問題をめぐって,交通施設の整備と環境保全の要請との間の調整が大きな問題となってきており,交通施設の整備は,益々その困難さを増している。このため,例えば,新幹線,高速道路等においては,建設が当初予定より著しく遅延し,建設費用も上昇し,また既に完成した施設も利用できない状況のまま放置される等その損失は大きい。 このほか,環境保全の要請は,地下鉄工事に見られる如く,工事時間,工事方法の制限を要求することもあり,工事期間の長期化,コストの増大をもたらすことがある。 なお,既存の交通施設においても,環境保全要求の高まりに応えるため,空港,新幹線等において, 〔2−3−10表〕のような対策を推進しているが,いずれの対策も収入増に結びつかない運輸サービスのコストアップの原因となりつつある。 以上で述べたように,空間,環境問題による制約に対処するためには,経営基盤の強化もさることながら土地利用計画,都市計画の適切な策定によって,交通空間の確保を図ること,空間生産性の高い大量交通機関を整備すること,環境影響評価の徹底を図ること等の諸施策を適時適切に推進していくことが必要である。
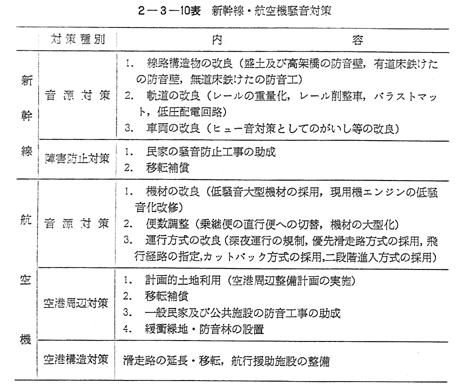
|