|
第1節 運輸事業の経営悪化昭和49年度における運輸事業の事業別損益状況は, 〔2−5−1表〕のとおり,旅客輸送量の伸び悩みと貨物輸送量の大幅な減少にもかかわらず,48年から49年に実施された運賃料金の改定等による寄与もあって,いずれの業種においても営業収入は増加した。しかし,48年秋の石油危機以降における諸経費の高騰と,49年春闘がもたらしたかってない大幅な賃金上昇によって,市況が好況であった海運業を除くすべての業種で営業費用の増加が営業収入の増加を上まわり,営業損益は悪化し,これに営業外損益を加えた経常損益も軒並み悪化した。すなわち,40年代を通じて悪化の一途をたどってきた鉄道,バス等の陸運事業部門の経常損益はいずれもその赤字幅を拡大し,個別企業ベースでみても,国鉄が6,500億円の巨額の欠損を計上したほか,大手民鉄及び公営鉄道(交通営団を含む。)では27社のすべてが,中小民鉄では59社串53社,バスでは218社中190社が赤字となるなどその大半が欠損を計上することとなった。
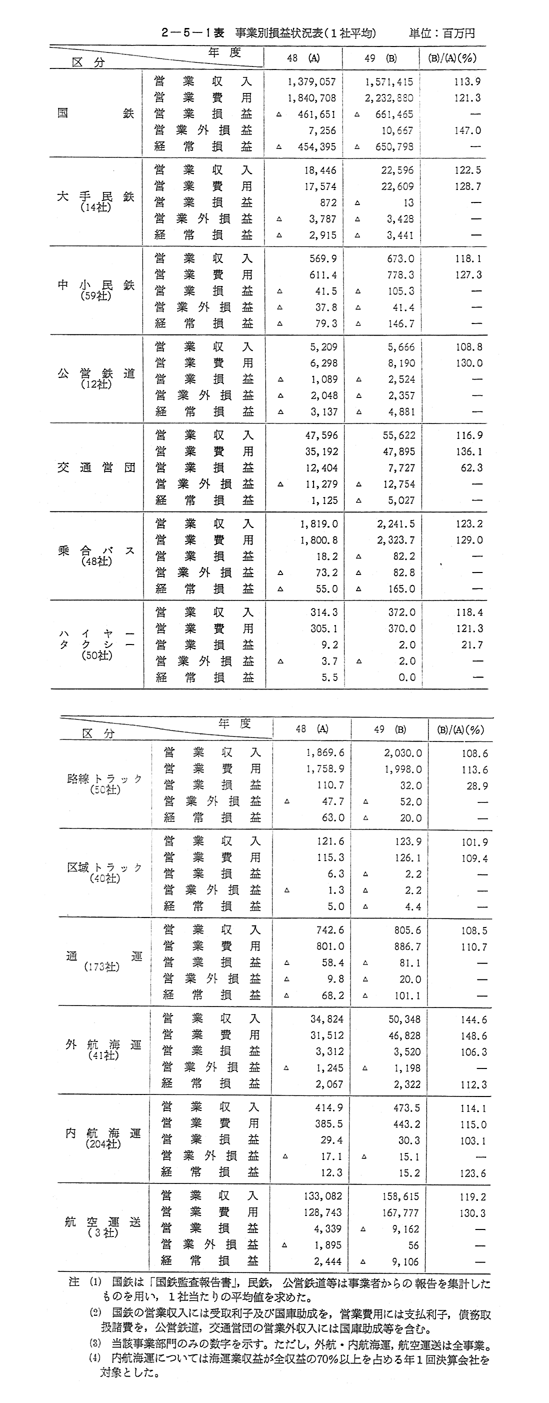
また,従来,比較的安定した経営を続けてきた海運,航空あるいは造船等の業種においても,世界的規模での景気の後退と経済構造の変化によって経営状況が悪化しつつあり,航空業にあっては日本航空(株)が一転して大幅な赤字を計上し,また,海運・造船業も船腹過剰という構造的な経営圧迫要因を抱え込むこととなった。
|