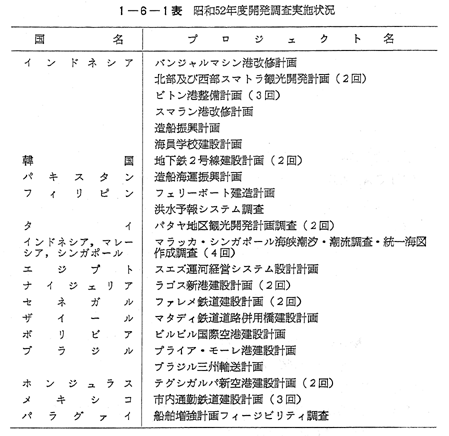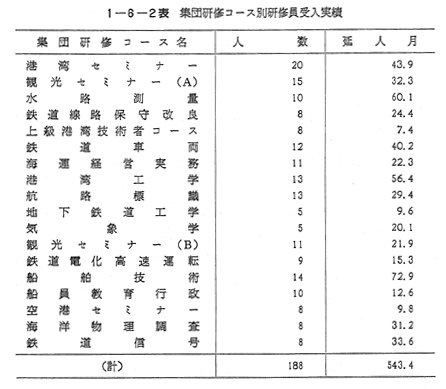|
1 技術協力
(1) 技術協力
発展途上国に対する技術協力は,原則として一元的に国際協力事業団(JICA)を通じて実施されており,開発調査事業,開発協力事業,研修生の受入れ,専門家の派遣,プロジェクト方式技術協力事業等で成り立っている。
まず開発調査事業とは,発展途上国において地域総合開発,社会開発を推進する場合に,それら開発計画策定のための高度な技術や実務経験をもつ専門家及び計画案をまとめる人材が不足している場合とかその態勢が不備な場合が多いので,相手国からの技術協力要請に基づき,専門家からなる調査団を編成し,現地調査,及び国内作業を通して,開発計画の作成,フィージビリティーの確認等の結果を発展途上国に提出するものである。52年度の実績は 〔1−6−1表〕のとおりである。
開発協力事業は,開発協力調査,技術指導及び投融資等審査調査に分類され,発展途上国において開発事業等に従事する本邦法人に対し必要な技術的支援を行い,さらには事業団の投融資に結び付けることにより,当該プロジェクトの経済協力効果を最大限に発揮させることであり,運輸関係ではマレーシアの航行援助施設整備に対し開発協力専門家として人材を派遣した例がある。
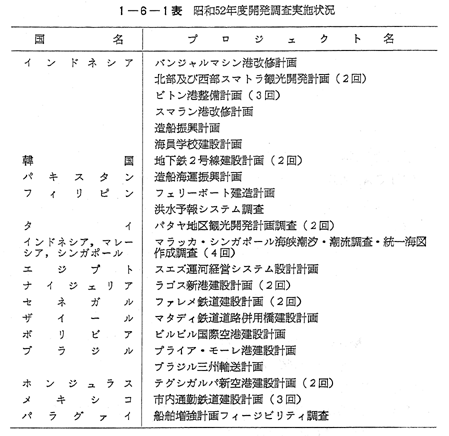
研修生の受入れは,発展途上国の政府,政府関係機関の職員や民間人を研修生として我が国に受入れ,行政や経営管理などを含む技術訓練を行うものであり,受入方式により集団研修と個別研修とに分けられる。集団研修は,実施時期,研修内容等があらかじめ定められていて,発展途上国から応募してきた研修生に対して実施されるものであり,運輸関係では,52年度には 〔1−6−2表〕にあるように18コース,188人に対し実施した。
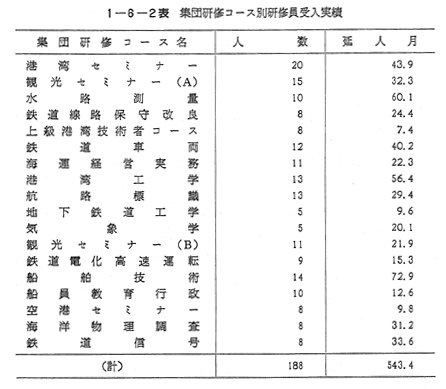
個別研修は,発展途上国からの要請によりその都度実施され,要請内容に応じ,それぞれの政府関係機関等で研修が行われる。
専用家の派遣は,発展途上国の要請に応じて,相手国の政府,政府関係機関,研究機関,学校等で企画立案,調査研究,指導,助言等の業務を行うために,我が国から専門家を派遣する事業であり,1年以上滞在する長期派遣と,問題の都度派遣する短期派遣(1年未満)とがある。
プロジェクト方式技術協力は,技術協力センター事業,農林業協力事業,保健医療協力事業,産業開発協力事業に大別されるが,そのうち技術協力センター事業は,発展途上国の経済社会開発にとって最も不定している技術者の訓練・養成及び科学技術の開発・普及分野における協力を目的として,技能訓練機関等を設置するものであり,運輸関係では,マレーシアの船舶機関士養成,エジプトのアラブ海運大学校に対する協力がある。
以上は,JICAを通じて協力が行われているが,このほかに,運輸省が(財)国際開発センターに委託して実施している運輸経済調査及び運輸省の補助を受けて,(社)海外運輸コンサルタンツ協会が実施している海外情報収簾調査とがある。
前者は,発展途上国の港湾,鉄道,空港及び道路等の運輸関係基盤施設について,基礎調査を実施するもので,52年度には南アメリカ2か国(コロンビア,ベネズエラ)の予備調査及び北アフリカ3か国(チュニジア,モロッコ,スーダン)の本調査を実施した。後者は,発展途上国における運輸関係プロジェクトの発掘等を目的とした調査であり,52年度には,東南アジア,中南米地域へ調査団8チームを派遣したなお,調査とは別に,後者においては,技術協力の充実に密接な関係をもつ,海外コンサルティング企業の育成強化のため,各種研修コースを設け,人材の育成を推進してしる。
(2) 大規模運輸経済プロジェクトの推進
中東,アフリカの産油国及び中進国においては運輸関係の大規模なプロジェクトの計画が数多く策定されているが,それら計画のうち相手国にとって有益であると考えられる大規模なプロジェクトについては,積極的に相手国に働きかけ合意を得て技術協力を推進している。52年度においては,メキシコ市の通勤鉄道建設プロジェクト及びナイジェリアのラゴス新港建設プロジェクトについて,JICAが調査を実施した。ラゴス新港建設プロジェクトについては,52年度において実施した新港の機能,規模及び最適地等についての調査に引き続き,53年度において具体的な新港開発計画を策定することになっている。
|