|
2 災害対策の推進
災害を極力未然に防止し,万一,災害が発生した場合は被害の拡大を防止し,早急に復旧作業を実施して,国民生活に及ぼす影響を最小限にとどめることは是非必要なことである。このため,運輸省,海上保安庁及び気象庁は,いずれも災害対策基本法に基づく指定行政機関として防災業務計画を定め,各種防災技術の研究,予警報の伝達,防災資機材の整備等,災害を防止するための各種施策を実施するとともに,災害発生時には緊急出動をはじめ,人員や救援物資の緊急輸送,港湾災害復旧事業の実施等災害復旧に全力をあげることとしている。なお,最近6年間の防災関係予算は 〔1−6−5表〕に示すとおりである。
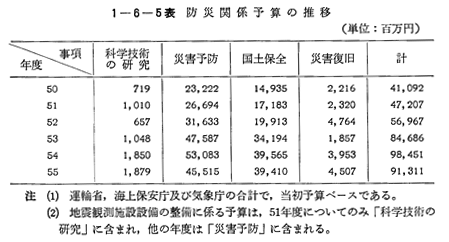
ア 海上防災対策の充実
イ 気象災害・火山対策の推進
また,近年における桜島等の火山活動の活発化に伴い,火山噴火予知の実用化,防災対策の強化等への社会の要請の高まりを受け,活動火山対策特別措置法により火山対策の強化が行われた。これに対応して,国民の生命及び身体を保護する必要を認めるときは,火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報すべき責務を果たすとともに,火山現象の研究,観測体制の整備,予知技術の開発等の推進に努めなければならないとする同法の趣旨と,測地学審議会の建議による第2次火山噴火予知計画を踏まえて,対策を推進する必要がある。
ウ 気候変動対策
70年代に気候変動に関する理論的研究が進み,気候変化の原因の一部に,大気中のじんあいの増加に起因する日射量の減少と大気中の炭酸ガスの増加に基づく赤外放射の減少等人間活動の影響があるのではないか,また,事態がこのまま進行すれば,21世紀中期には,気候が大きく変わるのではないかという世界各国の認識が高まってきた。 これを受けて,世界気象機関(WMO)は,20世紀最後の20年間にとって気候問題が人類の直面する重要な問題であるとして,昭和54年5月の総会で世界気候計画(WCP)を採択し,この推進を図っている。 このような世界の動きに対応して,気象庁は,54年10月以来,各分野の学識経験者及び関係省庁の職員からなる気候問題懇談会を開催し,気候変動の原因と影響について,学際的に検討を進めている。 さらに,気象庁は,気候変動に関する研究と観測体制の強化,気候資料の迅速な利用交換に役立つ気象データベースの検討,気候情報の農業,水資源,太陽エネルギー,その他エネルギー問題への応用についての関係省庁との協力,気候と社会の相互影響の解明等を強力に推進する必要がある。
エ 海岸災害対策の推進 |