|
1 激変する国際石油情勢と我が国のエネルギー事情1970年秋のリビア原油の値上げに端を発したいわゆるOPEC攻勢に始まり,78年秋のイラン政情不安による石油輸出削減等から石油需給がひっ迫化した79年に終わる70年代は,国際石油情勢にとってはまさに激動の10年間であった。 70年秋からのOPEC攻勢は,71年2月のテヘラン協定をはじめとする一連の価格諸協定の締結に成功し,また72年12月のペルシャ湾岸4か国のリヤド協定の締結により,いまひとつの目標であった産油国政府の事業参加を実現した。これにより,世界の原油市場は一転して買手市場から売手市場へとかわり,同時に産油国は原油の価格,生産の決定に関する主導権を獲得し,世界の石油情勢は大きく変化した。更に,73年10月の第4次中東戦争勃発とこれを背景にして展開されたアラブ産油国による石油供給削減,原油価格の一方的な大幅値上げ等の石油戦略により,産油国の立場は決定的なものとなり,以後,原油の価格,生産量の決定権は完全に産油国に移った。 この73年の第1次石油危機時約4倍に大幅値上げされた原油価格は,その後緩やかな上昇にとどまっていたが,78年後半に至り,石油需給が逼迫化する中で開かれた78年12月のOPECアブダビ総会では,79年中の四半期ごとの段階的値上げが決定され,その後は数回にわたり値上げが行われた。 標準油種であるアラビアンライトの価格の推移をみると, 〔2−1−45図〕のとおり石油危機前の73年1月には2.591ドル/バーレルであったものが,80年8月には30ドル/バーレルとおおよそ7年間で約12倍にも値上がりを示した。
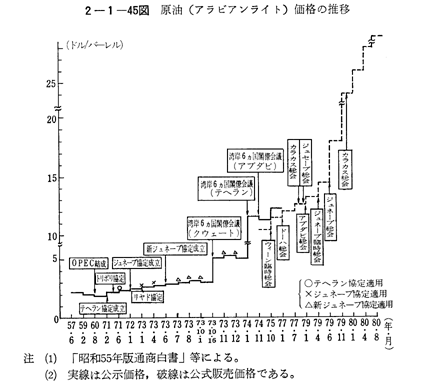
このような中で,中東をはじめとする産油国におけるメジャーズの地位は低下し,OPECの原油生産量に占めるメジャーズの取得割合は,70年の81.7%から78年には18,8%まで下がった 〔2−1−46図〕。
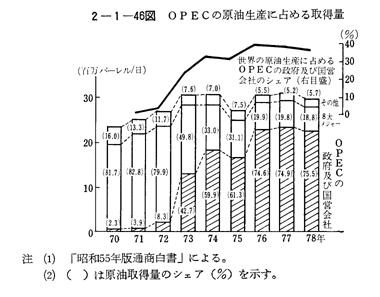
しかし,これらのメジャーズは,依然として巨大な資金力,技術力等を背景に,OPEC攻勢後も北海,アラスカ等の地域において石油開発を進める等世界の石油供給面で大きな力をもっている。
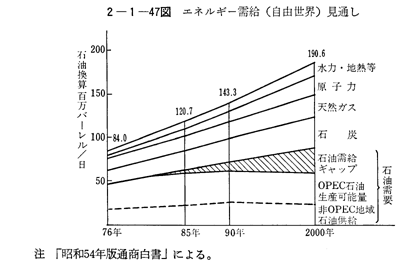
一方,我が国のエネルギー消費量は,70年度には石油換算で3億1,000万トンであったものが,78年度は4億100万トンと約30%の増加を示しており,自由世界の中ではアメリカに次ぐエネルギー消費国となっている 〔2−1−48図〕。
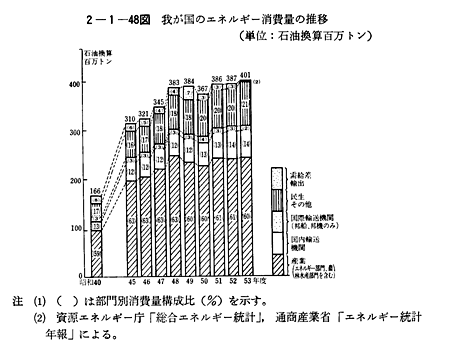
今後の我が国のエネルギー需給については,79年6月の東京サミットにおける石油輸入目標の合意等に基づき,同年8月に発表された長期エネルギー需給暫定見通し(総合エネルギー調査会需給部会中間報告)で予測されている 〔2−1−49図〕。
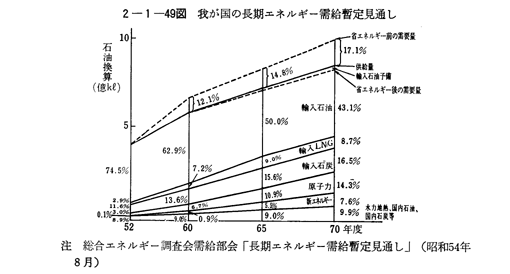
この見通しによれば,我が国のエネルギー需要は省エネルギー対策をとらない場合,昭和60,65,70の各年度においてそれぞれ6億6,200万キロリットル,8億2,200万キロリットル,9億7,300万キロリットルに達するものと見込まれている。省エネルギーについては,エネルギーの使用の合理化に関する法律の積極的な運用を中核とした省エネルギー対策の推進により,各年度12.1%,14.8%,17.1%程度にまで省エネルギー率を引き上げることが可能であると考えられており,その目標が達成された場合,省エネルギー後の需要は,それぞれ5億8,200万キロリットル,7億キロリットル,8億700万キロリットル程度になると見込まれている。
|