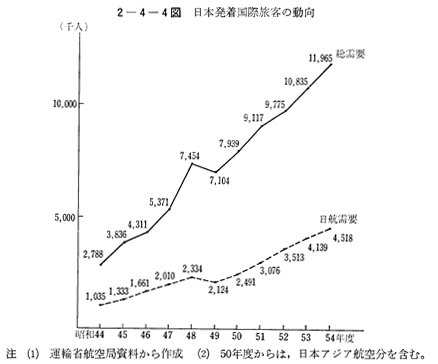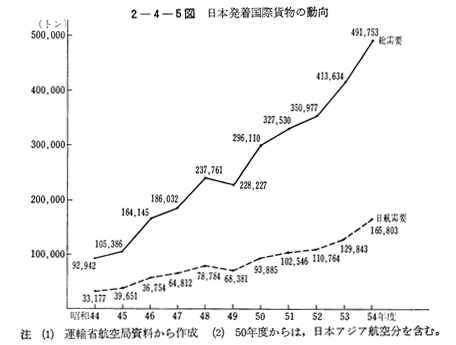|
2 国際航空輸送のめざましい発展
この10年間,我が国の国際的地位の向上とも相いまって,諸外国との航空協定締結,国際路線の拡充は比較的順調に進められた。
まず45年には,懸案であった日本航空のモスクワ経由欧州線の自主運航が開始され,従来の南回り,北回りと比べ欧州線は時間的に大幅に短縮されることとなった。これに続きフィリピン,メキシコ,ギリシャとも協定が締結された。また,49年には日中国交正常化後初の実務協定として日中航空協定が締結され,北京一東京間に定期航空路線が開設された。53年にはイラクとも航空協定が締結された。更に,同年5月には長らくの懸案であった新東京国際空港の開港が幾多の困難を乗り越えて遂に実現をみ,これを背景として,同年にはイラク,55年にはニュー・ジーランド,バングラデシュ,フィジー,スペインとの間にそれぞれ協定が結ばれ,定期路線が開設された。この結果,55年9月現在,我が国は36か国(うち仮署名1か国)と協定を締結しており,我が国に乗り入れている外国定期航空会社は36社にのぼり,また我が国航空企業は世界の44都市に乗り入れている。一方,従来国内線のみが就航していた国内空港についても,東南アジア等の近隣諸国との間の国際定期路線の開設が進められ,47年には名古屋,48年には新潟,鹿児島,54年には長崎,熊本,小松の各空港に国際定期便が就航を開始している。なお,我が国は現行の日米航空協定に存する種々の不平等を是正するため,51年日米航空交渉を開始したが,双方の立場の隔たりは大きく,現在のところ進展をみるに至っていない。
以上のような経過を背景として,我が国に係る国際航空輸送はこの10年間めざましく発展してきた。日本発着国際旅客数の推移を示したのが 〔2−4−4図〕である。
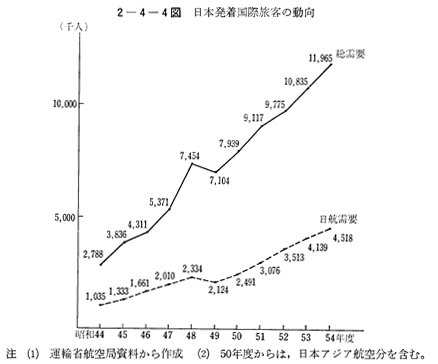
旅客数は,44年度の280万人から1,200万人と,約4.3倍に伸びている。その推移を見ると,40年代後半においては48年の第1次石油危機に続く世界的な景気停滞により,49年度から50年度にかけて一時的な伸びの低迷を見たものの,基調としては我が国経済の高度成長に伴い業務渡航が増大するとともに,所得の向上により海外旅行が身近なものと考えられ始めたこと等から日本人旅客を中心に観光旅客が増大したこと等もあって,年平均20%以上の大幅な伸びを示した。50年代に入り我が国経済が安定成長期に移行した後は,40年代ほどの伸びは見られなくなったものの,依然として堅調な増勢が続いたが,54年度からは第2次石油危機の影響により,増勢が鈍化している傾向にある。なお,これら旅客輸送量のうち我が国航空企業の輸送量は,44年度104万人(シェア37%)が54年度で450万人(シェア38%)(約4.3倍)と全体の伸び率をやや上まわる伸びを示している。国際民間航空機関(ICAO)加盟国の航空企業の国際有償定期輸送量の順位で見ると,日本航空は,44年の7位から54年には,パンアメリカン航空,英国航空,エール・フランスに次いで4位へと躍進を果たしている。
一方,国際航空貨物輸送の分野においては 〔2−4−5図〕のとおり,出入国貨物量は49年度に前年の石油危機の影響のため一時的に需要減となったが,全体的には44年度9万トンが54年度49万トンと5倍を超える伸びを示した。
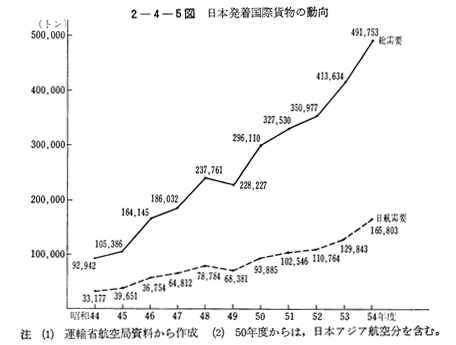
|