|
1 世界の国際航空政策の動向
バミューダ体制はそもそも,戦後の米国の絶対的に優位な力関係を背景に構築されているが,上述の国際航空をめぐる環境の変化によりその見直しの気運が高まっている。その発端は,バミューダ協定の一方の当事国であったイギリスが,バミューダ協定はその後の変遷を経て実態的に不平等であり,かつ新しい航空秩序の確立の必要ありとして,51年6月協定廃棄通告を行い,52年6月新協定(バミューダII)の合意を得たことである。このような不平等是正,秩序の再構築の動きは我が国をはじめ世界の多数の国に見られるところである。
アメリカは,戦後,世界の国際航空輸送において大きなシェアを占めてきたが,各国航空企業の発展等によりこの地位は相対的に低下してきており,最近ではそのシェアは20%を割っている 〔1-8-21表〕。また,バミューダIIの成立をはじめとする各国の不平等是正,航空秩序再構築の動きがアメリカに対して強まってきている。これに対してアメリカは,そのシェアの回復,拡大を図るべく,53年8月に自由競争主義を強く打ち出した新国際航空政策を発表した。新国際航空政策は,その具体的目標として,①競争的運賃の導入,②チャーターの自由化,③定期輸送における輸送力,便数,路線権等の規制の排除,④複数のアメリカ企業の弾力的な指定等を掲げ,このような競争機会の拡大が消費者の利益につながるものであり,各国との航空交渉はこれらの具体的目標の実現を自的として行うべきものとしている。
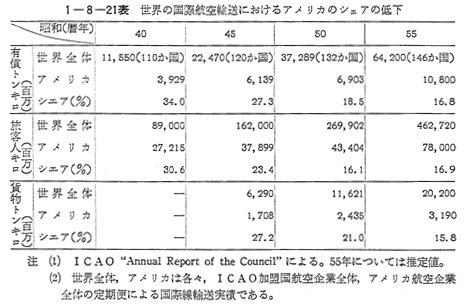
アメリカは,この新政策の発表の前後に各国と相次いで交渉を行い,アメリカの主張を大幅に受け入れさせた形で,リベラルアグリーメントと呼ばれる二国間協定を改定ないし締結した。これら諸協定の多くには,政府による輸送力規制の排除,運賃に関する発地国主義(ある国発の国際航空運賃は,当該国政府の認可のみで発効するという方式)ないし二重不承認主義(国際航空運賃は両国政府が不認可に合意しない限り発効するという方式)の採用,チャーター規制に関する発地国主義(ある国発のチャーターについては当該国の規制のみが適用されるという方式)の採用等,従来のバミューダ型協定には見られない新しい規定が盛り込まれている。
国際民間航空機関(ICAO)の従来の活動は航空の技術的問題,法律的問題に関するものが多かったが,近年,国際航空において深刻化している経済的問題についても世界的なベースで検討すべきであるとの要求が高まり,52年4月以降,①輸送力規制問題,②不定期航空問題,③運賃設定機構問題④運賃遵守問題等について検討が続けられている。
|