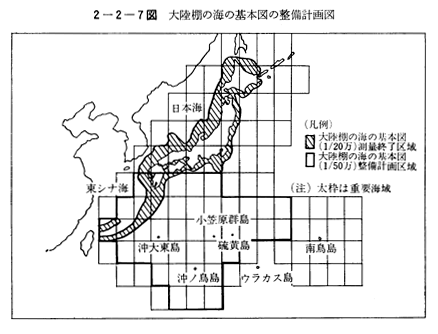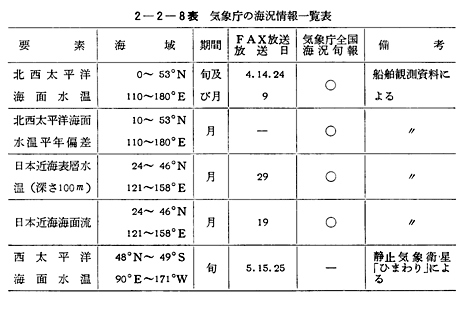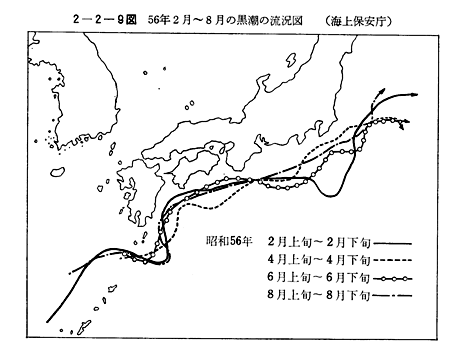|
3 新海洋秩序の形成と海洋調査及び開発の推進
(1) 海洋調査の推進
本年4月に採択された海洋法条約の審議の経緯及び概要は前述のとおりであるが,本条約が我が国について発効した場合,我が国は,12海里の領海を超えて距岸200海里に及ぶ排他的経済水域等について管轄権を行使し得ることとなる。
国土が狭小であり天然資源にも恵まれていない我が国が今後も経済社会の発展を図っていくためには,新たに管轄権を有することとなるこの広大な海洋空間(国土面積の約10倍)及びそこに賦存する生物資源,鉱物資源,エネルギー資源等の開発及び利用を環境保全に配慮しつつ積極的に推進していくことが極めて重要である。そのためには,領海,排他的経済水域等の正確な確定及び管轄海域における各種海洋の開発・利用のための基礎資料の整備がまずもって必要とされる。
運輸省では,これまで,調査用船舶,波浪観測施設,検潮所,ブイ,航空機,気象衛星等を配置して,海上交通の安全の確保,気象等の予警報,港湾・航路の整備,沿岸防災,海洋環境保全等の施策を円滑に実施するために必要とされる各種海洋データの整備に努めてきたが,今後とも,56年7月の運輸技術審議会答申「1980年代における海洋調査の推進方策について」に沿って各種海洋調査を積極的に推進し,海洋開発・利用の基礎固めに努めていくこととしている。
ア 領海,排他的経済水域及び大陸棚の確定のための調査
海洋法条約が発効した場合,加盟国は自国の領海に関し所要の基線又は外側の限界の線を確定し,更に,200海里排他的経済水域及び大陸棚に関する外側の限界の線を海図等に記載し,これらを適当に公表する義務を負うことになる。なお,自国の大陸棚が距岸200海里を超える場合には,自国について条約発効後10年以内に大陸棚の限界の詳細とその証拠となる海底地形及び海底地質構造等の資料を同条約に基づいて設置される「大陸棚の限界に関する委員会」に提出し,同委員会の勧告を基礎として沿岸国が大陸棚の外側の限界の線を設定することとなっている。海上保安庁では,沿岸の海の基本図の整備(48年度より),領海基線調査(52年度より),人工衛星を利用した遠隔島しょの位置精密測定(55年度より),測地衛星とレーザー測距装置等による日本列島の位置精密調査(57年度より)等の調査を行っているが,これらの調査の結果を踏まえ,領海,排他的経済水域等の外側の限界の線を確定しそれらを記載した海図の作成を行うこととしている。
なお,排他的経済水域を超えて我が国の大陸棚となる可能性のある沖大東海嶺,小笠原海台周辺等の海域における大陸棚外側の限界の線確定のための調査 〔2−2−7図〕を実施するため,56年度から最新鋭の大型測量船の建造を進めている(完成予定58年度)。
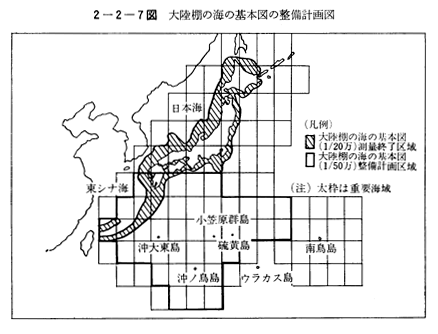
イ 海洋環境保全及び監視のための調査
海洋法条約は,沿岸国に対し海洋の開発及び利用から海洋環境を保護し,かつ,保全する義務を課しており,そのための国際協力をうたっている。運輸省では,船舶からの海洋への油の排出,廃棄物の投棄等について監視を強化するとともに,現況把握のために油分,重金属等についての分析調査を実施してきており,なお一層の充実強化が必要とされる。また,国際協力としてユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)で進められている海洋環境汚染全世界的調査(GIPME)の海洋汚染モニタリング計画に参加し,廃油ボールの漂流,漂着及び溶存・分散状油等に関する調査を実施している。
ウ 海洋データの国際交換の促進
世界各国で得られる海洋調査データの有効利用を図るため,その国際交換が行われている。
海上保安庁の海洋資料センターでは,我が国唯一の総合的海洋データバンクとしての役割を果たすとともに,IOCの推進する国際海洋資料の交換システムにおける我が国の責任国立海洋資料センターとしての機能を果たしている。同センターでは57年度から新たに波浪データを加え,IOCの標準的取扱データ17項日中14項目を取り扱うこととしており,今後ともデータ項目の増加及び量の増大に対応できるようデータの収集,整理及び保管体制の整備並びに提供体制の強化を進めている。一方,気象庁においては,世界気象機関(WMO)とIOCとの共同で推進している全世界海洋情報サービスシステム(IGOSS)計画に積極的に参加・協力し,表層水温,表面水温及び塩分のデータの即時国際交換を行っている。
エ 広域観測システムの整備
気象庁では,広大な海域において即時的な海洋データの取得を図るため,56年度には静止気象衛星「ひまわり2号」の打上げ,海洋気象ブイロボット8号機の整備のほか,気象・海洋観測船の測器の近代化等を行い観測精度及び観測能率の向上に努めた。また,一般船舶,漁船,国際機関の協力を前提とした即時的な広域海洋データ収集網の整備を進めるとともに,より迅速にかつ精度のよいデータを利用者に提供するための気象資料自動編集中継装置(ADESS)の整備拡充を図っている。
また,海上保安庁では,漂流ブイと人工衛星を利用した即時海洋データ取得システムの開発を進めており,56年度には漂流ブイの国産化等観測技術の向上,観測機器の開発を行い,黒潮の海流モニタリングを実施した。
オ その他
(ア) 海況情報の提供
気象庁は,気象・海象の予警報,海況等の提供の充実に努めており,56年度から外洋波浪実況図に加え,新たに24時間後の同予報図をFAX放送により発表している。また,同庁は 〔2−2−8表〕のとおり,旬及び月間の海洋情報を提供している。
海上保安庁では,日本近海において,最大の流量・流域を有する黒潮本流,大王埼沖の暖水渦,遠州灘沖の冷水塊の動向等の諸現象解明のための調査を進めるとともに海洋速報等により一般に通報している。
(イ) 海況予測の実施
気象庁では,毎年3月と5月に夏期を対象とした日本近海の海面水温,黒潮,親潮等の特徴的な海況予測を公表しており,56年度も引き続き予測手法の改良,予測期間の短縮等のための技術的検討を行った。
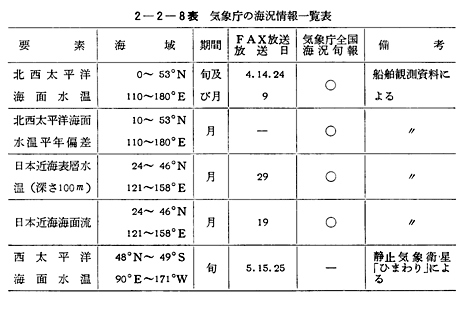
海上保安庁では,将来の海況予報の実施のための基礎資料を得るため,黒潮の動向を定期的に監視している 〔2−2−9図〕。
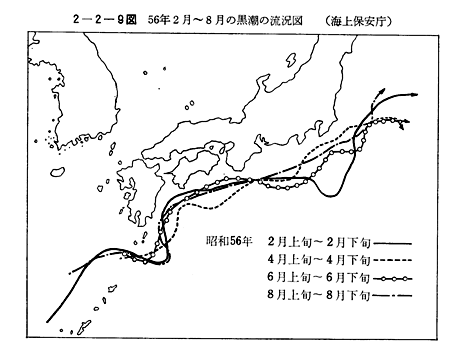
(ウ) 沿岸防災のための監視体制の強化
気象庁,港湾局,海上保安庁では,高潮,津波等による沿岸における自然災害の有効な防止を図るため,沿岸波浪,潮汐観測等の地域観測体制の拡充,観測データ処理の迅速化のためのテレメータ化による中央情報処理・監視体制の整備を図ってきているが,56年度も引き続きこれら諸施策を実施した。
(エ) 砕破帯域での観測の強化
港湾局では,港湾計画アセスメント手法の一環として,海底地形変動予測手法の開発に資するため,砕破帯域での波の変形,海浜流,漂砂等の現地観測を行うこととし,56年度には茨城県鹿島灘において観測用桟橋の建設に着手した。
(2) 海洋利用技術の開発
海洋空間の利用と各種海洋資源の開発を進めるためには,その基礎となる海洋利用技術の開発が不可欠である。
運輸省は,従来より,海洋利用技術として港湾建設技術及び造船技術の開発を推進しており,これら技術を駆使して流通及びエネルギー備蓄のための港湾整備,臨海部における工業用地等の造成,更には,沖縄アクアポリス,神戸ポートアイランド等にみられるような海上都市の建設等海洋空間の積極的利用を図ってきたところである。しかしながら,比較的容易に利用可能であった浅海域における沿岸空間の確保が今後困難となることが予想されており,より大水深下における大型海洋構造物の建設技術の開発が必要となっている。このため,港湾技術研究所及び船舶技術研究所において,埋立式,着底式及び浮体式の大型海洋構造物の建設におけるそれぞれの技術課題について研究開発が進められており,来たるべき海上空港,大水深港湾,沖合人工島等新たな建設ニーズへの対応を図っているところである。
海底資源開発技術に関しては,資源開発を効率よく進めるための各種海洋開発用機器に関する技術開発,海洋開発に不可欠な各種作業船の開発等を推進するとともに,最近の海底石油資源開発の大水深化に伴い,脚支持又はアンカー係留の不要な自動位置保持装置を備えた大深度石油掘削船の技術開発にも力を注いできている。
一方,海洋エネルギーに関しては,我が国は世界に先駆けて波エネルギーを利用した灯浮標の実用化に成功した。これは,海上保安庁が防衛庁等と協力し,小型ブイ用電源として開発したもので,無保守・省力化・省エネルギーを目的とし,比較的波浪及び船舶の輻輳する航跡波の多い所で保守条件の厳しい場所に設置されている。現在,波エネルギーの具体的利用方策の一つとして,積雪地域の港湾において波エネルギーを電力エネルギーに変換し,当該港湾内での融雪などに利用できないかといった研究が行われている。
このほか,海洋開発と表裏一体で進めなければならない海洋環境保全のための技術に関しても,大量流出油拡散防止,内湾等における堆積汚泥の除去等に関する技術開発を推進しており,開発と環境保全を同時に達成するための努力を続けている。
|