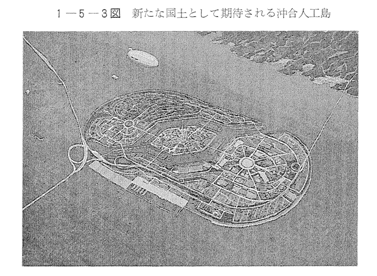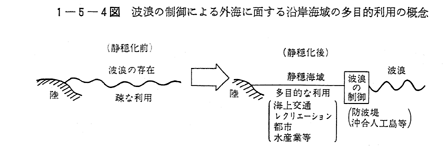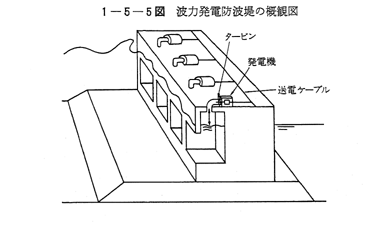|
3 海洋の開発・利用の推進
先に述べたとおり,今後の我が国の発展のために,海洋の開発・利用のより一層の推進が強く望まれているが,運輸省では,より広域にわたる海洋の開発・利用を促進するため,海域の利用の現状,自然的・社会的諸条件,地域における諸課題等を勘案のうえ,総合的な観点にたった施策を進めてきている。
(海域利用の現状と課題)
海洋空間の中で,沿岸海域は国民生活と密接に結びついた空間として盛んにその開発・利用が進められており,運輸省は従来から沿岸海域の開発等を通じこれらの海域の開発・利用の推進に関し重要な役割を担ってきている。しかし,多目的かつ高度に利用がなされているのは,一般的には,このような港湾やこれ以外の自然条件に恵まれた内湾・内海の一部であり,これらの海域を除いた沿岸海域は,総じて海域利用の程度は低く単機能的な利用にとどまっている。
多目的かつ高度な利用がなされている三大湾等の海域では,海域利用のニーズが高く,船舶の航行の安全確保,環境の保全・改善などの面での課題も多いことから,一層の計画的利用の推進が必要となっている。
また,海域利用の程度の低い,外海に面する沿岸海域は,我が国のフロンティアとして,将来に向けて,その開発・利用を誘導していく必要があるが,波浪等の厳しい自然条件等が原因となって,そのポテンシャルが十分に発揮されておらず,これらの海域の開発ポテンシャルを導き出すための施策が求められている。
これらの課題に対し,運輸省では以下に述べる施策を推進している。
(多目的かつ高度な利用がなされている海域における計画的利用の推進)
三大湾等の既に多目的かつ高度な利用のなされている海域には,複数の港湾区域が境を接して設定されており,これらを中心とした多様な海洋空間の利用を図るため,運輸省では,これら海域の利用と保全のあり方を検討し,総合的な観点にたった各種の方策を定め,計画的利用を推進してきているが,今後は,人工島等による新たな発展の場を整備するとともに,廃棄物の広域的処理,広域的な環境改善のための施策等を含め,一層の計画的利用を推進することとしている。
(外海に面する沿岸海域の有効利用の推進)
外海に面する沿岸海域の有効利用を促進するにあたっては,これを先導するプロジェクトの策定と推進,海洋環境の保全も含めた海域のポテンシャルに適合した開発利用の誘導等が必要であるが,従来から検討を進めてきている「沖合人工島構想」は,これまで多目的な利用のなされていない沖合海域に新たな国土を創造しようとする構想であり,運輸省では今後の海洋空間の有効利用推進のためのプロジェクトの有力な一つとして積極的に推進していくこととしている 〔1−5−3図〕。また,これら海域の有効利用を促進するためには,波浪の制御が必要不可欠であり,波浪の制御により波の荒い海域を内湾・内海なみの波静かな海域(静穏海域)とし,海域の利用ポテンシャルを高め,多目的な利用を図ろうとする構想についても,今後推進していくこととしている 〔1−5−4図〕。
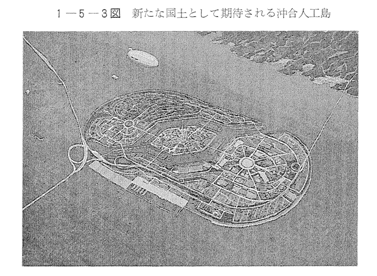
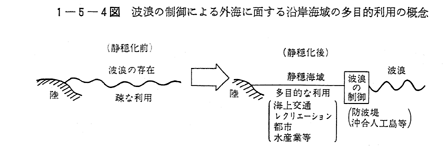
また,今後の海洋の開発・利用の推進のためには,より厳しい自然条件の克服のための技術開発が必要であり,運輸省では,港湾整備,海上空港整備等で培われた海洋土木技術及び世界の造船業をリードしてきた造船技術を結集することにより,これらの技術開発に取り組んでいる。
海洋空間利用技術に関しては,今後の利用海域の大水深化等に対応し,マルチセルラー式防波堤等の新型式防波堤,浮遊構造物等の開発を進めるとともに,耐久性,耐低温性に優れより広範な用途への適用が可能な鋼とコンクリートによるハイブリッド海洋構造物の開発を進めている。また,大水深海域における海洋構造物の建設に必要な水中作業ロボットの開発,洋上施工技術の開発等を行っている。
海底資源開発技術に関しては,注目される北極圏の豊富なエネルギー資源の開発のための氷海用石油掘削船等各種の海洋開発機器,作業用船舶の開発及び氷海域における資源開発と不可分な輸送手段確保のための砕氷タンカー等の氷海用船舶の研究を推進している。
海洋エネルギー利用技術に関しては,防波堤に発電機能をもたせた波力発電防波堤の開発を行っている 〔1−5−5図〕。
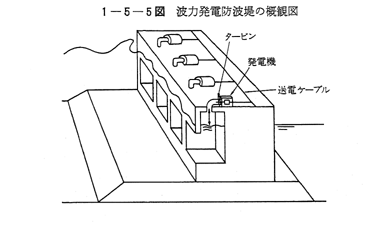
|