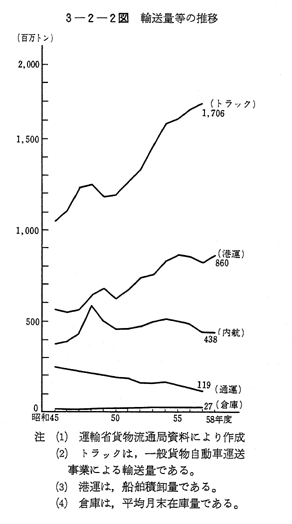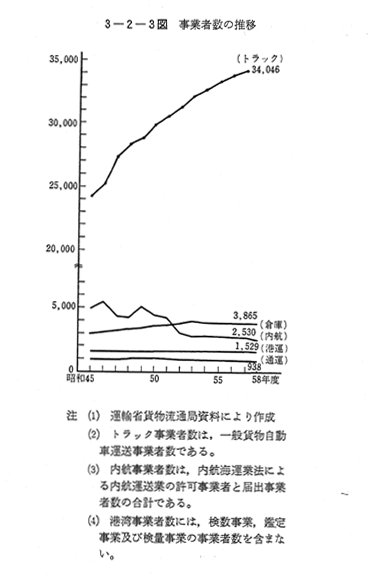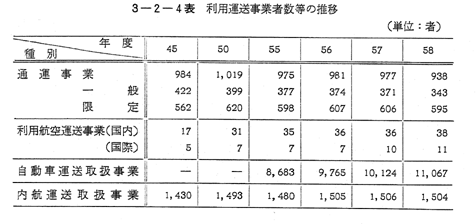|
2 個別の貨物流通企業対策等
(1) 貨物流通企業の現状
(貨物流通企業の活性化)
貨物流通関係の企業としては,トラック,内航,港運,通運,倉庫等があるがこのうちトラックが,最近の小量,多頻度,迅速な輸送を求める荷主ニーズを反映して輸送量,事業者数とも伸びているのに対し,その他については,素材産業の不況,港湾荷役の革新,国鉄貨物の合理化,在庫管理の強化等に伴い,内航,港運,通運,倉庫とも横ばいまたは減少の傾向にある 〔3-2-2図〕, 〔3-2-3図〕。
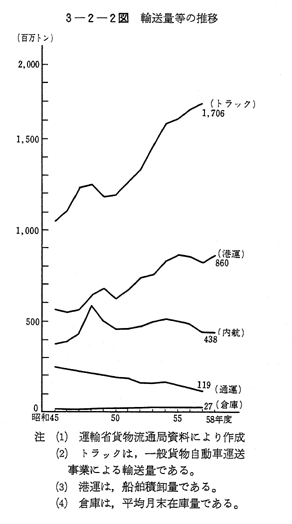
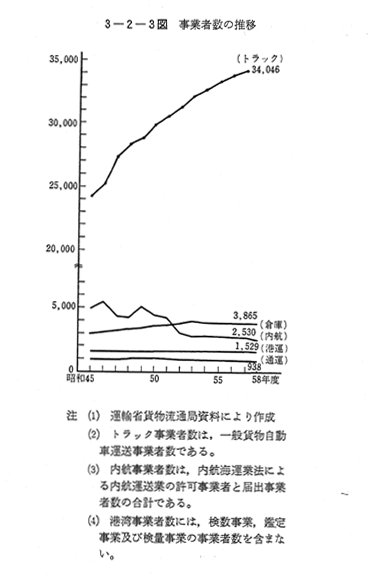
また,国鉄貨物については,トラック等他の輸送機関への転移等により,輸送量の減少が続いている。
貨物流通関係の企業は大部分が中小企業であることから,不況に直面している業種について適切な不況対策を講ずるとともに,より抜本的に構造改善対策を進め,その経営基盤を強化して貨物流通関係企業全体の活性化を図っていくことが必要である。
また,このような中小企業対策とあわせて,当面の輸送秩序の確立についても同時に進めていく必要がある。
(2) 内航海運対策
① 不況対策
(船腹過剰処理対策)
内航海運は,国内貨物輸送の47%(トンキロベース)を担う基幹的な輸送機関であり,石油,鉄鋼,セメント,石灰石等素材型産業の製品及び原材料がその大宗貨物となっているが,第2次石油危機以降の素材型産業から加工型産業への比重の移行等に伴う輸送需要の減少等により,構造的不況に陥っている。
この結果,貨物船及び油送船について著しい船腹過剰が生じており,船腹過剰の解消による需給バランスの回復が急務となっている。
このため,運輸省及び内航海運業界においては,次のような施策を講じてきている。
(ア) 内航船腹量の最高限度の設定
58年3月及び59年3月,船腹削減対策の目標を示すものとして,内航船腹量の最高限度を設定した。
(イ) 船腹削減対策の実施
(ア)の最高限度の設定を受けて,内航海運業界では日本内航海運組合総連合会を中心に船腹削減を行っている。
削減の方法は,スクラップ・アンド・ビルド方式及び不要船舶の買上げ方式の併用によっている。
(ウ) 税制上の特例措置
上記船腹削減対策及び次の構造改善対策の促進を図るため,59年度から,最高限度の設定された船種に属する船舶から減価償却資産への買換えで構造改善等に資するものについて課税の特例(圧縮記帳)が適用されることとなった。
(エ) 内航船舶の近代化
内航船舶の近代化とスクラップ・アンド・ビルドによる船腹削減を図るため,船舶整備公団が共有建造方式により内航船舶の建造を行っている。
② 構造改善対策
(内航海運業構造改善対策)
内航海運業界は,59年3月31日現在9,037事業者が存在し,このうち中小企業が96%を占めるという零細事業者乱立型の業界構造となっている。特に,船舶貸渡事業者にこの傾向が著しい。
このような状況を改善するため,59年6月に次のような骨子の内航海運業構造改善指針を策定し,所要の施策を推進していくこととしている。
ア 内航船舶貸渡事業者数を約20%減少させるとともに,内航海運組合を原則として県レベルの単位に再編統合すること。
イ このため,日本内航海運組合総連合会による転廃業助成金及び集約合併給付金の交付,資産の買換えの課税の特例の活用等の施策を総合的に実施すること。
③ 今後の方針
(内航海運の将来像の策定)
今後とも過剰船腹の処理及び構造改善のため以上の対策を着実に実施していくとともに,その後に続く内航海運の将来像を策定するための検討を行うこととしている。
(3) 港湾運送事業対策
(規制の見直しを実施)
近年のコンテナ埠頭等の近代的な港湾施設の整備,近代化船,合理化船の普及などにより,港湾運送においては,コンテナ荷役,サイロ荷役,自動車専用船荷役のようにはしけを介さずに船内作業,沿岸作業を一貫して行う革新荷役が増加し,港湾運送量に占める革新荷役の比率は全国ベースで40年の1.7%から57年の71.2%へと飛躍的に増大している。このような革新荷役の進展は,荷役効率の向上をもたらした反面で,港湾運送事業に関する規制が実態と乖離するという事態が生じてきたため,港湾運送事業に関する規制の見直しを行い,効率的な港湾運送事業の実施を将来にわたって確保するため,以下の措置を実施した。
① 荷役形態が在来荷役に比較して著しく異なる等により,高能率で荷役が行われているものについて適用する特殊料金について,その認可基準を定めた。
② 最近における荷役効率の向上等にかんがみ,施設及び労働者に係る免許基準について改定を行った。
③ 事業の種類について,船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して港湾荷役事業とすること及び一般港湾運送事業者についての下請に関する規制を弾力化し,コンテナ埠頭等の施設において自らの統括管理の下に一定量以上の港湾運送を行う場合にも関連事業者に下請をさせることを認めることを内容とする「港湾運送事業法の一部を改正する法律」が59年7月13日に成立し,同20日に公布された。
(構造改善対策の推進)
一方,取扱貨物量が減少し,厳しい経営状況にある在来荷役,特に需給の不均衡が恒常化し,構造不況に陥っているはしけ運送業,いかだ運送業については,各種不況対策法に基づく業種指定,財団法人港運構造改善促進財団の活用等により事業経営の安定化,雇用の安定化等を図ってきた。今後もこれらの諸制度を活用し,港湾運送事業の構造改善対策を推進していくこととしている。
(4) トラック運送事業対策
(求められる運営の効率化)
トラック輸送は我が国国内貨物輸送の大宗を占めているが,約3万5,000に上るトラック運送事業者はそのほとんどが経営基盤の脆弱な中小企業であり,荷主に対し取引上弱い立場に置かれることが多い。
このため,運賃ダンピング,過積載,過労運転,違法白トラ等のいわゆる輸送秩序の乱れが生じ,問題となっている。
また,近年,荷主サイドにおける物流コストの圧縮の影響を受けて,トラック運送事業の運営の効率化が強く要請されるほか,大気汚染,騒音等の公害防止の観点などからも,より効率的なトラック輸送体系の形成が求められている。
このため,運輸省としては次のような施策を推進している。
① 輸送秩序の確立はトラック運送事業が利用者の要請に応えて,良質なサービスを安定的かつ効率的に提供していくための大前提であるとの認識に立って,違法行為の取締りと違反の是正のための指導を行うほか,中小企業性を克服し,経営基盤を強固なものとするため協同組合化(58年度末935組合),施設の近代化,情報システム化,人材育成等を内容とする総合型構造改善事業を実施している。
② 効率的なトラック輸送体系の形成のため,自家用トラックから効率の良い営業用トラックへの転換,都市内における共同輸送システムの普及,フレートライナー,カーフェリー等を利用した協同一貫輸送の推進等を図っている。また,経済社会の変化に合わせて,輸送効率の向上を図るため,一般区域トラック運送事業の事業区域について見直しを行い,59年3月,従来の都府県等を単位とする事業区域を首都圏及び阪神圏については拡大し,東京都,神奈川県,千葉県及び埼玉県を合わせた首都圏区域並びに大阪府及び兵庫県を合わせた阪神圏区域という拡大事業区域の設定を認めることとした。
③ 運輸事業振興助成交付金(58年度約145億円)を活用し,社団法人全日本トラック協会及び各都道府県トラック協会を通じ,中小トラック運送事業の近代化,トラック輸送サービスの向上,交通安全対策,環境対策,トラック運転者の休憩施設であるトラックステーションの整備(59年10月末現在13か所)等の施策を推進している。
運輸省としては,我が国物流体系の中心を占めるトラック輸送が多様化する利用者のニーズに今後とも応えていくため,諸般の施策を通じ,トラック運送事業の発展を図っていくこととしている。
(5) 国鉄貨物輸送の合理化
国鉄貨物輸送は,近年,輸送量が減少し続けており,58年度においても,271億トンキロと,国内貨物輸送の6.4%まで落ち込んでいる。
これは,主としてヤード系集結輸送の輸送速度が遅く,また,到着日時が不明確である等輸送サービスの質が劣り,トラック等への転移が進んだためと考えられる。
そこで,国鉄貨物輸送が,大量,定型という鉄道特性を十分に発揮するために,59年2月,非効率なヤード系集結輸送を全廃し,拠点間直行輸送システムへ転換するとともに,貨物取扱駅を再編成し,低コストで競争力のある輸送機関の実現を図ったところである。
今後は,拠点間直行輸送システムをさらに深度化し,コンテナを中心とした効率的な輸送体制を確立することとしている。
これにあわせて,関連する通運業界についても,後述のような対策を講じていくこととしている。
(6) 利用運送事業等対策
① 利用運送事業等の現状
(重要性を増す利用運送事業等)
利用運送事業等には,内航運送取扱業,通運事業,自動車運送取扱事業,利用航空運送事業等があり,利用または取扱の相手方となる運送事業の動向と同様,自動車運送取扱事業及び利用航空運送事業が伸びている反面,内航運送取扱業及び通運事業は,横ばいまたは減少傾向にある 〔3-2-4表〕。
これらの事業は,運送事業者の販売窓口として,また高度化,多様化する荷主のニーズに応えて適切な輸送手段を選択するフォワーダーとして,貨物流通関係企業の発展に重要な役割を果たしており,今後とも健全な育成を図る必要がある。当面,前述の国鉄貨物輸送の合理化に対応する通運事業対策の推進が緊急の課題となっている。
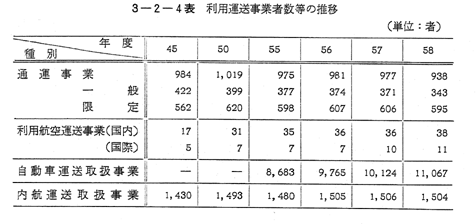
② 通運事業対策
(国鉄貨物合理化に対する通運対策)
国鉄の貨物輸送量は39年度の2億700万トンをピークに年々減少し,58年度においては8,600万トンにまで落ち込んでいる。この国鉄貨物輸送の低落と相次ぐ国鉄貨物の合理化等により,今後の通運事業経営は全体としては縮小傾向を辿り,各事業者は経営の一層の多角化,総合化を志向するものと思われ,通運行政もこれらの事態を踏まえた新しい展開を求められることとなる。
当面,59年2月に実施された国鉄貨物のシステムチェンジに関連した通運対策としては,次のような措置を講じた。
(ア) 運輸事業振興助成交付金の活用による融資制度を充実し,設備資金の融資限度額を引き上げる(施設については1駅1事業者につき2,500万円→5,000万円,車両・荷役機械等については1駅1事業者につき1,500万円→3,000万円)とともに,退職金資金等の運転資金(融資限度額1事業者につき5,000万円)を新たに融資対象に追加した。
(イ) 国鉄貨物合理化に基く貨物駅の廃止等により営業基盤を無くした通運事業者が引き続き営業活動を行えるよう,付換免許の統一基準を作成するとともに,免許等の行政事務の円滑化,迅速化を図るため,地方運輸局長に大幅な権限委譲を行った。
(ウ) 国鉄貨物合理化によって影響を受ける通運従業員の雇用の維持,安定を図るため,58年12月に通運業が雇用調整助成金の対象業種に指定された。
(エ) 国鉄貨物輸送の新体制に伴い,通運事業運賃料金につき,コンテナ通運デポ扱貨物の割引料金の設定,集配料の遠距離てい減制の拡大を行い,コンテナの増送を図った。
今後は,引き続き前記施策を推進するとともに,新しい貨物流通政策及び国鉄貨物輸送の今後のあり方に対応し,必要な施策を講じていくこととする。
(7) 貨物流通施設対策
① 貨物流通施設の整備
(倉庫とトラックターミナルの整備)
陸海空にわたる貨物の円滑かつ効率的な輸送を図る上で,流通の結節点等に立地する倉庫,トラックターミナル等の貨物流通施設は必要不可欠なものとなっている。
倉庫は,その保管機能を通じて,物資の需給調整を行い,国民生活及び産業活動の安定並びに物資の円滑な流通に大いに寄与してきている。このような倉庫の整備は,保管需要に見合って行われることが望ましいが,変化する需要に応じて短期的に供給量を調整することは難しいため,中,長期的見通しに基づいて計画的に行われる必要がある。
このような観点から,運輸省では,40年以来,5次にわたり,倉庫整備5ケ年計画を策定し,中期的保管需要の見通しとこれに基づく倉庫整備の目標値を示してきている。
一方,大都市の周辺等においては,トラックターミナルの整備が進められてきている。トラックターミナルは,都市間の貨物輸送拠点として,あるいは都市内の集配送の拠点として,さらには,貨物輸送の中継基地としての役割を果たしており,これによりトラック輸送の合理化,効率化が図られ,あわせて大都市の交通混雑の緩和にも資している。
これらの貨物流通施設の整備には多大の費用を要することから,その円滑な推進を図るために,政府関係金融機関による融資措置が講じられている。
(民営移行される日本自動車ターミナル(株))
なお,日本自動車ターミナル(株)については,58年3月の臨調答申において,「東京都西南部のターミナルの整備終了後,会社の経理的基盤を確立した上で,政府保有の株式を順次放出し,自立化の原則に従い民間法人化又は第三セクター化する」こととされ,59年1月の閣議において,関西国際空港株式会社を特殊法人として設立することに伴い,かつ,臨調答申に即し,特殊法人たる日本自動車ターミナル株式会社を60年6月末までに廃止し,民営移行することが決定されており,これに基づき現在所要の法案を準備しているところである。
② 新たな倉庫業の運営の在り方の検討
(新たなビジョン作り)
近年における産業構造や流通機構の変化,消費者の志向の変化等により,荷主企業における在庫の圧縮,流通経路の短縮化等のコスト節減による保管需要の減少,消費需要の多様化に伴う保管需要の多頻度少量化等,今日,倉庫を取り巻く物流環境は大きく変化しつつある。さらに,国際化,情報化も一層進展しており,これらに伴い,荷主企業からのニーズも益々高度化,多様化してきている。
このため運輸省では,このような変化に的確に対応した倉庫運営が図られるよう,荷主ニーズヘの対応,事業の総合化等を目的とする新たなビジョン作りを進めているところである。
|