|
2 分割・民営化後の鉄道事業の展望と今後の課題
ア 新たな,活力ある事業経営
これら新会社は,鉄道事業法という新たな法体系の中で,改革の理念である適正な経営管理,地域密着の事業展開を図りつつ,自らの経営責任の下,厳しい競争条件にある交通環境に対応し,健全な,活力ある事業運営を続けていくことが期待されている。そして,こうした期待に応えることができる経営基盤を,その発足に当たって確保することとしている。 具体的には,新会社発足に際し, ① 要員体制及び業務運営の最大限の合理化,効率化を図り,過剰な要員体制を改めることとしている。この結果,新会社等の職員数は,215,000人の規模が見込まれており,これは,61年度首の現在員277,000人の約2割減の体制である。 ② 最近の試算によれば,国鉄改革に当たって処理すべき長期債務等は37.5兆円となっている 〔2-2-3図〕。新会社に対しては,その健全かつ円滑な経営に支障が生じない範囲で国鉄長期債務を承継させることとしており,本州の3旅客会社及び貨物会社が承継する国鉄長期債務として4兆7,700億円が見込まれている。これに新幹線使用料の形で負担する債務額8兆4,600億円を加えても,61年度初の国鉄長期債務23兆5,600億円に比べ,大幅に軽減されることとなる。 なお,北海道,四国,九州の三島の旅客会社については,その厳しい経営環境にかんがみ,国鉄時代の長期債務を全て免除することとするほか,経営安定のための1兆1,800億円(試算値)の基金を設け,これから生ずる約900億円の利息収入を事業の運営に要する費用に充てることとしている。
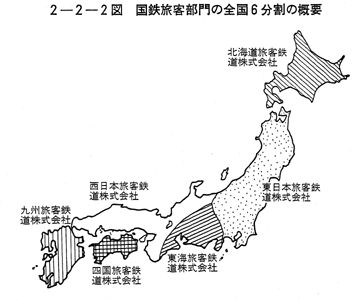
また,新会社は,61年9月に改正した運賃水準及び61年11月に実施したダイヤを引き継ぐこととなる。この結果,運賃制度としては,通算制が採用され,遠距離逓減制もそのまま維持される。また,ブルートレーン等の長距離列車も確保され新会社に引き継がれる。これに加え,11月ダイヤで全国的に導入を図った地域密着型の考え方は,新会社において更に一層推進され,より利用しやすい,親しまれる鉄道に向けて,様々な改善が図られるものと考えられる。また,「フルムーンパス」や「ナイスミディパス」等の全国的に利用される商品は,引き続き各社共同で販売されるであろうし,さらに創意を出し合って,今まで以上に良い商品が生み出されることが期待される。
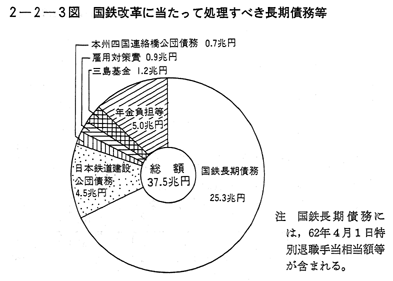
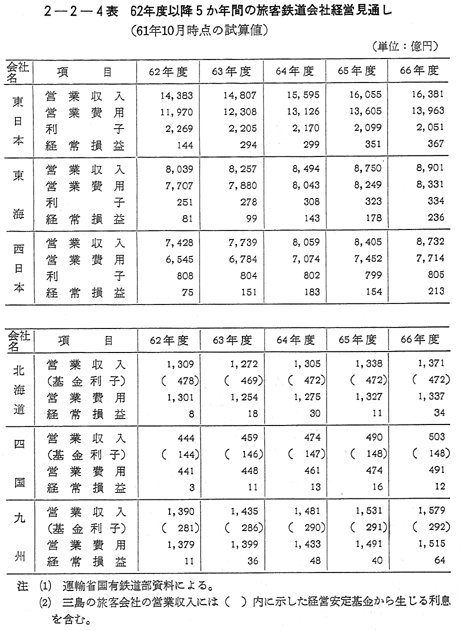
以上の体制の下で,発足する旅客会社の収支は当初より均衡し,以後経営努力を尽くすことによって,将来にわたり健全な経営を維持していけるものと見込まれている 〔2-2-4表〕。
イ 鉄道事業の新たな役割
(ア) 効率的な交通ネットワーク形成への寄与
鉄道による旅客輸送については,都市間輸送の分野でみれば,輸送距離300km~750kmといった中距離帯では今後とも鉄道が5割以上のシェアを堅持するものと考えられる。また,東京,大阪等の大都市圏やその他の主要都市の都市圏における輸送の分野についても,通勤・通学輸送を中心として輸送量は今後とも堅調に推移するものと考えられる。 また,'鉄道による貨物輸送については,長距離のコンテナ輸送及び石油,セメント等の大量定型輸送の分野において,現状においても,我が国の貨物輸送全体の中で相応のシェアを確保している。このような分野においては,徹底した輸送の効率化及びコストの低減を図ることにより,今後とも相応の役割を果たしうるものと考えている。 以上のような特性分野で鉄道が健全に運営され,効率的な交通体系の形成に資する役割を果たすことが必要であり,また,国民からも期待されるであろう。 今次改革の意義の第一のねらいは,国鉄の事業を効率的かつ活力ある事業運営が可能となるよう再生することにあり,健全経営の基盤整備と併せ,各社が効率的な経営に努めることにより,国鉄時代には十分発揮し難かった鉄道特性を取り戻し,これをより生かす方向で事業運営がなされるものと考える。これにより,鉄道の役割はより一層,利用者のニーズに沿ったものとなり,他の交通機関との適切な分担関係が形成され,望ましい交通ネットワークの整備に大きく寄与することとなろう。
(イ) 地域社会との調和と地域の発展への寄与
しかしながら,鉄道事業は通勤,通学,買物等の大量の日常交通を担っており,過去の私鉄の発展の歴史にも明らかなように,本来,地域と一体となり,地域の発展に寄与しつつ自らも経営を安定化させ,更なる飛躍を果たしていく面が大きいものと考えられる。 前述の61年ダイヤ改正の考え方にも見られるように,新会社は,分割・民営化により,全国画一のしがらみから逃れ,地域に目を向けた,地域社会に親しまれる鉄道として生まれ変わるべく 懸命の努力を続けるであろう。これによって,地域社会と鉄道との望ましい信頼関係が築き上げられ,地域の発展に寄与する鉄道会社としての使命が果たされることを強く期待するものである。 (利用しやすいサービス設定) このため,第一に,利用しやすいサービス設定が大切である。既にダイヤの改善については地域重視の考え方に沿った編成が試みられているが,この一層の推進が期待されるとともに,利用者の声を広くくみ取り,創意と工夫を生かして,スピードアップ,列車接続,始終発時刻,アコモデーションといった面での改善も,鋭意行われていくものと考える。 (地域との交流の密接化) 第二に,地域経済,地域社会との交流をより密接にし,地域の発展にできる限り寄与する方向で,対応を図っていくことが必要である。本社指向から地域指向へ経営の発想を改めることが分割・民営化により達成されれば,自らこうした対応がなされてくるものと考える。例えば,私鉄と比べ駅間の長い線区の改善のために新駅が設置されれば,駅周辺の再開発や道路接続の改良等によって地域住民の利便の向上に大きな効果を上げるであろう。また,駅は各地域の顔であり,周辺の商店街と合わせてその整備,活性化を図ることは,地域社会が進める街づくりと切り離して考えることはできない。なお,関連事業展開に当たっても,地域社会との調和のとれた営業活動を行うことが必要不可欠である。こうした点は新会社の経営方針に当然のことながら反映されるであろうし,またこれに応えていかなくてはならない。 (地方交通線の活性化) 第三に,地方交通線の活性化である。新会社における日常交通の重視及び地域社会との調和は,直ちに地方交通線の活性化に結びつくはずである。三陸鉄道(株)の例を見るまでもなく,地方の中小私鉄企業は,限られた輸送需要の中で,創意と工夫を生かし経営の効率化に努める一方,地域と一体となって集客努力を続け,何よりも,地元に愛される鉄道としての道を歩み,存続を図ってきている。新会社の経営する地方交通線は,特定地方交通線として第三セクターに転換した線区より輸送環境に恵まれているものが多く,また,本線のフィーダー線として全体の収益に寄与する面を持っていることから,より以上に存続,活性化が必要かつ可能な路線であり,新会社による経営の下で,より多くの地方交通線が地域の足として生かされるものと考える。
前述のとおり,国鉄改革の実施により,国鉄の経営していた鉄道事業の新たな発展が期待されるが,これと併せ,日本国有鉄道清算事業団の活動を中心とした,長期債務等の処理,職員再就職対策等に適切に対処していく必要がある。以下,それぞれの取組みの状況等について述べる。
ア 国鉄長期債務等の処理問題
また,長期債務等の本格的な処理のために必要な「新たな財源・措置」については,雇用対策,用地売却等の見通しのおおよそつくと考えられる段階で歳入・歳出の全般的な見通しとあわせ,検討,決定することとしているが,それまでの間,清算事業団に帰属した長期債務等の処理のため,財政事情の許容する範囲内で必要な国庫助成を行うとともに,清算事業団の資金繰りの円滑化を図るための措置を講ずる必要がある。
イ 国鉄職員雇用問題
この問題については,前述の「国鉄余剰人員雇用対策の基本方針について」(60年12月13日閣議決定)において,雇用の場の確保,新経営形態移行前後における再就職促進対策等の推進のための基本方針を定め,政府全体が一丸となって雇用対策の推進に全力を挙げて取り組んでいるところである。 国鉄改革に伴って生ずると見込まれる約6.1万人の再就職を必要とする職員の雇用の場の確保については,「国鉄等職員再就職計画」(61年9月12日閣議決定)で各分野別の再就職先の目標数が定められたところであるが,現在,公的部門,関連企業,一般産業界を合わせて,目標数を上回る数の採用の申し出が行われている。 また,新経営形態移行前の対策として,業務量に照らし著しく過剰である職員を少しでも減少させるため,希望退職を募集することとし,これを促進するための特別給付金の支給等を内容とする61年度特別措置法に基づき,6月30日から国鉄において希望退職者の募集を開始しているところである。 一方,改革後,清算事業団に移行することとなる職員に対しては,清算事業団において,職業指導,再就職のあっせん,再就職先のニーズを踏まえた教育訓練の実施等を行うことにより,3年間で全員が再就職することができるよう総合的,計画的な対策を講じていく必要がある。 政府としては,今後とも再就職に当たって国鉄職員及びその家族に不安を与えることのないよう,きめ細かな配慮を行うことにより,雇用対策の円滑な実施に万全を期していくこととしている。
ウ 国鉄共済年金問題
この問題については,第103回国会において,政府として「国鉄共済年金については,財政調整5箇年計画の終わる昭和64年度までは,政府として,国鉄の経営形態の動向を踏まえつつ国鉄の自助努力と国の負担を含め,諸般の検討を加え,支払に支障のないようにする。以上については,昭和61年度中に結論を得,その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ることとする。なお,昭和65年度以降分については,その後速やかに対策を講じ,支払の維持ができるよう措置する。」旨の統一見解を示したところであり,この見解に沿った各般の措置を検討・実施することにより,将来にわたって国鉄共済年金の円滑な支払を維持することが必要である。 このため,61年8月に大蔵大臣,運輸大臣,内閣官房長官及び年金問題担当大臣の4大臣で国鉄共済年金問題に関する閣僚懇談会を設け,この懇談会などにおいて,政府統一見解を踏まえ国鉄共済年金対策の検討を行っているところである。
国鉄の事業は,我が国の交通体系において極めて大きな役割を担っている。その事業が経営の危機に瀕している今,将来の世代にこの貴重な財産を引き継ぐために,我々は是非とも今回の改革を成功させなければならないと考える。
|