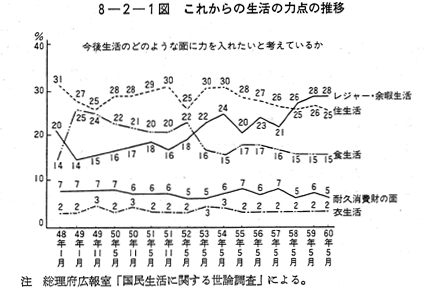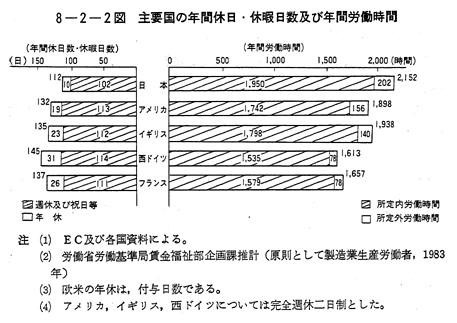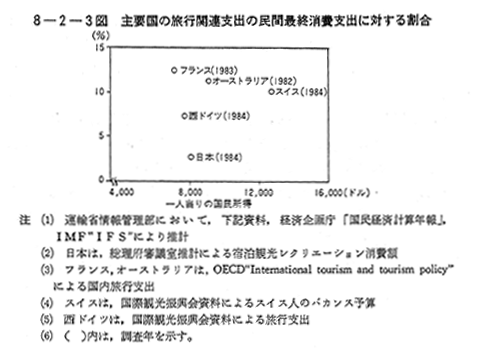|
1 国民意識の変化と余暇活動の動向
(余暇活動の意義)
国民意識の変化に伴い,近年,余暇活動は,衣食住と並んで国民生活の基本的要素と考えられている。総理府の「国民生活に関する世論調査」(昭和60年8月)によれば,今後の生活の力点を「レジャー・余暇生活」に置きたいという人が,58年以降「住生活」に取って代わり最上位を占めるに至った 〔8−2−1図〕。
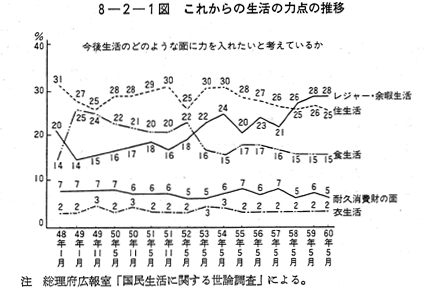
このように,戦後の食糧難時代を経て経済発展に全力を注いできた我が国が,その成果を上げ,生活レベルも物質的には相当満たされつつある現在,国民の意識の重点が余暇活動に向けられるようになったことは自然のすう勢といってよく,また,従来の経済重点志向から,ゆとり,創造性,ふれあい,健康などを求める人間らしさへの志向の変化は,それ自体として十分に意義が認められよう。
しかし,現在,我が国における余暇活動は,まだ量,質ともに必ずしも十分であるとは言えない状況にある。勤労者の余暇を休日数等でみると,30人以上の企業において,何らかの形で週休二日制の適用を受けている勤労者は77%(完全週休二日制は27%)であり,年次有給休暇の取得率も56%にすぎない(労働省59年賃金労働時間制度等総合調査報告)。また,休日・休暇日数を欧米と比較すると,我が国は年間20〜30日も少なく,年間労働時間も欧米諸国が1,600〜1,900時間台であるのに対し,我が国は2,100時間を超えている 〔8−2−2図〕。さらに,民間最終消費支出に対する旅行関連支出の割合をみても,西ドイツ7.8%,フランス12.3%に比べて我が国は3.2%と極めて少ない状況にある〔8-2-3図〕。
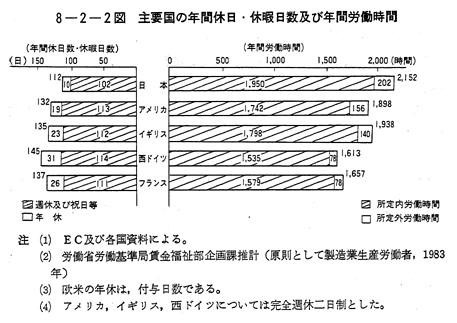
GNP世界第二位と経済大国になった我が国が,「世界の中の日本」として国際社会に幅広く受け入れられていくためには,余暇時間を有効に活用し,人間らしさを更に深め,「物」に片寄らない真の豊かさと柔軟性,あるいはそれらを通じた裾野の広い文化性を備えた国に成長していくことが今や重要な課題となっている。
(余暇活動の動向)
国民の余暇時間は,週休二日制や長期連続休暇の普及,主婦の家事時間の減少,高齢化社会の到来などにより拡大する傾向にあり,所得水準の向上とあいまって国民の余暇活動に対する潜在的需要は着実に増大している。総理府が行った「余暇と旅行に関する世論調査」(61年1月)によれば,平日の余暇時間は,「何もしないでのんびりする」,「テレビ,ラジオ,新聞,雑誌などの見聞き」などの休養型の過ごし方が多いが,週末などの休日や3日以上の連続した休日のように余暇時間が長くなるに従って,「軽い運動やスポーツ活動」,「飲食・ショッピング」,「宿泊旅行」,「日帰りの行楽」,「ドライブ」などの観光レクリエーションが増えていることがわかる 〔8−2−4図〕。したがって,今後,休日が増大していけば余暇の過ごし方は相対的にみて休養型が減り,スポーツ,旅行などの積極的な過ごし方のウェイトが高まることが予想される。
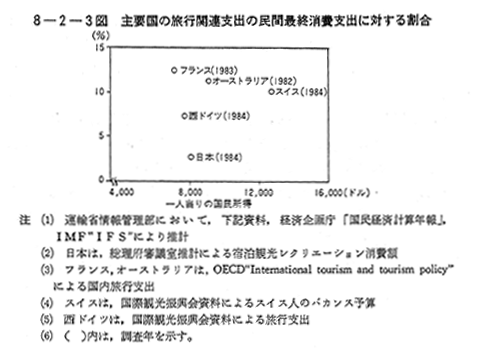

(余暇活動の促進)
国民の余暇活動へのニーズが前述のとおりであり,その円滑な促進が余暇活動の意義で述べたように重要であることを考えれば,国民の求める余暇が量的にも質的にも可能な限り実現される方向で,適切な対策が講じられるべきである。他方,経済摩擦や国際収支の大幅黒字などの見地からも,余暇活動に関してその消費支出を促すとともに,それに対応した施設などの投資も含めた内需拡大を図ることが必要である。
このため,労働時間についていえば,その短縮を図るなかで週休二日制の促進,連続休暇の着実な普及や年次有給休暇の一層の消化を図っていくことが求められる。運輸省においても,観光週間(8月1日〜7日)キャンペーン等を通じ,労働省等の関係省庁と連携して,「ほっとウィーク」を標語とした夏季における1週間以上の連続休暇の普及の促進を図っている。また,交通機関,道路,宿泊施設その他のレクリエーション施設への過度の集中による利用者の不便を避けるために,例えば連続休暇のとり方について,制度面,運用面からも検討が必要であるとともに,余暇活動を活発にするためのその他の環境作りについても一層の努力が重要である。
|