|
1 物流情報システムの整備(物流業界の情報化の現状) 近年における情報の伝達,処理に関する技術の進歩は著しいものがあるが,特に昭和60年4月の電気通信事業法の施行により電気通信事業が民間に開放されるなど,大幅に自由化されたことに伴い,産業の各分野において高度化・多様化する国民ニーズに対応した情報システムの構築が進展している。 物流業界においても,事業者が自らの業務の効率化を図るため,あるいは物流事業者相互間や物流事業者と荷主又は関連事業者との間で相互に物流情報を交換するため,情報通信ネットワークの形成が進められている。 すなわち,大手物流事業者の多くは,貨物の流れと情報の流れを一体的に管理することにより,貨物追跡,受発注,代金請求,在庫管理などに係る情報交換サービスを提供し,荷主の高度なサービス需要への対応を図る物流VAN注)を構築しているが,このうち,いくつかの事業者は,このネットワークを利用して一般的なVAN注)サービスを提供する事業にも進出している。また,この情報システムを利用した産地直送品の無店舗販売のような新たな事業への進出もみられる。さらに,62年9月,本格的な国際VAN注)の実現をめざした電気通信事業法の一部改正が施行されておきり,このような情報の国際化のなかで,大手物流事業者を中心に,物流情報システムを国際間の貿易情報交換などへと広げていく傾向にある。 一方,中小物流事業者においては,共同化によって情報システムへの参加や構築を行っている例もあるが,資金負担能力や人材の不足からネットワーク化が容易に進展しないという面もあるため,こうした中小物流事業者の情報化を効果的に進めることが今後の課題となっている。 (SHIPNETSの拡大) 港湾における船積貨物の輸出手続きや書類作成に係る貿易データの交換を貿易関連業種である海貨業者,船社,検量業者,検数業者間でオンライン化して行うシステムとして,61年4月にSHIPNETS(Shipping Cargo Information Network System : 港湾貨物情報ネットワークシステム)が本格稼働している。SHIPNETSは港湾貨物業務について,異業種間を統一した規格に基づいてネットワーク化した点で,国際的にみても先進的なシステムである。 現在その対象範囲は,当初の東京,横浜2港から大阪,神戸,名古屋港を加えた5大港に拡大し,ネットワークの回線接続の新規加入も進んでおり,SHIPNETSによるデータ交換を利署した船積貨物量の増大が期待されている。今後は,このシステムを核とした情報交換対象業務の拡大や他業種との接続の可能性の追求が課題であるとされている。 (共同輸送実験事業) 共同輸送は,物流の効率化とともに車両交通量の減少による環境改善効果など,その社会的意義は認識されているが,サービス面での差別化が打ち出せないことから,販売戦略上マイナスになるとの危ぐが抱かれる等の問題点があり,なかなか進展をみていないのが現状であった。 そこで受注,仕分,配車などを最新の情報システムを用いて処理し,従来の物流コスト削減効果の他に,受発注情報を利用した販売促進効果などをも併せもつ新しい共同輸送を開発,普及させることとし,61年度において「フレッシュネットワーキングシステム」と名付けて新しい形態の共同輸送実験事業を行った 〔6−2−2図〕。
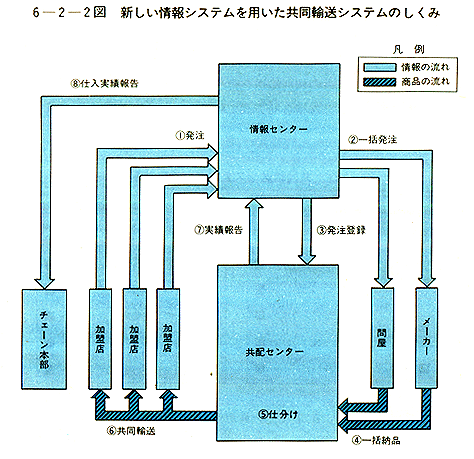
実験結果によると,まずコスト面においては,複数チェーンの参加などにより店舗数と取扱量が増加すれば,大幅な経費削減効果が期待できることが明らかになった。少量単位の発注が可能なことによる品揃えの充実や商品鮮度の向上といった面において,小売店側から評価を受けており,更に,一括配送による車両走行量の減少という公共的効果も期待できることが明らかになった。今後は関係業界への周知,普及を図ることとしている。
|