|
2 交通安全対策の推進
ア 自動車運送事業者の事故防止対策
自動車運送事業者は自家用自動車に範を示すべく一層の事故防止が望まれているところであり,運輸省としては,これらを踏まえて自動車運送事業者の運行管理体制の充実強化を図るため,運行管理者研修の充実,自動車運送事業者に対する指導・監督の徹底を図っている。 特に,62年2月下旬から3月上旬にかけ東北縦貫自動車道において,3回にわたり異常気象下における追突事故が連続して発生したことにかんがみ,運転者に対しては異常気象時に対する車間距離の保持,安全速度による運転の励行を,運行管理者に対しては,適切な運行計画の指示を行わせるよう全国の貨物自動車運送事業者を指導し,事故防止の徹底を図った。
イ 車両の安全確保
自動車等の道路運送車両の安全を確保するため,道路運送車両法に基づき,自動車の構造,装置等について,保安上の技術基準(道路運送車両の保安基準)が定められている。 この保安基準については,道路交通環境の変化等に対応し,26年以来60回にわたり改正が行われているが,今後は,特に自動車の安全基準の国際的整合化の見地から,安全基準の国際的調和活動に積極的に参画するための調査・研究の充実に努めていくこととしている。 (検査・整備制度) 自動車の安全の確保と公害の防止を図るため,国が自動車の検査(車検)を行うとともに,自動車のユーザーに対しその責任において一定期間ごとに定期点検整備を行うことを義務づけている。また,大型自動車等の使用者については,点検・整備等に関する事項を処理するため整備管理者を選任することを義務づけており,車両管理体制の充実強化を図るため整備管理者研修を行っている。さらに,民間団体によるユーザーの保守管理意識の向上のためのキャンペーンに対し国庫補助を行うなどによりユーザーの意識の向上に努めている。 なお,軽自動車検査体制の合理化の観点から,軽自動車検査協会を経営の自立化及び活性化を図る目的で,62年10月民間法人化した。 また,自動車分解整備事業者(自動車分解整備事業者数80,524(61年度末現在))に対しては,その業務の適正化を図るよう指導・監督を行っている。 整備事業の近代化については,第5次近代化計画及び経営戦略化構造改善計画に基づき,知識集約化,企業集約化,経営方式の適正化等を図る経営戦略化等を65年度を目標年度として推進している。また,整備事業を近代化し,指定整備の維持・拡大を図ることを目的として58年12月に創設された自動車整備近代化資金制度により,61年度末までに5,579件,約468億円の融資が行われている。 (オートマチック車の急発進・急加速問題への対応) 最近,社会的関心事となっているオートマチック車の急発進・急加速に関する事故については,車両の構造・装置の欠陥が直接的に事故の原因となった事例は確認されていないが,その事例の中には,少数ではあるものの運転者の誤操作だけでは説明しにくい事例も認められる。 このため,62年6月,(社)日本自動車工業会に対して原因究明の調査及び誤操作防止のための車両構造上の対策の検討を指示するとともに,公正中立な立場から交通安全公害研究所においても徹底した原因の究明を行っている。 なお,オートマチック車の事故防止は,基本的な正しい使い方について自動車使用者に周知することが肝要であることから,同工業会及び各自動車メーカーへその旨指示し,周知活動を実施させているところである。
ウ 自動車事故被害者の救済
このほか,自動車事故対策センターにおいて,交通遺児等に対する生活資金の貸付け,重度後遺障害者に対する介護料の支給,附属千葉療護センターにおける重度意識障害者に対する治療及び養護等を実施しているが,62年度は,同センターに加え,仙台市において重度意識障害者療護施設の整備に着手した。
鉄軌道における事故は長期減少傾向にあるが,安全性を一層高めるため,①施設面では,自動信号化,ATS(自動列車停止装置)の設置・改良,CTC(列車集中瀞脚装置)化,軌道強化,列車無線設備の整備等による鉄軌道施設の整備,②車両面では,コンピュータの利用等新しい技術を取り入れた検査方法の導入による車両の安全性の確保,③運転面では,乗務員等に対する教育訓練の充実,厳正な服務と適正な運行管理の徹底等による安全運行対策を実施している。
ア 海上交通環境の整備
61年度は,第7次港湾整備五箇年計画の初年度として,港内の船舶の安全を確保するため,新潟港等64港において防波堤,航路,泊地等の整備を行った。また,沿岸海域を航行する船舶の安全を確保するため,関門航路,備讃瀬戸航路等13の開発保全航路において開発又は保全の事業を行うとともに,室津港等11の避難港について整備を行った。 62年度は,引き続き防波堤等の施設の整備及び開発保全航路,避難港の整備を推進している。 (海上交通情報機構の整備) 海上保安庁では,ふくそうする海域における船舶の安全かつ能率的な運航を確保するため,海上交通に関する情報提供と航行管制を一元的に行う海上交通情報機構の整備を,東京湾に次いで備讃海域及び関門海域において進めてきており,62年7月には備讃瀬戸海上交通センターの運用を開始したところである。さらに,大阪湾や来島海峡においても,その整備について調査を行うこととしている。 (大規模プロジェクトに係る安全対策の推進) 東京湾,瀬戸再海等においては,東京湾横断道路,関西国際空港,本州西国連絡橋等の大境模プロジェクトが推進されているが,海上交通に大きな影響を与えるおそれがあることから,海上保安庁では,計画の策定段階からこれに参画し,建設中及び完成後の船舶の航行安全対策の指導等を実施している。 (灯浮標・海図等の整備) 海上保安庁では,浮標式の国際的統一に伴う灯浮標等の様式の変更工事を計画的に行っており,61年度は,瀬戸内海西部海域で約220基の工事を実施した。また,海図等の水路図誌を整備するとともに,船舶交通の安全に係る緊急を要する情報を航行警報等により)提供している。
イ 船舶の安全運航の確保
船員に着目した安全対策としては,船員災害の防止を図る観点から船員労務官による監査及び指導を行うほか,船員災害防止活動の促進に関する法律に基づき,58年度に策定した第4次船員災害防止基本計画に沿って,船舶所有者の自主的な安全衛生管理体制の機能強化等に重点を置き,種々の対策を実施してきている。 また,我が国の港に入港する外国船舶に対しては,「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に規定されている航海当直及び船員の資格証明に関する基準の適合性についての監督を実施している。このうち,特に船員の資格証明に関する監督については,全国一斉に集中的な監督を実施するなどにより、その実効を期している。 さらに,62年4月30日から,船舶の航行の安全を図るため,既に海技免状を取得している者に対し,5年毎に身体適性及び知識・技能のチェックを行う海技免状の有効期間の更新制度が開始された。それに伴い,更新を円滑に推進するため,(財)海技免状更新協力センターの設立を62年4月1日認可した。 近年,海難等が多発している漁船に対しては,事故防止対策及び事故が発生した場合の早期発見と生存対策について,船員の労働保護等のソフト面から総合的な検討を行うとともに,安全指導の強化のための講習会の開催等を実施した。 また,苫小牧港,八戸港,石巻港,長崎港及び鹿児島港の港域拡大等の状況にかんがみ,それぞれ苫小牧,八戸,仙台湾,長崎及び鹿児島水先区の拡張を行うこととしており,これにより一層の海上交通の安全確保を図る。 (旅客船の安全確保) 多数の旅客や自動車を運送する旅客船の安全を確保するため,事業免許の際,事前に事業計画等について審査するとともに,旅客運送活動全般を通じ一貫した安全対策を講ずるため,旅客航路事業者に運航管理者の選任,運航管理規程の作成等を義務づけている。 また,地方運輸局に配置された運航監理官により,旅客船及び事業所の監査,運航管理者に対する研修等を行い,安全確保体制の確立に努めている。 (海上交通ルール及び各種船舶の安全対策) 海上保安庁では,海上交通ルールを定める海上衝突予防法等の海上交通関係法令に基づく規制に加えて,船舶の種類に応じた各種の安全対策を講じている。 タンカー等の危険物積載船については,本邦に初めて就航する2万5,000総トン以上のLNG・LPGタンカー等に対する個別的な安全措置の指導等の施策を講じているほか,最近海難が増加しているプレジャーボート等については,小型船安全協会等の設立や海上安全指導員制度の推進を図っている。
ウ 船舶の安全性の確保
また,外国船に対しては,立入検査を実施し,SOLAS条約に規定されている船舶の構造設備に係る技術基準を満たすよう監督体制を強化しており,危険物等を輸送する船舶に対しては,引き続き立入検査を実施し,安全性の確保を図っている。 漁船については,正規の手続きを経ずに改造している事例が多く,人命の安全に係ることから,その立入検査を強力に実施している。プレジャーボートや遊漁船等小型船舶については,安全指導を強化している。 一方,船舶検査体制の合理化の観点から,型式承認及び事業場の認定制度の推進を行うとともに,小型船舶検査機構を経営の自立化及び活性化を図る目的で,62年10月民間法人化した。
エ 海上捜索救助体制の整備
60年6月の「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)の発効以来,国際的な捜索救助体制確立の動きは着実な進展を示している。61年12月には,「日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の海上における捜索及び救助に関する協定」が締結され,日本の北太平洋における捜索救助区域は,おおむね北緯17度以北,東経165度以西の海域となり,本邦からおよそ1,200海里にも及ぶこととなった。 海上保安序では,このような広大な我が国の捜索救助区域における国際的な捜索救助活動の責任を果たすため,広域哨戒体制の計画的な整備を進めてきており,ヘリコプター搭載型巡視船については,現存の8隻に加え2機搭載型及び1機搭載型各1隻,航空機については,長距離捜索救難機2機等の整備を推進している。 一方,遭難船舶の位置の推定,捜索区域の迅速・的確な決定,巡視船の早期派遣,必要な場合には民間船舶に協力を要請し,迅速・適切な捜索救助の実施を可能とするため,SAR条約により確立することを勧告されている船位通報制度を60年10月から運用しているが,61年には2,348隻の船舶が参加し,10件の海難救助に活用されている。海上保安庁では,より多くの船舶の参加促進を図るとともに,この制度の定着化に努めている。 さらに,SAR条約の目的を達成するため,国際海事機関(IMO)の活動に積極的に協力するとともに,中国等隣接国との間の捜索救助協定の早期締結に向けた努力をするなど国際的な協力・連携を推進している。 (GMDSSへの対応) 現在,IMOにおいて,最新のディジタル通信技術,衛星通信技術等を利用して,全地球的な遭難安全通信体制を確立しようとする「全世界的な海上における遭難・安全制度」(GMDSS)の導入(1991年予定)が検討されている。捜索救助活動を迅速かつ的確に実施するためには,我が国でもGMDSSの導入が必要不可欠であり,新しい海上保安通信体制の確立に向けて適切に対応していく必要がある。なお,本制度においては,極軌道衛星注1)を利用して遭難警報の中継及び測位を行うCOSPAS/SARSATシステム注2)が採用されているが,リアルタイム性を高めるため,運輸省では,静止衛星を利用して警報の即時中継を行うことについても検討することとしている。
ア 航空保安システムの整備
なお,61年度においては,釧路ARSR,青森ILS,江東及び広島VOR/DME整備を完了し運用を開始した。
イ 航空機の安全運航の確保
航空機の安全運航を確保するため,運輸省としては,航空運送事業者に対して航空機の運航基準,運航管理の実施方法,航空機乗組員の職務等運航業務に従事するものが遵守すべき事項を運航規程に定めるように義務づけて,その確実な実施を図るよう指導,監督を行っている。 (小型航空機の安全対策) 61年は小型航空機の航空事故が48件発生し,死者18人と例年にない発生状態となったため,航空事業者及び自家用小型航空機運航者に対して,無理のない飛行計画による運航の実施的確な気象情報の把握等を内容とする事故防止の徹底を指示し,必要に応じ航空事業者への立入検査を行い,運航体制の充実・強化についての指導を行った。 また,飛行中に最新の航空情報,気象情報等の情報の提供が円滑に行われ,万一の場合に迅速な捜索救難活動が実施されるよう,小型航空機の位置報告制度を62年3月より発足させている。 (危険物輸送対策) 近年各種化学薬品,放射性物質等の航空輸送が急速に増加し,その種類も多様化しているため,新たに危険物輸送対策官を置き,各航空運送事業者の危険物輸送体制の充実・強化を強力に指導,監督することとした。 (航空大学校の充実) 近年における航空技術の進展,運航環境に対応し得る乗員を養成するため,62年度は,高々度での計器飛行訓練が可能な双発ターボプロップ機注1)を導入するとともに,学科教育について専門科目の充実及び航空工学実験装置の導入を行った。 (航空保安要員の教育体制の充実) 航空保安大学校本校における新規採用職員に対する基礎研修及び同校岩沼分校における高度な専門技術修得のための研修について,その内容の充実に努めており,62年度においても一部研修施設の性能向上を図ることとしている。
ウ 日航機事故の原因究明
この事故は,ボーイング式747型機の構造・システムの安全性・フェール・セーフ性注2),53年の事故による損傷の修理,修理後の運航・点検整備,60年8月12日の事故発生時の飛行に関わる諸事実等極めて広範な事象が関与しているものであったが,調査の結果,事故機の後部圧力隔壁で進展していた疲労亀裂によって同隔壁の強度が低下し,まず,飛行中の客室与圧に耐えられなくなったこの隔壁,引き続いて尾部胴体・垂直尾翼・操縦系統が損壊し,飛行性の低下と主操縦機能の喪失をきたしたために生じたものと推定された。 さらに,疲労亀裂の発生・進展は,53年に行われた後部圧力隔壁の不適切な修理に起因しており,それが隔壁の損壊に至るまでに進展したことには,亀裂が点検整備で発見されなかったことも関与しているものと推定された。 次に,同種の事故の再発防止という観点から,航空機の大規模な構造修理が行われる場合の作業管理等に関する慎重な配慮,修理後に必要な継続監視についての指導の徹底及びフェール・セーフ性に関する規定の耐空性基準への追加の検討について勧告が行われた。また,将来の航空安全の向上に資するという観点から,緊急・異常時における乗組員の対応能力を高めるための方策及び目視点検による亀裂の発見に関する検討について建議が行われた。
エ 航空機の安全性の確保
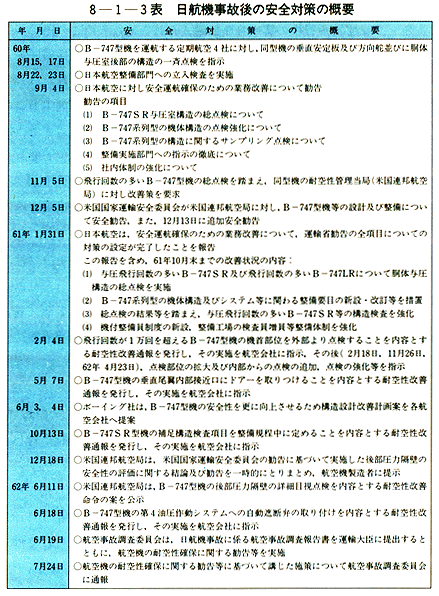
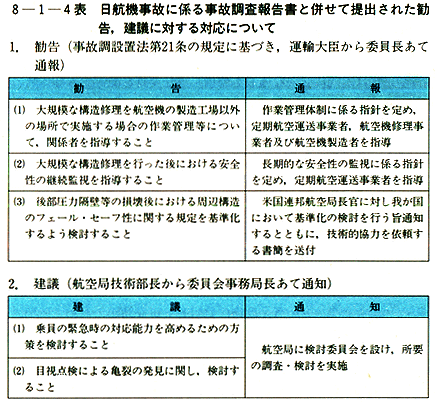
また,航空機に係る整備審査体制の充実を図るため,整備審査官を置き,航空運送事業者の点検整備体制の特性を充分把握するとともに,異常運航・故障情報,メーカーからの技術情報等を掌握したうえで,使用される航空機に適した整備が実施されるよう,各航空会社に対して整備関連諸規程の充実等について指導している。なお,62年7月からは故障報告制度を拡充・強化したところであり,今後とも安全性確認検査等を通じて安全運航の実態を把握し,各航空会社が運航及び整備体制の充実・強化に努めるよう強力に指導していくこととしている。
オ 緊急時における捜索救難体制の整備
カ 異常接近の再発防止
注1) 極軌道衛星:アメリカのNOAA,LANDSAT等,衛星の軌道面と地球の赤道面との傾斜角が90°に近い衛星。各周回毎に極域を通過するため,静止気象衛星では不可能な極域の観測に適し,また,一定の回数周回することにより全地球面を観測することが可能である。
|