|
2 ライフスタイルの変化と運輸
我が国の国際社会における地位は今や飛躍的に向上し,一人当たりのGNPは世界の最高水準に達するなど,多くの面で欧米先進国と比して遜色ない水準にまで達しているが,一方,低い居住水準,長い労働時間,高い生計費に象徴されるように,必ずしもこれまでの経済成長の成果が,国民生活の質の向上に反映されているとは言い難い状況にある。
運輸の面における技術革新や新たなサービスの提供は,国民生活に大きな変化をもたらしてきている。まず,運輸の発達によって,国民のライフスタイルの選択の範囲がどのように変化してきたかについて概観してみよう。
(ア) 高速化による行動圏の拡大
鉄道においては39年の東海道新幹線の開通により,それまで6時間30分かかっていた東京〜大阪間が2時間49分に短縮された。また,東北,上越新幹線の開通により,上野〜仙台間が1時間42分,上野〜新潟間が1時間39分で結ばれている。その結果,上越新幹線を利用した日帰りスキー客が増大したり,遠距離の日帰り出張などが可能となった。 航空においては,36年に初めてジェット機が国内線に就航して以来,現在では161の国内航空路線のうち,その64%にあたる102路線がジェット化され,短時間で各地が結ばれている。 さらに,高速道路の整備が進み,マイカーの普及と相まって,国民の週末におけるレクリエーションなどの活動を手軽なものとし,またその圏域を拡大した。 これらにより, 〔1−1−20図〕にみられるように,国民が片道3時間以内で到達できる日帰り行動圏は大幅に拡大した。 このように,国民の距離に対する抵抗感が急速に少なくなり,移動コストの相対的低下とも相まって,より容易かつ気軽に遠出を行えるようになってきた。
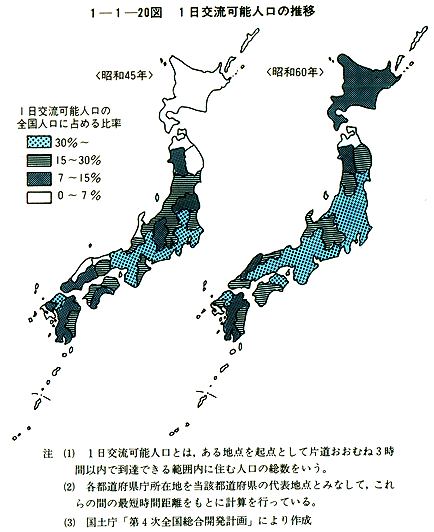
このような交通機関の高速化により,単身赴任者の週末帰省が容易化・一般化したり,地方や都市郊外の住宅と都心の住宅の使い分けといった新しいスタイルが現れてきている。また,新幹線を利用した新しい通勤形態が増加しているが,これは,比較的容易に良質な住宅を確保できる地域に居住し,大都市圏へ通勤するという新しいライフスタイルを新幹線という高速交通機関が可能にしたものと考えることができる。
(イ) 移動コストの相対的低下による旅行などの活性化,多様化
例えば,東京〜札幌間の航空運賃は,30年には10,200円,一人当たり一日平均国民所得の55日分であったが,60年には25,500円,4.4日分と10分の1以下に低下している。 また,東京-大阪間の鉄道運賃と一人当たり一日平均国民所得との関係を例にして見ると,30年には一日平均国民所得の約8日分を必要としていたものが,40年には3.4日分に,さらに60年時点では,2.2日分に低下している。高速道路については,東名・名神高速道路開通直後の45年には2.0日分を要していたが,60年時点では1.6日分になってきている 〔1−1−21表〕。
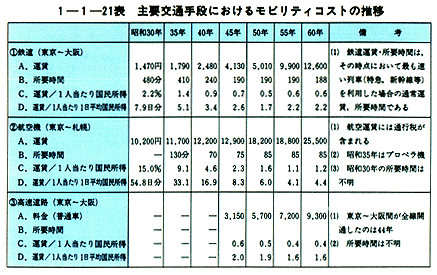
このような移動コストの相対的低下の結果,北海道までスキーに出かける人が増加したり,ハネムーンの主流が宮崎〜沖縄〜海外と変遷したり,最近の円高傾向もあって修学旅行,職場旅行についても海外旅行が増加している。
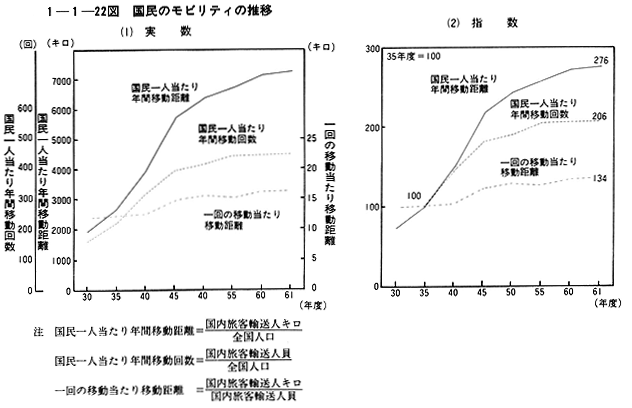
(ウ) 機動性の向上による行動圏の拡大
(エ) 物流システムの高度化による生活の多様化
(3) ライフスタイルの変化は運輸にどのような対応を求めてきたか
一方,国民生活,ライフスタイルは,国民の生活意識の変化,価値観の多様化や,国民をとりまく経済社会環境の変化などに対応して変化してきているが,このようなライフスタイルの変化に対して運輸がどうように対応してきているか,ここでは社会全体の基調,仕事,家庭,自由時間活動の4つの面に分けて概観する。
(ア) 基調
これに加え,近年においては快適化,高級化に対する要請も高まってきている。通勤電車の車両の冷房化が推進されたり,新幹線に二階建て車両が導入されるなど快適化,高級化が進められ好評を博している。 また経済の国際化に対応して,海外旅行,海外留学・勤務が増加したり,外国の産品が気軽に入手,消費できるようになるなど日常生活の国際化が進んできている。これに対応して国際運輸の面においても,国際線就航会社の複数化による航空サービスの向上が図られたり,国際宅配便サービスの開始など旅客・貨物両面において運輸サービスの充実が図られている。
(イ) 仕事面
また,勤務形態の多様化,女性のパートタイム通勤の増加や国際化の進展に伴う24時間型ビジネスの増加は,通常の通勤時間帯以外の輸送需要を増加させている。これに対しては,昼間及び深夜の列車の運行本数の増加や,終バスの時刻の延長や深夜バスの運行,都心での深夜時間帯を中心としたタクシーの増車などの対応がなされている。
(ウ) 家庭面
また,限られた空間の中で快適に住みたいという要請の強まり等に対しては,トランクルームサービスやフレイトビラ実験事業により対応が図られている。
(エ) 自由時間活動面
また,主婦,OL,シルバー層の旅行,レクリエーション活動が活発化しており,ナイスミディパス,フルムーンパスなどの特定の年齢層や女性に的を絞った割引切符が発売されている。
21世紀に向けてのライフスタイルの変化の方向を考える視点としては,さまざまのアプローチが考えられるが,運輸とのかかわりという視点に重点をおいて,「住」と「職」の関係から国民生活の基盤をなす居住地の選定,また我が国の経済発展を支えてきたビジネスライフのあり方について概観するとともに,今後各個人の生活の力点の置き方如何に対応して多様な活動が行われることとなると予想される自由時間の活用方策について概観してみた。
(ア) 家庭と勤務先のロケーション
(a) 大都市圏
21世紀に向けて,東京圏に過度に集中している諸機能の地方分散を促進して,多極分散型国土の形成をめざす各般の方策が講ぜられることとなっているが,それでもなお,東京圏への集中傾向はある程度避けられない見通しであり,東京圏内の都市構造自体について,現在の都心3区中心型から多数の副都心,業務核都市をもつ多核多心型へと転換するための施策が講ぜられることとなっている。 このような状況のなかで,大都市圏における居住空間に対するニーズや狭い居住空間をできる限り広く活用したいという要請は一層高まると予想され,まず第一にそれへの対応を考える必要があるが,全般的な傾向としては,限りある空間の制約等から好むと好まざるとにかかわらず,住宅の遠隔地化は今後さらに進まざるを得ないであろう。 また,こうしたなかで,通勤の遠距離,長時間化を避けるため,地方に家庭の本拠を置いて,週日は都心のセカンドハウスから通勤するとか,狭いながらも都心部に家庭の本拠をもって,週末に地方のセカンドハウスで過ごすといった複数の住居を使い分けるマルチハビテーションのスタイルの増加も予想される。さらに大都市圏から居住環境のよい地方へ家庭の本拠を移し,これに伴って勤務先も地方に求める場合も生じてくるものと考えられる。
(b) 地方圏
このような観点から,地方圏においては,雇用の確保を図るため魅力ある地域づくりを推進するとともに,地域交通ネットワークの維持・整備を図り,より豊かな生活を楽しむための環境づくりが必要となろう。 さらに,大都市と地方との交流を促進するため高速交通ネットワークの整備が必要となってこようが,かかる整備の推進を通じて,地域住民が大都市圏のライフスタイルを楽しむ形も増加してくることが予想される。
(イ) ビジネスライフ
一方,出張については,東京〜大阪など高速交通機関の利便性の高い区間については,日帰り出張が一般的となっているが,そうでない区間については宿泊を伴うことが前提となる。 しかしながら,このようなビジネスライフにも,国際化,情報化の進展,時間価値の高まりなどにより,次のような大きな変化の波が押し寄せている。 (a) 今後,経済活動の拡大に伴い,地域を越えた交流が活発化し,出張など長距離の業務交通の機会も増大するであろう。現在,限定的に行われている日帰り出張も,時間価値の高まり,労働時間短縮の要請に伴う効率的な業務活動の必要性から一般的なものとなってくるであろう。こうした,業務目的の交通需要の質的な側面としては,今後とも,目的地へできるだけ早く到達できること,すなわち高速性が最も重要視されよう。 (b) 情報のリアルタイム化,時間価値の高まりは,移動時間を有効に利用するニーズを高めてきている。現在でも新幹線に設置された公衆電話は,頻繁に使用されており,移動時間中の情報の授受は一般的になった。今後は,高度な通信手段を使った「動くオフィス」などへのニーズが高まるとともに,駅,空港などのターミナルが情報の拠点となることが望まれるであろう。 (c) 従来型の勤務形態が今後とも大部分を占めるであろうが,経済のソフト化,国際的経済活動の拡大などの経済社会情勢の変化により,業務時間帯が拡大するなど,いわゆる24時間都市化が一層進行し,金融関係に勤務するホワイトカラーを中心とする深夜勤務やフレックスタイム制など勤務形態が多様化することが考えられる。 (d) パソコン,ファクシミリなどの高度な情報伝達手段の発達・普及により,家庭においても,業務活動に必要な情報を授受することが可能となり,出勤せず自宅で業務活動を行う在宅勤務が出現している。また,郊外にパソコン,ファクシミリなどを設置した小規模なオフィス(サテライトオフィス)を設け,従業員は自宅の最寄りのサテライトオフィスに出勤するだけで済むサテライトオフィス勤務も現れてきている。 今後,情報化の進展により,移動が減少したり,あるいは必要でなくなるようなケースも出てこようが,これまでの情報化の進展が,フェイス・トゥ・フェイスの情報の価値を高めることにより全体として移動を活発化させてきた経緯を考えると,今後も情報と移動は,相乗関係を持ちつつ相互に活発化していくものと考えられる。
(ウ) 自由時間活動
(b) しかしながら,安定成長期に入り所得水準の上昇や高学歴化の進展による価値観の個性化,多様化を背景に,仕事以外にも自己実現の機会を積極的に求める生き方,すなわち仕事と仕事以外のどちらにも生きがいを見出すものが増加している。 現に,総理府の世論調査によれば,物質的な豊さよりも心の豊さに生活の力点を置く国民が相当多くなってきており,仕事以外の時間に対する認識も,仕事に備えて休養するための余暇としてとらえる消極的なものから,自己啓発あるいは自己発現の場として多種多様な活動を行うための積極的な意義を有する時間として把握する人が多くなってきている。 (c) このような国民の自由時間に対する認識の変化が基礎となって,週休2日制や長期連続休暇の普及,主婦の家事時間の減少,高齢化社会の到来などによる自由時間の増大により,自由時間活動に対する需要は,自然との触れ合い,スポーツ体験,健康充足など多様化を呈しながら量的にも拡大するものと考えられる。 また,出勤,帰宅途中に,例えば英会話,水泳などのカルチャー活動,スポーツ活動を行うことが広まりつつあるが,今後,労働時間の短縮などとも相まって,一日の中で仕事以外の時間を活用して多様な活動を行う新しいライフスタイルも定着してこよう。
(エ) 国際交流の進展
一方,日本を訪れる外国人も徐々に増加すると見込まれ,また,日本への外資系企業の進出や円高の進展に伴って,外国人の国内移動や国内における外国人との交流の機会が一層増加すると考えられる。
(オ) 高齢化社会の到来に伴う高齢者の社会参加
これに伴い,勤労者にとっては定年退職後,家庭の主婦にとっては子育てが終了した後,人生の中でかなりの時間的余裕が生じてきている。今後,「人生80年時代」のなかで,高齢者が従来「余生」と考えられていた定年退職後のライフステージをいかに充実したものとするかが重要となってくるものと考えられる。 このような観点から,今後高齢者が積極的に社会参加を行うライフスタイルが定着してくると考えられる。例えば,スポーツ,レクリエーションなどの活動に自ら積極的に取り組むライフスタイル,地域や文化サークル活動を通じて自分のコミュニティを形成していくライフスタイル,都会と地方の生活を交互に送るライフスタイルなど新しいライフスタイルが徐々に形成されつつある。
我が国は狭い国土,地震災害のおそれ等の自然条件の制約や,ある程度避けられない大都市集中などの問題点を抱えているが,他方,変化に満ちた景観,温暖な気候等の自然的好条件のほか,平均的知識レベルの高さと新技術の応用能力,システム運営の正確性・確実性など国民の資質,性格や歴史的背景からくる好条件に恵まれている。
|