| 機船ふたば機船グレート・ビクトリー衝突事件 旅客船兼自動車渡船ふたばが、船長ほか28人が乗り組み、旅客58人及び車両24台を載せ、昭和51年7月2日細島を発して広島に向い、諸島水道ミルガ瀬戸を北上していたとき、また、パナマ船籍の貨物船グレート・ビクトリーが、船長ほか39人が乗り組み、空倉のまま、同日午後広島港を発して徳山に向い、ミルガ瀬戸を南下していたとき、同2日午後7時44分ごろ両船が衝突した。 衝突の結果、ふたばは、左舷側中央部にくさび型の大破口を生じて沈没、乗客2人及び乗組員1人が死亡、乗客2人が行方不明、乗客4人及び乗組員6人が負傷し、グレート・ビクトリーは、左舷側等船首部に擦過傷及び凹傷を生じた。 本件は、カーフェリーが沈没するという大事件で、幸いにも被害を最小限に食い止めることが出来たが、カーフェリーによる海難がいかに危険であるかをまざまざと見せつけた事件で、我が国におけるカーフェリー海難の事故で、乗客に死者が出た最初の事件となった。 本件については、昭和52年2月19日広島地方海難審判庁で裁決があったが、これを不服として理事官及び両船側の補佐人から第二審の請求があり、同53年2月28日高等海難審判庁で裁決された。 広島地方海難審判理事所の調査経過 広島地方海難審判理事所は、本件を「指定重大海難事件」に指定するとともに、所内に調査検討会を設け、まずグレート・ビクトリーの関係者を先行して調査することに決定した。 中国人船員に対する事情聴取は、広島県警及びグレート・ビクトリー日本代理店の紹介による通訳人を介して行われ、一方、ふたば関係者の事情聴取も開始し、広島地方海難審判理事所では、約1か月という早さで調査を終了した。 これらの証拠を基にして理事官は、ふたばの船長及び一等航海士を受審人に、ふたばの運航管理者及びグレート・ビクトリーの船長をそれぞれ指定海難関係人に指定し、昭和51年7月30日広島地方海難審判庁に対して審判開始の申立を行った。 広島地方海難審判庁の審理経過 審判開始の申立を受けた広島地方海難審判庁では、重大海難事件に指定された本件を迅速に処理するため、集中審理方式を採用して、昭和51年9月9日第1回の審判を開廷し、こうして、申立から7か月後の昭和52年2月19日裁決の言渡しが行われたが、理事官及び両船側の補佐人から第二審の請求が行われた。 高等海難審判庁の審理経過 第1回審判は、昭和52年6月3日に開廷、2回の事実審理で結審し、昭和53年2月28日裁決の言渡があった。 その要旨は次のとおりである。 裁決 (船舶の要目)
(関係人の明細)
(損 害)
主文 本件衝突は、ふたば及びグレート・ビクトリーの両船が、それぞれ狭水道における適切な航法を守らなかったことに因って発生したものである。 理由 ふたばは、旅客船兼自動車渡船で、細島、広島航路に就航していたところ、船長及び一等航海士ほか27人が乗り組み、旅客58人車両24台を載せ、昭和51年7月2日正午、定刻に細島を発し、広島に向かった。 日向灘は台風7号の影響でうねりが高く、本船は30分ばかりの遅れで佐田岬を通過して瀬戸内海に入ったが、同7時ごろ大水無瀬島の少し手前に達したところで、一等航海士が当直に立ち、ついで同7時15分ごろ船長が昇橋して自ら運航の指揮にあたった。 同7時36分少し前大石燈標から90度(真方位、以下同じ。)650メートルばかりのところを通過した際、船長は、前示のとおり定期から遅れているうえ、気象及び潮汐の条件が良くなったので、従来何回となく通航して馴れている諸島水道ミルガ瀬戸を通ることにし、針路を同瀬戸を右舷船首に望む0度に定め、機関を16ノットばかりの全速力にかけて進行した。 定針する少し前、レーダー監視を兼ねて見張りにあたっていた一等航海士は、南下中のグレート・ビクトリー(以下グ号という。)の船体を薄暮のなか距離4海里ばかりに認め、同7時37分半ごろミルガ瀬戸から1.7海里ばかり手前に達し、同船との距離が約3海里となった際、船長に対し相手船と同瀬戸で出会うおそれがある旨を報告し、ついで同7時39分半ごろ根ナシ礁燈標から237度約1.1海里、同瀬戸の手前1.2海里ばかりに達し、相手船の緑燈を正船首少し右約2海里に見るとき再度同旨の報告をした。 この報告を受けた船長は、相手船がかなりの大型船であることを知っていたが、互いに針路を右転してそれぞれ水路の各右側につけば無難に航過できるものと思い、すみやかに速力を減じ、同瀬戸で行き会うことを避ける措置をとらず、同瀬戸の右側に向け針路を10度に転じ、相手船を左舷船首に望み続航した。 同7時42分相手船の緑燈を正船首少し左1,400メートルばかりに見るころ、船長は、針路信号のつもりで携帯信号燈により短光1回の信号を発し、さらに右側に寄せるため針路を12度に転じ、ついで13度、15度及び18度と連続して小刻みに右転しながらミルガ瀬戸の諸島寄りに全速力のまま進入した。 しかし、相手船に右転する気配がなく、同7時43分少し過ぎ緑燈を示したまま左舷船首400メートルばかりに迫ったので、同人ははじめて衝突の危険を感じ、同7時44分少し前リモコンにより機関を12ノットばかりの半速力とし、汽笛及び燈火運動の信号器で短音1回の信号を発し、右舵につづいて右舵一杯としたが行足が減じるいとまもなく、同7時44分船首がほぼ30度に向いたとき、諸島頂から287度420メートルばかりの同瀬戸最狭部において、グ号の船首がふたばの左舷側中央部に前方から約30度の角度で衝突した。 また、グ号は、広島港内で修理工事を終え、船長ほか39人が乗り組み、空倉のまま、同日午後5時35分ごろ同地を発し、徳山に向かった。 その後本船は、大須瀬戸及び奈沙美瀬戸を経て、同7時13分ごろ西五番之砠燈標を58度800メートルばかりに通過したが、そのころ船長は、諸島水道ミルガ瀬戸を通ることにし、津和地島の剣ノ鼻沖合に向け針路を148度に定め、機関を14.5ノットばかりの全速力にかけて進行した。 船長は、ミルガ瀬戸を通るのははじめてであったが、瀬戸内海水路誌等による水路調査をせず、海図(第142号)に推薦航路線が記載してあるので同航路線をたどり、明るいうちに通ればたいしたことはあるまいと思い、同7時35分ごろ剣ノ鼻から303度1,150メートルばかりの地点に達したとき、同瀬戸の中央から少し左寄りに向け針路を180度に転じて進行した。 同7時36分少し前船長は、右舷船首3.8海里ばかり、同瀬戸の南方にあたり北上するふたばの船体を薄暮のなかに認め、やがて客船であることがわかり、緑燈が見えていたので同瀬戸で行き会うとすれば互いに右舷を対して航過することになると思いそのまま続航中、同時40分少し前荒神鼻から15度0.5海里、同瀬戸の手前0.7海里ばかりの地点に達したとき、正船首少し右約1.8海里に近づいた相手船が、紅、緑2燈を示すようになったので不安を感じ、同時40分ごろ機関を停止した。 同7時42分少し過ぎ正船首少し右1,300メートルばかりに見る相手船の緑燈が隠れて紅燈のみを示し、自船の前路に急速に接近するようになったが、船長は、前示のように互いに右舷を対して航過することになると思っていたので、相手船はいずれ左転するものと考え、すみやかに行足を止め、同瀬戸で行き会うことを避ける措置をとらず、荒神鼻沖の礁脈を警戒してナッシング・スターボートを令し、かなりの行足をもって同瀬戸の諸島寄りに進入した。 しかし、相手船に左転する気配がなく、同7時43分少し過ぎ紅燈を示したまま右舷船首400メートルばかりに迫ったので、船長は、はじめて衝突の危険を感じ、機関を全速力後進にかけ、右舵一杯としたが効なく、衝突必至となったのでその直前機関を停止したものの、ほぼ原針路のまま4.5ノットばかりの行足をもって前示のとおり衝突した。 ふたばは、衝突直後発電機のブレーカーが飛んで船内の燈火がすべて消燈し、バッテリーによる非常燈が点燈し、間もなく浸水のため主機及び補機が停止し、船長は、一等航海士に対し、損傷状況の調査を、二等航海士に対し外部との連絡を、三等航海士に対し相手船の調査及びその外の記録を、機関長及び一等機関士に対し主機室及び補機室の各水密扉の閉鎖を、また、マネージャー(乗客に対するサービス部門の責任者)に対し、乗客の誘導をそれぞれ指示した。また、衝突後間もなく情島の本浦付近にいた漁船20隻余りが来援し、衝突時に生じた死者及び行方不明者を除く乗客及び乗組員の救助は順調に行われ、一方グ号においては、衝突後間もなく一等航海士が船首に行き、ふたばと連絡をとろうとしたが連絡がつかないうちに多数の漁船が来援したので船長は、人命救助については心配ないと思い、津和地島に接近したので同所に止まるのは危険と考え、いったん現場を離れた。 本件衝突は、ふたば及びグレート・ビクトリーの両船が、狭あいな諸島水道ミルガ瀬戸において互いに行き会う態勢となった場合、ふたば側において、相手船と同瀬戸で行き会うことを避ける措置をとらず、全速力のまま同瀬戸に進入したことと、グレート・ビクトリー側において、いったん機関を停止したものの、なお行き会うおそれがあったのにこれを避ける措置をとらず、かなりの行足をもって同瀬戸に進入したこととに因って発生したものである。 ふたば船長が、ふたばを運航し、狭あいな諸島水道ミルガ瀬戸を通航するにあたり、グレート・ビクトリーと同瀬戸で行き会う態勢となった場合、すみやかに速力を減じ、相手船と同瀬戸で行き会うことを避け、その動向を確かめたのち適宜の措置をとるべきであったのにこれを怠り、全速力のまま同瀬戸に進入したことに職務上の過失がある。 グレート・ビクトリー船長が、グレート・ビクトリーを運航し、狭あいな諸島水道ミルガ瀬戸を通航するにあたり、ふたばと同瀬戸で行き会う態勢となり、いったん機関を停止したもののなお行き会うおそれがある場合、すみやかに行足を止め、相手船と同瀬戸で行き会うことを避け、その動向を確かめたのち適宜の措置をとるべきであったのにこれを怠り、かなりの行足をもって同瀬戸に進入したことは、本件発生の原因となる。 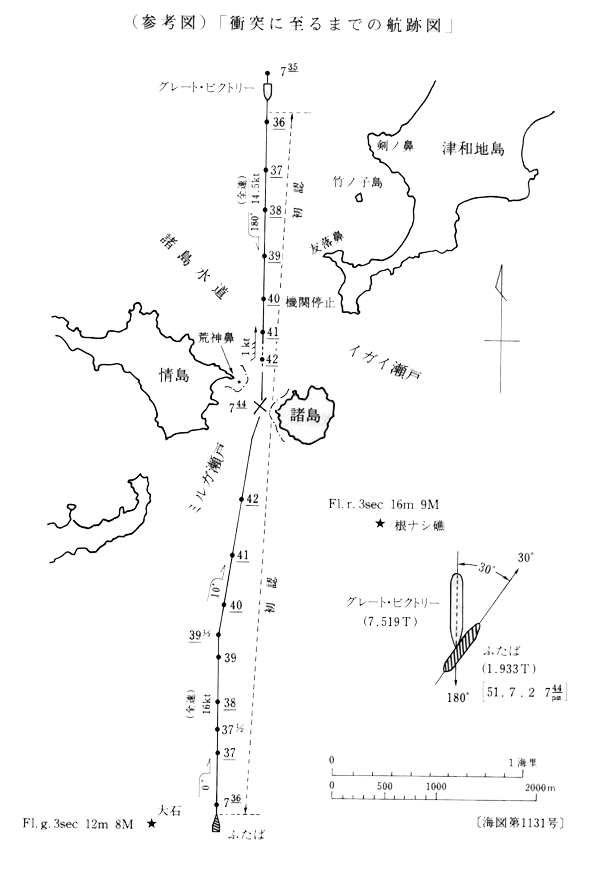 |