| 漁船第二十五五郎竹丸転覆事件 第二十五五郎竹丸は、まき網漁業に従事する網船で、20人が乗り組み、平成6年12月26日操業の目的で、船首1.81メートル船尾2.55メートルの喫水をもって、海上強風警報が発表されているなか、船団の僚船4隻とともに午後0時45分戸田漁港を発し、御前埼南東方沖合の漁場に向かった。 第二十五五郎竹丸は、満載出港状態の積高を大幅に上回る漁網、その他の漁具を搭載した状態で、魚群探索を行いながら御前埼沖合を南下していたところ、風波が増大したので操業を断念して帰航することにし、戸田漁港へ向けて航行中、大波を受けて甲板上に多量の滞留水を生じ、排水できないまま右舷側に大きく傾き、午後7時10分ごろ御前埼沖合において、復原力を喪失し、右舷側に転覆した。 転覆の結果、第二十五五郎竹丸は沈没し、乗組員20人のうち2人は救助されたが、残る18人が死亡・行方不明となった。 本件については、平成8年4月26日横浜地方海難審判庁で裁決された。 横浜地方海難審判理事所の調査経過 横浜地方海難審判理事所では、本件を「重大海難事件」に指定し、第二十五五郎竹丸乗組員、船団乗組員等に事情聴取を行い、理事官は、船舶所有者を指定海難関係人に指定して、平成7年4月13日横浜地方海難審判庁に対して審判開始の申立てを行った。 横浜地方海難審判庁の審理経過 横浜地方海難審判庁は、参審員の参加を決定して、7回にわたって審理し、その間12名証人尋問等を行い、平成8年4月26日裁決の言渡しが行われた。 裁決の要旨は、次のとおりである。 裁決 (船舶の要目)
(関係人の明細)
(損害)
主文 本件転覆は、気象海象に対する配慮不十分で、発航することを中止しなかったことと、満載喫水線の不遵守で、復原力を確保できなかったこととに因って発生したものである。 船舶所有者が、乗組員に対して、満載喫水線の遵守についての指導監督が十分でなかったことは、本件発生の原因となる。 理由 (事実) 第二十五五郎竹丸(以下「二五号」という。)は、船長ほか19人が乗り組み、操業の目的で、船首1.81メートル船尾2.55メートルの喫水をもって、平成6年12月26日午後0時45分戸田漁港を発し、御前埼南東方沖合5海里ばかりの漁場に向かった。 船長は、漁業協同組合所属の他の大型の船団が発航を見合わせているなか、発航とともに船団長及び機関長に補佐させて自ら操舵操船に当たり、自船に引き続いて順次発航した五郎竹丸船団の僚船4隻とともに御浜埼を替わって針路を南西方にとり、機関を約10ノットの全速力前進にかけて魚群探索を行いながら南下し、石花海に達したころから次第に風波が増大し、同4時ごろ北緯34度40分線に達したとき、風力5の北東風となり雨が降り始めて波高は約2メートルとなったものの、更に同探索を続けながら続航し、御前埼沖合に達したころ北東風が風力6になって波高が約2メートル以上に達し、加えて東南東方から約2メートルに達するうねりを受けるようになった。 同5時58分ごろ船団長は、船橋で船長とともに大王埼からの気象情報を聞き、更に荒天が予想される状況となって、操業することを断念し、自船団の各船に対して網洗いに備えながら一団となって魚群探索を続けながら帰港するように指示し、同6時2分ごろ御前埼灯台から153度(真方位、以下同じ。)3.6海里ばかりの地点において、針路をほぼ戸田漁港南方の大埼に向首する46度に定めて自動操舵としたところ、風波を正船首少し左から受ける状態となって船体の動揺が大きくなり、船体に対して機関の出力が大きいことも相まって波の打ち込みが激しくなり、これを避けるため機関を約7.7ノットに減速し、風波に抗して約5.7ノットの航力で同漁港に向けて帰航の途に就いた。 船長は、波の打ち込みが次第に激しくなったのを認めたが、機関を更に減速して波の来襲に応じて断続的に中立にするなどの荒天をしのぐ措置をとらないまま、1時間当たり6回ほどの割合で大波に遭遇するときだけ機関を中立とし、波の衝撃を緩和してこれを乗り切りながら進行した。 船長は、漁網が抱水して喫水が深くなってほとんど乾舷がない状態となり、放水口からの排水が十分に行われず、やがて甲板上へ打ち込んだ海水が滞留するようになり、船型の左右非対称と滞留水の影響で右舷側へ傾斜するようになったものの、正船首少し左方から波浪を受ける状態で、なおも自動操舵のまま進行し、波による船首の振揺により、針路の保持が困難となって、同7時ごろ一時的に操舵不能となり、船首が右舷側に落とされて船体が波に横たわる状況となったものの、手動操舵に切り替えてこれを切り抜け、針路を元に戻して続航し、同時10分少し前大波に抗して機関を中立としたとき、船首が大波に突っ込みこれを甲板上にすくい上げるとともに船速が落ち、船首が急激に右舷側に落とされて船体が波に横たわると同時に奔入した海水と滞留水とが一挙に右舷側に押し寄せ、排水できないまま右舷側に大きく傾き、同7時10分ごろ御前埼灯台から78度6.4海里ばかりの地点において、引き続く風上舷からの大波で復原力を喪失し、ほぼ南東に向首して停止状態となったまま右舷側に転覆した。 当時、天候は雨で風力7の北東風が吹き、波高約2メートルの北東方からの風浪と約2メートルの南東方からのうねりがあり、日没時刻は午後4時42分で、潮候は上げ潮の初期であった。 転覆の結果、通信長、甲板長、機関員、司厨員ほか数人の乗組員が海上に投げ出され、同7時13分ごろ船体はほぼ南東に向首してその場で船首から沈没した。 五郎竹丸船団の各船は、運搬船第三五郎竹丸から船団の最後尾に追随していた二五号のレーダー映像がスコープから消失したとの連絡を受け、灯船第五五郎竹丸が無線呼出しを行ったが応答がなく、更に秋丸及び運搬船第十二五郎竹丸号が船舶電話による直接の呼出しをしたが、海岸局から二五号の電源は切れていて通話圏外にいる旨の連絡を受けたことから同船の遭難を知り、同月26日午後7時50分ごろ第三五郎竹丸が確認していた二五号のレーダー映像消失地点に向けて全船が一斉に反転し、船舶電話で船舶所有者に連絡するとともに捜索に向かい、同8時10分ごろ同地点付近に至って海面に浮遊する板切れや油を認め、その後二五号のかごなどの浮遊物を発見し、付近一帯の捜索を続行した。 一方、船舶所有者は、直ちに二五号のレーダー映像が消失した旨を漁業協同組合長に連絡するとともに、浜平丸船団に直接連絡して捜索の応援を依頼し、清水海上保安部にもその事実を伝えた。 同10時10分ごろ漁業協同組合では、対策本部を設置し、既に捜索中の五郎竹丸船団に、浜平丸船団4隻、大師丸船団6隻及び弁天丸の合計11隻を加えて捜索を行い、清水海上保安部では、多数の巡視船艇を出動させて捜索を開始し、翌朝から航空機を含めて沈没地点付近を中心に捜索範囲を拡大して捜索を続行し、通信長、甲板長、機関員及び司厨員の4人はいずれも僚船に救助されて病院に搬送されたが、通信長及び甲板長はいずれも溺水で死亡し、同月30日午後5時20分ごろ測量船が水深320メートルの沈没地点に付近海底と異なった形状物を探知し、引き続き捜索を行ったが、乗組員16人は行方不明となり、のちいずれも死亡と認定され、また、二五号は、沈没により全損となって船舶原簿が抹消され、同船の滅失によって五郎竹丸船団の各船は、その後いずれも売却されて同船団は解散された。 (原 因) 本件転覆は、冬期、静岡県御前埼沖合で操業を行うに当たり、海上強風警報が発表され荒天が予想される際、気象海象に対する配慮不十分で、発航することを中止しなかったことと、発航に当たり、満載喫水線の不遵守で、大波を受けて甲板上に多量の滞留水を生じ、復原力を確保できなかったこととに因って発生したものである。 船舶所有者が、第二十五五郎竹丸の乗組員に対して、満載喫水線の遵守についての指導監督が十分でなかったことは、本件発生の原因となる。 (指定海難関係人の所為) 船舶所有者が、冬期、静岡県御前埼沖合で操業を行わせるに当たり、第二十五五郎竹丸の乗組員に対して、満載喫水線の遵守についての指導監督が十分でなかったことは本件発生の原因となる。船舶所有者に対しては、本件発生後五郎竹丸船団を解散し、以後の操業を取り止めたことに徴し、勧告しない。 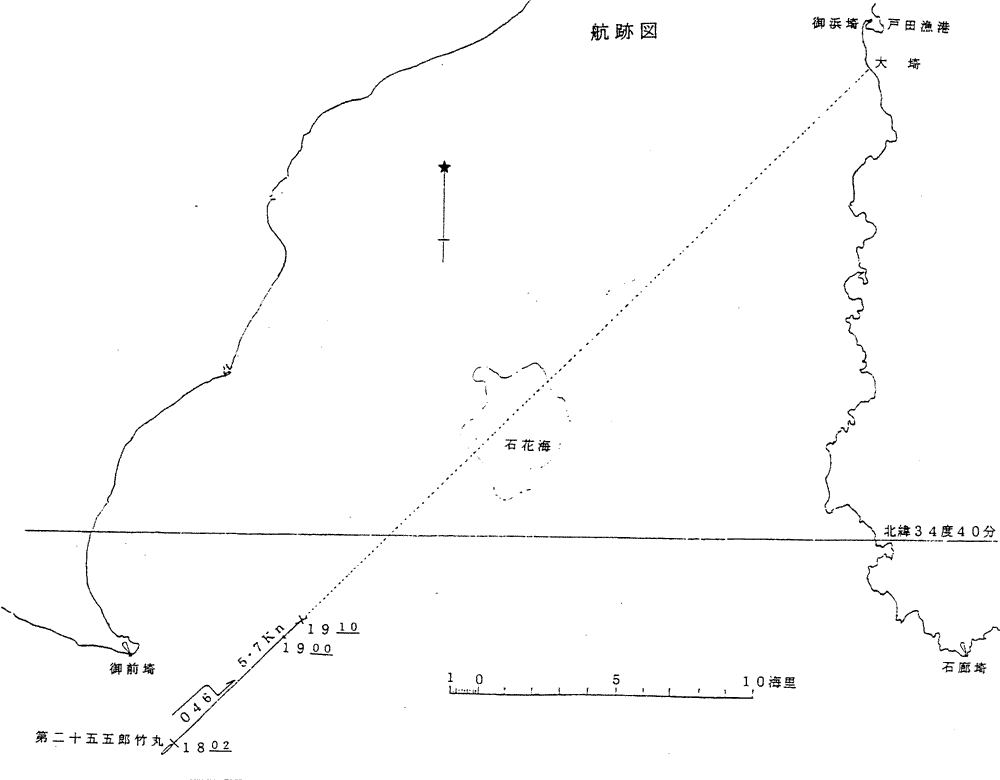 |