Œڑ’zٹîڈ€–@ژ{چs—ك‰üگ³ˆؤ‚جٹT—v
–عژں
‚PپDچق—؟پAچ\‘¢“™‚ةŒW‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚جگ®”ُ
(1)چق—؟ٹضŒWپi•s”Rچق—؟پAڈ€•s”Rچق—؟پA“ï”Rچق—؟پj
–@—¥‘و“ٌڈً‘و‹مچ†‚ة‚¨‚¢‚ؤپAگ—ك‚إ•s”Rگ«”\پi•s”Rچق—؟‚ة•K—v‚بگ«”\پj‹y‚ر•s”Rگ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ً’è‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚³‚ꂽ‚±‚ئژَ‚¯پA—ك‘و108ڈً‚ج‚Q‚ة‚¨‚¢‚ؤ•s”Rگ«”\‹y‚ر‚»‚ج‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ً’è‚ك‚éپB‚ـ‚½پA‹Kگ§“à—e‚ھ‚·‚ׂؤگ—كژ–چ€‚إ‚ ‚邽‚كپAگ—ك‚ة‚¨‚¢‚ؤ’è‹`‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈ€•s”Rچق—؟‹y‚ر“ï”Rچق—؟‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚à“¯—l‚ةگ«”\‚ئ‚»‚جٹîڈ€‚ً–¾ٹm‰»‚·‚邱‚ئ‚ئ‚µپAچق—؟‚ة‰‚¶‚ؤ•K—v‚بگ«”\‚ًژں‚ج‚ئ‚¨‚è’è‚ك‚éپB
<•s”Rچق—؟“™‚ة•K—v‚بگ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€>
’تڈي‚ج‰خچذ‚ة‚و‚é‰خ”M‚ھ‰ء‚¦‚ç‚ꂽڈêچ‡‚ةپA‰ء”MٹJژnŒمژں‚ج•\‚ةŒf‚°‚éژٹشپA•\‚ةŒf‚°‚é—vŒڈ‚ً–‚½‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئپB
|
|
|
|
|
•s”Rچق—؟(—ك‘و108ڈً‚ج‚Qپj
|
20•ھٹش
|
پE”Rڈؤ‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ
پE–h‰خڈم—LٹQ‚ب‘¹ڈ‚ًگ¶‚¶‚ب‚¢‚±‚ئ پE”ً“ïڈم—LٹQ‚ب‰Œ–”‚حƒKƒX‚ً”گ¶‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ |
|
ڈ€•s”Rچق—؟(—ك‘و‚Pڈً)
|
10•ھٹش
|
|
|
“ï”Rچق—؟(—ك‘و‚Pڈً)
|
‚T•ھٹش
|
(2)
چ\‘¢ٹضŒW
‡@پ@‘د‰خچ\‘¢“™پi‘د‰خچ\‘¢پAڈ€‘د‰خچ\‘¢پA–h‰خچ\‘¢پAڈ€–h‰خچ\‘¢پj
پ@–@‰üگ³‚ة‚و‚è‘د‰خچ\‘¢“™‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‚»‚جگ«”\پi‘د‰خگ«”\“™پj‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ًگ—ك‚إ’è‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ًژَ‚¯پAŒڑ’z•¨‚ج“|‰َپA‰„ڈؤ‚ً–hژ~“™‚·‚邽‚ك‚ةٹeچ\‘¢‚ة•K—v‚بگ«”\‚ة‚آ‚¢‚ؤڈ]—ˆ‚جٹîڈ€‚ة‚و‚éگ…ڈ€‚ً“¥ڈP‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAŒڑ’z•¨‚ج•”•ھ‚ة‰‚¶‚ؤپAگ«”\‚ج“à—e‚ً”ٌ‘¹ڈگ«پAژص”Mگ«پAژص‰ٹگ«‚ة‹و•ھ‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚è–¾ٹm‰»‚µپAˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ة‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ً’è‚ك‚éپB
<‘د‰خچ\‘¢“™‚ة•K—v‚بگ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€>
پE‘د‰خچ\‘¢‚ة‚ ‚آ‚ؤ‚حپAŒڑ’z•¨‚جٹe•”•ھ‚ھ•\‚ةŒf‚°‚é‰خچذ‚ة‚و‚é‰خ”M‚ً•\‚ةŒf‚°‚éژٹش‰ء‚¦‚ç‚ꂽڈêچ‡‚ةپA•\‚ةŒf‚°‚é—vŒڈ‚ً–‚½‚·‚±‚ئپB
پE‘د‰خچ\‘¢ˆبٹO‚جچ\‘¢‚ة‚ ‚آ‚ؤ‚حپAŒڑ’z•¨‚جٹe•”•ھ‚ھ•\‚ةŒf‚°‚é‰خچذ‚ة‚و‚é‰خ”M‚ً‰ء‚¦‚ç‚ꂽڈêچ‡‚ةپA‰ء”MٹJژnŒم•\‚ةŒf‚°‚éژٹشپA•\‚ةŒf‚°‚é—vŒڈ‚ً–‚½‚·‚±‚ئپB
|
|
|
|
|
|
|
‘د‰خچ\‘¢
(—ك‘و107ڈً) |
‘د—ح•ا¤’Œ¤ڈ°¤‚ح‚褉®چھ¤ٹK’i
|
’تڈي‚ج‰خچذ
|
‚Pژٹش‚ًٹî–{‚ئ‚µپAŒڑ’z•¨‚جٹK‚ة‰‚¶‚ؤ‚Rژٹش‚ـ‚إٹ„‘پi‰®چھ‹y‚رٹK’i‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح30•ھٹشپj
|
”ٌ‘¹ڈگ«
|
|
•ا¤ڈ°
|
’تڈي‚ج‰خچذ
|
‚PژٹشپiٹO•ا‚ج‰„ڈؤ‚ج‚¨‚»‚ê‚ج‚ب‚¢•”•ھ‚ح30•ھٹشپj
|
ژص”Mگ«
|
|
|
ٹO•ا¤‰®چھ
|
‰®“à‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذ
|
‚Pژٹشپi‰®چھ‹y‚رٹO•ا‚ج‰„ڈؤ‚ج‚¨‚»‚ê‚ج‚ب‚¢•”•ھ‚ح30•ھٹشپj
|
ژص‰ٹگ«
|
|
|
ڈ€‘د‰خچ\‘¢
(—ك‘و107ڈً‚ج2) |
‘د—ح•ا¤’Œ¤ڈ°¤‚ح‚褉®چھپAٹK’i
|
’تڈي‚ج‰خچذ
|
45•ھٹشپi‰®چھ‹y‚رٹK’i‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح30•ھٹشپj
|
”ٌ‘¹ڈگ«
|
|
•ا¤ڈ°¤Œ¬—
|
’تڈي‚ج‰خچذ
|
45•ھٹش(ٹO•ا‹y‚رŒ¬— ‚ج‰„ڈؤ‚ج‚¨‚»‚ê‚ج‚ب‚¢•”•ھ‚ح30•ھٹشپj
|
ژص”Mگ«
|
|
|
ٹO•اپA‰®چھ
|
‰®“à‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذ
|
45•ھٹش(‰®چھ‹y‚رٹO•ا‚ج‰„ڈؤ‚ج‚¨‚»‚ê‚ج‚ب‚¢•”•ھ‚ح30•ھٹش)
|
ژص‰ٹگ«
|
|
|
ڈ€‘د‰خچ\‘¢
(—ك‘و115ڈً‚ج2‚ج2) |
‘د—ح•ا¤’Œ¤ڈ°¤‚ح‚è
|
’تڈي‚ج‰خچذ
|
‚Pژٹش
|
”ٌ‘¹ڈگ«
|
|
•ا¤ڈ°¤Œ¬— (‰„ڈؤ‚ج‚¨‚»‚ê‚ج‚ ‚é•”•ھپj
|
’تڈي‚ج‰خچذ
|
‚Pژٹش
|
ژص”Mگ«
|
|
|
ٹO•ا
|
‰®“à‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذ
|
‚Pژٹش
|
ژص‰ٹگ«
|
|
|
–h‰خچ\‘¢
(—ك‘و108ڈً) |
ٹO•ا(‘د—ح•ا)
|
ژüˆح‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذ
|
30•ھٹش
|
”ٌ‘¹ڈگ«
|
|
ٹO•ا¤Œ¬—
|
ژüˆح‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذ
|
30•ھٹش
|
ژص”Mگ«
|
|
|
ڈ€–h‰خچ\‘¢
(—ك‘و109ڈً‚ج‚U) |
ٹO•ا(‘د—ح•ا)
|
ژüˆح‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذ
|
20•ھٹش
|
”ٌ‘¹ڈگ«
|
|
ٹO•ا
|
ژüˆح‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذ
|
20•ھٹش
|
ژص”Mگ«
|
|
|
‰®چھ‚جچ\‘¢
(—ك‘و109ڈً‚ج3پA‘و113ڈً) |
‰®چھ
|
‰®“à‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذ
|
20•ھٹش
|
ژص‰ٹگ«
|
|
ڈ°پi“Vˆنپj‚جچ\‘¢(—ك‘و109ڈً‚ج3پA‘و115ڈً‚ج‚Q)
|
ڈ°پA’¼‰؛‚ج“Vˆن
|
‰®“à‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذ
|
30•ھٹش
|
”ٌ‘¹ڈگ«
ژص”Mگ« |
|
‚ذ‚³‚µ“™‚جچ\‘¢(—ك‘و115ڈً‚ج2‚ج2¤‘و139ڈً‚ج2‚ج3)
|
‚ذ‚³‚µ“™
|
’تڈي‚ج‰خچذ
|
20•ھٹش
|
ژص‰ٹگ«
|
(’چ)”ٌ‘¹ڈگ«پFچ\‘¢‘د—حڈمژxڈل‚ج‚ ‚鑹ڈ‚ًگ¶‚¶‚ب‚¢‚±‚ئ
ژص”Mگ«پ@پF‰ء”M–تˆبٹO‚ج–ت‚ج‰·“x‚ھ“–ٹY–ت‚ةگع‚·‚é‰آ”R•¨‚ج”Rڈؤ‚ج‚¨‚»‚ê‚ج‚ ‚鉷“xˆبڈم‚ةڈمڈ¸‚µ‚ب‚¢‚±‚ئپB
ژص‰ٹگ«پ@پF‰®ٹO‚ة‰خ‰ٹ‚ًڈo‚·‚¨‚»‚ê‚ج‚ ‚鑹ڈ‚ًگ¶‚¶‚ب‚¢‚±‚ئپB
’تڈي‚ج‰خچذپFˆê”ت“I‚ةŒڑ’z•¨‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚邱‚ئ‚ھ‘z’肳‚ê‚é‰خچذ‚ً•\‚·—pŒê‚ئ‚µ‚ؤ—p‚¢‚ؤ‚¨‚èپA‰®“à‚إ”گ¶‚·‚é‰خچذپAŒڑ’z•¨‚جژüˆح‚إ”گ¶‚·‚é‰خچذ‚ج—¼•û‚ًٹـ‚ق‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB“ء‚ة‰خچذ‚ًŒہ’è‚·‚éڈêچ‡‚ة‚حپu‰®“à‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذپv–”‚حپuŒڑ’z•¨‚جژüˆح‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذپv‚ئ‚¢‚¤—pŒê‚ً—p‚¢‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@‡Aپ@–h‰خپEڈ€–h‰خ’nˆوپA22ڈً‹وˆو‚ج‰®چھ
پ@ڈ]—ˆپA•s”Rچق—؟‚إ‘¢‚è–”‚ح‚س‚‚±‚ئ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پA‰®چھ•s”R‹وˆوپA–h‰خ’nˆو‹y‚رڈ€–h‰خ’nˆو‚ج‰®چھ‚ة•K—v‚بگ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ًگ—ك‚إ’è‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ًژَ‚¯پA‰®چھ‚ھ‰خ‚ج•²‚ة‚و‚蔉ٹ‚µژüˆح‚ة‰„ڈؤ‚·‚邱‚ئپA‰خ‚ج•²‚ة‚و‚è”R‚¦”²‚¯‚邱‚ئ‚ة‚و‚è“–ٹYŒڑ’z•¨‚ة‚¨‚¢‚ؤ‰خچذ‚ھ”گ¶‚·‚邱‚ئ‚ً–hژ~‚·‚邽‚كپAژں‚ج‚ئ‚¨‚èپA•K—v‚ب‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ً’è‚ك‚éپB
‚ـ‚½پAژه—vچ\‘¢•”‚ًڈ€‘د‰خچ\‘¢‚ئ‚µ‚½Œڑ’z•¨‚ئ“¯“™‚جگ«”\‚ً—L‚·‚éŒڑ’z•¨‚ج‰®چھ‚ة‚آ‚¢‚ؤپA•s”Rچق—؟‚إ‘¢‚è–”‚ح‚س‚‚±‚ئ‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‹K’è‚ً“¯—l‚جژïژ|‚©‚ç–@‘و22ڈً‚ة‹K’è‚·‚éچ\‘¢‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
<‰®چھ‚ة•K—v‚بگ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€>
Œڑ’z•¨‚ج‘¶‚·‚é‹وˆو‚ة‰‚¶‚ؤپA•\‚ةŒf‚°‚é‰خچذ‚ة‚و‚é‰خ‚ج•²‚ة‚و‚èپA•\‚ةŒf‚°‚é—vŒڈ‚ً–‚½‚·‚±‚ئپB
|
|
|
|
|
22ڈً‹وˆو‚جŒڑ’z•¨‚ج‰®چھ
(—ك‘و109ڈً‚ج5پj |
’تڈي‚ج‰خچذ
|
پE–h‰خڈم—LٹQ‚ب”‰ٹ‚ً‚µ‚ب‚¢‚±‚ئپB
پE‰®“à‚ة‰خ‰ٹ‚ھ’B‚·‚鑹ڈ‚ًگ¶‚¶‚ب‚¢‚±‚ئپB–h‰خڈم—LٹQ‚ب‘¹ڈ‚ًگ¶‚¶‚ب‚¢‚±‚ئپi•s”Rگ«‚ج•¨•i‚ً•غٹا‚·‚é‘qŒة“™‚إ‰®چھˆبٹO‚جژه—vچ\‘¢•”‚ھڈ€•s”Rچق—؟‚إ‘¢‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚ج‰®چھ‚ًڈœ‚پBپj |
|
–h‰خ’nˆو‹y‚رڈ€–h‰خ’nˆو‚جŒڑ’z•¨‚ج‰®چھ
(—ك‘و136ڈً‚ج2‚ج3) |
ژsٹX’n‚ة‚¨‚¯‚é’تڈي‚ج‰خچذ
|
(’چ)
ژsٹX’n‚ة‚¨‚¯‚é’تڈي‚ج‰خچذ‚ة‚و‚é‰خ‚ج•²‚حپA’تڈي‚ج‹وˆو‚و‚è‚àŒڑ’z•¨ژü•س‚جژsٹX’n‚ھâf–§‚إ‚ ‚èپA‰خ‚ج•²‚ج‘ه‚«‚³‚à‘ه‚«‚‚ب‚邱‚ئ‚ھ—\‘z‚³‚ê‚邽‚كپA“–ٹY’nˆو‚إ‚ج‰خچذ‚جڈَ‹µ‚ًچl—¶‚µ‚ؤ‚و‚è‘ه‚«‚ب‰خ‚ج•²‚ة‘خ‚·‚éگ«”\‚ً‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(3)
–h‰خگف”ُٹضŒW
‘د‰خŒڑ’z•¨“™‚جٹO•ا‚جٹJŒû•”‚ةگف‚¯‚é–h‰خگف”ُ‹y‚ر–h‰خپEڈ€–h‰خ’nˆو“à‚جŒڑ’z•¨‚جٹO•ا‚جٹJŒû•”‚ةگف‚¯‚é–h‰خگف”ُ‹y‚ر‚»‚جگ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ًگ—ك‚إ’è‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ًژَ‚¯پA–h‰خگف”ُ‚ً’è‚ك‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپA‚»‚ꂼ‚êگ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ً’è‚ك‚éپB
‚ـ‚½پAڈ]—ˆگ—ك‚ة‚¨‚¢‚ؤ‹K’肵‚ؤ‚¢‚½‚Pژٹشˆبڈم‚جگ«”\‚ً—L‚·‚é–h‰خگف”ُ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚à“¯—l‚ةگ«”\‹K’艻‚ًچs‚¢پAŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚½چ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ئ‚·‚é‚ׂ«‚±‚ئ‚ً‹K’è‚·‚éپB
<گ—ك‚إ’è‚ك‚é–h‰خگف”ُ>پi—ك‘و109ڈًپj
–h‰خŒثپAƒhƒŒƒ“ƒ`ƒƒپ[“™‰خ‰ٹ‚ًژص‚é‚à‚ج‚ً’è‚ك‚éپB
‚ـ‚½پAڈ]—ˆ‚ج‹K’è‚ً“¥ڈP‚µپAٹJŒû•”‚ئ—×’n‹«ٹEگü“™‚ً—LŒّ‚ةژص‚éٹO•اپA•»“™‚ً–h‰خگف”ُ‚ئ‚ف‚ب‚·‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپB
<–h‰خگف”ُ‚ة•K—v‚بگ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€>
پE–h‰خگف”ُ‚ة‰‚¶‚ؤپA•\‚ةŒf‚°‚é‰خچذ‚ة‚و‚é‰خ”M‚ھ‰ء‚¦‚ç‚ꂽڈêچ‡‚ةپA•\‚ةŒf‚°‚éژٹشپA•\‚ةŒf‚°‚é—vŒڈ‚ً–‚½‚·‚±‚ئپB
|
|
|
|
|
|
‘د‰خŒڑ’z•¨‚جٹO•ا‚جٹJŒû•”‚ةگف‚¯‚é–h‰خگف”ُ(—ك‘و109ڈً‚ج5پj
|
’تڈي‚ج‰خچذ
|
20•ھٹش
|
پE‰ء”M–تˆبٹO‚ج–ت‚ة‰خ‰ٹ‚ًڈo‚³‚ب‚¢‚±‚ئ
|
|
–h‰خ’nˆو‹y‚رڈ€–h‰خ’nˆو‚جŒڑ’z•¨‚جٹJŒû•”‚ةگف‚¯‚é–h‰خگف”ُ(—ك‘و136ڈً‚ج2‚ج2)
|
ژüˆح‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é’تڈي‚ج‰خچذ
|
20•ھٹش
|
|
|
–h‰خ‹و‰و‚ة—p‚¢‚é–h‰خگف”ُپi“ء’è–h‰خگف”ُپj(—ك‘و112ڈً‘و1چ€)
|
’تڈي‚ج‰خچذ
|
‚Pژٹش
|
‚QپD‘د‰خŒڑ’z•¨‚جژه—vچ\‘¢•”‚جگ«”\ٹضŒWپi—ك‘و108ڈً‚ج‚Rپj
پ@(1)
‘د‰خŒڑ’z•¨‚جژه—vچ\‘¢•”
‚±‚ê‚ـ‚إپA‘د‰خŒڑ’z•¨‚حژه—vچ\‘¢•”‚ًˆê—¥‚ة‘د‰خچ\‘¢‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ھپAچ،‰ٌ‚ج–@‰üگ³‚ة‚و‚èپA‘د‰خŒڑ’z•¨‚جژه—vچ\‘¢•”‚حژں‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ئ‚³‚ꂽپBپi–@‘و2ڈً‘و‹مچ†‚ج“ٌپj
‡@‘د‰خچ\‘¢
‡A‰خچذ‚ھڈI—¹‚·‚é‚ـ‚إ‘د‚¦‚邱‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤگ—ك‚إ’è‚ك‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج
پ@Œ»چs‹K’è‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA‘د‰خچ\‘¢‚جژه—vچ\‘¢•”‚حŒڑ’z•¨‚ج•”•ھ‚ة‰‚¶‚ؤˆê—¥‚بژٹش‘د‚¦‚é‘د‰خچ\‘¢‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‹ك”N‚ة‚¨‚¯‚éŒڑ’z•¨‚ج–h‰خ‚ةٹض‚·‚é‹ZڈpٹJ”‚جگi“W‚ة‚و‚èŒڑ’z•¨‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é‰خچذ‚جگ«ڈَ‚ً—\‘ھ‚·‚éچHٹw“I•û–@‚ھٹJ”‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‚±‚جژè–@‚ً—p‚¢‚ؤ—\‘ھ‚³‚ê‚é‰خچذ‚ة‘خ‚µ‚ؤ‘د‚¦‚éگ«”\‚ً—L‚·‚éژه—vچ\‘¢•”‚ة‚آ‚¢‚ؤ‘د‰خچ\‘¢‚ئ“¯—l‚ةژو‚舵‚¤‚±‚ئ‚ئ‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@‚±‚ج‚½‚كپAگ—ك‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA‘د‰خŒڑ’z•¨‚جژه—vچ\‘¢•”‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ًپAژه—vچ\‘¢•”‚ھ‰؛‹L‚جگ«”\‚جٹîڈ€‚ة“Kچ‡‚·‚邱‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤˆê”ت“I‚بŒںڈط–@پi‘د‰خگ«”\Œںڈط–@پj‚ة‚و‚èٹm‚©‚ك‚ç‚ꂽ‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
|
پگ«”\‚جٹîڈ€پi‘و‚Pچ€پj
‡@پ@‰®“à‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚ھ—\‘ھ‚³‚ê‚é‰خچذ‚ة‚و‚é‰خ”M‚ھ‰ء‚¦‚ç‚ꂽڈêچ‡‚ةˆب‰؛‚ج—vŒڈ‚ً–‚½‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئپB پE‘د—ح•اپA’ŒپAڈ°پA‚ح‚èپA‰®چھ‹y‚رٹK’i‚ة‚ ‚آ‚ؤ‚حپAژ©ڈd‹y‚رگدچع‰×ڈdپi‘½گل‹وˆو‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚حژ©ڈdپAگدچع‰×ڈd‹y‚رگدگل‰×ڈdپBˆب‰؛“¯‚¶پBپj‚ة‚و‚é—ح‚ھگ¶‚¶‚½ڈَ‘ش‚إ”ٌ‘¹ڈگ«‚ً—L‚·‚邱‚ئپB پE•ا‹y‚رڈ°‚ة‚ ‚آ‚ؤ‚حپAژص”Mگ«‚ً—L‚·‚邱‚ئپB پEٹO•ا‹y‚ر‰®چھ‚ة‚ ‚آ‚ؤ‚حپAژص‰ٹگ«‚ً—L‚·‚邱‚ئپB ‡Aپ@ٹO•ا‚ة‚ ‚آ‚ؤ‚حپAŒڑ’z•¨‚جژüˆح‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é‰خچذ‚ة‚و‚é‰خ”M‚ھ‰ء‚¦‚ç‚ꂽڈêچ‡‚ةˆب‰؛‚ج—vŒڈ‚ً–‚½‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئپB پE‘د—ح•ا‚إ‚ ‚éٹO•ا‚ة‚ ‚آ‚ؤ‚حپAژ©ڈd‹y‚رگدچع‰×ڈd‚ة‚و‚é—ح‚ھگ¶‚¶‚½ڈَ‘ش‚إ”ٌ‘¹ڈگ«‚ً—L‚·‚邱‚ئپB پEژص”Mگ«‚ً—L‚·‚邱‚ئپB |
(’چ)
”ٌ‘¹ڈگ«پFچ\‘¢‘د—حڈمژxڈل‚ج‚ ‚鑹ڈ‚ًگ¶‚¶‚ب‚¢‚±‚ئ
ژص”Mگ«پF‰ء”M–تˆبٹO‚ج–ت‚ج‰·“x‚ھ“–ٹY–ت‚ةگع‚·‚é‰آ”R•¨‚ج”Rڈؤ‚ج‚¨‚»‚ê‚ج‚ ‚鉷“xˆبڈم‚ةڈمڈ¸‚µ‚ب‚¢‚±‚ئپB
ژص‰ٹگ«پF‰®ٹO‚ة‰خ‰ٹ‚ًڈo‚·‚¨‚»‚ê‚ج‚ ‚鑹ڈ‚ًگ¶‚¶‚ب‚¢‚±‚ئپB
|
پ‘د‰خگ«”\Œںڈط–@‚جٹT—vپi‘و‚Qچ€پj
‡@‰®“à‰خچذ‚ة‚آ‚¢‚ؤŒڑ’z•¨‚جژ؛‚²‚ئ‚ة—\‘ھ‚³‚ê‚é‰خچذ‚جŒp‘±ژٹش‹y‚ر“–ٹYژ؛‚جژه—vچ\‘¢•”‚ھ—\‘ھ‚³‚ê‚é‰خچذ‚ة‘د‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éژٹشپi‰®“à‰خچذ•غ—L‘د‰خژٹشپj‚ً‹پ‚كپA‰®“à‰خچذ•غ—L‘د‰خژٹش‚ھ‰خچذ‚جŒp‘±ژٹشˆبڈم‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚éپB پE‰خچذ‚جŒp‘±ژٹش‚حپA“–ٹYژ؛‚ج‰آ”R•¨‚ج‘چ””M—ت‚ًژٹش“–‚½‚è‚ج””M—ت‚إڈœ‚µ‚ؤŒvژZ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB‘چ””M—ت‚حپAژ؛‚ج—p“rپA“à‘•‚ة—p‚¢‚éچق—؟‚ة‰‚¶‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚èژZڈo‚·‚邱‚ئ‚ئ‚µپAژٹش“–‚½‚è‚ج””M—ت‚حژ؛‚ج—p“rپAٹJŒû•”‚جŒ`ڈَ“™‚ة‰‚¶‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB پEژه—vچ\‘¢•”‚ج‰®“à‰خچذ•غ—L‘د‰خژٹش‚حپAژه—vچ\‘¢•”‚جچ\‘¢•û–@پAŒڑ’z•¨‚جژ©ڈd“™‚ة‚و‚ء‚ؤژه—vچ\‘¢•”‚ةگ¶‚¶‚é—ح‹y‚ر—\‘ھ‚³‚ê‚é‰خچذ‚ة‚و‚鉷“x‚جگ„ˆع‚ة‰‚¶‚ؤپAŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‡AٹO•ا‚ھŒڑ’z•¨‚جژüˆح‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚·‚é‰خچذ‚ة‘د‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éژٹشپi‰®ٹO‰خچذ•غ—L‘د‰خژٹشپj‚ً‹پ‚كپA‰®ٹO‰خچذ•غ—L‘د‰خژٹش‚ھ‚Pژٹشپi‰„ڈؤ‚ج‚¨‚»‚ê‚ج‚ ‚é•”•ھˆبٹO‚ج•”•ھ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح30•ھٹشپjˆبڈم‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚éپB پEٹO•ا‚ج‰®ٹO‰خچذ•غ—L‘د‰خژٹش‚حپAٹO•ا‚جچ\‘¢•û–@‹y‚رŒڑ’z•¨‚جژ©ڈd“™‚ة‚و‚ء‚ؤٹO•ا‚ةگ¶‚¶‚é—ح‚ة‰‚¶‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB |
پ@‚ـ‚½پAژه—vچ\‘¢•”‚ً‰خچذ‚ھڈI—¹‚·‚é‚ـ‚إ‘د‚¦‚邱‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‘د‰خگ«”\Œںڈط–@‚ة‚و‚ء‚ؤٹm‚©‚ك‚ç‚ꂽ‚à‚ج–”‚ح‘هگb”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ئ‚µ‚½Œڑ’z•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤگ—ك‚جٹe‹K’è‚ً“K—p‚·‚éڈêچ‡‚ج“K—pٹضŒW‚ًگ®—‚·‚邽‚كپA“–ٹYŒڑ’z•¨‚ج•”•ھ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAگ—ك‚ج•K—v‚ب‹K’è‚ج“K—p‚ة“–‚½‚è‘د‰خچ\‘¢“™‚إ‚ ‚é‚à‚ج‚ئ‚ف‚ب‚·‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپBپi‘و‚Rچ€پj
پ@‚³‚ç‚ةپAژه—vچ\‘¢•”‚ھ‰خچذ‚ھڈI—¹‚·‚é‚ـ‚إ‘د‚¦‚邱‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‘د‰خگ«”\Œںڈط–@‚ة‚و‚èٹm‚©‚ك‚ç‚ꂽ‚à‚ج–”‚ح‘هگb”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚éŒڑ’z•¨‚ج•ا–”‚حڈ°‚جٹJŒû•”‚ةگف‚¯‚é–h‰خگف”ُ‚ة‚آ‚¢‚ؤپA“–ٹYŒڑ’z•¨‚ج‰®“à‚ة‚¨‚¢‚ؤ”گ¶‚ھ—\‘ھ‚³‚ê‚é‰خچذ‚ة‚و‚é‰خ”M‚ھ‰ء‚¦‚ç‚ꂽڈêچ‡‚ةپA“–ٹY‰ء”M–تˆبٹO‚ج–ت‚ة‰خ‰ٹ‚ًڈo‚³‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤ–h‰خ‹و‰وŒںڈط–@‚ة‚و‚ء‚ؤٹm‚©‚ك‚ç‚ꂽ‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAگ—ك‚ج•K—v‚ب‹K’è‚ج“K—p‚ة“–‚½‚è“ء’è–h‰خگف”ُ“™‚ئ‚ف‚ب‚·‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپBپi‘و‚Sچ€پj
|
پ–h‰خ‹و‰وŒںڈط–@‚جٹT—vپi‘و‚Tچ€پj
پ›Œڑ’z•¨‚جژ؛‚²‚ئ‚ة—\‘ھ‚³‚ê‚é‰خچذ‚جŒp‘±ژٹش‹y‚ر“–ٹYژ؛‚ج•اپAڈ°‚جٹJŒû•”‚ةگف‚¯‚ç‚ê‚é–h‰خگف”ُ‚ھ—\‘ھ‚³‚ê‚é‰خچذ‚ة‘د‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éژٹشپi•غ—Lژص‰ٹژٹشپj‚ً‹پ‚كپA•غ—Lژص‰ٹژٹش‚ھ‰خچذ‚جŒp‘±ژٹشˆبڈم‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚éپB پE
‰خچذ‚جŒp‘±ژٹش‚ح‘د‰خگ«”\Œںڈط–@‚ئ“¯—l‚ج•û–@‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB پE
•غ—Lژص‰ٹژٹش‚ح–h‰خگف”ُ‚جچ\‘¢•û–@پA—\‘ھ‚³‚ê‚é‰خچذ‚ة‚و‚鉷“x‚جگ„ˆع‚ة‰‚¶‚ؤŒڑگف‘هگb‚ج’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB |
(2)‘ه‹K–حŒڑ’z•¨‚جگ—ك‚إ’è‚ك‚é•”•ھپi—ك‘و109ڈً‚ج‚Sپj
–@‘و21ڈً‘و‚Pچ€‹y‚ر‘و‚Qچ€‚ج‘ه‹K–ح‚بŒڑ’z•¨‚إگ—ك‚إ’è‚ك‚é•”•ھ‚ة‰آ”Rچق—؟‚ً—p‚¢‚½‚à‚ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAژه—vچ\‘¢•”‚ً–@‘و‚Qڈً‘و‹مچ†‚ج“ٌƒC‚ةٹY“–‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚·‚ׂ«‚±‚ئ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‰خچذژ‚ةŒڑ’z•¨‚ج“|‰َ‚ً–hژ~‚·‚邽‚كپA•K—v‚ب•”•ھ‚ئ‚µ‚ؤپAژ©ڈd–”‚حگدچع‰×ڈdپi‘½گل‹وˆو‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAژ©ڈdژل‚µ‚‚حگدچع‰×ڈd–”‚حگدگلپj‚ًژx‚¦‚é•”•ھ‚ً’è‚ك‚éپi—ك‘و109ڈً‚ج‚Sپj
‚RپD”ً“ïˆہ‘SŒںڈط‚ًچs‚¤Œڑ’z•¨‚جٹK–”‚حŒڑ’z•¨‚ة‘خ‚·‚éٹîڈ€‚ج“K—pٹضŒWپi—ك‘و129ڈً‚ج2پA‘و129ڈً‚ج2‚ج2پj
پ@پ@ڈ]—ˆپA”ً“ïٹضŒW‹K’è‚ئ‚µ‚ؤپAˆê’è‹K–حˆبڈم‚جŒڑ’z•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚بچ€–ع‚ة‚آ‚¢‚ؤ‹K’è‚ًگف‚¯‚ؤ‚¢‚éپB
ƒCپ@‰خچذ‚ة‚و‚鉌“™‚جٹg‘هŒoکH‚ئ‚ب‚è‚â‚·‚¢ٹK’iژ؛“™‚ج‚½‚ؤŒٹ‚ج•”•ھ‚ج‹و‰وپAڈء–h‘à‚ة‚و‚é‹~ڈ•ٹˆ“®“™‚جچ¢“ï‚ھ“ء‚ة—\‘ھ‚³‚ê‚é11ٹKˆبڈم‚جٹK‚ة‚¨‚¯‚é‹و‰و“™‚ةٹض‚·‚é‹K’è
ƒچپ@’¼’تٹK’i‚ـ‚إ‚ج•àچs‹——£پAکL‰؛‚ج•پA”ً“ïٹK’i‚جچ\‘¢“™‚ج”ً“ïژ{گف‚ةٹض‚·‚é‹K’è
ƒnپ@”r‰Œگف”ُپA”ٌڈي—pڈئ–¾‘•’uپA”ٌڈي—pگi“üŒûپA•~’n“à’تکH“™‚جگف’uپAچ\‘¢‚ةٹض‚·‚é‹K’è
ƒjپ@‹ڈژ؛پA’تکH“™‚ج“à‘•‚جژdڈم‚°‚ةŒW‚é‹K’è
‹ك”N‚جŒڑ’z•¨‚ةٹض‚·‚é–h‰خ‹Zڈp‚جگi“W‚ة‚و‚èپAŒڑ’z•¨‚ة‚¨‚¢‚ؤ‰خچذ‚ھ”گ¶‚µ‚½ڈêچ‡‚ةپA“–ٹYŒڑ’z•¨“à‚جچفٹظژز‚ج”ً“ïچs“®‚ً—\‘ھ‚µپA“¯ژ‚ة‰خچذ‚ة‚و‚鉌پAƒKƒX‚جڈَ‘ش‚ً—\‘ھ‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚èپA‰خچذژ‚ج”ً“ï‚جˆہ‘Sگ«‚ًٹm”F‚·‚éچHٹw“Iژè–@‚ھٹJ”‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
‚±‚¤‚µ‚½چHٹw“Iژè–@‚ً“±“ü‚µپAŒڑ’z•¨‚جٹK–”‚حŒڑ’z•¨‚إپA”ً“ïˆہ‘Sگ«”\‚ً—L‚·‚邱‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤˆê”ت“I‚بŒںڈط–@پi”ً“ïˆہ‘SŒںڈط–@پj‚ة‚و‚èٹm‚©‚ك‚ç‚ꂽ‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAڈم‹L‚جƒC‚©‚çƒj‚ـ‚إŒf‚°‚é‹K’è‚جˆê•”‚ة‚آ‚¢‚ؤ“K—p‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپB
|
پٹK”ً“ïˆہ‘Sگ«”\پi—ك‘و129ڈً‚ج2‘و2چ€پj
پEپ@“–ٹYٹK‚ج‚¢‚¸‚ê‚جژ؛‚©‚ç‰خچذ‚ھ”گ¶‚µ‚½ڈêچ‡‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àپA“–ٹYٹK‚ة‘¶‚·‚éژز‚ج‚·‚ׂؤ‚ھپA“–ٹYٹK‚©‚ç‚ج”ً“ï‚ًڈI—¹‚·‚é‚ـ‚إ‚جٹشپA“–ٹYٹK‚جٹe‹ڈژ؛‹y‚رٹe‹ڈژ؛‚©‚ç’¼’تٹK’i‚ة’ت‚¸‚éکL‰؛“™‚ة‚¨‚¢‚ؤ”ً“ïڈمژxڈل‚ھ‚ ‚éچ‚‚³‚ـ‚إ‰Œ–”‚حƒKƒX‚ھچ~‰؛‚µ‚ب‚¢‚±‚ئپB |
|
پٹK”ً“ïˆہ‘SŒںڈط–@‚جٹT—vپi—ك‘و129ڈً‚ج2‘و3چ€پj
‡@“–ٹYٹK‚جٹe‹ڈژ؛‚©‚ç”ً“ï‚ًڈI—¹‚·‚é‚ـ‚إ‚جژٹش‚ئ“–ٹY‹ڈژ؛‚ھ‰Œ–”‚حƒKƒX‚ة‚و‚ء‚ؤٹ댯‚ئ‚ب‚é‚ـ‚إ‚جژٹش‚ً”نٹr‚µپAٹe‹ڈژ؛‚©‚çˆہ‘S‚ة”ً“ï‚ھ‚إ‚«‚邱‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚éپB پE‹ڈژ؛‚©‚ç‚ج”ً“ï‚ھڈI—¹‚·‚éژٹش‚حپA”ً“ï‚ًٹJژn‚·‚é‚ـ‚إ‚جژٹشپAڈoŒû‚ـ‚إ‚ج•àچsژٹش‹y‚رڈoŒû‚ً’ت‰ك‚·‚é‚ج‚ة—v‚·‚éژٹش‚جچ‡Œv‚ئ‚µپAژ؛‚ج—p“rپAڈ°–تگدپAڈo“üŒû‚ج•“™‚ة‰‚¶‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB پE‹ڈژ؛‚ھ‰ŒپEƒKƒX‚ة‚و‚ء‚ؤٹ댯‚ئ‚ب‚éژٹش‚حپAٹe‹ڈژ؛‚ج—p“rپA”r‰Œگف”ُ‚جچ\‘¢پA“à‘•‚جژdڈم‚°‚ة—p‚¢‚éچق—؟‚جژي—ق“™‚ة‰‚¶‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB ‡A“–ٹYٹK‚جٹe‰خچذژ؛‚²‚ئ‚ةپA“–ٹYژ؛‚إ‰خچذ‚ھ”گ¶‚µ‚½ڈêچ‡‚ةپA“–ٹYٹK‚©‚ç‚ج”ً“ï‚ھڈI—¹‚·‚éژٹش‚ئ“–ٹYٹK‚ج”ً“ïŒoکH‚ة‚¨‚¢‚ؤ‰ŒپEƒKƒX‚ة‚و‚ء‚ؤٹ댯‚ئ‚ب‚é‚ـ‚إ‚جژٹش‚ً”نٹr‚µپA‰خچذژ‚ةٹeٹK‚©‚çˆہ‘S‚ة”ً“ï‚ھ‚إ‚«‚邱‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚éپB پEٹK‚©‚ç‚ج”ً“ï‚ھڈI—¹‚·‚é‚ـ‚إ‚جژٹش‚حپA”ً“ï‚ًٹJژn‚·‚é‚ـ‚إ‚جژٹشپAٹK’i‚جڈo“üŒû‚ـ‚إ‚ج•àچsژٹش‹y‚رڈo“üŒû‚ً’ت‰ك‚·‚é‚ج‚ة—v‚·‚éژٹش‚جچ‡Œv‚ئ‚µپAٹe‰خچذژ؛‚²‚ئ‚ةپAٹeژ؛‚ج—p“rپAڈ°–تگدپAڈo“üŒû‚ج•پAٹK’i‚ـ‚إ‚ج‹——£“™‚ة‰‚¶‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB پEٹeٹK‚ج”ً“ïŒoکH‚ھ‰ŒپEƒKƒX‚ة‚و‚ء‚ؤٹ댯‚ئ‚ب‚éژٹش‚حپAٹe‰خچذژ؛‚²‚ئ‚ةپAٹeژ؛‚ج—p“rپA”r‰Œگف”ُ‚جچ\‘¢پA“à‘•‚جژdڈم‚°‚ة—p‚¢‚éچق—؟‚جژي—ق“™‚ة‰‚¶‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB |
|
پ‘Sٹظ”ً“ïˆہ‘Sگ«”\پi—ك‘و129ڈً‚ج2‚ج2‘و2چ€پj
پEپ@“–ٹYŒڑ’z•¨‚ج‚¢‚¸‚ê‚جژ؛‚©‚ç‰خچذ‚ھ”گ¶‚µ‚½ڈêچ‡‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àپA“–ٹYŒڑ’z•¨‚جچفٹظژز‚ج‚·‚ׂؤ‚ھپA“–ٹYŒڑ’z•¨‚©‚ç‚ج”ً“ï‚ًڈI—¹‚·‚é‚ـ‚إ‚جٹشپA“–ٹYŒڑ’z•¨‚جٹe‹ڈژ؛‹y‚رٹe‹ڈژ؛‚©‚ç’nڈم‚ة’ت‚¸‚éکL‰؛پAٹK’i“™‚ة‚¨‚¢‚ؤ”ً“ïڈمژxڈل‚ھ‚ ‚éچ‚‚³‚ـ‚إ‰Œ–”‚حƒKƒX‚ھچ~‰؛‚µ‚ب‚¢‚±‚ئپB |
|
پ‘Sٹظ”ً“ïˆہ‘SŒںڈط–@‚جٹT—vپi—ك‘و129ڈً‚ج2‚ج2‘و3چ€پj
‡@Œڑ’z•¨‚جٹeٹK‚ھٹK”ً“ïˆہ‘Sگ«”\‚ً—L‚·‚邱‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤٹK”ً“ïˆہ‘SŒںڈط–@‚ة‚و‚ء‚ؤٹm”F ‡A“–ٹYŒڑ’z•¨‚جٹeٹK‚جٹe‰خچذژ؛‚²‚ئ‚ةپA“–ٹYژ؛‚إ‰خچذ‚ھ”گ¶‚µ‚½ڈêچ‡‚ةپA“–ٹYŒڑ’z•¨‚©‚ç‚ج”ً“ï‚ھڈI—¹‚·‚éژٹش‚ئٹK’iژ؛–”‚ح“–ٹYٹK‚ج’¼ڈمٹKˆبڈم‚جٹK‚ة‰ŒپEƒKƒX‚ھ—¬“ü‚·‚éژٹش‚ً”نٹr‚µپA‰خچذژ‚ةŒڑ’z•¨‚©‚çˆہ‘S‚ة”ً“ï‚ھ‚إ‚«‚邱‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚éپB پEŒڑ’z•¨‚©‚ç‚ج”ً“ï‚ھڈI—¹‚·‚é‚ـ‚إ‚جژٹش‚حپA”ً“ï‚ًٹJژn‚·‚é‚ـ‚إ‚جژٹشپA’nڈم‚ة’ت‚¸‚éڈoŒû‚ـ‚إ‚ج•àچsژٹش‹y‚رڈoŒû‚ً’ت‰ك‚·‚é‚ج‚ة—v‚·‚éژٹش‚جچ‡Œv‚ئ‚µپA“–ٹYŒڑ’z•¨‚جٹeٹK‚جٹe‰خچذژ؛‚²‚ئ‚ةپAŒڑ’z•¨‚ج—p“rپAڈ°–تگدپAڈo“üŒû‚ج•“™‚ة‰‚¶‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB پEٹK’i–”‚ح‰خچذژ؛‚ج’¼ڈمٹKˆبڈم‚جٹK‚ة‰Œ‚ھ—¬“ü‚·‚é‚ـ‚إ‚جژٹش‚حپA‰خچذژ؛‚ج—p“rپA”r‰Œگف”ُ‚جچ\‘¢پA“à‘•‚جژdڈم‚°‚ة—p‚¢‚éچق—؟‚جژي—ق“™‚ة‰‚¶‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB |
(1)
–h‰خ‹و‰وٹضŒWپi—ك‘و112ڈًپj
‡@پ@چ‚‘w‹و‰و‚ج“K—pڈœٹO‚جٹîڈ€پi‘و8چ€پj
پ@11ٹKˆبڈم‚جٹK‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAڈء–h‘à‚ة‚و‚é‹~ڈ•ٹˆ“®“™‚ة‚آ‚¢‚ؤ“ء‚ةچ¢“ï‚ھ—\‘ھ‚³‚ê‚邱‚ئ‚©‚çپA‰خچذژ‚ة‰خچذ‚جٹg‘ه‚ً’x‰„‚³‚¹پA”ً“ï‚جˆہ‘Sگ«‚ًٹm•غ‚·‚邽‚كپA100‡uˆب“à‚²‚ئ‚ة‘د‰خچ\‘¢‚جڈ°“™‚إ‹و‰و‚·‚邱‚ئ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‹¤“¯ڈZ‘î‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA‡@Œڑ’z•¨‚جچ\‘¢‚ة‚آ‚¢‚ؤڈn’m‚µ‚½“ء’èپEڈگ”‚جژز‚ة‚و‚ء‚ؤ—ک—p‚³‚êپA‡AڈZŒث’Pˆت‚ج‹و‰و‚ھگف‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¨‚èپA’تڈي‚ح200‡u’ِ“x‚ة‹و‰و‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ê‚خپA‰خچذژ‚ج”ً“ïˆہ‘Sگ«‚ھٹm•غ‚³‚ê‚邱‚ئ‚©‚çپA200‡uˆب‰؛‚ج‹¤“¯ڈZ‘î‚جڈZŒث‚إڈZŒث‚²‚ئ‚ة‹و‰و‚³‚ꂽ‚à‚ج‚ح100‡uˆب“à‚²‚ئ‚ة‹و‰و‚·‚邱‚ئ‚ً—v‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‡Aپ@‚½‚ؤŒٹ‹و‰و‚ةٹض‚·‚é‹K’è‚ج–¾ٹm‰»پi‘و9چ€پj
Œڑ’z•¨‚جٹK’iژ؛پAڈ¸چ~کH“™‚ج‰خچذژ‚ة‰Œ“™ٹg‘ه‚·‚éŒoکH‚ئ‚ب‚è‚â‚·‚¢‚½‚ؤŒٹ‚ج•”•ھ‚ً‚»‚ج‘¼‚ج•”‚ئ‚ً‹و‰و‚·‚邱‚ئ‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‹¤“¯ڈZ‘î‚جڈZŒث‚إ•،گ”‚جٹK‚ً—L‚·‚鋤“¯ڈZ‘î‚جڈZŒث‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAڈZŒث‚²‚ئ‚ة‘¼‚ج•”•ھ‚ئ‹و‰و‚·‚邱‚ئ‚ئ‚µپAڈZŒث“à‚جٹK’i‚ج•”•ھ“™‚ح‚»‚ج‘¼‚ج•”•ھ‚ئ‹و‰و‚·‚邱‚ئ‚ح—v‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپAڈً•¶ڈم‚à‚±‚جژïژ|‚ً–¾ٹm‰»‚·‚邽‚كپA‚½‚ؤŒٹ‹و‰و‚ً—v‚µ‚ب‚¢•”•ھ‚ئ‚µ‚ؤ‹¤“¯ڈZ‘î‚جڈZŒث“à‚جٹK’iژ؛“™‚ً‰ء‚¦‚éپB
‡Bپ@–h‰خ‹و‰و‚ة—p‚¢‚é–h‰خگف”ُ‚جٹîڈ€‚ة‚آ‚¢‚ؤپi‘و14چ€پj
–h‰خ‹و‰و‚ة—p‚¢‚é–h‰خگف”ُ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAٹmژہ‚ة‰خچذ‚جٹg‘ه‚ً–hژ~پE—}گ§‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ة”ً“ïڈم‚جژxڈل‚ً—ˆ‚³‚ب‚¢‚½‚كپA•K—v‚ئ‚ب‚éگ«”\پi‰خچذژ‚ة•آچ½“™‚إ‚«‚邱‚ئپA’تچs‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邱‚ئپAژ©“®“I‚ة•آچ½“™‚·‚邱‚ئپAژص‰Œگ«‚ً—L‚·‚邱‚ئپj‚ً‹K’肵پA“–ٹYگ«”\‚ً—L‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚½چ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‡Cپ@–h‰خƒ_ƒ“ƒpپ[‚ج‹Zڈp“Iٹîڈ€پi‘و16چ€پj
–h‰خ‹و‰و‚ً—â–[پE’g–[“™‚ج•—“¹‚ھٹر’ت‚·‚éڈêچ‡پA‚»‚جٹر’ت•”•ھ‚ً’ت‚¶‚ؤ‰خچذ‚ھ‹و‰و‚ً’´‚¦‚ؤٹg‘ه‚·‚邱‚ئ‚ً–hژ~پE—}گ§‚·‚邽‚كپA–h‰خ‹و‰و‚ًٹر’ت‚·‚é•”•ھ‚ة‰خ‰ٹ‹y‚ر‰Œ‚ًژص‚éگف”ُ‚إ‚ ‚é–h‰خƒ_ƒ“ƒpپ[‚ًگف‚¯‚邱‚ئ‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚±‚ج–h‰خƒ_ƒ“ƒpپ[‚ة‚آ‚¢‚ؤپA•—“¹‚ةگف‚¯‚é–h‰خگف”ُ‚ئ‚µ‚ؤژو‚舵‚¤‚±‚ئ‚ئ‚µپA•—“¹‚ةگف‚¯‚é–h‰خگف”ُ‚ئ‚µ‚ؤ•K—v‚ئ‚ب‚éگ«”\پiژ©“®“I‚ة•آچ½‚·‚邱‚ئپAژص‰Œگ«‚ً—L‚·‚邱‚ئپj‚ً‹K’肵پA“–ٹYگ«”\‚ً—L‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚½چ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(2)
”ً“ïژ{گف“™ٹضŒW
‡@پ@”ً“ïٹK’i‚جگف’uٹîڈ€پi—ك‘و122ڈًپj
Œ»چs‹K’è‚إ‚حپA‚TٹKˆبڈم‚جٹK–”‚ح’n‰؛‚QٹKˆب‰؛‚جٹK‚ة’ت‚¸‚é’¼’تٹK’i‚ح”ً“ïٹK’i“™‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ً‹K’è‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپA‚TٹKˆبڈم‚جٹK‚جڈ°–تگد‚جچ‡Œv‚ھ100‡uˆب‰؛‚جڈêچ‡‚ة‚حپA‚TٹKˆبڈم‚ج•”•ھ‚©‚ç‚ج”ً“ï‚ح’Zژٹش‚إڈI—¹‚·‚邽‚كپA”ً“ïٹK’i“™‚جگف’u‚ً—v‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB“–ٹY‹K’è‚ھ‚TٹKˆبڈم‚جٹK‚ة’ت‚¸‚é”ً“ïٹK’i‚جگف’u‚ً—v‚µ‚ب‚¢ڈêچ‡‚ج‹K’è‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ً–¾ٹm‰»‚µپA‚ـ‚½پA‚±‚ê‚ة•¹‚¹پA’n‰؛‚QٹKˆب‰؛‚جٹK‚جڈ°–تگد‚جچ‡Œv‚ھ100‡uˆب‰؛‚إ‚ ‚éڈêچ‡‚ة‚حپA’n‰؛‚QٹKˆب‰؛‚جٹK‚ة’ت‚¸‚é”ً“ïٹK’i‚جگف’u‚ً—v‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚ـ‚½پAژه—vچ\‘¢•”‚ً‘د‰خچ\‘¢‚ئ‚µ‚½Œڑ’z•¨‚إ100‡uˆب“à‚²‚ئ‚ة‹و‰و‚µ‚½ڈêچ‡‚ة‚ح”ً“ïٹK’i“™‚جگف’u‚ً—v‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚±‚جڈêچ‡‚ة100‡uˆب“à‚²‚ئ‚ة‹و‰و‚·‚ׂ«•”•ھ‚ة‚حپA‹و‰و‚·‚邱‚ئ‚ھچ¢“ï–”‚ح‹و‰و‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚è”ً“ïڈم•s—ک‚ئ‚ب‚éٹK’iژ؛پAڈ¸چ~‹@‚جڈ¸چ~کHپAکL‰؛“™‚ج”ً“ï‚ج—p‚ة‹ں‚·‚é•”•ھ‚ًٹـ‚ـ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًڈً•¶ڈم–¾ٹm‰»‚·‚éپB
‡Aپ@‹¤“¯ڈZ‘î‚جڈZŒث‚ة‚آ‚¢‚ؤ”ً“ïٹK’i“™‚جگف’u‚ً—v‚µ‚ب‚¢ڈêچ‡‚جٹîڈ€‚جŒ©’¼‚µپi—ك‘و122ڈًپj
11ٹKˆبڈم‚جٹK‚ة‚¨‚¯‚é–h‰خ‹و‰و‚ئ“¯—l‚جژïژ|‚©‚狤“¯ڈZ‘î‚جڈZŒث‚إ200‡uˆب“à‚²‚ئ‚ة‹و‰و‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚ة‚حپA”ً“ïٹK’i“™‚جگف’u‚ً—v‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‡Bپ@”r‰Œگف”ُ‚جگف’uٹîڈ€پi—ك‘و126ڈً‚ج‚Qپj
11ٹKˆبڈم‚ج–h‰خ‹و‰و‚ئ“¯—l‚جژïژ|‚©‚狤“¯ڈZ‘î‚جڈZŒث‚إ200‡uˆب“à‚²‚ئ‚ة‹و‰و‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚ة‚حپA”r‰Œگف”ُ‚جگف’u‚ً—v‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚ـ‚½پA“Vˆن‚جچ‚‚¢‹ڈژ؛‚إ“à‘•‚ھ•s”R‰»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‹ڈژ؛“™‚إ‚حپA‰خچذژ‚ة”گ¶‚·‚鉌“™‚ج”گ¶‚ھڈ‚ب‚پA‚©‚آپA”ً“ïڈمژxڈل‚ج‚ ‚éچ‚‚³‚ـ‚إچ~‰؛‚·‚é‚ج‚ة—v‚·‚éژٹش‚ھ’·‚¢‚±‚ئ‚©‚ç”r‰Œگف”ُ‚ًگف‚¯‚ب‚‚ئ‚à’تڈي‚ح‰خچذژ‚ج”ً“ïˆہ‘Sگ«‚ھ‘¹‚ب‚ي‚ê‚邱‚ئ‚ح‚ب‚¢پB‚±‚ج‚و‚¤‚ب‹ڈژ؛“™پA‰خچذ‚ھ”گ¶‚µ‚½ڈêچ‡‚ة”ً“ïڈمژxڈل‚ج‚ ‚éچ‚‚³‚ـ‚إ‰Œ–”‚حƒKƒX‚جچ~‰؛‚ھگ¶‚¶‚ب‚¢•”•ھ‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚½•”•ھ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA”r‰Œگف”ُ‚جگف’u‚ً—v‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‡Cپ@“ءژê‚بچ\‘¢•û–@‚ج”r‰Œگف”ُ‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€پi—ك‘و126ڈً‚ج‚Rپj
‹ك”NپA”r‰Œگف”ُ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAٹeژي‚ج‹ZڈpٹJ”‚ھگi“W‚µ‚ؤ‚¨‚èپA‘—•—‹@‚ًگف‚¯‚邱‚ئ‚ة‚و‚èپA—LŒّ‚ة‰Œ‚ً”rڈoپEگ§Œن‚·‚é•ûژ®‚ج‚à‚ج“™‚ھژہ—p‰»‚³‚ê‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚¤‚µ‚½گV‚½‚ب‹Zڈp‚ئچ،Œم‚ج‹ZڈpٹJ”‚جگi“W‚ةگv‘¬‚ة‘خ‰‚·‚邽‚كپA“ءژê‚بچ\‘¢‚ج”r‰Œگف”ُ‚إپA‚»‚جچ\‘¢‚ةٹض‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھچ\‘¢•û–@‚ً’è‚ك‚½ڈêچ‡‚ة‚حپAŒ»چs‚ج”r‰Œگف”ُ‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ً“K—p‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‡Dپ@”ٌڈي—p‚جگi“üŒû‚جگف’uٹîڈ€پi—ك‘و126ڈً‚ج‚Uپj
31‚چˆب‰؛‚ج•”•ھ‚ة‚ ‚é‚RٹKˆبڈم‚جٹK‚ة‚حپAŒ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤ”ٌڈي—p‚جه×گi“üŒû‚جگف’u‚ھ•K—v‚إ‚ ‚é‚ھپA•s”Rگ«‚جچق—؟‚ج•غٹا‚ج‚ف‚ة—p‚¢‚ç‚ê‚éٹK–”‚ح“ء•ت‚ب——R‚ة‚و‚è—p“rڈم‚â‚ق‚ً‚¦‚ب‚¢ٹK“™‚إپA’¼ڈمٹK–”‚ح’¼‰؛ٹK‚©‚çگi“üڈo—ˆ‚éڈêچ‡‚ة‚ح”ٌڈي—pگi“üŒû‚جگف’u‚ً—v‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(3)
“à‘•گ§ŒہٹضŒWپi—ك‘و129ڈًپj
ˆê’è‚ج“ءژêŒڑ’z•¨پAˆê’è‹K–حˆبڈم‚جŒڑ’z•¨‚ج•اپA“Vˆن‚جژ؛“à‚ة–ت‚·‚é•”•ھ‚جژdڈم‚°‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAŒڑ’z•¨‚ج•”•ھ‚ة‰‚¶‚ؤˆê—¥‚ةڈ€•s”Rچق—؟–”‚ح“ï”Rچق—؟‚إ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‹ك”N‚جŒ¤‹†‚ة‚و‚èپA—ل‚¦‚خ“Vˆن‚ً•s”Rچق—؟‚إژdڈم‚°پA•ا‚جˆê•”‚ة–طچق“™‚ً—p‚¢‚éژdڈم‚°“™پAŒ»چs‹K’è‚ئˆظ‚ب‚é•û–@‚ة‚و‚ء‚½ڈêچ‡‚إ‚àپA“¯—l‚جŒّ‰ت‚ھٹْ‘ز‚إ‚«‚éڈêچ‡‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚ھ”»–¾‚µ‚ؤ‚¢‚邽‚كپAŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚èŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚é‘gچ‡‚¹‚ة‚و‚é“à‘•‚جژdڈم‚°‚ة‚و‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(4)
ٹبˆص‚بچ\‘¢‚جŒڑ’z•¨ٹضŒWپi—ك‘و136ڈً‚ج9پj
ٹبˆص‚بچ\‘¢‚جŒڑ’z•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAٹJ•ْŒ^Œڑ’z•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤ1,500‡uˆب‰؛پA”؟•z‚ً—p‚¢‚éŒڑ’z•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤ1,000‡uˆب‰؛‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‹ك”NپAژ©‘–ژ®‚جژ©“®ژشژشŒةپA”؟•z‚ً—p‚¢‚éŒڑ’z•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جŒڑ’zژہگر‚ھ‘‰ء‚µ‚ؤ‚«‚½‚±‚ئپA‚±‚ê‚ç‚ة‚آ‚¢‚ؤ–@‘و38ڈً‚ج‹K’è‚ج‰^—p‚ة‚و‚è‹Zڈp“I’mŒ©‚ھ’~گد‚³‚ê‚ؤ‚«‚½“™‚ً“¥‚ـ‚¦‚ؤٹبˆص‚بچ\‘¢‚جŒڑ’z•¨‚ج‘خڈغ”حˆح‚ً3,000‡uˆب‰؛‚ج‚à‚ج‚ئ‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@
‚PپDŒہٹE‘د—حŒvژZ‚ج“±“üپi‘و‚W‚Qڈً‚ج‚Uپj
ژd—l‚ً‘O’ٌ‚ئ‚¹‚¸پA‰×ڈd‹y‚رٹO—ح‚ھŒڑ’z•¨‚ةچى—p‚µ‚ؤ‚¢‚éچغ‚جŒڑ’z•¨‚ةگ¶‚¸‚é—ح‹y‚ر•دŒ`‚ً’¼گعژZڈo‚·‚é•û–@پiŒہٹE‘د—حŒvژZپj‚ً“±“ü‚µپAŒ»چs‚جچ\‘¢ŒvژZ‹K’è‚ئ‚ج‘I‘ًگ§‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
ڈ]—ˆ‚جچ\‘¢ŒvژZ‚حپA•دŒ`‚ًگ³ٹm‚ة”cˆ¬‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½‚½‚كژd—l‹K’è‚ة“Kچ‡‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ً‘O’ٌ‚ئ‚µ‚ؤپA•K—v‚ب‘د—ح‚ًŒvژZ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
ŒہٹE‘د—حŒvژZ‚حپA‹ة‚ك‚ؤ‘ه‹K–ح‚بگدگل‹y‚ر–\•—‚ة‘خ‚·‚éˆہ‘Sگ«‚ً’¼گعŒںڈط‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپA’nگkژ‚ة‚¨‚¯‚éŒڑ’z•¨‚ج•دŒ`‚ًŒvژZ‚µپA‚»‚ê‚ةٹî‚أ‚¢‚ؤ•K—v‚ب‘د—ح‚ًŒvژZ‚µ‚ؤ‹پ‚كپAˆہ‘Sگ«‚ًٹm”F‚·‚éژè–@‚إ‚ ‚éپB‚»‚ج‚½‚كپAŒہٹE‘د—حŒvژZ‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAڈ]—ˆ‚جچ\‘¢ŒvژZ‚ئˆظ‚ب‚èپA‘د‹vگ«“™‚ةٹض‚·‚é‹K’èˆبٹO‚جژd—l‹K’è‚ج“K—p‚ً•s—v‚ئ‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@گk“x‚V‚ة‘ٹ“–‚·‚é’nگk‚ة‘خ‚·‚éŒںڈط‚ً”نٹr‚·‚é‚ئژں‚ج‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB
|
|
ŒہٹE‘د—حŒvژZ
|
•غ—Lگ…•½‘د—ح–@پiŒ»چsپj
|
|
Œڑ’z•¨‚ج•دŒ`‚إ‚«‚éŒہٹE
|
ژZ’è‚·‚éپB
|
ژZ’肵‚ب‚¢پB
|
|
ٹeٹK‚ةگ¶‚¸‚é—ح
|
Œڑ’z•¨‚جژہ‘شپi•sگ®Œ`پE•s‹دژ؟پj‹y‚ر•دŒ`‚إ‚«‚éŒہٹE‚ًچl—¶‚µ‚ؤگ¸ژZ
|
Œڑ’z•¨‚ھگ®Œ`‚©‚آ‹دژ؟پ@‚إ‚ ‚é‚ئ‰¼’肵‚ؤŒvژZ
|
|
ٹeٹK‚ة•K—v‚ئ‚³‚ê‚é‘د—ح
|
ٹeٹK‚ةگ¶‚¸‚é—حˆبڈم‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًٹm”F
|
ٹeٹK‚ةگ¶‚¸‚é—ح‚ًŒڑ’z•¨‚ج•sگ®Œ`پA•s‹دژ؟“™‚ًچl—¶‚µ‚ؤ•âگ³‚µ‚½ڈم‚إپA‚»‚ج—حˆبڈم‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًٹm”F
|
پ@پپ@ŒہٹE‘د—حŒvژZ‚جٹT—v
‡@Œڑ’z•¨‚ج‘¶چفٹْٹش’†‚ة‚P‰ٌˆبڈم‘ک‹ِ‚·‚é‰آ”\گ«‚جچ‚‚¢گدگلپA–\•—“™‚ة‚آ‚¢‚ؤپAŒڑ’z•¨‚ھ‘¹ڈ‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚邱‚ئپBپi‹ï‘ج“I‚ة‚حپAŒڑ’z•¨‚ج•”چق‚ةگ¶‚¸‚鉗ح“x‚ھ‹–—e‰—ح“x‚ً’´‚¦‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm”FپBڈ]—ˆ‚ئ“¯—l‚جŒvژZژè–@پj
‡Aگدگلژ‹y‚ر–\•—ژ‚ةŒW‚éŒںڈط‚ة‚آ‚¢‚ؤپAڈ]—ˆ‚حچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‹ة‚ك‚ؤ‹H‚ة”گ¶‚·‚é‘ه‹K–ح‚بگدگل‹y‚ر–\•—‚ة‘خ‚µ‚ؤŒڑ’z•¨‚ھ“|‰َپA•ِ‰َ“™‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚邱‚ئپBپi‹ï‘ج“I‚ة‚حپAŒڑ’z•¨‚ةگ¶‚¸‚é—ح‚ئپAچق—؟‹“x‚©‚çژZڈo‚µ‚½•”چق‚ج‘د—ح‚ئ‚ً”نٹr‚·‚éپBگV‚µ‚¢ŒvژZژè–@پj
‡BŒڑ’z•¨‚ج‘¶چفٹْٹش’†‚ة‚P‰ٌˆبڈم‘ک‹ِ‚·‚é‰آ”\گ«‚جچ‚‚¢’nگk‚ة‚آ‚¢‚ؤپAŒڑ’z•¨‚ج’nڈم•”•ھ‚ھ‘¹ڈ‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚邱‚ئپBپiگV‚µ‚¢ŒvژZژè–@پj
|
ƒn‚إ‹پ‚ك‚½’nگk—ح‚ھپAٹe‘w‚ھ‘¹ڈ‚·‚éŒہٹE‚ج‘د—ح‚ً’´‚¦‚ب‚¢‚±‚ئ‹y‚رƒj‚إ‹پ‚ك‚½‘wٹش•دˆت‚ھ‚Pپ^‚Q‚O‚O‚ً’´‚¦‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚éپB
|
ƒCپ@Œڑ’z•¨‚جٹeٹK‚ھ‘¹ڈ‚·‚éŒہٹE‚ج‘wٹش•دˆتپi‘¹ڈŒہٹE•دˆتپj‚ًŒvژZ‚·‚éپB
ƒچپ@‘¹ڈŒہٹE•دˆت‚ة‘خ‰‚·‚éŒڑ’z•¨‚جŒإ—Lژüٹْپi‘¹ڈŒہٹEŒإ—Lژüٹْپj‚ًŒvژZ‚·‚éپB
ƒnپ@ٹeٹK‚ةچى—p‚·‚é’nگk—ح‚ً‘¹ڈŒہٹEŒإ—Lژüٹْ‚ة‘خ‰‚·‚é‰ء‘¬“xپi’n”ص‚ج‘•پA’nˆوŒWگ”‚ًچl—¶‚µ‚½‚à‚جپjپAٹeٹK‚جژ؟—تپAٹeٹK‚ج‰ء‘¬“x•ھ•z‚©‚ç‹پ‚ك‚éپB
ƒjپ@ƒn‚ج‰ء‘¬“x‚ھچى—p‚µ‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚جٹeٹK‚ج‘wٹش•دˆت‚ًŒvژZ‚·‚éپB
‡CŒڑ’z•¨‚ج‘¶چفٹْٹش’†‚ة‚P‰ٌˆبڈم‘ک‹ِ‚·‚é‰آ”\گ«‚جچ‚‚¢’nگk‚ة‚آ‚¢‚ؤپAŒڑ’z•¨‚ج’n‰؛•”•ھ‚ھ‘¹ڈ‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚邱‚ئپBپi‹ï‘ج“I‚ة‚حپAŒڑ’z•¨‚ج’n‰؛•”•ھ‚ج•”چق‚ةگ¶‚¸‚鉗ح“x‚ھ‹–—e‰—ح“x‚ً’´‚¦‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm”FپBڈ]—ˆ‚ئ“¯—l‚جŒvژZژè–@پj
‡D‹ة‚ك‚ؤ‹H‚ة”گ¶‚·‚é’nگk‚ة‚آ‚¢‚ؤپAŒڑ’z•¨‚ج’nڈم•”•ھ‚ھ“|‰َپA•ِ‰َ“™‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚邱‚ئپBپiگV‚µ‚¢ŒvژZژè–@پj
|
پ@ƒn‚إ‹پ‚ك‚½’nگk—ح‚ھپAٹe‘w‚ھ•ِ‰َ‚·‚éŒہٹE‚ج‘د—ح‚ً’´‚¦‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚éپB
|
ƒCپ@Œڑ’z•¨‚جٹeٹK‚ھ•ِ‰َ‚·‚éŒہٹE‚ج‘wٹش•دˆتپiˆہ‘SŒہٹE•دˆتپj‚ًŒvژZ‚·‚éپB
ƒچپ@ˆہ‘SŒہٹE•دˆت‚ة‘خ‰‚·‚éŒڑ’z•¨‚جŒإ—Lژüٹْپiˆہ‘SŒہٹEŒإ—Lژüٹْپj‚ًŒvژZ‚·‚éپB
ƒnپ@ٹeٹK‚ةچى—p‚·‚é’nگk—ح‚ًˆہ‘SŒہٹEŒإ—Lژüٹْ‚ة‘خ‰‚·‚é‰ء‘¬“xپi’n”ص‚ج‘•پA’nˆوŒWگ”‚ًچl—¶‚µ‚½‚à‚جپjپAٹeٹK‚جژ؟—تپAٹeٹK‚ج‰ء‘¬“x•ھ•zپAŒڑ’z•¨‚جŒ¸گٹگ«‚©‚ç‹پ‚ك‚éپB
‡Eژg—pڈم‚جژxڈل‚ئ‚ب‚é•دŒ`–”‚حگU“®‚ھ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚邱‚ئپB
پ@
پiڈ°‹y‚ر‚ح‚è‚ة‚آ‚¢‚ؤ•دŒ`—ت‚ًŒvژZپBڈ]—ˆ‚ئ“¯—l‚جŒvژZژè–@پj
‡F ٹO‘•چق“™‚ھچ\‘¢‘د—حڈمˆہ‘S‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚邱‚ئپB
پ@پ@پi‡B‚جŒvژZ‰ك’ِ‚إژZڈo‚·‚éŒڑ’z•¨‚جٹeٹK‚ج‘wٹش•دˆتپAٹeٹK‚ةگ¶‚¸‚é‰ء‘¬“x‚ة‚و‚èٹO‘•چق‚ةگ¶‚¸‚鉗ح“x‚ھ‹–—e‰—ح“x‚ً’´‚¦‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm”FپBگV‚µ‚¢ŒvژZژè–@پj
ŒہٹE‘د—حŒvژZ‚حپA’nگkژ‚جŒںڈط‚ة‚¨‚¢‚ؤŒڑ’z•¨‚جٹeٹK‚ھ“¯ˆê•ûŒü‚ة•دŒ`‚µ‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚ة“K—p‚³‚ê‚éپBŒڑ’z•¨‚جچ‚‚³‚ھ‚U‚Oƒپپ[ƒgƒ‹’ِ“x‚ـ‚إ‚حپAŒڑ’z•¨‚جٹeٹK‚ح“¯ˆê•ûŒü‚ة•دŒ`‚·‚é‚ھپAچ‚‚³‚ھ‚U‚Oƒپپ[ƒgƒ‹‚ً’´‚¦‚é‚ئپAٹeٹK‚ج•دŒ`•ûŒü‚ھ“¯ˆê•ûŒü‚إ‚ب‚‚ب‚錻ڈغ‚ھŒ»‚ê‚ح‚¶‚كپA‚±‚جŒ»ڈغ‚حŒڑ’z•¨‚ھچ‚‚‚ب‚ê‚خ‚ب‚é‚ظ‚اŒ°’ک‚ة‚ب‚éپB‚»‚ج‚½‚كپAچ‚‚³‚ھ‚U‚Oƒپپ[ƒgƒ‹‚ً’´‚¦‚éŒڑ’z•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAŒہٹE‘د—حŒvژZ‚إ‚حگ¸“x‚و‚Œڑ’z•¨‚ةگ¶‚¸‚é—ح‹y‚ر•دˆت‚ًژZڈo‚·‚邱‚ئ‚ھچ¢“ï‚ئ‚ب‚éپB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپAچ‚‚³‚ھ‚U‚Oƒپپ[ƒgƒ‹‚ً’´‚¦‚éŒڑ’z•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAŒڑ’z•¨‚جٹeٹK‚ج•دŒ`‚ھ“¯ˆê•ûŒü‚إ‚ب‚¢ڈêچ‡‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àپA’nگkژ“™‚ةŒڑ’z•¨‚ةگ¶‚¸‚é—ح‚ئ•دŒ`‚ًکA‘±“I‚ةŒvژZ‚·‚邱‚ئ‚ج‚إ‚«‚éچ‚“x‚بچ\‘¢ŒvژZ‚ة‚و‚èˆہ‘Sگ«‚ًٹm‚©‚ك‚邱‚ئ‚ً‹`–±•t‚¯‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚U‚Oƒپپ[ƒgƒ‹‚ً’´‚¦‚éŒڑ’z•¨‚ة“K—p‚إ‚«‚éچ\‘¢ŒvژZ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‰ك‹ژ‚ج–@‘و‚R‚Wڈً‚ج‰^—p‚جژہگر‚©‚çپA‘S‚ؤ‚جŒڑ’z•¨‚جˆہ‘Sگ«‚ً•]‰؟‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚ئ”»’f‚إ‚«‚éژè–@‚ھٹm—§‚µ‚ؤ‚«‚½‚±‚ئ‚©‚çپA“–ٹYژè–@‚ًŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚µ‚©‚µ‚ب‚ھ‚çپA“–ٹYژè–@‚ًŒآپX‚جŒڑ’z•¨‚ة“K—p‚·‚é‚ة“–‚½‚ء‚ؤ‚حپAŒڑ’z•¨‚ج’ŒپA—ہ“™‚جŒ`ڈَپAچقژ؟“™‚©‚çŒڑ’z•¨ٹe•”‚ج•دŒ`‚ج‚µ‚ة‚‚³‚ًچl—¶‚µ‚ؤپA‘S‘ج‚جگU“®ƒ‚ƒfƒ‹‚ًچىگ¬‚µ‚ؤپAژٹش‚جŒo‰ك‚ةڈ]‚ء‚ؤŒڑ’z•¨‚ة‚ا‚ج‚و‚¤‚ة—ح‹y‚ر•دŒ`‚ھگ¶‚¶‚ؤ‚¢‚‚©‚ً‰ًگح‚µ‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ئ‚ب‚é‚ھپA“–ٹY‰ًگح‚ھ“Kگط‚ةچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚©‚ً”»’f‚·‚邽‚ك‚ة‚حچ‚“x‚ب‹Zڈp“I’mŒ©‚ھ•K—v‚إ‚ ‚èپAŒڑ’zژهژ–“™‚ة‚و‚éŒڑ’zٹm”F‚إ‚ح‘خڈˆ‚ھچ¢“ï‚إ‚ ‚邱‚ئ‚©‚çپAŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ج‘خڈغ‚ئ‚ب‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚QپDگ«”\‹K’艻‚ة”؛‚¤ژd—l‹K’è‚ج“K—pٹضŒW‚جگ®—پi‘و‚R‚Uڈًپj
–@‘و‚Q‚Oڈً‘و‚Pچ†‚ج‹K’è‚ة‚و‚èپAŒڑ’z•¨‚جˆہ‘Sڈم•K—v‚بچ\‘¢•û–@‚ةٹض‚µ‚ؤگ—ك‚إ‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ً’è‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‘و‚Pگك‚©‚ç‘و‚Vگك‚ج‚Q‚ـ‚إ‚ة’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ج‚ف‚إ‚حپA‘S‚ؤ‚جŒڑ’z•¨‚جˆہ‘Sگ«‚ً’S•غ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚ح‚¢‚¦‚ب‚¢‚±‚ئ‚©‚çپAˆê’è‹K–حˆبڈم‚جŒڑ’z•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘و‚Pگك‚©‚ç‘و‚Vگك‚ج‚Q‚ـ‚إ‚ة’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ة“Kچ‡‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ة‰ء‚¦پAچ\‘¢ŒvژZ‚ة‚و‚èˆہ‘Sگ«‚ھٹm‚©‚ك‚ç‚ꂽچ\‘¢•û–@‚ئ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢ژ|‚ً–¾ٹm‚ة‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚RپDژd—l‹K’è‚ج–¾ٹm‰»“™‚جŒ©’¼‚µ
(1)Œڑ’z•¨‚جٹî‘b‚جژd—l‹K’è‚جگ®”ُپi‘و‚R‚Wڈًپj
Œڑ’z•¨‚جٹî‘b‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‚±‚ê‚ـ‚إ‹ï‘ج“I‚بچ\‘¢Œ`ژ®“™‚جژd—lٹîڈ€‚ھ’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB‚±‚ج‚½‚كپAژd—l‹K’è‚ج–¾ٹm‰»‚جٹد“_‚©‚çپAٹî‘b‚جچ\‘¢‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚éچ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپBŒڑگف‘هگb‚ج’è‚ك‚éچ\‘¢•û–@‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAٹî‘b‚جگ،–@پAŒ`ڈَپA“S‹ط‚ج”z’u‚ج•û–@“™‚ً’è‚ك‚éپB
(2)پ@–ط‘¢Œڑ’z•¨‚ج‘دگk•ا‚ج”z’u‹K’è‚جگ®”ُپi‘و‚S‚Uڈًپj
–ط‘¢‚جŒڑ’z•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAˆê’è—ت‚ج‘دگk•ا‚ً’قچ‡‚¢‚و‚”z’u‚·‚éژ|’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‹ï‘ج“I‚بŒvژZ•û–@“™‚ج•]‰؟ٹîڈ€‚ھ’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB‚±‚ج‚½‚كپAٹîڈ€‚ج–¾ٹm‰»‚ًگ}‚éٹد“_‚©‚çپA–ط‘¢Œڑ’z•¨‚ج‘دگk•ا‚ج”z’u‚ج•û–@‚ةٹض‚·‚éŒڑگف‘هگb‚ج’è‚ك‚éٹîڈ€‚ة‚و‚ç‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپBŒڑگف‘هگb‚ج’è‚ك‚éٹîڈ€‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAŒڑ’z•¨‚ج•”•ھ–ˆ‚ج‘دگk•ا—ت‚جٹ„چ‡“™‚ً’è‚ك‚éپB
(3)پ@–ط‘¢Œڑ’z•¨‚جŒpژèپAژdŒû“™‚ةŒW‚éژd—l‹K’è‚ج–¾ٹm‰»پi‘و‚S‚Vڈًپj
–ط‘¢Œڑ’z•¨‚ج’ŒپA‚ح‚èپA‹ط‚©‚¢‚جŒpژèپAژdŒû“™‚جگعچ‡•”‚ح‚»‚ج•”•ھ‚ج‘¶چف‰—ح‚ً“`‚¦‚é‚و‚¤‚ة‹ظŒ‹‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢ژ|’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپAژg—p‚·‚é‹à•¨‚âچ\‘¢Œ`ژ®“™‚جڈعچׂة‚آ‚¢‚ؤ–¾ٹm‚ة‹K’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB‚±‚ج‚½‚كپAژd—l‹K’è‚ج–¾ٹm‰»‚جٹد“_‚©‚çپAچ\‘¢‘د—حڈمژه—v‚بژ²‘g“™‚ة‚¨‚¯‚éŒpژèپAژdŒû“™‚جگعچ‡•”‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚éچ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپBŒڑگف‘هگb‚ج’è‚ك‚éچ\‘¢•û–@‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAŒpژèپAژdŒû“™‚جŒ`ڈَپAگعچ‡•”چق‚جژي—ق“™‚ً’è‚ك‚éپB
(4)پ@“Sچœ‘¢‚ج’Œ‹r‚جژd—l‹K’è‚ج–¾ٹm‰»پi‘و‚U‚Uڈًپj
“Sچœ‘¢‚ج’Œ‹r‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAٹî‘b‚ةƒAƒ“ƒJپ[ƒ{ƒ‹ƒg‚إ‹ظŒ‹‚·‚é“™‚جچ\‘¢•û–@‚ة‚و‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‹ï‘ج“I‚بژd—l‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚±‚ئ‚©‚çپA‚»‚جچ\‘¢•û–@“™‚جژd—l‹K’è‚ج–¾ٹm‰»‚ج•K—v‚ھ‚ ‚éپB
‚±‚ج‚½‚كپA“Sچœ‘¢‚ج’Œ‹r‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚éچ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپBŒڑگف‘هگb‚ج’è‚ك‚éچ\‘¢•û–@‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA’Œ‹r‚جژي—قپAگ،–@پAŒ`ڈَ“™‚ً’è‚ك‚éپB
(5)پ@“Sچœ‘¢‚ج—nگع‚ةŒW‚é‹K’è‚جگ®”ُپi‘و‚U‚Vڈًپj
ڈ]—ˆپA“Sچœ“™چ|چق“¯ژm‚ج—nگعگعچ‡•”‚ة‚آ‚¢‚ؤڈعچׂب‹Zڈpٹîڈ€‚ھ’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB‚±‚ج‚½‚كپA“Sچœ‘¢‚ج—nگع‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚éچ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپBŒڑگف‘هگb‚ج’è‚ك‚éچ\‘¢•û–@‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA—LٹQ‚ب—nگعŒ‡ٹׂھ‚ب‚¢‚±‚ئپA—nگع•”‚جگ،–@پAŒ`ڈَ“™‚ً’è‚ك‚éپB
(6)پ@“S‹طƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒgŒڑ’z•¨‚جژه‹ط“™‚جŒpژè‚ةŒW‚é‹K’è‚ج–¾ٹm‰»پi‘و‚V‚Rڈًپj
“S‹طƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒgŒڑ’z•¨‚جژه‹ط“™‚ج“S‹ط‚ًگع‘±‚·‚éڈêچ‡پAŒ»چs‹K’è‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAڈd‚ثŒpژè‚ةŒW‚é‹K’è‚ج‚ف‚ھگ®”ُ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپAŒڑگفچHژ–‚جŒ»ڈَ‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAڈd‚ثŒpژè‚ً—p‚¢‚éژ–—ل‚حڈگ”‚إ‚ ‚èپA‘ه”¼‚حˆ³گعپi“S‹ط‚ج’[•”‚ئ’[•”‚ئ‚ً”M‚ئˆ³—ح‚ً‰ء‚¦‚ؤگع‘±‚·‚éچ\–@پj“™‚جچ\–@‚ة‚و‚èگع‘±‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ج‚½‚كپAڈd‚ثŒpژèˆبٹO‚ج“S‹ط‚جŒpژè‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚éچ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚éپBŒڑگف‘هگb‚ج’è‚ك‚éچ\‘¢•û–@‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAŒpژè‚جژي—قپAگ،–@پAŒ`ڈَ“™‚ً’è‚ك‚éپB
(7)ژd—l‹K’è‚ً“K—pڈœٹO‚ئ‚إ‚«‚éچ\‘¢ŒvژZ‚ج–¾ٹm‰»
پ@پi‘و‚S‚RڈًپA‘و‚S‚WڈًپA‘و‚U‚Qڈً‚ج‚WپA‘و‚U‚XڈًپA‘و‚V‚RڈًپA‘و‚V‚VڈًپA
پ@پ@‘و‚V‚Vڈً‚ج‚QپA‘و‚V‚WڈًپA‘و‚V‚Wڈً‚ج‚Qپj
ژd—l‹K’è‚ً“K—pڈœٹO‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éچ\‘¢ŒvژZ‚ج‹K’è‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAڈ]—ˆ‚و‚èˆت’u•t‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚±‚ë‚إ‚ ‚é‚ھپAŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚邱‚ئ“™‚ة‚و‚è‹K’è‚ج–¾ٹm‰»‚ًگ}‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(1)
ƒXƒeƒ“ƒŒƒXچ|‚ةŒW‚é‹K’è‚جگ®”ُپi‘و‚U‚SڈًپA‘و‚X‚OڈًپA‘و‚X‚Uڈًپj
ƒXƒeƒ“ƒŒƒXچ|‚حپA’Y‘fچ|‚ة”ن‚בد‹vگ«پA‘د‰خگ«“™‚ة—D‚ê‚ؤ‚¢‚éچ|چق‚إ‚ ‚é‚ھپAˆê”ت“I‚ب‹Zڈp‚ئ‚µ‚ؤ•پ‹yپE’è’…‚µ‚ؤ‚«‚½‚½‚كپAƒXƒeƒ“ƒŒƒXچ|‚ً“Sچœ‘¢‚ج‹K’è‚ةˆت’u•t‚¯‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‹ï‘ج“I‹Zڈpٹîڈ€‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAƒٹƒxƒbƒgگعچ‡‚ً‹ضژ~‚·‚éˆبٹO‚حپA’تڈي‚ج’Y‘fچ|‚ئ“¯—l‚ج‹K’è‚ً“K—p‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(2)
چ‚‚³‚P‚R‚چ–”‚حŒ¬چ‚‚X‚چ‚ً’´‚¦‚é‘gگد‘¢‚ج•â‹‚ةŒW‚é‹K’è‚جگ®”ُ
پ@پ@پi‘و‚T‚Qڈً‚ج‚Xپj
چ‚‚³‚P‚R‚چ–”‚حŒ¬چ‚‚X‚چ‚ً’´‚¦‚é‘gگد‘¢‚جŒڑگف‚ًŒ´‘¥‹ضژ~‚µ‚ؤ‚¢‚½–@‘و‚Q‚Pڈً‘و‚Rچ€‚ھچيڈœ‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ة”؛‚¢پAچ‚‚³‚P‚R‚چ–”‚حŒ¬چ‚‚X‚چ‚ً’´‚¦‚é‘gگد‘¢‚ةŒW‚é•â‹•û–@‚جٹîڈ€‚جگ®”ُ‚ًچs‚¤پB
پiژذپj“ْ–{Œڑ’zٹw‰ï‚ة‚¨‚¯‚錤‹†گ¬‰ت“™چإگV‚ج’mŒ©‚ةٹî‚أ‚«Œ©’¼‚µ‚ًچs‚¤پB
(1)
گدگل‰×ڈd
گدگل‰×ڈd‚جژZ’è‚ة—p‚¢‚éگدگلگ[‚جگف’è‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAٹe’n•û‚ة‚¨‚¢‚ؤ‰^—p‚ة•s“ˆê‚ھ‚ف‚ç‚ê‚é‚ئ‚جژw“E‚ھ‚ ‚éپB‰^—p‚جگ®چ‡‰»‚ًگ}‚邽‚كپAŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚éگدگلگ[‚جژZ’è•û–@‚جٹîڈ€‚ةٹî‚أ‚«“ء’èچsگ’،‚ھگدگلگ[‚ًگف’è‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚ـ‚½پA‰®چھ‚جŒù”z‚ة‚و‚éگدگلگ[‚ج’لŒ¸•û–@‚ًپAچ‘چغ‹KٹiپiISO4355پj‚ةگ®چ‡‰»‚·‚éپB
(2)
•—ˆ³—ح
Œ»چف‘Sچ‘ˆê—¥‚ة’è‚ك‚ؤ‚¢‚鑬“xˆ³‚ًپAٹe’n•û‚ة‚¨‚¯‚é•—‘¬‹y‚رŒڑ’z•¨‚جژü•سژsٹX’n‚جڈَ‹µ‚ًچl—¶‚µ‚ؤژZ’è‚·‚é•û–@‚ة‰ü‚ك‚éپB
‹ï‘ج“I‚ة‚حپAژں‚جژ®‚ة‚و‚èژZڈo‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚‘پپ0.6
‚d ‚uo‚Qپ@پ@پ@
‚‘پF‘¬“xˆ³پi‚m/‚چ‚Qپj
‚dپFژsٹX’n‚جڈَ‹µ‹y‚رŒڑ’z•¨‚جچ‚‚³‚ة‚و‚éŒWگ”پiژZڈo•û–@‚حپAŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚éپBپj
‚uoپFٹe’nˆو‚ج’nڈم‚P‚O‚چ‚ج•½‹د•—‘¬پi‚چ/‚“پjپi‚R‚Oپ`‚S‚U‚چ/‚“‚ج”حˆح‚إŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚éپBپj
‚ـ‚½پA•——حŒWگ”‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAچإگV‚ج’mŒ©‚ةٹî‚أ‚«Œ©’¼‚µ‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ئ‚·‚é‚ھپAŒWگ”‚جگف’è‚ھڈعچ׉»‚·‚邱‚ئ‹y‚رچ،Œم‚جژہŒ±پEŒ¤‹†‚ةٹî‚أ‚«ڈ‡ژں‹K’è‚ج’ا‰ء‚ًچs‚¤•K—v‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚©‚çپAŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(1)–طچق‚ج‹–—e‰—ح“x‹y‚رچق—؟‹“x‚جŒ©’¼‚µ
چإگV‚ج’²چ¸پEŒ¤‹†‚جŒ‹‰تپA‰×ڈd‚جŒp‘±ژٹش‚ئ–طچق‚ج‹“x‚ئ‚جٹضŒW‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚©‚çپA–طچق‚ج‹–—e‰—ح“x‹y‚رچق—؟‹“x‚جگف’è•ûژ®‚ً‰ü‚ك‚éپBŒ»چفپAژ÷ژي–ˆ‚ة‹ï‘ج‚جگ”’l‚إ‹K’肵‚ؤ‚¢‚é•ûژ®‚ًپAچ|چق“™‚ئ“¯—l‚ةپAٹîڈ€‹“x‚ئ‚جٹضŒW‚إ‹K’è‚·‚é•ûژ®‚ة‰ü‚كپAژ÷ژي–ˆ‚جٹîڈ€‹“x‚حŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(2)ƒXƒeƒ“ƒŒƒXچ|‚ج‹–—e‰—ح“x‹y‚رچق—؟‹“x‚ةŒW‚é‹K’è‚جگ®”ُ
ƒXƒeƒ“ƒŒƒXچ|‚ً“Sچœ‘¢‚ةژg—p‚إ‚«‚éچ|چق‚ئ‚µ‚ؤˆت’u•t‚¯‚邱‚ئ‚ة”؛‚¢پAچ\‘¢ŒvژZ‚ة—p‚¢‚é‹–—e‰—ح“x‹y‚رچق—؟‹“x‚ةŒW‚é‹K’è‚ًگ®”ُ‚·‚éپB
(3)ƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‚ج‹–—e‰—ح“x‹y‚رچق—؟‹“x‚ج“ء—ل‹K’è‚جگ®”ُ
ƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‚ج‹–—e‰—ح“x‹y‚رچق—؟‹“x‚ة‚آ‚¢‚ؤپAˆظŒ`“S‹ط‚ً—p‚¢‚éڈêچ‡‹y‚رچ‚‹“xƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‚ً—p‚¢‚éڈêچ‡‚ج“ء—ل‚ة‚آ‚¢‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(4)
Œv—ت–@‚ج‰üگ³‚ة”؛‚¤‚r‚h’Pˆت‰»پiگف”ُ‚ة‚¨‚¢‚ؤ“¯‚¶پBپj
Œv—ت–@‚ج‹K’è‚ئ‚جگ®چ‡‚ًگ}‚邽‚كپAڈd—تƒLƒچƒOƒ‰ƒ€“™‚ج’Pˆت‚ً—p‚¢‚ؤ’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‹K’è‚ًپAƒjƒ…پ[ƒgƒ““™‚جچ‘چغ’PˆتŒn‚ً—p‚¢‚½‹K’è‚ة‰ü‚ك‚éپB
(1)
چجŒُ‹K’è‚ج“K—p‚ًژَ‚¯‚é‹ڈژ؛‚جŒہ’è
–@‘و‚Q‚Wڈً‚ة‚¨‚¢‚ؤپAڈZ‘î“™‚ج‹ڈژ؛‚ة‚حˆê’è‚جٹJŒû•”‚ًگف‚¯پAچجŒُ‚ًٹm•غ‚·‚邱‚ئ‚ھ‹`–±‚أ‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپBچ،‰ٌ‚ج–@‰üگ³‚ة‚¨‚¢‚ؤ–@‘و‚Q‚Wڈً‘و‚Pچ€‚ھ‰üگ³‚³‚êپA‹ڈڈZ‚ج‚½‚ك‚ج‹ڈژ؛پAٹwچZ‚ج‹³ژ؛پA•a‰@‚ج•aژ؛‹y‚ر‚»‚ج‘¼چجŒُ‹K’è‚ج“K—p‚ًژَ‚¯‚é‹ڈژ؛‚ًگ—ك‚إ’è‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ًژَ‚¯پA—ك‘و‚P‚Xڈً‚ة‚¨‚¢‚ؤچجŒُ‹K’è‚ج“K—p‚ًژَ‚¯‚é‹ڈژ؛‚ً’è‚ك‚éپB
پ›چجŒُ‹K’è‚ج“K—p‚ًژَ‚¯‚é‹ڈژ؛پi—ك‘و‚P‚Xڈًپj
–@—¥‚إ’è‚ك‚½‹ڈڈZ‚ج‚½‚ك‚ج‹ڈژ؛پAٹwچZ‚ج‹³ژ؛پA•a‰@‚ج•aژ؛ˆبٹO‚جچجŒُ‹K’è‚ج“K—p‚ًژَ‚¯‚é‹ڈژ؛‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAژ™“¶پAچ‚—îژز“™‰qگ¶ڈم‚ج”z—¶‚ً•K—v‚ئ‚·‚éژز‚ھ’·ژٹشŒp‘±“I‚ة‚¢‚é‹ڈژ؛‚إ‚ ‚é•غˆçڈٹ‚ج•غˆçژ؛پAگf—أڈٹ‚ج•aژ؛پAژ™“¶•ںژƒژ{گف“™‚جگQژ؛پA•غˆçپEŒP—û“™‚ة‹ں‚·‚é‹ڈژ؛‹y‚ر•a‰@پAگf—أڈٹ“™‚ج’kکbژ؛“™‚ج‹ڈژ؛‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(2)
—LŒّ–تگد‚جژZ’è•û–@‚جچ‡—‰»
چجŒُ‚ة—LŒّ‚ب–تگد‚جژZ’è‚ًچs‚¤‚½‚كپAŒ»چs‹K’è‚إ‚ح—×’n‹«ٹEگü‚ـ‚إ‚ج‹——£‚ة‰‚¶ˆê’è‚جچ‚‚³‚ً‹«‚ةˆê—¥‚ة‚»‚ê‚و‚èڈم‚ًچجŒُڈم—LŒّ‚ئ‚µپA‚»‚ê‚و‚è‰؛‚ً—LŒّ‚إ‚ح‚ب‚¢‚ئ‚·‚é•û–@‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
‚µ‚©‚µپAژہچغ‚ة‘‹‚ة“üژث‚·‚éŒُ‚ج—ت‚حپAکA‘±“I‚ة•د‰»‚µ‰؛‚ةچs‚‚ظ‚اژں‘و‚ةڈ‚ب‚‚ب‚邱‚ئ‚©‚çپA‰؛‚ج•û‚ج‘‹‚à‚»‚ج–تگد‚ً‘ه‚«‚‚·‚邱‚ئ‚إ“¯ˆê‚جŒُ‚ج—ت‚ً‹ڈژ؛“à‚ةژو‚è“ü‚ê‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB
‚±‚ج‚½‚كپAŒ»چs‚ج‹K’è‚إچجŒُڈم—LŒّ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈêڈٹ‚ج–¾‚邳‚ًٹîڈ€‚ئ‚µ‚ؤپA‚ا‚ج’ِ“x–¾‚é‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚ًپA—×’n‹«ٹEگü‚ـ‚إ‚ج‹——£‚ئŒڑ’z•¨‚جچ‚‚³‚ة‰‚¶‚ؤژZ’è‚·‚éچجŒُ•âگ³ŒWگ”‚ً’è‹`‚µپA‚±‚ê‚ً‘‹‚ج–تگد‚ةڈو‚¶‚ؤپAچجŒُڈم—LŒّ‚ب‘‹‚ج–تگد‚ً‹پ‚ك‚é•ûژ®‚ئ‚·‚éپB
‚±‚ê‚ة‚و‚ء‚ؤپAڈ]—ˆچجŒُڈم—LŒّ‚إ‚ب‚¢‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½•”•ھ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àپA‘‹‚ً‘ه‚«‚‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤژ؛“à‚ة“üژث‚·‚éŒُ‚ج—ت‚ً“¯‚¶‚ئ‚·‚ê‚خ‹ڈژ؛‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚éپB
‚ب‚¨پA‚±‚ج—×’n‹«ٹEگü‚ئŒڑ’z•¨‚ج‹——£‚ھ—£‚ê‚ؤ‚‚é‚ئپA’n”ص–ت‚©‚甽ژث‚µ‚ؤ“ü‚ء‚ؤ‚‚éŒُ‚ج‰e‹؟‚ھ‘ه‚«‚‚ب‚èپA’P‚ة—×’n‹«ٹEگü‚ـ‚إ‚ج‹——£‚ئŒڑ’z•¨‚جچ‚‚³‚ة‚و‚è‹پ‚ك‚½’l‚و‚è‚àژہچغ‚ة‚حپA‘½‚‚جŒُ‚ج—ت‚ھژ؛“à‚ة“ü‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚éپB
‚±‚ج‚½‚كپAڈ]—ˆ‚و‚èچH‹ئŒnپEڈ¤‹ئŒn’nˆو‚إ‚حپA‚±‚ج‰e‹؟‚ًٹ¨ˆؤ‚µ‚T‚چˆبڈم—×’n‹«ٹEگü‚©‚ç—£‚ꂽڈêچ‡‚حپAŒڑ’z•¨‚جچ‚‚³‚ة‚و‚炸پA‚·‚ׂؤ‚ج‘‹‚ًچجŒُڈم—LŒّ‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚±‚ë‚إ‚ ‚éپBچ،‰ٌپAچجŒُ‚جژZ’è‚ھچجŒُ•âگ³ŒWگ”‚إ’è‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚邽‚كپA‚±‚ج‹——£‚حپAچجŒُ•âگ³ŒWگ”‚ھ‚P–¢–‚ئ‚ب‚éڈêچ‡‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚àپA‚±‚ê‚ً‚P‚ئ‚·‚é‹——£‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚ـ‚½پA‹ك”NڈZ‹ڈŒn’nˆو‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àچ‚‘w‰»‚ة‚و‚èپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب•âگ³‚ًچs‚¤•K—vگ«‚ھچ‚‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚邽‚كپA“¯—l‚جچl‚¦•û‚إڈZ‹ڈŒn’nˆو‚ج‹——£‚ً‚V‚چ‚ئ‚µ‚ؤ’è‚ك‚éپB‚ـ‚½پAچ،‰ٌ‚جŒں“¢‚جŒ‹‰تپAڈ¤‹ئŒn’nˆو‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA‚S‚چ‚إ“¯—l‚جŒ‹‰ت‚ھ“¾‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ھ–¾‚ç‚©‚ئ‚ب‚ء‚½‚½‚كپAڈ¤‹ئŒn’nˆو‚إ‚ح‚±‚ج‹——£‚ً‚S‚چ‚ئ‰ü‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پy—LŒّ–تگد‚جژZ’è•û–@چ‡—‰»‚جƒCƒپپ[ƒWپz
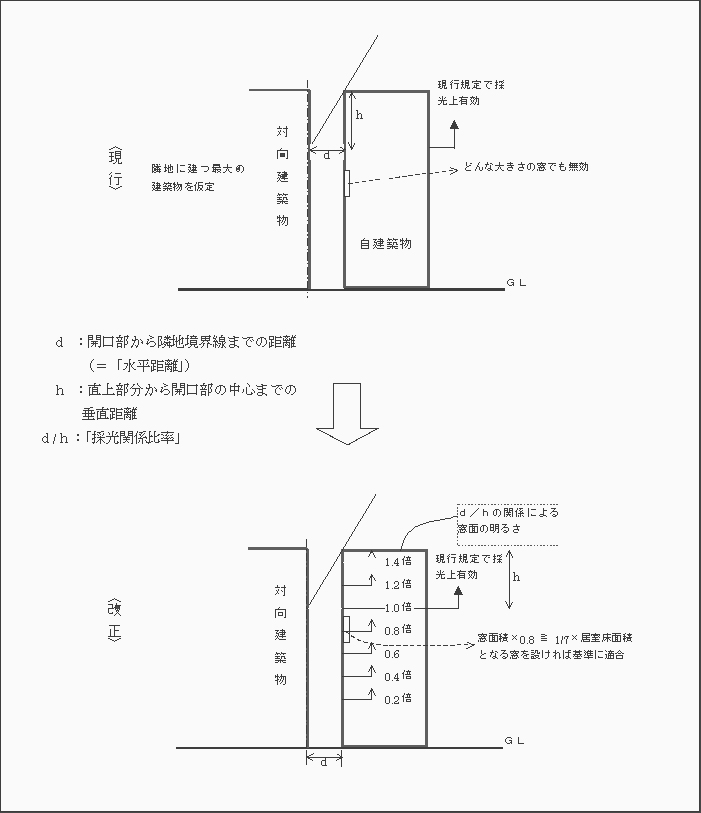
پ›—LŒّ–تگد‚جژZ’è•û–@پi—ك‘و‚Q‚Oڈًپj
—LŒّ–تگدپپ‘‹‚ج–تگدپ~چجŒُ•âگ³ŒWگ”
پ@پ¦چجŒُ•âگ³ŒWگ”‚حپA—×’n‹«ٹEگü‚ـ‚إ‚ج‹——£‚ئŒڑ’z•¨‚جچ‚‚³‚ة‰‚¶‚ؤ’è‚ك‚½ژZ’è’l‚ةپA—×’n‹«ٹEگü‚ـ‚إ‚ج‹——£پA‘خ–ت‚·‚é‚à‚ج‚ھ“¹کH‚إ‚ ‚é‚©”غ‚©“™‚ة‚و‚è•âگ³‚ً‰ء‚¦‚éپB
(1)
‹ڈژ؛‚جٹ·‹C‚ة‚آ‚¢‚ؤ
‹ڈژ؛‚جٹ·‹Cگف”ُ‚ة‚آ‚¢‚ؤپAژ©‘Rٹ·‹Cگف”ُ‚ةگف‚¯‚é”r‹C“›‚ج—LŒّ’f–تگدپA‹@ٹBٹ·‹Cگف”ُ‚ج—LŒّٹ·‹C—تپiŒڑ•¨‚â•”‰®‚جŒ`ڈَ‚ة‚و‚炸‚ةگ«”\‚ًٹm•غ‚إ‚«‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤˆê—¥‚ة’è‚ك‚ؤ‚¢‚é—تپj“™‚جچ€–ع‚ة‚آ‚¢‚ؤژd—l‹K’è‚ً’è‚كگ§Œہ‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚éپBچ،‰ٌ‚جگ—ك‰üگ³‚ة‚¨‚¢‚ؤپAگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپAٹ·‹Cگف”ُ‚جچ\‘¢‚حپAژd—l‹K’è‚ض“Kچ‡‚µ‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج–”‚حگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚إ‚ ‚é‚à‚ج‚ئ‚·‚éپB‚»‚ج‘¼Œ»چs‚جژd—l‹K’è‚جŒ©’¼‚µ‚ًچs‚¤پB
پ¦گ«”\‹K’艻‚ة‚و‚èپA‚و‚èڈ‚ب‚¢ٹ·‹C—ت‚إچإ’لŒہ‚جژ؛“àٹآ‹«‚ًٹm•غ‚·‚é•û–@‚ًٹJ”‚·‚邱‚ئ‚ھ‰آ”\‚ئ‚ب‚邽‚كپA—â–[‚â’g–[‚ًŒّ—¦—ا‚چs‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ›‹ڈژ؛‚جٹ·‹C‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi—ك‘و‚Q‚Oڈً‚ج‚Qپj
“–ٹY‹ڈژ؛‚إ‘z’肳‚ê‚é’تڈي‚جژg—pڈَ‘ش‚ة‚¨‚¢‚ؤپA“–ٹY‹ڈژ؛“à‚جگl‚ھ’تڈيٹˆ“®‚·‚邱‚ئ‚ھ‘z’肳‚ê‚é‹َٹش‚ج’Yژ_ƒKƒX‚جٹـ—L—¦‚ً‚¨‚¨‚ق‚ث•S–œ•ھ‚جگçˆب‰؛‚ةپA“–ٹY‹َٹش‚جˆêژ_‰»’Y‘f‚جٹـ—L—¦‚ً‚¨‚¨‚ق‚ث•S–œ•ھ‚جڈ\ˆب‰؛‚ة•غ‚آٹ·‹C‚ھ‚إ‚«‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئپ@“™
(2)
‰خ‹Cژg—pژ؛‚جٹ·‹C‚ة‚آ‚¢‚ؤ
ڈ]—ˆپA’²—ژ؛“™‚ةگف’u‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚éٹ·‹Cگف”ُ‚ة‚آ‚¢‚ؤ“Kگط‚ةٹ·‹C‚ًچs‚¤‚½‚ك‚ة‹‹‹CŒûپA”r‹CŒû‚ج–تگد“™‚جچ€–ع‚ة‚آ‚¢‚ؤژd—l‹K’è‚ً’è‚كگ§Œہ‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚éپBچ،‰ٌ‚جگ—ك‰üگ³‚ة‚¨‚¢‚ؤپAژd—l‹K’è‚ئ‚µ‚ؤٹ·‹Cگî“™‚ًگف‚¯‚½ڈêچ‡‚جٹ·‹C—ت‚ةٹض‚·‚éٹîڈ€‚ً’è‚ك‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپAٹ·‹Cگف”ُ‚جچ\‘¢‚حپAژd—l‹K’è‚ض“Kچ‡‚µ‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج–”‚حگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚éپB
پ¦پ@گ«”\‹K’艻‚ة‚و‚èپA‚و‚èŒّ—¦“I‚بٹ·‹Cگف”ُ‚جٹJ”‚ھ‘£گi‚³‚ê‚éپB
پ›‰خ‹Cژg—pژ؛‚جٹ·‹Cگف”ُ‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi—ك‘و‚Q‚Oڈً‚ج‚Rپj
‰خ‚ًژg—p‚·‚éگف”ُ–”‚حٹي‹ï‚ج’تڈي‚جژg—pڈَ‘ش‚ة‚¨‚¢‚ؤپAˆظڈي‚ب‰خ‚ج”Rڈؤ‚ھگ¶‚¶‚ب‚¢‚و‚¤“–ٹY‹ڈژ؛“à‚جژ_‘f‚جٹـ—L—¦‚ً‚¨‚¨‚ق‚ث“ٌڈ\پEŒـƒpپ[ƒZƒ“ƒgˆبڈم‚ة•غ‚آٹ·‹C‚ھ‚إ‚«‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئپB
ڈ]—ˆپA–hژ¼‚ج‚½‚كچإ‰؛ٹK‚جڈ°‚ً–ط‘¢‚ئ‚µ‚½‹ڈژ؛‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚حپAڈ°‚جچ‚‚³‚ً‚S‚T‡pˆبڈم‚ئ‚·‚邱‚ئ“™‚ًژd—l‹K’è‚ئ‚µ‚ؤ’è‚ك‚ؤ‚¢‚éپBچ،‰ٌ‚جگ—ك‰üگ³‚ة‚¨‚¢‚ؤپAگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپA‚±‚ج‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAژd—l‹K’è‚ض‚ج“Kچ‡‚ً—v‚µ‚ب‚¢‚à‚ج‚ئ‚·‚éپB
پ›‹ڈژ؛‚جڈ°‚ج–hژ¼•û–@‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi—ك‘و‚Q‚Qڈًپj
چإ‰؛ٹK‚ج‹ڈژ؛‚جڈ°‚جچ\‘¢‚ھپA’n–ت‚©‚ç”گ¶‚·‚éگ…ڈِ‹C‚ة‚و‚ء‚ؤ•…گH‚µ‚ب‚¢‚±‚ئپB
‚SپD’nٹK‚ة‚¨‚¯‚éڈZ‘î“™‚ج‹ڈژ؛‚ج‹Zڈp“Iٹîڈ€
چ،‰ٌ‚ج–@‰üگ³‚ة‚و‚èپA’nٹK‚ة‚¨‚¯‚éڈZ‘î“™‚ج‹ڈژ؛‚ًگف‚¯‚邱‚ئ‚ًŒ´‘¥‹ضژ~‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½‹K’è‚ً‰ü‚كپA‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ً’è‚كپA‚±‚ê‚ة“Kچ‡‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚³‚ꂽپB‚±‚ج‚½‚كپA–@‘و‚Q‚Xڈً‚جˆد”C‚ةٹî‚أ‚«پA’nٹK‚ة‚¨‚¯‚éڈZ‘î“™‚ج‹ڈژ؛‚ج–hژ¼“™‚جٹîڈ€‚ًژd—l‹K’è‚ئ‚µ‚ؤ’è‚ك‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپA–hگ…‚ج‘[’u‚ة‚آ‚¢‚ؤگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپA–hگ…‚ج‘[’u‚حپAژd—l‹K’è‚ض“Kچ‡‚µ‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج–”‚حگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›’nٹK‚ة‚¨‚¯‚éڈZ‘î“™‚ج‹ڈژ؛‚ج‹Zڈp“Iٹîڈ€پi—ك‘و‚Q‚Qڈً‚ج‚Qپj
پ@ژں‚جٹîڈ€‚ة“Kچ‡‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ
پE‚©‚ç‚ع‚è‚ة–ت‚µٹJŒû•”‚ھگف‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ–”‚حٹ·‹Cگف”ُ“™‚ھگف‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئپB“™پi–hژ¼‚ج‘[’uپj
پE’¼گع“y‚ةگع‚·‚é•”•ھ‚ئ‹ڈژ؛‚ة–ت‚·‚é•”•ھ‚جٹش‚ة‹ڈژ؛“à‚ض‚جگ…‚جگZ“§‚ً–hژ~‚·‚邽‚ك‚ج‹َŒ„‚ًگف‚¯پA‚»‚ج‹َŒ„‚©‚çگ…‚ً”rڈo‚·‚邽‚ك‚جگف”ُ‚ًگف‚¯‚邱‚ئپB“™پi–hگ…‚ج‘[’uپj
پ›’nٹK‚ة‚¨‚¯‚éڈZ‘î“™‚ج‹ڈژ؛‚ج–hگ…‚ج‘[’u‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi—ك‘و‚Q‚Qڈً‚ج‚Qپj
ٹO•ا“™‚ج’¼گع“y‚ةگع‚·‚é•”•ھ‚©‚ç‹ڈژ؛“à‚ةگ…‚ھگZ“§‚µ‚ب‚¢‚±‚ئپB
‚TپD’·‰®–”‚ح‹¤“¯ڈZ‘î‚جٹeŒث‚جٹE•ا‚جژص‰¹چ\‘¢
–@‘و‚R‚Oڈً‚جˆد”C‚ةٹî‚أ‚«پA’·‰®–”‚ح‹¤“¯ڈZ‘î‚جٹeŒث‚جٹE•ا‚جژص‰¹گ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ً’è‚ك‚éپB
پ›ژص‰¹گ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€پi—ك‘و‚Q‚Qڈً‚ج‚Rپj
ٹE•ا‚ة‚و‚鉹‚ج’لŒ¸Œّ‰ت‚ھپAˆê’è‚جگU“®گ”‚ة‘خ‚µ—׉ئ‚ج‰ïکb“™‚ج“à—e‚ھ•ھ‚©‚ç‚ب‚¢’ِ“x‚ج“§‰ك‘¹ژ¸ˆبڈم‚إ‚ ‚邱‚ئپB‚ب‚¨پA‚±‚ê‚حپAŒ»چs‚ئ“¯گ…ڈ€‚جٹîڈ€‚إ‚ ‚éپB
(1)
ٹK’i•‚جژZ’è•û–@پi—ك‘و‚Q‚Rڈًپj
Œڑ’z•¨“à‚إ‚جŒڑ•¨‚ة‹Nˆِ‚·‚éژ–Œج‚إٹK’i‚حپA“]—ژ“™‚جٹ댯‚ج‘ه‚«‚¢ڈêڈٹ‚إ‚ ‚èژè‚·‚è‚ًگف‚¯‚é•K—vگ«‚ھچ‚‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپBˆê•ûپA•‚ج‹·‚¢ژè‚·‚è‚إ‚ ‚ê‚خپA‚»‚ê‚ة‚و‚èٹK’i‚ج•‚ھ‘½ڈŒ¸ڈ‚µ‚ؤ‚àˆہ‘S‚ةٹK’i‚ًڈ¸چ~‚·‚邽‚ك‚ة‰e‹؟‚حڈ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھ–¾‚ç‚©‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ج‚½‚كپAٹK’i•‚جژZ’è‚ة‚ ‚½‚è•‚P‚O‡p‚ـ‚إ‚ًŒہ“x‚ةپA‚ب‚¢‚à‚ج‚ئ‚ف‚ب‚µ‚ؤژZ’è‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(2)
ژè‚·‚è‚جگف’u‚ج‹`–±‚أ‚¯پi—ك‘و‚Q‚Tڈًپj
چ‚—‚جگi“W‚ً“¥‚ـ‚¦پAٹK’i‚ض‚جژè‚·‚è‚جگف’u‚ً‹`–±‚أ‚¯‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
(1)
‚‚فژو‚è•ضڈٹ“™
‚‚فژو‚è•ضڈٹ‚جچ\‘¢پA“ءژêŒڑ’z•¨‹y‚ر“ء’è‹وˆو‚ج•ضڈٹ‚جچ\‘¢‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAڈ]—ˆ‚جژd—l‹K’è‚ً‰ü‚كپAگ«”\‹K’è‚ًگف‚¯پA‚±‚ê‚ç‚ج•ضڈٹ‚جچ\‘¢‚حپAگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚½چ\‘¢•û–@–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB‚ـ‚½پA‰ü—ا•ض‘…‚ة‚آ‚¢‚ؤپAŒڑگف‘هگb‚ھ•ت‚ةٹîڈ€‚ً’è‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éژ|‚ج‹K’è‚ً”pژ~‚µپAڈ]—ˆ‚±‚ج‹K’è‚ةٹî‚أ‚«چگژ¦‚إˆت’u‚أ‚¯‚ؤ‚¢‚½ژd—l‚ًگ—ك‚ةژو‚è“ü‚ê‚éپB
پ›‚‚فژو‚è•ضڈٹ‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi—ك‘و‚Q‚Xڈًپj
پ@پ@›”A‚ةگع‚·‚é•”•ھ‚©‚çکRگ…‚µ‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئپ@“™
پ›“ءژêŒڑ’z•¨‹y‚ر“ء’è‹وˆو‚ج•ضڈٹ‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi—ك‘و‚R‚Oڈًپj
•ضٹي‹y‚رڈ¬•ضٹي‚©‚ç•ض‘…‚ـ‚إ‚ج‰کگ…ٹا‚ھپA‰کگ…‚ًگZ“§‚³‚¹‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئپ@“™
پ@(2)
›”Aڈٍ‰»‘…
–@‘و‚R‚Pڈً‘و‚Qچ€‚جˆد”C‚ةٹî‚أ‚«پA‚µ”Aڈٍ‰»‘…‚ة‚آ‚¢‚ؤ‰ک•¨ڈˆ—گ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€‚ً’è‚ك‚éپB
پ@پ›‰ک•¨ڈˆ—گ«”\‚ةٹض‚·‚é‹Zڈp“Iٹîڈ€پi—ك‘و‚R‚Qڈًپj
’تڈي‚جژg—pڈَ‘ش‚ة‚¨‚¢‚ؤپA•ْ—¬گ…‚ج‰ک‚êپi‚a‚n‚cپiگ¶•¨‰»ٹw“Iژ_‘f—v‹پ—تپjپj‚ھˆê’è’lˆب‰؛‚إ‚ ‚邱‚ئپi‚a‚n‚c‚ج’l‚حپAڈ]—ˆ—ك‘و‚R‚Qڈً‚إ‹پ‚ك‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚ة“¯‚¶پjپ@“™
ڈ]—ˆپA‰Œ“ث‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‰خچذ‚ج”گ¶‚ج–hژ~“™‚جٹد“_‚©‚ç‰خ‚ج•²‚ة‚و‚鉄ڈؤ‚ج–hژ~پA‰Œ“ث‚ج‰ك”M‚ة‚و‚é‰خچذ‚ج–hژ~“™‚جچ€–ع‚ة‚آ‚¢‚ؤژd—l‹K’è‚ة‚و‚èگ§Œہ‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ج‚¤‚؟‰Œ“ث‚ج‰ك”M‚ة‚و‚é‰خچذ‚ج–hژ~‚جچ€–ع‚ة‚آ‚¢‚ؤپAگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپAژd—l‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج–”‚حگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›‰Œ“ث‚ج‰ك”M‚ة‚و‚é‰خچذ‚ج–hژ~‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi—ك‘و‚P‚P‚Tڈًپj
‰Œ“ث‚جژüˆح‚ة‚ ‚éŒڑ’z•¨‚ج•”•ھ‚ً‰Œ“ث“à‚ج”pƒKƒX‚»‚ج‘¼‚جگ¶گ¬•¨‚ج”M‚ة‚و‚è”Rڈؤ‚³‚¹‚ب‚¢‚±‚ئپ@“™
‰خچذژ‚ة‚¨‚¢‚ؤ‰~ٹٹ‚ب”ً“ï‚ً’S•غ‚·‚邽‚كپAˆê’è‚جŒڑ’z•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤ”ٌڈي—pڈئ–¾گف”ُ‚جگف’u‚ً‹`–±‚أ‚¯‚ؤ‚¢‚éپB
”ٌڈي—pڈئ–¾‚جچ\‘¢‚ة‚آ‚¢‚ؤپAڈ]—ˆپAڈ°–ت‚إ‚جڈئ“xپA—\”ُ“dŒ¹‚جگف’u“™‚جچ€–ع‚ة‚آ‚¢‚ؤژd—l‹K’è‚ة‚و‚èگ§Œہ‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚éپBچ،‰ٌ‚جگ—ك‰üگ³‚ة‚¨‚¢‚ؤپAگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپA”ٌڈي—pڈئ–¾گف”ُ‚جچ\‘¢‚حپAژd—l‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج–”‚حگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›”ٌڈي—pڈئ–¾‚جگ«”\‹K’èپi‘و‚P‚Q‚Uڈً‚ج‚Tپj
‰خچذژ‚ة‚¨‚¢‚ؤپA’â“d‚µ‚½ڈêچ‡‚ةژ©“®“I‚ة“_“”‚µپA‚©‚آپA”ً“ï‚·‚é‚ـ‚إ‚جٹش‚ةپA“–ٹYŒڑ’z•¨‚جژ؛“à‚ج‰·“x‚ھڈمڈ¸‚µ‚½ڈêچ‡‚ة‚ ‚آ‚ؤ‚àڈ°–ت‚ة‚¨‚¢‚ؤˆêƒ‹ƒNƒXˆبڈم‚جڈئ“x‚ًٹm•غ‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邱‚ئ
‚P‚OپDŒڑ’zگف”ُ‚جچ\‘¢‹“xپi‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚Q‚ج‚Sپj
ڈ]—ˆپAŒڑ’zگف”ُ‚جچ\‘¢‹“x‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAٹeگف”ُ‚²‚ئ‚ة’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ھپAڈ¸چ~‹@‚ًڈœ‚«‹¤’ت‚µ‚½ژ–چ€‚ھ‘½‚پA‚و‚èˆê——گ«‚ج‚ ‚é‹K’è‚ئ‚·‚邽‚كپAچ،‰ٌپAگ®—‚µ‚ؤˆت’u‚أ‚¯‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚ـ‚½پA‰®ڈم‚©‚ç“ثڈo‚·‚éگ…‘…پA‰Œ“ث“™‚حپA‹‚¢•—ˆ³—ح‚ًژَ‚¯پA‚ـ‚½پA’nگk“™‚ج‰e‹؟‚ً‘ه‚«‚ژَ‚¯‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚邽‚كˆہ‘Sگ«‚جŒںڈط‚ًچ\‘¢ŒvژZ‚ة‚و‚èچs‚¤‚±‚ئ‚ً‹`–±‚أ‚¯‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‚P‚PپD‹‹گ…پA”rگ…‚»‚ج‘¼‚ج”zٹاگف”ُ
پ@(1)
–h‰خ‹و‰و“™‚جٹر’ت•”‚ة—p‚¢‚é”zٹا‚جچ\‘¢
ڈ]—ˆپA‹‹گ…ٹاپA”z“dٹا“™‚ھ–h‰خ‹و‰و“™‚ًٹر’ت‚·‚é•”•ھ‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‚»‚ج•”•ھ‚©‚牄ڈؤ‚·‚邱‚ئ‚ً–h‚®‚½‚ك”zٹاگف”ُ‚ً•s”Rچق—؟‚ئ‚·‚éژd—l‹K’è‚ھگف‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپBچ،‰ٌ‚جگ—ك‰üگ³‚ة‚و‚èگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپA–h‰خ‹و‰و‚ًٹر’ت‚·‚é”zٹاگف”ُ‚حپAژd—l‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج–”‚حگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›–h‰خ‹و‰و“™‚ًٹر’ت‚·‚é•”•ھ‚ج”zٹا‚جچق—؟‚جگ«”\‹K’èپi‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚Q‚ج‚Tپj
–h‰خ‹و‰و“™‚ًٹر’ت‚·‚éٹا‚ة’تڈي‚ج‰خچذ‚ة‚و‚é‰خ”M‚ھ‰ء‚¦‚ç‚ꂽڈêچ‡‚ةپA‰ء”MٹJژnŒمˆê’èژٹشپi–h‰خ‹و‰و“™‚ة—v‹پ‚³‚ê‚éگ«”\‚ة‰‚¶پA‚Q‚O•ھٹشپA‚S‚T•ھٹش–”‚ح‚Pژٹشپj–h‰خ‹و‰و“™‚ج‰ء”M‘¤‚ج”½‘خ‘¤‚ة‰خچذ‚ًڈo‚·Œ´ˆِ‚ئ‚ب‚é‹T—ô‚»‚ج‘¼‚ج‘¹ڈ‚ًگ¶‚¶‚ب‚¢‚±‚ئپB
(2)
ˆù—؟گ…‚ج”zٹاگف”ُ‚جچق—؟
ڈ]—ˆپAˆù—؟گ…‚ج‰کگُ‚ً–hژ~‚·‚邽‚كپAˆù—؟گ…‚ج”zٹاگف”ُ‚جچقژ؟‚ة‚آ‚¢‚ؤ•sگZ“§ژ؟‚ج‘دگ…چق—؟‚ئ‚·‚é“™‚جژd—l‹K’è‚ً’è‚كگ§Œہ‚ً‚¨‚±‚ب‚ء‚ؤ‚«‚½پBچ،‰ٌ‚جگ—ك‰üگ³‚ة‚¨‚¢‚ؤپA‚±‚ج‹K’è‚ًگ«”\‹K’è‚ة‰ü‚كپAˆù—؟گ…‚ج”zٹاگف”ُ‚حپA“–ٹYگ«”\‚ً—L‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚½چ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›ˆù—؟گ…‚ج”zٹاگف”ُ‚جگ«”\‹K’èپi‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚Q‚ج‚Tپj
”zٹاگف”ُ‚©‚çکRگ…‚µ‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئ‹y‚ر”zٹاگف”ُ‚©‚ç—nڈo‚·‚镨ژ؟‚ة‚و‚ء‚ؤ‰کگُ‚³‚ê‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئپB
(3)
—â‹p“ƒ‚ج–h‰خگ«”\
چ‚‘wٹK‚ج‰®ڈم‚ة‚ ‚èپAˆê’[’…‰خ‚µ‚½ڈêچ‡ڈء‰خ‚ھچ¢“ï‚ب—â‹p“ƒگف”ُ‚ج–h‰خگ«”\‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAڈ]—ˆژd—l‹K’è‚إ’è‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚«‚½پBچ،‰ٌ‚ج‰üگ³‚ة“–‚½‚èپAگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپA—â‹p“ƒ‚جچ\‘¢‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAژd—l‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج–”‚حگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›—â‹p“ƒ‚ج–h‰خگ«”\پi—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚Q‚ج‚Vپj
—â‹p“ƒگف”ُ‚ج“à•”‚ھ”Rڈؤ‚µ‚½ڈêچ‡‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àŒڑ’z•¨‚ج‘¼‚ج•”•ھ‚ھ’…‰خ‚·‚鉷“xˆبڈم‚ةڈمڈ¸‚³‚¹‚ب‚¢‚±‚ئ
(4)
‚»‚ج‘¼
‡@ˆê’è‹K–حˆبڈم‚جŒڑ’z•¨‚ةگف‚¯‚é•—“¹“™‚ً•s”Rچق—؟‚ئ‚·‚é‹K’è‚ة‚آ‚¢‚ؤپAˆê‚آ‚جڈZŒث“à‚ج‚ف‚ج‚½‚ك‚ج•—“¹“™‹ا•”“I‚ةگف‚¯‚ç‚ê‚é•—“¹“™‚ج“K—p‚ًڈœٹO‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپBپi—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚Q‚ج‚T‘و‚Pچ€پj
‡Aٹ·‹Cگف”ُ‚ة‚آ‚¢‚ؤپAٹ·‹Cگف”ُ‚ج‘½—l‰»پi‘ه‹َٹش‚ج‹ڈژ؛‚ة‚¨‚¯‚éˆê’è‚جڈêڈٹ‚ًŒہ‚ء‚½‹َ‹C‚ج’²گ®پj“™‚ً“¥‚ـ‚¦‚½ٹîڈ€‚جŒ©’¼‚µ‚ًچs‚¤پBپi—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚Q‚ج‚Uپj
(1)
“K—p”حˆح‚ج–¾ٹm‰»
ƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[پAƒ_ƒ€ƒEƒGپ[ƒ^پ[‚ج’è‹`‚ًچs‚¤‚ئ‚ئ‚à‚ةپAƒ_ƒ€ƒEƒGپ[ƒ^پ[‚ج–¼ڈج‚ً‰ü‚كڈ¬‰×•¨گê—pڈ¸چ~‹@‚ئ‚·‚éپB
(2)
ƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[
‡@چ\‘¢ڈمژه—v‚ب•”•ھ
ڈ]—ˆپAƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚جچ\‘¢ڈمژه—v‚ب•”•ھ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‚©‚²‚ج—ژ‰؛‚ً–h‚®‚½‚كژd—l‹K’è‹y‚رچ\‘¢ŒvژZ‚ة‚و‚èگ§Œہ‚ًچs‚ء‚ؤ‚«‚½پBچ،‰ٌ‚جگ—ك‰üگ³‚إ‚±‚ê‚ً‰ü‚ك‚ؤگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپA‚±‚ج‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤپAŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚½چ\‘¢•û–@پAƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‹“xŒںڈط–@‚ة‚و‚èŒںڈط‚ًچs‚ء‚½‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚éپB
‚»‚ج‘¼‰®ٹO‚ةگف‚¯‚éƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚ةٹض‚µپA•—ˆ³—ح‚ة‘خ‚·‚éˆہ‘Sگ«‚ًŒںڈط‚·‚邱‚ئ‚ً‹`–±‚أ‚¯‚é“™‚ج‹K’è‚ًگف‚¯‚éپB
پ›ƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚جچ\‘¢ڈمژه—v‚ب•”•ھ‚ةٹض‚·‚éگ«”\‚جٹîڈ€پi‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚Sپj
پ@گف’uژ‹y‚رژg—pژ‚ج‚©‚²‹y‚ر‚©‚²‚ً‚آ‚è–”‚حژx‚¦‚éژه—v‚بژxژ•”•ھ‚ھ’تڈي‚جژg—pڈَ‘ش‚ة‚¨‚¯‚é–€‘¹–”‚ح”وکJ”j‰َ‚ًچl—¶‚µ‚ؤژں‚جٹîڈ€‚ة“Kچ‡‚·‚邱‚ئپB
پE‚©‚²‚جڈ¸چ~‚ة‚و‚ء‚ؤ–€‘¹–”‚ح”وکJ”j‰َ‚ًگ¶‚¸‚邨‚»‚ê‚ج‚ ‚é•”•ھˆبٹO‚ج•”•ھ‚حپA’تڈي‚جڈ¸چ~ژ‚جڈصŒ‚‹y‚رˆہ‘S‘•’u‚ھچى“®‚µ‚½ڈêچ‡‚جڈصŒ‚‚ة‚و‚葹ڈ‚ًگ¶‚¶‚ب‚¢‚±‚ئپB
پE‚©‚²‚جڈ¸چ~‚ة‚و‚ء‚ؤ–€‘¹–”‚ح”وکJ”j‰َ‚ًگ¶‚¸‚邨‚»‚ê‚ج‚ ‚é•”•ھ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA’تڈي‚جژg—pڈَ‘ش‚ة‚¨‚¢‚ؤپA’تڈي‚جڈ¸چ~ژ‚جڈصŒ‚‹y‚رˆہ‘S‘•’u‚ھچى“®‚µ‚½ڈêچ‡‚جڈصŒ‚‚ة‚و‚è‚©‚²‚ج—ژ‰؛‚ً‚à‚½‚ç‚·‚و‚¤‚ب‘¹ڈ‚ھگ¶‚¶‚ب‚¢‚±‚ئپB
پiƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‹“xŒںڈط–@‚جٹT—vپj
1)پ@’تڈي‚جڈ¸چ~ژپAˆہ‘S‘•’u‚جچى“®ژ‚ةچ\‘¢ڈمژه—v‚ب•”چق‚جٹe’f–ت‚ةگ¶‚¸‚鉗ح“x‚ًژZ’è‚·‚éپB
2)پ@گف’uژ‹y‚رژg—pژ‚ج‚»‚ꂼ‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤڈ¸چ~ژپAˆہ‘S‘•’u‚جچى“®ژ‚ة‘خ‰‚µ‚½‹–—e‰—ح“xپiگف’uژ‚ج’l‚ح’تڈي‚جژg—pڈَ‘ش‚ج–€‘¹پE”وکJ‚ًچl—¶‚µ‚ؤپAژg—pژ‚و‚è—]—T‚ًŒ©چ‚ٌ‚¾’l‚ئ‚·‚éپBپj‚ً’è‚كپA1)‚إ‹پ‚ك‚½‰—ح“x‚ھ‚±‚ê‚ً’´‚¦‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚éپB
3)پ@–€‘¹پE”وکJ‚ة‚و‚éچق—؟‹“x‚ج’ل‰؛‚ھگ¶‚¸‚é•”چقپiژهچُ“™پj‚جˆê•”‚ھ”j’f‚µ‚½ڈêچ‡‚ةپA“–ٹY•”چق‚جٹe’f–ت‚ةگ¶‚¸‚鉗ح“x‚ً‹پ‚كپA‚±‚ê‚ھپA‚©‚²‚ج—ژ‰؛‚ً‚à‚½‚ç‚·‚و‚¤‚ب‹–—e‰—ح“x‚ً’´‚¦‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًٹm‚©‚ك‚éپB
‡Aگ§ŒنٹيپEگ§“®‘•’u
ƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚جگ§Œنٹي‹y‚رگ§“®‘•’u‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚ًˆہ‘S‚ة—ک—p‚·‚邽‚ك‚ةڈd—v‚ب‹@”\‚ً—L‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‚±‚ê‚ـ‚إŒآپX‚ج‘•’u‚جگف’u‚ً‹پ‚ك‚é‚ب‚ا‚جژd—l‹K’è‚ة‚و‚èگ§Œہ‚ًچs‚ء‚ؤ‚«‚½پBچ،‰ٌ‚جگ—ك‰üگ³‚إگ§ŒنٹيپEگ§“®‘•’u‚ةٹض‚µپAگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپA‚»‚جچ\‘¢‚حپA‚±‚ج‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ج’è‚ك‚½چ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›گ§Œنٹي‚جگ«”\‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚Wپj
‚©‚²‚ةگl‚ھڈو‚è–”‚ح•¨‚ھگد‚فچ‚ـ‚ꂽڈêچ‡‚ةپA‚©‚²‚ج’âژ~ˆت’u‚ھ’ک‚µ‚ˆع“®‚¹‚¸پA‚©‚آپAƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚ج•غژç“_Œں‚ًˆہ‘S‚ةچs‚¤‚½‚ك‚ة•K—v‚بگ§Œن‚ھ‚إ‚«‚é‚à‚ج
پ›ƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚جگ§“®‘•’u‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚P‚Oپj
‚©‚²‚ھڈ¸چ~کH‚ج’¸•”–”‚ح’ê•”‚ةڈص“ث‚·‚邨‚»‚ê‚ھ‚ ‚éڈêچ‡‚ةپAژ©“®“IپA‚©‚آپA’iٹK“I‚ةچى“®‚µپA‚±‚ê‚ة‚و‚è‚©‚²‚ةگ¶‚¸‚éگ‚’¼•ûŒü‚ج‰ء‘¬“x‚ھ‚XپD‚W‚چپ^‚“‚Qپi—§‚ء‚ؤ‚¢‚éگl‚ةٹëٹQ‚ًگ¶‚¶‚³‚¹‚ب‚¢ƒŒƒxƒ‹پj‚ًپAگ…•½•ûŒü‚ج‰ء‘¬“x‚ھ‚T.‚O‚چپ^‚“‚Qپi—§‚ء‚ؤ‚¢‚éگl‚ھ•ا“™‚ة‹‚‚ ‚½‚èٹëٹQ‚ًگ¶‚¶‚邱‚ئ‚ج‚ب‚¢ƒŒƒxƒ‹پj‚ً’´‚¦‚邱‚ئ‚ب‚ˆہ‘S‚ة‚©‚²‚ًگ§ژ~‚³‚¹‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئپ@“™
‡B
‚»‚ج‘¼‚ج‰üگ³
پE‚©‚²‹y‚رڈ¸چ~کH‚ج“à‘•‚ةٹض‚µپA–h‰خچق—؟‚جگ«”\‚ھ–¾‚ç‚©‚ئ‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚ة”؛‚¢پA•s”Rچق—؟‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ً‹پ‚ك‚ؤ‚¢‚½ڈ]—ˆ‚ج‹K’è‚ً‰ü‚كپA‚©‚²“à“™‚جڈ¬‚³‚ب‰خ‹C‚ة‘خ‚µ•K—v‚بگ«”\‚ً—L‚·‚é“ï”Rچق—؟‚إ—ا‚¢‚±‚ئ‚ئ‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAڈ¬‹K–ح‚بŒڑ’z•¨‚ةگف‚¯‚éƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚ةٹض‚·‚éچق—؟گ§Œہ‚ً”pژ~‚·‚éپi—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚U‹y‚ر‚Vپj
پE‚Q•ûŒüڈo“ü‚èŒû‚جگ§Œہ‚ج”pژ~پiŒ»چs—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚T‹y‚ر‚Uپj
پEٹeٹK‹گ§’âژ~‘•’u‚ج‹`–±‚أ‚¯‚ج”pژ~پiŒ»چs—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚Xپj
(3)
ƒGƒXƒJƒŒپ[ƒ^پ[
پ@ƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚ةڈ€‚¶‚ؤگ«”\‹K’艻‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAژd—l‹K’è‚جŒ©’¼‚µ‚ًچs‚¤پB
‡@‘¬“xگ§Œہ‚جŒ©’¼‚µپi—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚P‚Q‘و‚Pچ€پj
چإ‹ك‚جƒGƒXƒJƒŒپ[ƒ^پ[‚جˆہ‘Sگ«‚ةٹض‚·‚é’mŒ©پAŒù”z‚ج‚ن‚é‚¢ƒGƒXƒJƒŒپ[ƒ^پ[“™‚جٹJ”ڈَ‹µ“™‚ً“¥‚ـ‚¦پA“¥’i‚ج’èٹi‘¬“x‚جڈمŒہ‚ً‚R‚O‚چ‚©‚çˆّ‚«ڈم‚°پA‚T‚O‚چ‚ـ‚إ‚ج”حˆح“à‚إپAƒGƒXƒJƒŒپ[ƒ^پ[‚جŒù”z‚ة‰‚¶Œڑگف‘هگb‚ج’è‚ك‚鑬“xˆب‰؛‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
‡Aچ\‘¢ڈمژه—v‚ب•”•ھ
ƒGƒXƒJƒŒپ[ƒ^پ[‚ةڈ€‚¶پAگ«”\‹K’艻‚ًچs‚¤پB
پ›ƒGƒXƒJƒŒپ[ƒ^پ[‚جچ\‘¢ڈمژه—v‚ب•”•ھ‚ةٹض‚·‚éگ«”\‚جٹîڈ€پi‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚P‚Q‘و‚Qچ€پj
ƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚ج‹K’è‚ًڈ€—p‚·‚éپB
‡Bگ§“®‘•’u
‘½—l‚ب‘¬“x‚جƒGƒXƒJƒŒپ[ƒ^پ[‚ھٹJ”‚³‚ê‚آ‚آ‚ ‚邱‚ئ‚ًژَ‚¯پAچ،‰ٌ‚جگ—ك‰üگ³‚ة‚¨‚¢‚ؤگ§“®‘•’u‚ةٹض‚µپAگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپAگ§“®‘•’u‚جچ\‘¢‚حپA‚±‚جگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚½چ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›ƒGƒXƒJƒŒپ[ƒ^پ[‚جگ§“®‘•’u‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚P‚Q‘و‚Tچ€پj
گl–”‚ح•¨‚ةٹëٹQ‚ھگ¶‚¶‚邨‚»‚ê‚ ‚éڈêچ‡‚ة“¥’i‚ةگ¶‚¸‚éگiچs•ûŒü‚ج‰ء‘¬“x‚ھ‚PپD‚Q‚T‚چپ^‚“‚Qپi“¥’iڈم‚جگl‚ھƒoƒ‰ƒ“ƒX‚ً•ِ‚·‚¨‚»‚ê‚جڈ‚ب‚¢ƒŒƒxƒ‹پj‚ً’´‚¦‚邱‚ئ‚ب‚ˆہ‘S‚ة“¥’i‚ًگ§ژ~‚³‚¹‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئپ@
‡C‚»‚ج‘¼
پE–¢‚¾‚ةƒGƒXƒJƒŒپ[ƒ^پ[‚ئ“Vˆن‚ج‚·‚«ٹش“™‚جٹش‚ةگl‚ھ‚ح‚³‚ـ‚ê‚éژ–Œج‚ھ‘½‚¢ڈَ‹µ‚ةٹس‚فپA‚ح‚³‚ـ‚ê–hژ~‘[’u‚ج‹‰»‚ًچs‚¤پBپi—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚P‚Q‘و‚Pچ€پj
پE—A“ü‚ج‰~ٹٹ‰»‚جٹد“_‚©‚çپAƒGƒXƒJƒŒپ[ƒ^پ[‚ج•‚جژZ’è•û–@‚ًڈ”ٹOچ‘‚ج—ل‚ةگ®چ‡‰»‚·‚éپi—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚P‚Q‘و‚Pچ€پj
پ@(3)
ڈ¬‰×•¨گê—pڈ¸چ~‹@
پ@چإ‹ك‚جژ–Œج—ل‚ً“¥‚ـ‚¦پA‚©‚²‚ھ‚»‚جٹK‚ة’âژ~‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢ڈêچ‡‚ةڈo‚µ“ü‚êŒû‚ھٹJ‚©‚ب‚¢چ\‘¢‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ً‹`–±‚أ‚¯‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAڈ¸چ~کH‚ج“à‘•‚ةٹض‚·‚éچق—؟گ§Œہ‚جٹةکa‚ًچs‚¤پB
(4)
”ٌڈي—pƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[
“r’†‚إٹK‚ج–تگد‚ھڈ¬‚³‚‚ب‚é‚à‚ج“™”ٌڈي—pڈ¸چ~‹@‚ً—ک—p‚µ‚ب‚‚à”ً“ïڈمڈء‰خڈمژxڈل‚ھ‚ب‚¢ٹK‚ة‚ح’âژ~‚·‚邱‚ئ‚ً—v‚µ‚ب‚¢‚à‚ج‚ئ‚·‚éپBپi—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚P‚R‚ج‚Qپj
ڈ]—ˆپA”ً—‹گف”ُ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAژd—l‹K’è‚ة‚و‚èگ§Œہ‚ًچs‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚éپBچ،‰ٌ‚جگ—ك‰üگ³‚إپAگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپA”ً—‹گف”ُ‚جچ\‘¢‚حپA‚±‚جگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚½چ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›”ً—‹گف”ُ‚جگ«”\‹K’艻پi—ك‘و‚P‚Q‚Xڈً‚ج‚P‚Tپj
—‹Œ‚‚ة‚و‚ء‚ؤگ¶‚¸‚é“d—¬‚ًŒڑ’z•¨‚ة”يٹQ‚ً‹y‚ع‚·‚±‚ئ‚ب‚ˆہ‘S‚ة’n’†‚ة—¬‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚à‚ج
(1)
چ\‘¢ڈمژه—v‚ب•”•ھپi—ك‘و‚P‚S‚Sڈً‘و‚Pچ†پj
پ@‚±‚ê‚ـ‚إپAچ|‘¢پA“S‹طƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‘¢پA“Sچœ“S‹طƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‘¢‚ةŒہ‚ء‚ؤ‚¢‚½چق—؟‚جگ§Œہ‚ً‰ü‚كپAچق—؟‚ة‰‚¶‚½چ\‘¢•û–@‹y‚رچ\‘¢ŒvژZ‚ج‹`–±‚أ‚¯‚ًچs‚¤پB
(2)
–€‘¹–”‚ح”وکJ”j‰َ‚ة‚و‚èچق—؟‹“x‚ج’ل‰؛‚ھگ¶‚¶‚邨‚»‚ê‚ج‚ ‚é•”•ھپi—ك‘و‚P‚S‚Sڈً‘و‚Qچ†پj
چ\‘¢ڈمژه—v‚ب•”•ھ‚إ–€‘¹“™‚ة‚و‚èچق—؟‹“x‚ج’ل‰؛‚ھگ¶‚¶‚é•”•ھ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[“¯—lپA–€‘¹–”‚ح”وکJ”j‰َ‚ة‚و‚éچق—؟‹“x‚ج’ل‰؛‚ة”z—¶‚µ‚½گفŒv‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ھ•K—v‚ئ‚ب‚éپB‚±‚ج‚½‚كƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚ةڈ€‚¶پAگ«”\‹K’è‚ً’è‚ك‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›—V‹Yژ{گف‚جچ\‘¢ڈمژه—v‚ب•”•ھ‚ةٹض‚·‚éگ«”\‚جٹîڈ€پi—ك‘و‚P‚S‚Sڈً‘و“ٌچ†پj
ƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚ج‹K’è‚ًڈ€—p‚·‚éپB
(3)
‹qگب•”•ھ
—V‹Yژ{گف‚ھ‘½—l‰»‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚çپA‹qگب•”•ھ‚ج—ژ‰؛–hژ~‚ج‘[’u‚ة‚آ‚¢‚ؤپAگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپA‚±‚ج•”•ھ‚جچ\‘¢‚حپAگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚½چ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›‹qگب•”•ھ‚©‚ç‚ج—ژ‰؛‚ج–hژ~‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi—ك‘و‚P‚S‚Sڈً‘وژlچ†پj
‘–چs–”‚ح‰ٌ“]ژ‚جڈصŒ‚‹y‚ر”ٌڈيژ~‚ك‘•’u‚جچى“®ژ‚جڈصŒ‚‚ھ‰ء‚¦‚ç‚ꂽڈêچ‡‚ةپA‹qگب‚ة‚¢‚éگl‚ً—ژ‰؛‚³‚¹‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئپB
(4)
”ٌڈيژ~‚ك‘•’u‚جچ\‘¢
—V‹Yژ{گف‚ھ‘½—l‰»‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚çپAچ،‰ٌ‚جگ—ك‰üگ³‚إ”ٌڈيژ~‚ك‘•’u‚ةٹض‚µگ«”\‹K’è‚ً’è‚كپA”ٌڈيژ~‚ك‘•’u‚جچ\‘¢‚ة‚آ‚¢‚ؤپAگ«”\‹K’è‚ة“Kچ‡‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ھ’è‚ك‚½چ\‘¢•û–@‚ً—p‚¢‚é‚à‚ج–”‚حŒڑگف‘هگb‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ئ‚·‚éپB
پ›—V‹Yژ{گف‚جگ§“®‘•’u‚ةٹض‚·‚éگ«”\‹K’èپi‘و‚P‚S‚Sڈً‘و‚Uچ†پj
ژ©“®“I‚ةچى“®‚µپA‚©‚آپA“–ٹY‹qگب•”•ھˆبٹO‚ج—V‹Yژ{گف‚ج•”•ھ‚ةڈص“ث‚·‚邱‚ئ‚ب‚گ§ژ~‚إ‚«‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئپ@