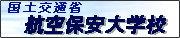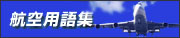第3回今後の空港のあり方に関する研究会
| 1.日時 |
| 平成19年12月 6日(木) 14:00~16:00 |
| 2.場所 |
| 中央合同庁舎3号館 国土交通省11階特別会議室 |
| 3.出席者 |
| <研究会メンバー>(50音順、敬称略) |
| 樫谷隆夫、金本良嗣、竹内伝史、富澤秀機、松田英三、廻洋子、屋井鉄雄、山内弘隆、山本雄二郎 |
| <国土交通省> |
| 鈴木航空局長 他 |
| 4.主な議題 |
| 今後の空港の整備及び運営に関する制度について |
| 5.議事概要 |
|
○事務局より資料に沿って説明。その後、質疑応答。 ○委員から出された主な意見 ・ 基本方針や空港会社の作成する中期的計画については、一度策定したら終わりという ・ 完全民営化後の成田国際空港がどのように変わっていくのかという点について地元に ・ 外資規制により防ぐべき事態と大口規制により防ぐべき事態は全く異なるものであり、 ・ 羽田空港のあり方というものを具体的に考えた場合、ターミナルビルへの資本規制は ・ 施設の細分毎に細かく料金規制をかけるというのは避けた方がよいと思っている。空港 ・ 料金規制を上限認可制に拠ることとした場合、上限料金を算出する上で、料金により ・ 料金規制を届出変更命令により行おうとすると、変更命令の発動要件の定め方が難 ・ 成田国際空港について、完全民営化する時の料金規制がどうなっているかによって株 ・ 地方公共団体が管理する空港については、地方公共団体の判断に基づいて、コストに ・ 空港整備特別会計の独法化等の議論が摘み残されている中、空港の整備、運営に関 ・ 空港の「設置」「管理」という言葉は古めかしく、整備より運営を重要視していこうという |