

各地方建設局長あて
記
|
|
|
別紙1 ○○ダムの建設に関する基本計画(案)
1 建設の目的
(1) 洪水調節
○○ダムの建設される地点における計画洪水流量毎秒○○○立方メートルのうち、毎秒○○○立方メートルの洪水調節を行い、下流○○川の○○地先の計画高水流量毎秒○○○立方メートルを毎秒○○○立方メートルに低減させる。
(2) かんがい
>○○川沿岸の○○○ヘクタールの農地に対するかんがい用水の補給を行う。このうち○○○ヘクタールの農地に対するかんがい用水の補給は、専用の施設を新設して行う。
(3) 発電
○○ダムの建設に伴つて新設される○○発電所及び○○発電所において、それぞれ最大出力○○○○キロワツト及び○○○○キロワツトの発電を行い、下流○○発電所及び○○発電所における電力量の増加を図る。
2 位置及び名称
(1) 位置
○○川水系○○川 右岸 ○○県○○郡○○村○○
(左岸○○県○○郡○○村○○)
(2) 名称
○○ダム
3 規模及び型式
(1) 規模
堤高(基礎岩盤から最高水位までをいう。)○○○メートル
(2) 型式
○○式○○○○○ダム
4 貯留量、取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分に関する事項
(1) 貯留量
イ 総貯留量
最高水位は、標高○○○メートルとし、総貯留量は、○○,○○○,○○○立方メートルとする。
ロ 有効貯留量
最低水位は、標高○○○メートルとし、有効貯留量は総貯留量のうち、標高○○○メートルから標高○○○メートルまでの有効水深○○メートルの貯留量○○,○○○,○○○立方メートルとする。
(2) 取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分
イ 洪水調節
洪水期(毎年○月○日から○月○日までの間をいう。)においては、洪水調節を行う場合を除き、水位を標高○○○メートル以下に制限するものとする。洪水調節は、予備放流により標高○○○メートルを限度として水位を低下させ、当該水位から標高○○○メートルまでの容量最大○○,○○○,○○○立方メートルを利用して行うものとする。
なお、洪水期以外においても、洪水調節は予備放流により行うことができるものとする。
ロ かんがい
かんがい期(毎年○月○日から○月○日までの間をいう。)においては、かんがい用水補給のために、○○地点における流量が、下記の流量にみたないときは、当該流量を確保するに必要な水量を○○ダムから放流するものとする。
○月○日から○月○日まで、毎秒○.○立方メートル(うち、特定かんがい用水の必要量に相当するもの○○立方メートル)
○月○日から○月○日まで、毎秒○.○立方メートル(うち、特定かんがい用水の必要量に相当するもの○○立方メートル)
以下同様 〃 〃
かんがいのための有効貯留量は、標高○○○メートル以上の○○,○○○,○○○立方メートルとし、かんがい期においては、かんがいのために水位を低下させる場合を除き、水位を下記の基準水位以上に保つものとする。
○月○日 標高 ○○○メートル
○月○日 標高 ○○○メートル
以下同様
ハ 発電
○○発電所の取水量は毎秒○○立方メートル以内、○○発電所の取水量は毎秒○○立方メートル以内とし、必要に応じ○○調整池において○○発電所からの放流量を逆調整するものとする。発電のための有効貯留量は、標高○○○メートルから標高○○○メートルまでの○○,○○○,○○○立方メートルとする。ただし、発電は、イに規定する洪水調節及びロに規定するかんがいに支障を与えない範囲において行うものとする。
5 ダム使用権の設定予定者
○○○(発電)
6 建設に要する費用及びその負担に関する事項
(1) 建設に要する費用の概算額
○,○○○,○○○,○○○円
(2) 建設に要する費用の負担者及び負担額
イ 河川法第27条の規定に基く国並びに○○県及び○○県の負担額
建設に要する費用に1,000分の○○○を乗じた額とする。
なお、県の負担額について○○県と○○県とが分担する割合は○○県1,000分の○○○,○○県1,000分の○○○とする。
ロ 特定多目的ダム法第7条第1項の規定に基く○○の負担額
建設に要する費用に1,000分の○○○を乗じた額とする。
ハ 特定多目的ダム法第9条第1項の規定に基く○○の負担額
建設に要する費用に1,000分の○○○を乗じた額とする。
ニ 特定多目的ダム法第10条第1項の規定に基く○○の負担額
イに規定する国並びに○○県及び○○県の負担額のうち、建設に要する費用に1,000分の○○○を乗じた額の10分の1の額
|
|
|
|
別紙2 基本計画の添付図書作成要領
1 流域一覧図
縮尺(1/200,000)地理調査所地勢図使用のこと。
記入事項
2 計画概要図
縮尺(1/50,000)地理調査所地形図使用のこと。
記入事項
ダム……朱色
貯水池……青色
発電所及び水路……朱色
この他1に記載した事項を適宜記入すること。
3 ダム構造図
以上の図面を1枚の用紙にまとめること。
4 貯水池容量配分図
最高水位(洪水調節満水位を記入すること。)
常時満水位
洪水期制限水位
農業確保水位(最高のものを記入すること。)
水道確保水位(最高のものを記入すること。)
最低水位
以上の事項を1枚の図面にまとめること。
5 洪水調節説明図書
洪水調節図(流入量、放流量、貯水位、ゲート開度等を記入すること。)
流量配分図(ダム築造前のものを( )内に併記すること。)
以上の図面を1枚の用紙にまとめること。
洪水調節計画説明書
下流改修工事の計画洪水流量及び進捗状況、本計画の計画洪水流量(発生年月日及び連続雨量を記入すること。)、洪水調節の方法、経済効果等について簡単な説明を加えること。
6 かんがい計画説明図書
かんがい用水給水区域図(縮尺(1/50,000)2の計画概要図に記入してもよいこと。)
専用施設計画概要図(新設の場合のみ必要であること。)
頭首工及び主要幹線水路の平面図、縦断面図、標準断面図等を適宜な縮尺で1枚にまとめたものであること。
計画説明書
受益面積、期間別用水量、ダムからの放流又は取水の方法、経済効果、専用施設の工事費内訳等について説明を加えること。
7 発電計画説明図書
専用施設計画概要図
取水口及び水路の平面図、縦断図及び標準断面図並びに調圧水槽、鉄管路、発電所、放水路、取水堰堤等の説明図を適宜な縮尺で1枚にまとめたものであること。
計画説明書
最大、常時、常時尖頭、渇水期平均、渇水期尖頭等につき、発電力、使用水量及び有効落差の一覧表を作成するとともに、月別平均発生電力量、同換算電力量、下流増電力量、同換算電力量、専用工事費内訳等を明記し、発電計画の説明を加えること。
8 上水道及び工業用水道説明図書
給水区域図(縮尺(1/50,000)2の計画概要図に記入してもよいこと。)
専用施設計画概要図
頭首工及び主要幹線水路の平面図、縦断図及び標準断面図並びに主要構造物等の説明図を適宜な縮尺で1枚にまとめたものであること。
計画説明書
上水道については、給水入口、給水量(m3/S、m3/D)、専用工事費内訳等を、工業用水道については、給水面積、主要工場名、給水量(m3/S、m3/D)、専用工事費内訳等を明記し、ダムからの放流又は取水の方法、経済効果等について説明を加えること。
(註)
1 添付図書1式フアイルに左とぢとし、1部提出すること。
2 フアイルの大きさは、縦30cm、横23cmのものを標準とすること。
3 図面の大きさは、特に指定しないが、折畳み寸法は、縦29cm、横20cm(綴込の部分の長さを含むこと。)とし、右下隅に番号及び図面名を下記要領により記入し、折り畳んだ際に表となるよう作成すること。
記
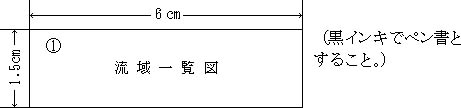
|
|
|
| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |