

北海道開発建設部長・沖縄総合事務局建設部長・各地方建設局道路部長・各都道府県知事・土木部長・九大市土木局長・本州四国連絡橋公団工務部長 参考送付先 日本道路公団技術部長・首都高速道路公団保全施設部長・阪神高速道路公団保全部長あて
|
|
|
標識令の規定
|
標準値
|
|
|
|
|
|
|
1)
都市部の道路
|
2)地方部の道路及び自動車専用道路(3)を除く)
|
3)設計速度八〇km/h以上の自動車専用道路
|
|
車道中央線
(実線二本)
|
幅(t)
|
〇・一〇〜〇・一五
|
〇・一五
|
〇・一五
|
〇・一五
|
|
|
実線間隔(d)
|
〇・一〇〜〇・一五
|
〇・一五
|
〇・一五
|
〇・一五
|
|
車道中央線(実線一本)
|
幅(t)
|
〇・一五〜〇・二〇
|
〇・二〇
|
〇・二〇
|
〇・二〇
|
|
車道中央線
(破線)
|
長さ
(l1)
|
三・〇〇〜一〇・〇〇
|
五・〇〇
|
五・〇〇
|
五・〇〇
|
|
|
間隔
(l2)
|
l1
|
五・〇〇
|
五・〇〇
|
五・〇〇
|
|
|
幅(t)
|
〇・一二〜〇・一五
|
〇・一五
(〇・一二)
|
〇・一五
|
〇・一五
|
|
車線境界線
(実線)
|
幅(t)
|
〇・一〇〜〇・一五
|
〇・一五
|
〇・一五
|
〇・一五
|
|
車線境界線
(破線)
|
長さ
(l1)
|
三・〇〇〜一〇・〇〇
|
六・〇〇
(五・〇〇)
|
六・〇〇
(五・〇〇)
|
八・〇〇
|
|
|
間隔
(l2)
|
(一・〇〜二・〇)
l1
|
九・〇〇
(五・〇〇)
|
九・〇〇
(五・〇〇)
|
一二・〇〇
|
|
|
幅(t)
|
〇・一〇〜〇・一五
|
〇・一五
|
〇・一五
|
〇・一五
|
|
車道外側線
|
幅(t)
|
〇・一五〜〇・二〇
|
〇・一五
|
〇・一五
|
〇・二〇
|
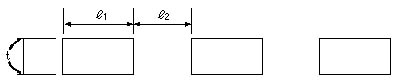
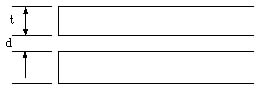
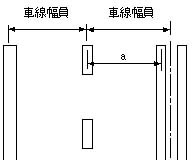
|
|
| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |