

都道府県建築主管部長あて
記
|
|
|
別添1 防火対象物にかかる表示、公表制度の実施について
昭和五六年五月一五日
消防予第一一一号
消防庁次長から各都道府県知事あて通知
昨年一一月に発生した栃木県の川治プリンスホテルの火災においては、防火管理面の不備等消防機関の立入検査の結果に基づく指摘事項の改善が十分に行われていない点が指摘されたところである。この種の不特定多数の者を収容する防火対象物の火災による惨事を防止するためには、防火対象物の関係者自らが防火について配慮することはもとより、消防機関においても消防法令違反の防火対象物に対し、厳格に消防法に基づく措置命令を発する等により早急に違反の是正を図るとともに、国民に対して防火対象物における防火管理の状況、消防用設備等の設置状況等に関する情報を提供し、防火安全体制の確立を図る必要がある。
このことから、「防火対象物における消防用設備等の設置状況の表示方法及び公表方法」について、昭和四七年一一月二八日付け消防予第一九八号都道府県知事あて消防庁次長通知により御指導願っているところであるが、昭和四九年の消防法の大幅な改正もあって、全国的にはこれが広く実施されていない実状にある。
これらのことにかんがみ、「表示、公表制度」について再検討した結果、別添1「防火基準適合表示要綱」及び別添2「消防法違反公表要綱」により、「防火対象物にかかる表示、公表制度」の実施を図ることとしたので、左記事項に留意のうえ、貴管下市町村に対しても示達し、よろしく御指導願いたい。
なお、本通知により、昭和四七年一一月二八日付け消防予第一九八号、都道府県知事あて消防庁次長通知については、これを廃止するので、この旨承知願いたい。
記
1 表示については、川治プリンスホテルの火災事故にかんがみ、当面、旅館、ホテル等(消防法施行令別表第一(五)項イ)について、昭和五六年度から実施するものとする。
2 1に掲げる防火対象物のほか、別添1「防火基準適合表示要綱」2の「表示対象物」については、市町村の実状に応じ適宜選択を行うことができるものであること。
なお、対象物の規模等に応じ、別添1「防火基準適合表示要綱」3の「表示基準」の項目を追加することができるものであること。
3 表示を行うための立入検査は、努めて一定期間内に行い、「表示基準」に適合する防火対象物に対しては、一定時期に「表示マーク」を交付することができるように配慮すること。
4 別記「表示基準」のうち、建築構造等の判定については、特定行政庁に意見を求める等して、適確な判断を行うこととされたいこと。
なお、このことについては、建設省とも調整済であるので、念のため申し添える。
5 防火対象物の関係者等に対して、この「防火対象物にかかる表示、公表制度」の趣旨について、十分周知の徹底を図られたいこと。
|
|
|
|
別添1 防火基準適合表示要綱
昭和五六年五月一五日制定
平成二年八月二九日改正
1 表示の目的
旅館、ホテル等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全体制の重要性にかんがみ、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等を促進するとともに、その情報を住民に公開するため、防火上一定の基準に適合している防火対象物について、その旨の「表示」を行うものとする。
2 表示対象物
防火対象物が防火上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、消防法施行令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、及び(十六)項イに掲げる防火対象物で次の(一)及び(二)に該当するものとする。
(1) 消防法第八条の適用があるもの
(2) 防火対象物の階数が三以上のもの
3 表示基準
表示の基準は、別記のとおりとする。
4 表示マークの交付
(1) 消防長又は消防署長は、表示のための立入調査を行い、防火対象物における防火管理の状況、消防用設備等の設置の状況等について「表示基準」により審査し、当該基準に適合していると認める防火対象物の関係者に対してその旨を文書により通知するとともに「表示マーク」を交付するものとする。
(2) 立入調査を行った後において、所要の改善が行われた防火対象物については、その時期に表示マークを交付するものとする。
(3) 「表示マーク」の有効期間は、原則として1年とする。
(4) 2年以上継続して表示基準に適合していると認められる防火対象物については、その旨を表示する「適継続章」を貼付した表示マークを交付するものとする。
この場合、貼付する適継続章の枚数は、表示基準に適合していると認められる期間に応じて、次表に定めるところによること。
(5) 表示マーク及び適継続章は別図のとおりとする。
5 表示マークの返還
(1) 消防長又は消防署長は、有効期間中であっても次の各号のいずれかに該当する防火対象物の関係者については、表示マークを返還させるものとする。
1) 火災が発生した防火対象物(出火原因又は出火時の対応について関係者の責に帰すべき事由がないと認められるものを除く。)
2) 立入検査等によって表示基準に適合しないことが明らかとなった防火対象物
3) 1)及び2)によるほか、消防法令違反の指摘を受け、かつ当該指摘事項について何らの是正措置がとられない防火対象物
(2) (1)2)の場合において、一回の立入検査等によっては判定基準への適合状態の維持の適否について判断を行うことが困難である場合は、再度立入検査等を行い、不適合の状態が確認されたときは表示マークを返還させるものとする。
(3) 表示マークを返還させる際には、その理由を附記した文書により防火対象物の関係者に通知するものとする。
6 表示マークの再交付
5の規定により表示マークを返還させた防火対象物において、その後の立入検査等によって所要の是正措置がとられたと認められ、かつ、違反が繰り返されるおそれがないと判断される場合には、表示マークを再交付するものとする。なお、この判断に際しては、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。
|
|
|
|
別記 表示基準 第1 点検項目
表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目のうち該当する項目とし、第2に示す「判定基準」により審査し適合するかどうかを判定するものとする。
(注) 該当の有無欄は、有無のいずれかを○で囲むとともに、該当有については、判定欄の適・不適のいずれかを○で囲むこと。
第2 判定基準
1 防火管理等
次に掲げる事項に適合していることを確認するものとする。
(1) 防火管理者の選任及び届出がされていること。
(2) 消防計画の作成及び届出がされていること。
(3) 避難施設等の自主チェック体制が適正に機能していること。
(4) 消防計画に基づく消火訓練及び避難訓練を年二回以上行っていること。
(5) 共同防火管理義務対象物にあっては、共同防火管理協議事項の作成及び届出がされていること。
(6) 次に掲げる事項その他防火・避難施設等について重大な違反がないこと。
1) 防火区画の防火戸の閉鎖障害
2) 階段・廊下・出入口等の避難障害
3) 消防用設備等の電源しゃ断
4) 消防用設備等の音響警報装置の装置の停止
(7) 消防長又は消防署長が指定した場所における裸火の使用は、使用承認を受け、かつ、使用承認の条件に適合していること。
(8) 防災対象物品は、防炎性能を有しているものが使用されていること。
(9) 消防法第一七条の三の三に基づく定期点検及び報告が行われていること。
(10) 防火対象物の用途ごとに示されている防火管理体制指導マニュアルによる検証に適合していること。
2 消防用設備等
消防法令上必要な消防用設備等が設置され、それぞれ次に掲げる事項に適合していることを確認するものとする。
(1) 消火器
1) 設置数に不足がないこと。
2) 消火器の種別が設置場所に適応したものであること。
3) 消火器の底部等に破損がないこと。
(2) 屋内(外)消火栓設備
1) 未警戒区域、非常電源の未設置及びホース、ノズルの未設置がないこと。
2) 起動装置の機能が適正であること(遠隔操作により確認する。)。
3) 加圧送水装置の機能が適正であること(定格試験により確認する。)。
4) 自家発電設備の起動が適正であること。
(3) スプリナクラー設備
1) 未警戒区域及び非常電源の未設置がないこと。
2) 起動装置の機能が適正であること(末端試験弁を操作して確認する。)。
3) 加圧送水機能が適正であること(定格試験により確認する。)。
4) 流水検知装置の機能が適正であること(警報装置の作動を確認する。)。
5) 自家発電設備の起動が適正であること。
6) ヘッドの破損及び送水口の破損・変形がないこと。
7) 呼水槽の水量が適正であること。
(4) 自動火災報知設備
1) 未警戒区域がないこと。
2) 火災表示、作動試験及び回路道通試験結果が良好であること。
3) 非常電源(予備電源)の自動切替が適正であること。
4) 音響装置の鳴動が適正であること。
(5) 漏電火災警報器
1) 未設置がないこと。
2) 音響装置の鳴動が適正であること(試験ボタンを操作して確認をする。)。
(6) 非常ベル、自動式サイレン
1) 未設置がないこと。
2) 非常電源の自動切替が適正であること。
3) 音響装置の鳴動が適正であること。
(7) 放送設備
1) スピーカーの未設置がないこと。
2) 操作装置等の機能が適正であること(放送試験により確認する。)。
3) 起動装置の機能が適正であること。
4) 非常電源の自動切替が適正であること。
(8) 避難器具
1) 設置数が適正であること。
2) 設置位置及び種類が適正であること。
(9) 誘導灯
1) 未設置がないこと。
2) 設置位置が適正であること。
3) 正常に点灯していること。
4) 正常電源の自動切替が適正であること。
3 危険物施設等
次に掲げる事項に適合していることを確認するものとする。
(1) 設置及び変更について許可を受けていること。
(2) 保安距離及び保有空地が確保されていること。
(3) 種類及び数量の変更は、届出がされていること。
(4) 消火設備が設置されており、機能不良がないこと。
(5) タンク、配管等の破損及び油もれがないこと。
(6) 壁、床及び防火戸の破損がないこと。
(7) 保安監督者の選任及び届出がされていること。
(8) 危険物取扱者以外の者の危険物の取扱いが行われていないこと(甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いのある場合を除く。)。
(9) 消防法第一四条の三の二に基づく定期点検が行われていること。
4 少量危険物、指定可燃物
火災予防条例に基づき、消防長又は消防署長に届出がされていることを確認すること。
5 火気の使用設備・器具
次に掲げる事項に適合していることを確認するものとする。
(1) 火災予防条例に基づき消防長又は消防署長に届出がされていること。
(2) 機器、配管に破損、亀裂及び燃料もれがないこと。
(3) 燃料タンク(LPG容器を含む。)の位置、構造及び保有距離が適正であり、破損、亀裂、燃料漏れがないこと。
(4) 煙突又は排気筒が設置され、離隔距離及び貫通部の防水措置が適正で、かつ、破損、亀裂がないこと。
6 電気設備
次に掲げる事項に適合していることを確認するものとする。
(1) 変電設備、発電設備及び蓄電池設備
1) 火災予防条例に基づき消防長又は消防署長に届出がされていること。
2) 設置場所の壁、天井、床及び防火戸の構造が適正であること。
(2) 配分電盤の開閉器及び配線用しゃ断器等
1) 絶縁抵抗値が適正であること。
2) 過熱、損傷がないこと。
7 建築構造等
次に掲げる事項に適合していることを確認するものとする。
なお、必要に応じて、特定行政庁の意見を聞くものとする。
(1) 建築構造等
主要構造部の構造不適がないこと。
(2) 防火区画
竪穴区画が設けられ、当該壁、床及び防火戸の構造が適正で、かつ、破損等がないこと。
(3) 階段
必要な数の直通階段、避難階段及び特別避難階段が設置され、その構造が適正であること。
|
|
|
|
別図
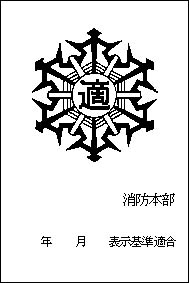
表示マーク

適継続章
|
|
|
|
別添2 消防法違反公表要綱
1 公表の目的
消防法に基づく措置命令違反の防火対象物についての情報を住民に公開することにより、住民の防火安全に対する認識を高めるとともに、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置等を促進するため「公表」を行うものとする。
2 公表対象物
消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物とする。
3 公表基準
防火管理、消防用設備等が消防法令に違反していること又は火災が発生したならば人命に対する危険度が高いと認められること等により、消防法に基づき期限を付した措置命令を発し、当該命令に違反して期限内に何らの必要な措置も講じない防火対象物について「公表」を行うものとする。
4 公表内容
(1) 防火対象物の所在地及び名称
(2) 違反内容
5 公表方法
4の内容について報道機関に公表するとともに、公報紙等に掲載して「公表」を行うものとする。
|
|
|
|
別添2 防火対象物にかかる表示、公表制度の運用について
消防予第一一三号
昭和五六年五月一九日
消防庁予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて通知
旅館、ホテル等に係る防火安全の確保については、種々御指導願っているところであるが、昭和五六年五月一五日付け消防予第一一一号、各都道府県知事あて消防庁次長通知の実施に当っての細目は、次により運用することとした。
このことから、貴職におかれては、左記事項に十分留意されるとともに、貴管下市町村に対しその旨を示達され、よろしく御指導願いたい。
記
1 昭和五六年度における表示制度の実施については、秋の行楽シーズンまでに、「表示マーク」の交付及び表示が完了すること。なお、昭和五六年一〇月末日現在における表示制度の実施状況等について、別紙様式1により報告されたいこと。
2 既存防火対象物で、立入調査の際、現に増築又は模様替えを行っている防火対象物については、増築又は模様替えを行っている部分を除いた部分について判定を行うこと。なお、当該増築又は模様替えが終了した後、増築又は模様替えを行った部分を含めた防火対象物全体について再度判定を行うこと。
3 判定基準に基づき判定するに当っては、当該防火対象物について消防法施行令第三二条の規定を適用している点検項目がある場合には、その適用があるものとして判定すること。
4 点検項目のうち建築構造等に関する項目について、判定基準に基づき判定するに際しては、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和四四年政令第八号)による改正後の建築基準法施行令の規定(関係条文については、別添資料1を参照。)に基づき、判定すること。なお、建築物防災対策要綱(昭和五四年三月二七日付け建設省住指発第五八号特定行政庁あて建設事務次官通知、別添資料2を参照。)に定める措置が講ぜられている防火対象物についても、判定基準に適合しているものとして取扱うこと。
また、これらの判定にあたっては必要に応じて特定行政庁に意見を求める等して判断されたいこと。
5 防火対象物が判定基準に適合しなくなった場合のほか、立入検査の結果、判定基準に掲げる事項以外の事項でも、消防法令違反の指摘を受け、かつ、当該指摘事項について何らの是正措置が執られていない防火対象物については「表示マーク」を返還させるものとしているが、これは立入検査の結果、消防法違反があれば直に「表示マーク」を返還させる趣旨ではなく、その返還を放置すれば、火災の発生、人命の損傷を生ずる危険性が高い事項について消防機関として所要の指示を行ったにもかかわらず、何らの是正措置を講じない場合に、「表示マーク」を返還させるよう運用すること。
6 「表示マーク」の交付に際しては、別紙様式2「表示マークの交付書」を発行するとともに、「表示マーク交付整理簿」を備え付け、「表示マーク」の交付に関する必要事項を記録すること。
7 立入調査を行った結果、点検項目に違反していることが判明したときは、当該違反事項の是正について指導することはもとより、関係者が「表示マーク」の交付を受けるために講ずべき措置を具体的に指示するものとすること。
8 「表示マーク」は、財団法人全国消防協会があっせんを行うこととしており、「表示マーク」のあっせんの申込方法等については、別途同協会より通知される予定であること。
9 「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について、(昭和五六年二月一〇付け消防予第三五号各都道府県消防主管部長あて消防庁予防救急課長通知)の2に基づく「旅行関係者からの照会に対する回答書」の記載事項については、要綱の点検項目について行うこと。
|
|
|
|
別紙様式 〔略〕 |
|
|
| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |