平成17年度観光の状況
第5章 魅力ある観光地の形成
第3節 文化遺産の保存と観光への活用
3 文化財・歴史的風土・文化遺産の観光への活用
地域伝統芸能等を活用し、地域の特色を生かした観光の振興を図るため、平成17年10月14日から3日間にわたり、山形県酒田市・鶴岡市・庄内町において開催された「第13回地域伝統芸能全国フェスティバル」について後援を行った。
国民共有の財産であり、地域の歴史的・文化的シンボルである史跡等については、城の石垣や古墳石室の修理といった保存のための整備、建物復元・遺構の露出展示やガイダンス施設の設置といった活用のための整備を行い、その魅力を高めることで、地域の観光資源として活用されている。
また、我が国の歴史を理解する上で極めて重要な街道、水路などのうち往時のたたずまいを残しているものを「歴史の道」として選び、それに沿う地域を一体のものとして保存・整備し、活用を図っている。
「伝統的集落における歴史的環境整備を中心とした地域活性化方策の調査・検討報告書」では、約1,000地区が保存の望まれる地区としてリストアップされた。
この調査によって歴史的な価値が明らかにされた地区については、文化財保護法に基づき、市町村が行う伝統的建造物群保存地区の決定やその保存等に関し指導・助言を行うとともに、その中から重要伝統的建造物群保存地区の選定を積極的に進めており(平成17年末では73地区、図5‐3‐1)、市町村が行う事業に対して助成措置が講じられ、地区内の整備が進められている。
図5-3-1 重要伝統的建造物群保存地区 一覧
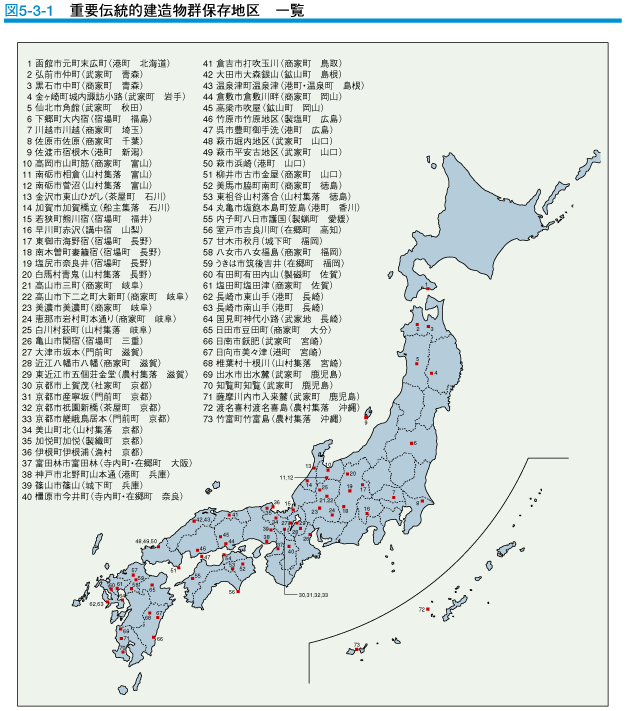
重要伝統的建造物群保存地区では、公開活用施設の見学等を通した学習と交流が図られ、また、地元住民による個性的なまちづくりが進められるなど、歴史的集落・街並みの保存が地域づくりに生かされている。
さらに、文化財建造物や歴史的集落・街並みを保存・活用しつつ、より成熟した観光を促進するための方策検討の基礎的調査として「国際観光に資する地域資源活性化方策調査」に基づき、文化財建造物等の保存・活用施策の展開を目指し、歴史的集落・街並みの保存事業と観光とのより成熟した連携を推進するための検討を行った。
| (4) 「わたしの旅~日本の歴史と文化をたずねて~2005」と旅行商品化に向けた取組 |
「旅」を通じて日本の歴史と文化をたずねる「わたしの旅」プランを広く募集した。
786プランの応募の中から、提案者の思いが詰まった魅力的な105プランを100選として選定し、さらにその中から、「大賞」を1プラン、「特別賞」を9プラン選定した。
今回選定された105プランを広く活用してもらうよう、ホームページによる情報提供や都道府県等に対する周知等の広報活動を行ってきている。
また、「わたしの旅」に係るパンフレットを作成し、その意義や具体的ルートについて広く周知を図るとともに、関係省庁、旅行業団体等からなる検討委員会を開催し、「わたしの旅」応募プランを生かした旅行振興方策を検討しているところである。
外国人旅行者の日本への観光交流を単に一回限りの異文化との出会いにとどめることなく、より深い相互理解につなげていくためには、我々日本人の日本の歴史や文化への理解を深めるとともに、外国人の視点をも取り入れて文化観光資源を発掘し、それらを多くの旅行者に、好みに応じて触れ・体験できるようにすることが重要であることから、こうした知的欲求を満たすことを目的とする観光を「文化観光」と位置付け、その意義や文化観光の普及方策等について検討を行うため「文化観光懇談会」(座長:赤坂憲雄氏-東北芸術工科大学教授-)を開催し、平成17年7月より検討を進めているところである。
その一環として、県及び市町村観光担当課、観光協会の職員、ボランティアガイド等広く歴史や文化に携わる方々を対象とした『文化観光の集い』を開催した。
また、異文化で育った人々に、より深く日本文化を伝える糸口や方法を探るため、河合隼雄文化庁長官等がガイドとなり、外国人を対象とした「日本の庭園から日本人の美意識・自然観を学ぶモデルツアー」を14の国・地域から20名の参加を得て実施した。
▲上賀茂神社宮司説明風景
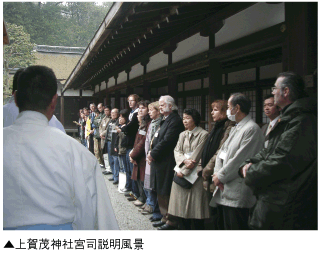
|
|