■ 1 宿泊産業の現状分析
宿泊産業全体の市場規模は、バブル経済期に急速に拡大したことを受けて1991年には4兆9,440億円にまで達したものの、その後は主に最も大きな内訳を占める旅館の衰退を反映して長期的な縮小傾向にあり、2004年には1991年に比べて33%減の3兆3,130億円にまで減少している。
▼宿泊産業の市場規模

▼主要ホテルの客室利用率
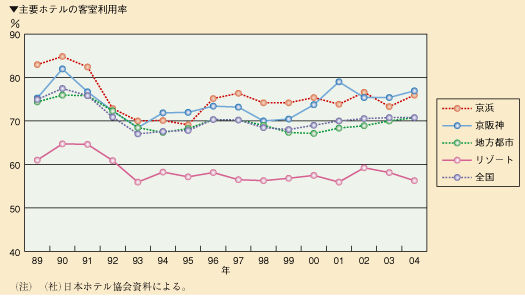
ホテル業の経営状況は、バブル経済後の1990年代前半には落ち込んだものの、その後は徐々に回復してきている。主要ホテルの客室利用率の推移をみると、バブル経済期の1990年には首都圏で84.9%、全国平均でも77.6%の高水準を記録したが、1993年には首都圏で69.9%、全国平均で67.1%にまで下落した。しかしながら、その後、客室利用率は徐々に回復し、2004年には首都圏で76.2%、全国平均で71.8%にまで改善した。
これに対し、旅館業の経営状況は、バブル経済後の長期的な低落傾向に歯止めがかからない状況にある。主要旅館の定員稼働率は、1991年の48.3%からほぼ一貫して減少を続けており、2003年には39.8%にまで低下した。特に、客室数100室以上の大旅館において、定員稼働率の低下が著しい。
▼主要旅館の定員稼働率
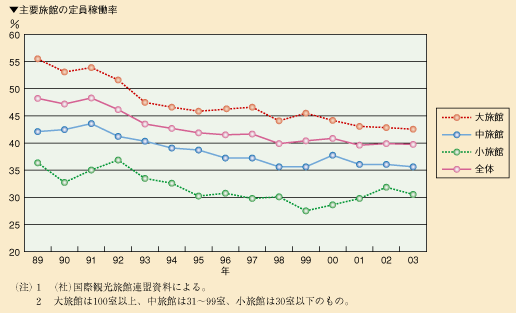
■ 2 近年のホテル業界の動向
2005年から2008年頃にかけて、世界的に展開し強力なブランド力を誇る外資系のホテルチェーンが相次いで都心の大規模再開発地に進出する動きがあり、客室数が大きく増加することから、競争の激化が見込まれ、関係者の間でホテル業界の2007年問題と呼ばれている。
2005年頃から進出しているこれらの外資系ホテルに特徴的なのは、マネジメント契約により運営、ブランド、マーケティングの各面で委託を受ける形態のみにとどまらず、不動産の所有者と賃貸借契約を締結し、経営(損益)のリスクについても外資系ホテル会社が関与する形態も見られるなど、運営形態が多様化している点である。
このように外資系ホテルチェーンによる日本進出が近年相次いでいる背景には、基本的に日本のホテル市場が拡大傾向にあること、バブル経済後の地価下落と再開発の進展により都心の一等地への進出のハードルが低くなったことが挙げられよう。また、これに加え、日本から海外への旅行客が近年増加していることから、日本に進出することによって日本でのブランド認知度が向上すれば、世界各地に立地する自社チェーンホテルへの日本からの顧客の獲得につながるという利点もある。
外資系ホテルの進出を受けて、これを迎え撃つ日本の既存シティホテルにおいても、施設のリノベーションのための投資を行う動きや、不動産の所有とホテル事業の運営を分離することにより経営の効率化を図る動きが目立っている。今後、既存のシティホテルは外資系のラグジュアリーホテルとの競争の中で顧客を継続的に獲得できるような価値あるサービスの提供を目指す必要があると言えよう。
■ 3 近年の旅館業界の動向
旅館業については、先にみたように長期的な市場規模の縮小が続いている。
このような中で、1990年代に入って消費者の旅行需要が個人や小規模グループでの旅行、滞在型の旅行にシフトしており、それまで主流であった宴会目的の団体客による旅行需要は減少している。しかしながら、多くの旅館はバブル経済期に宴会目的の団体旅行需要に対応して、1室当たりの定員が多い客室の増設・増築や大広間、宴会場等の設備整備に投資を行ったことから、過重な債務が負担となって更なる資金の借入れが困難となり、新たな旅行需要に対応した設備投資を行うことができず、その一方で施設が老朽化し、また大型の客室に個人客を宿泊させることにより定員稼働率が低下する結果、さらに経営が悪化するという悪循環に陥っている状況にある。
このような状況から、経営が破綻し倒産する旅館も相次いでおり、帝国データバンクによれば、2000年以降、旅館・ホテル業者の倒産件数は毎年100件を超える高水準で推移している。
▼旅館・ホテル業者の倒産推移

こうした中で、経営破綻した旅館を民間のスポンサーが買い取って、新たな資金を投下して顧客のニーズに応じた設備整備やマーケティング、組織改革等に取り組むことにより、旅館の再生に成功する事例が注目されている。
その一方で、小型旅館の中には、洗練された隠れ宿のコンセプトに沿って客室に併設した露天風呂や貸切り露天風呂を備え、旬の地料理を提供するなどにより、日常を離れた高級感を求める女性客、カップル客や滞在型の癒しを求める家族旅行客、個人客等を獲得し、堅調な営業成績を上げているものも見られる。
また、近年、インターネットの普及により小規模な宿泊施設の販売チャンネルが生まれたことを背景として、従来のホテルや旅館の区分には当てはまらない、ニッチ市場に特化した個性的な宿泊施設の形態が出現する動きがあり注目される。
■ 4 宿泊産業の課題と今後の方向性
ホテル業界と旅館業界に共通して言えることは、生活水準の改善や海外旅行経験の増加等により人々の宿泊旅行に対する要求水準が高くなっている状況の中で、顧客を満足させ、さらには満足を超えた感動を与えることにより、顧客を継続的に獲得していく必要があるということである。このためには、市場におけるポジショニング及びビジョンを確立し、これに基づき戦略的に、マーケティング、組織・人材管理、施設のリノベーションのための投資等を行っていくことが重要である。
ホテル業界においては、ラグジュアリーホテルと宿泊特化型ホテルへの二極化の進展という市場環境を踏まえると、その中間に位置付けられる既存のシティホテルは、両者に顧客を奪われることにより埋没してしまうことが懸念される。
しかしながら、このような市場環境の中でも、自らの施設の市場におけるポジショニングを明確に設定し、周辺の競合施設と差別化できるようなアイデンティティの確立と的確なマーケティング活動に努めていけば、ホテル業の市場が全体としては拡大基調にあることもあり、持続的に利益を上げていくことは困難ではないだろう。
一方、旅館業界においては、市場規模の縮小傾向や近年の団体旅行から個人旅行への旅行需要の大きなシフトを踏まえて、新たな個人客や小規模グループ客を中心に顧客ターゲットの見直しを行うとともに、それに応じて施設のコンセプトを明確化し、適切なマーケティングや施設改修への投資、組織運営等を行っていくことが求められている。もっとも、多くの旅館では老朽化した施設を個人客仕様に改装するための追加的な資金借入れが困難な状況にあることから、既存の施設スペックを前提としつつ、市場の変化に対応したコンセプトをどのように実施に移していくのか、厳しい選択をせまられているのが実情である。
今後の国内旅行需要の主流となっていくと見込まれる個人客やグループ旅行客、滞在型の宿泊客をターゲットとしていく場合には、食事について地産地消のメニューづくりを行うことや、いわゆる泊食分離を行っていくことも課題となる。
また、旅館の再生に取り組むに当たっては、同じ観光地内の旅館、観光施設、土産販売店等の関係者が連携して観光地の改善を行うことにより、観光地全体としての誘客に大きな効果を上げる可能性があることも考慮する必要がある。
最後に、観光立国の実現に向けたビジット・ジャパン・キャンペーン等の取組により、今後さらに増加することが見込まれる外国人旅行者を受け入れるための体制整備も、ホテル業及び旅館業に共通する重要な課題である。具体的には、韓国、台湾、中国をはじめとするアジア諸国や、欧米からの旅行者に対応して、各国の言語による予約サイトの整備やマーケティング活動を行うとともに、外国人宿泊客を適切に接遇できるよう従業員の研修・スキルアップを行うことや、宿泊施設内において各国の言語によるTV放送の視聴を可能にすること、また各国の新聞を備え置くこと等も必要であろう。
|
|