平成19年度観光の状況
第II部 平成18年度の観光の状況及び施策
第4章 国際観光の振興
第1節 外国人観光旅客の来訪の促進
1)ビジット・ジャパン・キャンペーンの概要
我が国の観光魅力は、外国人の共感を呼び起こす「ソフトパワー」であり、グローバリゼーションの下、一人一人の交流を通じ相互理解の促進を図ることは、国家間の外交を補完し、安全保障に大きく貢献するものである。また、我が国の少子高齢化に伴う人口減少や周辺諸国の経済発展に対応して、観光交流を促進し、地域活性化に貢献するとともに、外国人観光旅客の受入れに伴う国内ビジネスを後押ししていく必要がある。
これを踏まえ、平成15年より、「YOKOSO!JAPAN」のロゴ・キャッチフレーズの下、ビジット・ジャパン・キャンペーンの取組を官民一体で推進してきており、平成15年に521万人であった訪日外国人旅行者数は、平成19年には835万人と過去最高を記録している。
▲「YOKOSO!JAPAN」ロゴ

2)ビジット・ジャパン・キャンペーンの実施体制
平成14年6月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」を受け同年12月に策定された「グローバル観光戦略」に基づき、ビジット・ジャパン・キャンペーンの実施体制は、官民一体となった体制を整備している。
具体的には、国土交通大臣を本部長とし、旅行業者、運送事業者、マスコミ等を始めとする47の民間企業・団体のほか、国・地方自治体からなるビジット・ジャパン・キャンペーン実施本部を設置し、その下に執行委員会及び事務局を置いて取り組んできたところである。
また、海外においては、在外公館の長(大使や総領事)を会長とし、現地における関係団体・企業等の代表で構成されるビジット・ジャパン・キャンペーン現地推進会を設置している。
3)ビジット・ジャパン・キャンペーン事業
(独)国際観光振興機構(JNTO)及びビジット・ジャパン・キャンペーン実施本部事務局の協力の下、日本の観光魅力を海外に発信するとともに、魅力的な訪日旅行商品の造成等を行うビジット・ジャパン・キャンペーン事業を実施している。
具体的には、日本を訪れる外国人旅行者の多い12か国・地域(韓国、台湾、中国、香港、タイ、シンガポール、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア)を重点市場として定めるとともに、各市場の特性を踏まえ、重点市場を対象として、外国人旅行者の訪日促進のための事業を実施している。
また、平成19年度より、重点市場に次ぐ3か国(インド、ロシア、マレーシア)を有望新興市場として定め、効果的なプロモーションに取り組むことができるよう戦略的な市場調査を開始している。
外国人旅行者の訪日促進のための事業としては、主に、以下の事業を実施している。
1)旅行会社招請事業
対象国の旅行会社等を日本に招請し、国内の観光地を視察するとともに、国内の旅行会社、宿泊業者等との商談会や旅行説明会を開催することにより、日本向けの旅行商品の造成を支援する事業。
2)ツアー共同広告事業
対象国の旅行会社等と共同で訪日ツアー商品の広告を行う事業。
3)メディア招請事業
対象国の記者、テレビクルー等を招請することにより、日本の観光資源等を紹介する記事やテレビ番組の作成等を支援する事業。
▲道後温泉を取材する台湾のTVクルー

4)広告宣伝事業
新聞、テレビ等に広告宣伝を展開することにより、日本の観光魅力を紹介し、観光目的地としての日本の認知度を高める事業。
5)情報発信事業
ホームページを通じて、日本の基本的な観光情報、日本文化、トレンド等の情報発信を充実する事業。
6)旅行博出展等事業
対象国において行われる国際旅行博覧会・展示会等への出展や、訪日セミナーの開催等により、観光目的地としての日本や、訪日ツアーへの関心を高め、需要を喚起させる事業(表II-4-1-1)。
表II-4-1-1ビジット・ジャパン・キャンペーンにより出展した主な旅行博
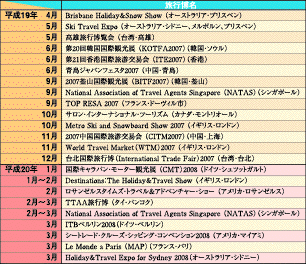
4)ビジット・ジャパン・キャンペーンにおける具体的な取組の例
1)YOKOSO!JAPAN トラベルマート
訪日旅行商品の造成を支援するため、海外の旅行会社、メディアを日本に招請し、国内の観光地を視察させるとともに、日本の旅行会社、宿泊業者等との情報交換やビジネス交渉等を行う大商談会「YOKOSO!JAPAN トラベルマート」を実施している。
平成19年4月に幕張メッセで行った「YOKOSO!JAPAN トラベルマート2007春」では、11か国より海外の旅行会社97名が日本を訪れ、日本の254の観光関係団体・企業との商談会を実施した。また、平成19年11月にパシフィコ横浜で行った「YOKOSO!JAPAN トラベルマート2007秋」では、28か国より海外の旅行会社、メディア264名が日本を訪れ、日本の337の観光関係団体・企業との商談会を実施した。
2)YOKOSO!JAPAN WEEKS
東アジアの旧正月前後の期間を対象に、訪日旅行促進の集中的キャンペーンを実施するとともに、国内において外国人観光客を受け入れ、おもてなしの心を醸成させるため、「YOKOSO!JAPAN WEEKS」として、国内外における集中的キャンペーンを実施している。
「YOKOSO!JAPAN WEEKS 2008」は平成20年1月20日から同年2月29日の期間で行われ、「ショッピング三昧」をテーマとして、外国人旅行者向けの割引やプレゼント等約180件の特典や、「日本を体験する旅」をテーマとして、約50件の外国人向けの体験活動メニューを用意した。そのほか、日本各地の観光地における外国人観光客を歓迎するためのイベントの実施、約800箇所の外国人向け簡易案内所「YOKOSO!JAPAN DESK」の設置等の取組も実施した。
▲YOKOSO!JAPAN WEEKSポスター

3)観光広報親善大使等の任命、活用
平成16年に「観光広報親善大使」として女優の木村佳乃さんを任命し、様々な機会を通じた日本の観光魅力のPRを行った。平成19年4月には冬柴国土交通大臣とともにインドを訪問し、平成19年が日印観光交流年であることを記念して開催された「日印観光交流年の夕べ」に出席し、日本の観光魅力のアピールに貢献した。
また、平成19年4月にはタイの女優のTik(ティック)さんを「ビジット・ジャパン・キャンペーンタイ親善大使」に、フィギュアスケート選手として活躍している浅田舞選手・浅田真央選手を「日加観光親善大使」に、台湾の女優・歌手・モデルの頼雅妍(ライ・メーガン)さんを「ビジット・ジャパン・キャンペーン台湾観光親善大使」に、平成19年5月には日韓両国で活躍する韓国人歌手のユンナさんを「ビジット・ジャパン・キャンペーン韓国観光親善大使」に、平成19年6月には香港の歌手・女優の薛凱(フィオナ・シッ)さんを「ビジット・ジャパン・キャンペーン香港観光親善大使」にそれぞれ任命し、各国における新聞、テレビ等の広告宣伝や、国際旅行博覧会・展示会等の出展等の機会において、日本の観光魅力のPRを行った。
4)YOKOSO!JAPAN大使
外国人旅行者の受入れ体制に関する仕組みの構築や外国人に対する日本の魅力の発信といった努力に公的評価を付与することにより、訪日促進の諸活動が広がることを期待し、一層の外国人旅行者の訪日を推進するため、他の関係者の手本となる優れた取組を行った者を「YOKOSO!JAPAN大使」として任命することとし、平成20年1月に第1弾として17名を決定した。この17名は「YOKOSO!JAPAN大使」選定委員会(座長:石森秀三北海道大学観光学高等研究センター長)において選定された。
今後も、順次任命し19年度から3ヵ年で100名を目途として選定を行っていくこととしている(図II-4-1-2)。
▲「YOKOSO!JAPAN 大使」任命式
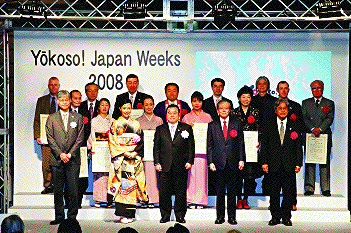
図II-4-1-2 「YOKOSO!JAPAN大使」の一覧
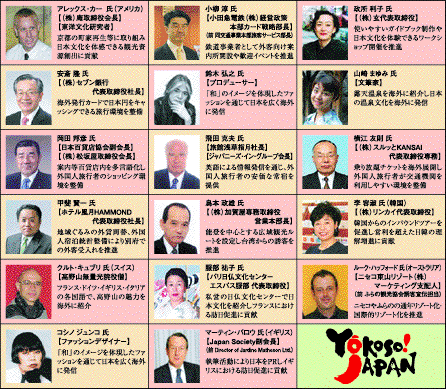
| (2) 北海道洞爺湖サミットを契機とした観光振興の取組 |
「観光立国推進戦略会議」は、先進各国首脳のみならず、各国政府関係者、報道関係者等が多数北海道を訪問する「北海道洞爺湖サミット」を、国内外に北海道及び日本の魅力を強力に情報発信する好機ととらえ、これを活用するため、平成19年11月に開催された「第11回観光立国推進戦略会議」において「北海道洞爺湖サミットを契機とした北海道・日本の魅力の世界への発信及び観光振興に関する提言」を取りまとめた。提言の中では、1)花を中心とする豊かな自然、海山の食、環境との共生等、北海道の地域特性を生かした北海道ブランドの確立を図ること、2)北海道における滞在・体験の満足度を高めるよう、画一的なサービスを脱し、サービスの多様化・高付加価値化やホスピタリティーの向上・充実を図ること、3)的確な情報発信を行うことにより、国内外における北海道観光の認知度向上を図ること、という三つの視点から確固たる北海道ブランドを構築し、こうした視点に沿った具体的施策を実施することが重要とされた。
| (3) 独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)による情報発信等 |
(独)国際観光振興機構(JNTO)においては、訪日外国人旅行者の多い国・地域に13の海外事務所を設置しており、在外公館をはじめ、現地の旅行業界、メディア、政府とのネットワークを駆使して、旅行市場情報の収集、我が国の観光魅力の広報・宣伝、現地旅行会社に対する訪日旅行商品の造成・販売支援、海外セールスを実施する日本の地方自治体・民間企業に対するコンサルティング等、多岐にわたる活動を行うとともに、ビジット・ジャパン・キャンペーンへの貢献を最大の使命として、活発な活動を展開し、訪日外国人旅行者の増大を図った(図II-4-1-3)。
図II-4-1-3 (独)国際観光振興機構の海外事務所(13箇所)
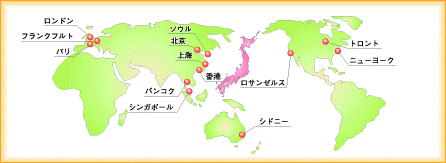
また、旅行目的地としての日本の認知度向上を図るとともに、訪日旅行者による旅行計画検討や各種予約等をサポートするため、7言語(英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、フランス語、ドイツ語、タイ語)による訪日旅行情報のポータルサイト(http://www.jnto.go.jp)の運営を行っており、情報発信に大きな効果を発揮した。
各地方運輸局等においては、地方自治体を始めとする地域が行う外国人旅行者の訪日促進のための取組と連携して、地域の観光魅力を海外に発信するとともに、地域への魅力的な訪日旅行商品の造成等を支援するビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業を実施している。
| (5) 大使・総領事公邸等を活用した観光プロモーション等の実施 |
大使・総領事館等在外公館においては、日本の魅力を発信する活動を実施し、観光客誘致のために積極的に取り組んだ。具体例として、在外公館長を会長とするビジット・ジャパン・キャンペーン現地推進委員会の開催、海外における観光展や見本市等への出展、観光をテーマとする講演会等を行った。
また、様々な文化事業を実施するとともに、現地マスメディア、ホームページを通じ、我が国の伝統及び現代文化、先端技術、美しい自然、地方の魅力等を総合的に紹介した。さらに、大使・総領事公邸、広報文化センター等において、地方公共団体等と連携して観光広報関連事業等を開催し、平成19年度は、在ニューヨーク日本国総領事館における埼玉県川越市の観光プロモーション・物産展、在フランス日本国大使公邸及び在アトランタ日本国総領事公邸における愛知県の中部国際空港プロモーション等を14件実施した。
通常、東京に在住している駐日各国大使等に地方を訪問する機会を提供することにより、我が国の多様な魅力を知ってもらい、その魅力を各国に発信してもらうことに努めた。
1)駐日各国大使の地方視察
年に一度、駐日各国大使を対象に、地方公共団体等地域の関係者と提携し、異なる地方の視察プログラムを実施している。視察時には、歴史的建造物を始め、地場産業、学生を含む地元住民との交流の場を設けるなど、広くその地方の特色に触れるよう努め、首都以外の地方独自の文化、伝統、産業、自然環境等我が国の多様性に富む魅力を知ってもらうよう取り組んでいる。平成19年度は11月7日から9日(2泊3日)の日程で和歌山県において実施した。
2)駐日外交官家族の一般家庭ホームステイ受入れ
年に一度、駐日の外交官家族を対象に、一般家庭でのホームステイにより、我が国の日常生活を体験するとともに、お互いの文化交流をするプログラムを実施している。同プログラム時だけではなく、終了後も受入れ家族との交流が続くなど、交流の輪が広がっていることが期待される。平成19年度は10月20日から21日(1泊2日)の日程で栃木県において実施した。
地域レベルの国際交流・国際協力を一層推進することを目的として、幅広く国際交流に携わる団体からの参加者を対象とした会議、自治体国際交流支援のためのレセプション、国際会議、国際情勢等各種情報の提供を積極的に実施した。
さらに、我が国の大使・総領事等が、一時帰国等の機会を利用して、任国・地域とゆかりのある我が国地方公共団体等を訪問し、地方公共団体等との意見交換を行い連携を強化した。平成19年度は、50件実施した。
芸術家、文化人等、文化に携わる者を、一定期間「文化交流使」に指名し、海外に派遣し、当該国所在の受入れ機関の協力を得つつ、日本文化に関する講演、講習や実演デモンストレーション等を行うなど、世界の人々の日本文化への理解の深化や、日本と外国の文化人のネットワークの形成・強化につながる活動を展開しており、今後も引き続き実施することとしている。
日本の文化について把握し、国内外の芸術団体や芸術系大学等に情報提供するなど、日本文化を総合的に発信するホームページの構築に向けて、発信情報の整備をしており、今後も引き続き実施することとしている。
また、在外公館や(独)国際交流基金による、公演、展示、映画祭といった文化交流事業を通じ、アニメや漫画といったポップカルチャーを含む日本の文化や社会、さらには日本人の価値観に対する理解を深め、日本への信頼へとつなげていくための努力を行っている。特に、各国との外交上の節目の年には、規模の大きい総合的な文化事業(周年記念事業)を政府関係機関や民間団体・企業等と連携して行い、重点的な交流を行うことで、より一層効果的な対日理解を目指している。平成19年は、「日中国交正常化35周年」を記念した「日中文化・スポーツ交流年」、「日印文化協定締結50周年」を記念した「日印交流年」等が行われた。
在外公館等で開催するレセプション等で、現地の要人やオピニオンリーダー等を対象に、日本からの高品質な日本食・日本食材を提供し、その魅力を伝える「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を中国、アメリカ等17か国において計23回実施するとともに、海外に在住し日本食・日本食材等の海外での紹介・普及等に多大に貢献してきた功労者に対して表彰を行った。
また、「日中国交正常化35周年」及び「日中文化・スポーツ交流年」の記念事業の一環として実施された「日中のお祭りin北京」において、ビジット・ジャパン・キャンペーンと連携して日本産米のPRを実施するとともに、台湾、マレーシア、シンガポールの旅行博における日本コーナーにおいて、日本食を紹介するパンフレットの配布やDVDの放映等を行った。
さらに、日本食のショールームである海外の日本食レストランの信頼度を高め、日本食の普及を通じて日本食材の輸出促進を図るため、平成19年7月に民間有志により、NPO法人日本食レストラン海外普及推進機構(JRO)が設立され、支部となる台北、上海、バンコク、ロンドン等において、日本食レストラン関係者のネットワークを築くとともに、それぞれの地域において、日本食レストランに関する情報を発信する普及啓発活動、料理人の調理技術・衛生知識の向上等を目指す教育研修活動、優良日本食レストランの推奨活動等の活動に対して支援を行っている。
また、ビジット・ジャパン・キャンペーンにおいても、日本食・日本食材等を始めとする観光魅力について、海外へ発信している。
▲日本食レストラン海外普及推進機構(JRO)ロンドン支部での日本食イベント

ポップカルチャーへの関心を日本そのものに対する理解、関心へとつなげていくために、在外公館及び(独)国際交流基金を通じた文化交流を促進している。ポップカルチャーを通じた文化外交の一環として、2007年5月には「国際漫画賞」を創設し、海外で漫画文化の普及に貢献する漫画家を顕彰した。
また、我が国メディア芸術の次代を担う優れたクリエイターを発掘・育成し、国内各地のメディア芸術拠点の活動の支援、拠点連携を図るとともに、平成20年2月6日~17日に「メディア芸術祭」(来場者数約44,000人)を開催し、優れたメディア芸術作品を国内外に積極的に発信した。
さらに、メディア芸術分野等において、諸外国の芸術家等とのワークショップを通じた人材育成やコンテンツの共同制作等を推進した。
今後も、こうした日本文化に対する関心及び理解を一層高めることとしている。
| (12) 和のコンテンツの情報発信及びネットワーク化 |
我が国への外客誘致を行う上で、特に、外国人富裕層(ラグジュアリー層)をターゲットとして誘致するビジネスモデルを構築するため、海外に対するプロモーションを強化していくこととした。
このため、フランス・カンヌで毎年開催される、高級・豪華旅行をテーマとした旅行博「インターナショナル・ラグジュアリー・トラベル・マーケット(ILTM)」に初めて日本ブースを出展した。オープニングセレモニーにおいては「ジャパンナイト」を開催し、世界中の富裕層向けの旅行業関係者、メディア関係者、出展者に向け、日本の仏閣、着物、伝統芸能、伝統工芸等「本物」の和のコンテンツの魅力を発信した。
NHKが実施するテレビ国際放送について、放送法改正により、番組制作等を専門の子会社に委託する制度を新たに設けるなど、外国人向けに特化した新放送の実施体制に関する制度整備を行った。
| 2 国内における交通、宿泊その他の観光旅行に要する費用に関する情報の提供 |
欧米を中心として、海外では日本は物価が高いというイメージがあり、訪日旅行を敬遠してしまう傾向があることから、このイメージを払拭するため、諸外国と我が国の物価を比較し、飲食店や宿泊施設等の価格の実態に係る情報を紹介する「AFFORDABLE JAPAN」パンフレットを作成し、様々な機会を通じて海外において配布している。
▲「AFFORDABLE JAPAN」パンフレット
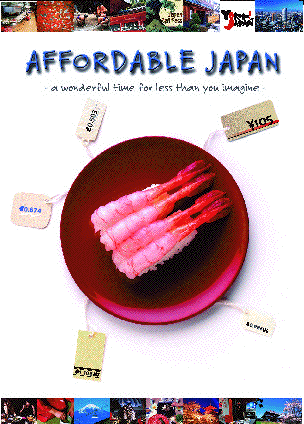
| (2) 公共交通事業者等による情報提供促進措置の促進 |
平成18年4月1日に施行された、「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(外客来訪促進法)」によって、特に多数の外国人観光客が利用する区間等については、公共交通事業者等(平成20年4月現在249事業者)に対して「情報提供促進実施計画」の作成、実施が義務付けられた。現在、公共交通事業者等によって、同計画に基づいた外国語等による「情報提供促進措置事業」が実施されているところであり、このうち一部の事業に対して支援を行った。
また、平成18年2月と3月に開かれた「外国人から見た観光まちづくり懇談会」における指摘を受け、平成19年度は、旭川空港等地方空港20箇所及び鉄道駅2箇所にて、外国人の視点から見た案内表示の使いやすさについて、留学生等の協力を得て、外国人による「ひとり歩き点検隊」を実施した(図II-4-1-4)。
図II-4-1-4 外国人による「ひとり歩き点検隊」実施箇所
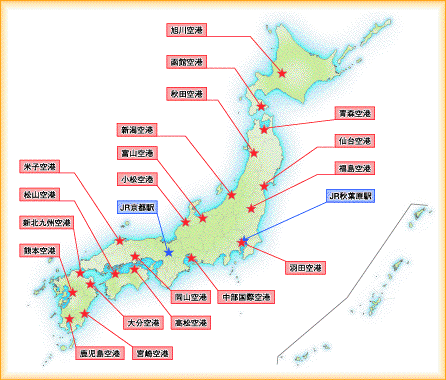
鉄軌道事業者においては、駅等における外国人旅行者等に対する情報提供については、「公共交通機関における外国語等による情報提供促進措置ガイドライン」に則した整備を行っており、出入口、のりば、きっぷ売り場等の基本情報について日本語に加え、英語、ピクトグラムによる案内表示を行った。また、特に首都圏等の外国人利用の多いエリアにおいては、これらに加え、韓国語、中国語の多言語化にも積極的に取り組んだ。
今後もこれらの情報提供促進措置を促進していくこととしている。
▲函館空港の「ひとり歩き点検隊」の様子

外国人観光旅行者の利用が見込まれるバスターミナルについては、外国人旅行者の利便を図るため外国語による案内表示等に関する計画策定を義務付け、また、それ以外の策定が義務付けられていないバスターミナルについても案内表示の対応を促進した。
今後も引き続き、案内表示等に関する計画策定等に基づき、案内表示対応を推進していく
| 3 国際会議その他の国際的な規模で開催される行事の誘致の促進 |
1)国際会議等の誘致・開催をめぐる動き
国際会議を我が国に誘致し、我が国において国際会議を開催することは、我が国の情報発信力の強化、地域活性化に加え、国際交流の拡大、観光立国の推進にも資する重要な取組である。
一方、我が国における国際会議の開催件数について見ると、平成15年には247件とアジアで首位であったが、平成18年には166件と減少し、シンガポール、中国、韓国に次いでアジアで4位に後退している。これは、近隣のアジア諸国においては、国際会議の開催を主要産業として位置付け、多額の予算により、誘致活動や開催に対して積極的に支援するとともに、参加者に対する様々な便宜供与、誘致・運営に携わる人材の育成強化等に取り組んでいる一方、我が国では、誘致主体による取組にとどまり、国を挙げた推進体制が整っておらず立ち遅れており、相対的に競争力を失っていることが要因と考えられる。
こうした状況を踏まえ、平成18年9月の安倍前内閣総理大臣の所信表明演説及び平成19年6月に閣議決定された「観光立国推進基本計画」において、「今後5年以内に我が国における国際会議の開催件数を5割以上伸ばし、アジアにおける最大の開催国を目指す」との目標が掲げられたところである。
これを受け、平成19年5月、全府省庁がメンバーとなる国際会議開催・誘致拡大局長級会合において、国際会議等の誘致・開催推進のための基本戦略として、「国際会議の開催・誘致推進による国際交流拡大プログラム」が取りまとめられ、本プログラムに沿って、国を挙げた誘致・開催推進体制の整備、誘致活動や開催・受入れに対する支援等を行うこととなった。
また、平成19年6月には官邸において「国際会議開催・誘致推進連絡会議」が開催され、経済界、学界、地方自治体等に対する働きかけが行われた。
なお、沖縄での国際会議等の開催については、「国際会議等各種会議の沖縄開催の推進について」(平成12年6月20日閣議了解)を踏まえ、これまでも政府として推進してきたところであるが、平成20年6月に「北海道洞爺湖サミット」に先立ち、沖縄において地球規模の課題解決に向けた科学技術の強化等について議論するため、初の「G8科学技術大臣会合」が開催されることとなった。
2)国際会議等の誘致・開催推進の具体的な取組
国際会議の誘致・開催を推進するため、主に、以下の取組を実施した。
1)国際会議の誘致・開催に係る調査
我が国における国際会議の誘致・開催に係る動向、ニーズを把握し、誘致主体のニーズに応じた支援を行うため、(独)国際観光振興機構(JNTO)とも連携し、国際会議の誘致・開催に係る調査を実施した。
2)一元的なコンサルティング窓口
「国際会議の開催・誘致推進による国際交流拡大プログラム」を踏まえ、平成19年5月より国際会議の誘致・開催のための一元的なコンサルティング窓口を国土交通省総合政策局国際観光課に設置した。
3)国際会議観光都市
「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(コンベンション法)」に基づき、国際会議の誘致に熱心な市町村を国際会議観光都市として認定し、(独)国際観光振興機構(JNTO)等による支援を行っている。
平成19年8月には、さいたま市が新たに「国際会議観光都市」に認定され、国際会議観光都市は51都市となった。
4)国際ミーティング・エキスポ(IME)
平成19年12月、東京国際フォーラムにおいて、我が国で唯一の国際コンベンション見本市である「国際ミーティング・エキスポ(IME)2007」を開催した。同見本市においては、国内外の国際会議関係団体・企業、地方自治体、メディア等が一堂に会し、情報交換や商談会等が行われた。
5)国際会議の誘致支援
国土交通省のコンサルティング窓口を通じて、関係省庁とも連携し、内閣総理大臣等による招請状の発出、在外公館による国際会議の開催国決定権者に対する働きかけ等の支援を実施した。また、海外において行われる国際コンベンション見本市への出展や、国際会議の開催国決定権者の我が国への招請を通じて、国際会議の開催適地としての日本の魅力をPRした(表II-4-1-5)。
表II-4-1-5 誘致に成功した国際会議の例
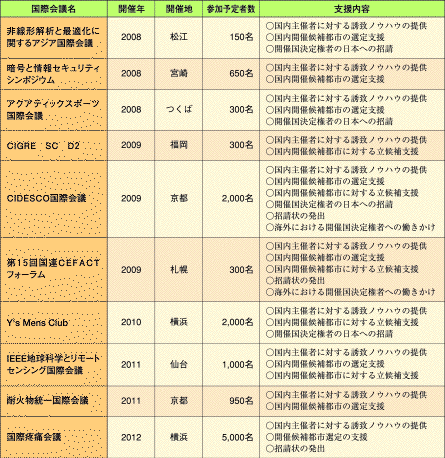
6)国際会議の開催支援
特定公益増進法人である(独)国際観光振興機構(JNTO)において、寄附金・交付金制度を通じた国際会議の開催支援を行うとともに、円滑な開催のためのノウハウの提供等の支援を実施した。
内外の芸術家、文化人等を招へいし、座談会・講演・鼎談等の形式により世界の文化芸術の最新の諸相や動向について語り合うことを目的として平成15年から開催している。
平成19年度は11月10日から「文化の多様性」を共通テーマに関西、東京、九州で5つのセッションを行い、世界に向け文化芸術のメッセージを強く発信しており、今後も引き続き実施することとしている。
| 4 外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善、通訳案内サービスの向上その他の外国人観光旅客の受入れの体制の確保等 |
我が国は、日本社会の安全の確保という観点を踏まえつつ、我が国と諸外国との観光を含む人的交流の促進の観点より、査証面において外国人旅行者の訪日が円滑となるような措置を実施している。
訪日旅行者の顕著な増加が見られる中国については、平成17年7月より中国全土を対象として団体観光査証を発給しているが、申請人の利便を図るため、平成19年5月からは中国におけるすべての我が国在外公館(香港を除く)において同査証の発給を開始した。この結果、平成19年の団体観光査証発給数は約26万1千件と前年に比して約66%増加した。また、少人数で自由な観光という中国側の要望にこたえ、平成20年3月からは新たに2名又は3名からなる一定の経済力のある家族が観光のために訪日する際にも査証を発給している(家族観光査証)。
今後とも、不法滞在・犯罪・テロ等を防ぐために査証審査を厳格に行う一方、健全な人的交流を促進する観点から、問題のない申請については査証発給手続きの迅速化・円滑化に努めていく。
観光立国の推進に資するため、本年度も地方都市へ観光に訪れる外国人旅行者に円滑な上陸審査を行うことを目的に、観光旅行者の増加が続く韓国・台湾に入国審査官を派遣し、出発地において入国目的等を事前に確認することにより、到着後の上陸審査を迅速に行うことを可能とする「プレクリアランス(事前確認)」を実施したほか、上陸審査の際、入国目的等に疑義が持たれる旅客を別室で審査し、他の旅客の審査を滞らせないようにする「セカンダリ審査(二次審査)」、事前旅客情報システム(APIS)の効果的な活用を図ること等により、入国手続の迅速化・円滑化を図った。
また、平成19年11月から、一定の要件に該当する在留外国人が、上陸許可及び出国確認の証印を受けることなく出入国できるようにする、指紋等の個人識別情報を利用した「自動化ゲート」を導入し、更なる出入国手続の迅速化・円滑化を図った。
さらに、各検疫所では、鳥インフルエンザ(H5N1)患者発生国からの入国者に対し、体温計測の実施等の検疫強化を行っているところであるが、サーモグラフィー等を活用することにより、手続の迅速化に努めている。
平成18年4月1日より施行の「通訳案内士法」及び「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(外客来訪促進法)」に基づき、以下のような「通訳案内士制度」の充実を図った。
1)一つの都道府県の範囲に限って通訳案内業務を行うことができる「地域限定通訳案内士」制度の創設により、平成19年度より岩手県、静岡県、長崎県、沖縄県の4県が「地域限定通訳案内士試験」を実施した。
2)また、「通訳ガイド検索システム」の機能強化によりガイドサービスの需給のミスマッチの解消を図るほか、海外でも通訳ガイド制度の周知を実施するなど、通訳ガイドの有資格者の活用の促進を図った。
なお、「観光立国推進基本計画」における、平成23年度までに「通訳案内士」の登録者数を15,000人(「地域限定通訳案内士」を含む)とする目標に向け、「通訳案内士」の登録者数は前年よりも約700人増加した(表II-4-1-6)。
表II-4-1-6 通訳案内士登録者の言語別内訳表
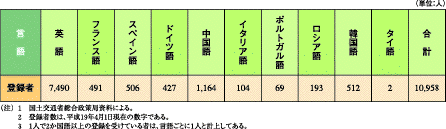
地域の魅力を紹介する「観光ボランティアガイド」について、ガイド技術の向上、ガイド相互の情報交換の場として(社)日本観光協会が毎年1回「地域紹介・観光ボランティアガイド全国大会」を開催している。全国のボランティアガイド数は3万4,290人、ボランティアガイド組織は全国で1,311団体となっている(平成20年3月末)。
また、(独)国際観光振興機構(JNTO)では街頭・車内等で困っている外国人旅行者にボランティアで通訳を行う「善意通訳(グッドウィルガイド)」について、年間を通じて募集を行っており、その趣旨に賛同する善意通訳登録希望者に対して善意通訳バッジと善意通訳カードを交付するなどの善意通訳普及運動を行っている。善意通訳登録者は、更なる活動の機会を求めて有志が「善意通訳組織(SGG)」を結成しており、同行ガイドや国際イベントの通訳補助などの活動を行っている。全国の善意通訳登録者数は53,350人、「善意通訳組織(SGG)」は全国で81団体となっている(平成20年3月現在)。
個別のニーズに応じて移動する旅行形態への志向の高まりとともに、「道路交通法」の改正により外国運転免許制度の対象となる国又は地域に台湾が含まれることとなったため、国内を自動車で旅行する外国人旅行者の増加が見込まれる。
特に、北海道では、豊かな自然環境、さわやかな夏や雪・流氷が見られる冬等明瞭な四季、これらが育んだ景観、豊富な農水産物等が台湾を含むアジアからの多くの旅行者を魅了しているとともに、観光資源が広域に分散していることから、外国人旅行者がレンタカーを活用して周遊する観光のための環境整備を図る必要がある。このため、平成19年度に、北海道の「道の駅」において外国語で情報提供を行う端末の整備や日本語版カーナビゲーションでも目的地設定を容易にする英語版パンフレットを作成した。また、関係行政機関、事業者団体等からなる「北海道外国人観光客ドライブ観光促進連絡協議会」を開催した。
| (6) 航空自由化による戦略的な国際航空ネットワークの構築 |
平成19年8月に、「日韓航空当局間協議」において、空港容量に制約のある我が国の首都圏関連路線を除き、日韓相互に、乗り入れ地点及び便数の制限を廃止し、航空自由化を実現することで合意した。これに続き、同年11月にタイとの間で、また平成20年1月にマカオ及び香港との間で、日韓間と同様の航空自由化を実現することで合意した。
平成19年11月に、自由化交渉の妥結前でも暫定的に、地方空港への乗り入れを認める方針を、外国航空会社に対して通知した。
| (7) 羽田空港の更なる国際化、大都市圏国際空港の24時間化 |
平成19年9月29日の「日中国交正常化35周年」の記念日に、羽田空港と上海虹橋空港を結ぶ国際旅客チャーター便の就航を実現するとともに、利用者利便向上のため、暫定国際線ターミナルの改修・拡張工事を行った。
羽田空港における深夜早朝時間帯(23時~6時)について、積極的に国際旅客チャーター便の運航を推進しており、平成19年度においては、計414便の運航があった。これに加え、平成19年6月より、新たに特定時間帯(20時半~23時の出発、6時~8時半の到着)についても、国際旅客チャーター便の運航を可能とし、平成20年3月末までに計34便のチャーター便運航があった。また、深夜早朝時間帯のアクセス改善のため、検討委員会を発足させ、検討を始めた。
関西国際空港については、平成19年8月2日に2本目の滑走路が供用され、我が国初の完全24時間運用可能な国際拠点空港が誕生した。中部国際空港については、24時間運用(メンテナンスによる閉鎖を除く)を生かし、旅客・貨物便の誘致による深夜時間帯を含めた空港の利活用を推進している。
| (8) 農山漁村での外国人が快適に観光できる環境の整備 |
農山漁村における外国人旅行者受入れの意識を醸成し、地域ビジネスとなる受入れプランと体制の整備を促すために、農山漁村での外国人旅行者受入れのモデル地区を6箇所(宮城県東松島市、埼玉県さいたま市、富山県立山市、長野県飯山市、岐阜県高山市、熊本県山都町)選定し、外国人モニター等を活用して、外国人旅行者受入れモデルとなる地区を育成した。
今後も引き続きモデル地区の育成を実施することとしている。
| (9) 博物館・美術館等における外国人への対応の促進 |
国、独立行政法人、都道府県立等の博物館・美術館については、外国人見学者の受入れ体制等に対する調査研究を行うとともに、「公立博物館の設置及び運営に関する望ましい基準」(平成15年文部科学省告示第113号)を定め、外国語表示等、必要な施設及び設備を備えるよう促してきている。平成19年度は、都道府県教育委員会等に対し、観光立国推進基本計画に盛り込まれた博物館・美術館等における外国人見学者への対応について、外国語表示に関するアンケート調査を行うとともに、各館において外国人受入れ体制の充実が図られるよう周知を行った。
なお、我が国の代表的な博物館である、各国立の博物館の取組状況は以下のとおりである。
1)国立文化財機構
国立文化財機構では、施設やサービスについて周知を図るため、案内板の表示や展覧会における展示品のキャプション等について英語併記としているほか、所蔵している国宝重要文化財をインターネットで閲覧できるデジタル高精細画像システムを、多言語(英語、中国語、韓国語、フランス語)で発信し、外国人への対応の促進を図っている。
2)国立美術館
国立美術館では、施設やサービスについて周知を図るため、案内リーフレットやホームページの外国語での作成、インフォメーションにおける英語案内を行い、外国人来館者が利用しやすい環境の充実を図っている。また、作品名等のキャプションの英語併記等、展示品等についての理解の促進に努めている。
3)国立科学博物館
国立科学博物館では、音声ガイド等、ITを効果的に活用した多言語(英語、中国語、韓国語)による文字・音声情報による展示解説を行うなど、海外からの旅行者を始め、すべての人々が利用しやすい環境の充実に努めている。
今後も計画や告示の趣旨の周知を通じ、博物館・美術館を、外国人を始め誰もが快適に利用することができるよう促していく予定である。
伝統芸能等のライブエンターテインメントについて、日本の伝統芸能を観劇するための情報を発信し、訪日外国人観光旅客数増加を目的として、平成18年度に作成・配布した「歌舞伎」「文楽」「伝統音楽」の英文パンフレットに引き続き、平成19年度は「能楽」の英文パンフレットを作成し、外国人総合案内所、ホテル等に配布した。
また、外国人にも劇場施設やサービスについて周知を図るため、劇場案内リーフレットを外国語(英語等)で作成したほか、公演内容の理解を促進するため、歌舞伎・文楽公演時におけるイヤホンガイド英語版の提供及びプログラムへの英文掲載(国立劇場)や、各座席に設置の字幕装置による英語字幕の提供(国立能楽堂)を行った。
この取組は今後も引き続き実施することとしている。
| (11) 国立公園等における外国人観光旅行者に向けた情報提供 |
国立公園等における公園利用施設の整備に当たり、外国人に向けたインフォメーション機能の強化を図るため、国直轄のビジターセンターの展示での多言語表示や外国語表記の誘導標識・案内標識の整備等を進めた。
また、国立公園を紹介する英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語のパンフレットを作成し、国内外で広く配布するとともに、国立公園を紹介するホームページの英語での作成や、成田国際空港での国立公園写真展の開催等を通じて、外国人に向けて日本の国立公園に関する情報を発信した。
|
|