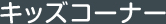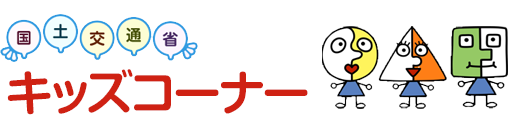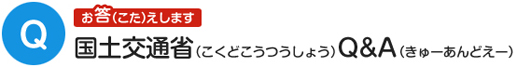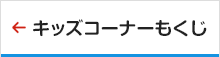国土交通省Q&A
海上交通(かいじょうこうつう)
Q 海上交通を発展させるためにどのような取り組みを行っていますか?
Q 水上バスはどのように利用されていますか?また、渋滞は起こりませんか?
Q 大型船の船長になるには、どうすればよいですか?
Q 大型貨物船はどこで、どのように造っていますか?
 |
海上交通を発展させるためにどのような取り組みを行っていますか?
|
 |
みなさんは、海外から日本に運ばれてくる貨物のうち、何%が船で運ばれてくるか知っていますか?実は、99.6%が船で運ばれてきています。 周囲を海で囲まれた日本にとって、海上交通はとても重要です。国土交通省では、海上交通の発展のために以下のような仕事をしています。 外航海運(日本と外国との間を結ぶ海上輸送)では、日本の海運会社が世界で活躍できる環境を整える仕事などをしています。 内航海運(国内の海上輸送)でも、トラックと比べ環境にやさしい船の利用を促す仕事や、離島航路を維持する仕事などをしています。 日本の造船業(船を造る仕事)や舶用工業(船のエンジンなどを造る仕事)は世界トップレベルです。環境にやさしい船の開発の支援や、造船業を目指す若者を増やし、育てるための取り組みなどもしています。 船舶の安全な航行のための検査や、船員を目指す学生・生徒の教育と訓練にも力を入れています。
|


 |
大型貨物船はどこで、どのように造っていますか?
|
 |
大型貨物船は、造船所の工場で造られています。 まず初めに、運ぶ貨物によって色々な船の形があるので、用途に合った船の設計図を作ります。 その設計図に沿って、必要な材料、部品を調達して、船体をいくつかのブロックに分けて組立てていきます。 それぞれのブロックが完成したら、大きなクレーンで船台(船を組立てる台)の上に持ち上げ、溶接して組立てることでようやく船の形になります。 その後、船台から進水(初めて海に船を浮かべること)をして、実際に海上を航行する試運転が終わると貨物船として完成します。 また、進水のときは、進水式といって、船の発注者や製造者などの関係者が集まり、船の命名も同時に行われます。 このように多くの工程の中で、設計を行う人や溶接を行う人など、さまざまな知識や技術を持った人が携わって一つの船が完成します。
|