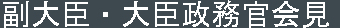加納副大臣就任会見要旨
2008年8月20日(水) 15:00 ~ 15:30
国土交通省会見室
加納時男
閣議・閣僚懇
(副大臣)皆様こんにちは。この度国土交通副大臣を拝命いたしました加納時男でございます、よろしくお願い致します。
質疑応答
(問)幹事社から2問あります。1つは就任に当たっての抱負、もう1つは任期中にこれだけはやりたいということが何かありましたら宜しくお願い致します。
(答)第1点目ですが、就任に当たりまして各部局から説明を受けました。それを聞いて感じたことが3点程ございます。1つは国土交通省の受け持つ仕事が非常に幅広く、しかも非常に重たいものであるということを感じました。国民生活の屋台骨と言いますか、国民生活や経済を支える基礎的なインフラの整備とその管理を担当していること、それから陸上、海上、航空に渡る全ての交通政策を担当していること、そしてまた観光政策も担当していること、こういったこともあり、非常にその領域が広く、そして責任が重いと思っております。加えて、最近大変残念な事がございました。ご案内の通り、北海道開発局における入札談合事件があり、逮捕者、起訴者が出たこと、また、道路関係ですが、業務執行上社会の批判を受けるような行動があったことは誠に遺憾であると思っています。こういったことを十分考え、身の引き締まる思いですが、後段の事については深く反省するとともに省内の文化、省内の仕事のやり方を改革し、責任を果たしていかなければならない。第1点は非常に重い責任を感じたという印象です。第2点については大臣からご指示がございまして、私の担当は交通政策全般、観光、北海道、危機管理、安全関係でございますが、加えまして、原油対策についても担当するようにというご指示がありました。これらを通じて感じたことは、私にとっては未知の領域がたくさんございます。初めて経験することもございます。そういう意味では謙虚に学び早とちりしないようしっかり考えていきたい、よく相談しながらやっていきたいというのが第一義でございますし、もう一つは私がこれまでに色んな事を経験してきた、その経験が生かせる分野が結構あるなということが感じられたことでございます。意外にこういうことが多いので謙虚さと同時に、ある確信を持って進めていきたいというのが第2の感想です。最後になりますが、国民の安全や安心の確保を図るという非常に重要な役目を持った省でございます。また、地域の活性化や再生に繋がる行政がここの担当でございます。そういう意味では6万2千人の職員の仲間と手を組み、そしてまた、金子副大臣、西銘、岡田、谷口3政務官と力を併せて、谷垣大臣を補佐して参りたいというのが私の抱負でございます。
第2のご質問ですが、私の任期中、任期はいつまでかよく分かりませんが、やりたいことというものを率直に申し上げたいと思います。基本的には他の副大臣、政務官と同じだと思いますが、先ほど申し上げたような信頼感を損なう不祥事があった役所です。抜本的な対策により再発防止を図り信頼回復をしていきたいということが、共通のやりたいことのベースでございます。その上で担当部門に即して2、3点申し上げたいと思います。
第1点は観光立国の実現でございます。観光は豊かな国民生活、それからまた地域経済の活性化と言われますが、私はそれに加えてもう1つ、観光はお互いの理解を通じて、例えば国際観光になりますと国の安全保障になるのではないか。私も仕事柄これまでに多くの国を訪問していますが、そういう時に感じたことは、行ったことのない国を抽象的に新聞やテレビで理解するよりも、実際に行った国、来てもらった国、そういうひとつひとつの接触が国と国との相互理解の第一歩だと思っています。これは実はこれを通じて安全保障になると考えておりますので、観光政策というのは今も申し上げた三つの観点からも非常に重要だと思っています。折しもこの10月1日から観光庁が新たに発足致します。そういう時期に参りましたので、よく観光政策5つの柱と言っていますが、1、2、3、4、5というのでしょうか。これも色々と聞いてなるほどと思いましたが、日本を訪れる外国人を1000万人にしよう、日本からの外国へ訪れる人を2000万人にしよう、これが1、2です。3というのは国内観光消費を30兆円にしよう、4というのは1年間の平均宿泊数を4泊以上にしよう、5は国際会議の数を5割増しにしようと。これを数年の間に達成しようという意欲的な目的を達成するように、私も微力ながら努力していきたいと思っています。1が観光立国です。
2が交通分野における安全安心対策の確立です。交通事故をはじめとする様々な事故、災害、それからテロの防止が大きな焦点になると思います。こういう意味では従来からやってまいりました技術的な検査や監査も勿論大事ですが、2つの観点、1つはソフト面から強化していく、運輸安全マネジメントを制度化するというのが1つであります。もう一つは委員会の改編強化であり、従来からある航空・鉄道事故調査委員会、それから高等海難審判庁を総合して総合的な安全委員会、運輸安全委員会と称しますが、これに改組するということが決まりました。こういったことを通じ、交通分野における安全安心対策を強化して参りたいというのが2点目です。
最後になりますが、3点目として気候変動への対応でございます。私もこれまで党の政務調査会の副会長等、様々な仕事を担当して参りましたが、その中で気候変動対策で国土交通省との関わりは非常に気になっていたところです。と申しますのは日本全体として脱炭素政策をとっておりますが、その中で1990年に比べて産業部門は5%の効率化に成功しています。しかしながら、実際にCO2が増えたのは運輸部門と民生部門と言っていますが、住宅とかビル関係です。もうお気付きのようにこの運輸関係の担当は我が省です。ビル、住宅の担当、これも我が省です。そういう意味では我が省において担当している分野では、真に残念ながらこれまでCO2が増えてきているのが事実です。運輸部門で17%プラスです。民生部門で35%プラスです。やることは一杯あります。今まで私はこういったことを党のまとめ役としてやってきましたけれども、ポイントは3つあると思います。
1つは効率化、2つ目が燃料転換、3つ目がシステム化ということです。国土交通省に即して言いますと、効率化で言えば住宅の断熱化、廃熱の回収、こういったようなこと。自動車で言えば燃費の向上がこれに当たります。
フュエルスイッチイング、燃料転換で言えば灯油、化石燃料を燃やすものから、化石燃料を燃やさないで冷暖房、給湯をやっていくような住宅のエネルギーシステム、ヒートポンプの活用等です。自動車で言えば、自動車の燃料はこの百年間石油一筋でした。これを何とかして転換していきたい。今スタートしましたハイブリッドから、その次の段階としてはプラグインハイブリッドと言っていますが、これに手がける。そしてその先は電気自動車と、こういった流れです。その他にバイオエタノールの活用ですとか、水素自動車とか、色々ありますが、いずれにしても石油以外の燃料に転換していくのも非常に重要です。これをどこで担当するのか。これも我が省だと思っています。
3点目のシステム問題です。地域交通システムが非常に今苦しんでいます。私も選挙区が全国ですので全国を走り回っていますけれども、地方鉄道の利用がどんどん減ってきている。会社が赤字になっている、利用者も減っている。こういった中でどうやって地域交通システムを新しく生まれ変わらせるのか。大変な問題だと思います。これが実は温暖化対策の1つのキーになっています。それからまた物流で言えばモータルシフトがあります。ちょっと長くなりましたが、この3つ、観光立国、交通分野の安全・安心、地球温暖化対策、こういったことを私は何とか自分の任期中に、任期はなるべく長いことを願っていますけれども、その間に全力を挙げてやっていきたいと思っています。
(問)先程、安全保障という点が出たと思うのですが、海上保安庁も所管なさると思うのですが、海上保安庁の方からの、最近の原油高騰とか、毎年非常に予算が厳しいという状況があると思うのですが、こういった現状をどのうようにご理解なさっているかお聞かせください。
(答)仰るとおり、安全保障という面で我が省の担っている役割の1つである海上保安庁の役割は非常に大きいと思っています。日本の場合は、国土の面積が世界の0.34%で小さい訳ですけれども、そこに今3%弱の人が住んでいる。非常に小さな国なんですけれども少なくとも水域という面で見れば、ご存じの通り世界第6位の領域を持っています。日本は島が一杯あって領海に加えて排他的経済水域が大きいものですから、世界第6位になっています。そういった中で非常にこの我が海上保安庁としましては諸外国と比べると相対的には少ない人数、1万2千人おりますけれど、これで何とか船艇、航空機をやっています。予算の面では1千8百58億円位になりますか、2千億円をちょっと切っていると記憶していますけれども、そのくらいの予算でして、何が問題かと言いますと、1つはテロの脅威が出ています。例えば不審船が出てくる。特に国境警備ですが、国籍不明な船あるいは国籍が分かっている船でも様々な不審な行動を取る船が出ていますが、これに対して海上保安庁がまず一歩前へ出まして、そしていよいよ緊急の場合には海上自衛隊に支援を頼むということになりますけれども、海上保安庁として果たすべき第1弾としての使命を十分果たすために今の装備で十分であろうかということ、今私は毎日ヒアリングをしているところです。予算の問題もあるのでしょうけれども、私の印象では船が若干建造が遅れるというか、不十分な所があります。航空機は今73機ありますけれどもこれも十分かどうか。つまり船舶も459隻ありますけれども、船の量、飛行機の量、これも勿論大事ですけれども、その性能また近代化が非常に大事だと思っています。そういう点では大きな課題があるのではないかと思っています。日本の場合、海上保安庁が果たすべき治安の役割、国境の警備の話、海難救助等色々ありますけれども、いずれにしましても今予算のご質問がありましたが、厳しい制約がありますけれど、エネルギーと並んで日本の国としての安全保障の面も非常に重視しなければならないことですので、国の安全保障の面から海上保安庁の予算については厳しい中ではありますけれども要請をしていきたいと思っています。
(問)今、観光立国の実現をということがありましたけれども、長官人事についてどのような方が望ましいとお考えかお聞かせください。
(答)ご質問はこの10月1日に発足する観光庁の人事についてどう考えるかということですが、答え難いご質問だと思っていますが、抽象論で言わせて頂きます。具体的に誰がいいということを言うべきではありませんし言うこともできません。抽象的なことで勘弁して頂きます。私はこう思っています。観光庁の長官については3つの資格要件が必要だと思っています。1つは強力なリーダーシップが必要である。これは新しく生まれるものでありますし、関係省庁を始め諸外国の政府や観光機関との間で色々な交渉事があります。そういう時によく全体をまとめていく強いリーダーシップ、2つ目には、幅広い識見が必要だと思います。3つ目には、タフな交渉力・調整力です。オリンピックが真っ盛りですが、日本人は譲るのが好きで直ぐ譲ってしまうのですが、そうではなく、ある時にはタフにならなくてはいけない。そういう意味では交渉力・調整力がもの凄く大事だと思います。業務だけ詳しく知っていればいいということでは無く、今申し上げたような三つの資格要件を持った方がいいと思いますので、民間か官かというご質問だと思いますが、今申した資格要件が満たせば、民間だろうと官だろうと構わないと個人的意見ですが、私はそう思います。
(問)大体いつ頃までに決められますか。
(答)日にちは決定していまして、10月1日が発令ですので、その前にとそこまでは決まっていますが、具体的に8月中か9月中かについてはまだ決まっていません。
(問)先程、自分が生かせる分野があると感じていると、未知の分野も多いが自分の経験を生かせる分野も多いと仰いましたが、具体的にどのようなことですか。
(答)これまで色々なことをやってきましたが、例えば政務調査会の副会長をやっていました。そこでは政策全般を見ます。当然のことながら、縦割りの分野で世の中とかく出来ていまして、役所も縦割りだと思います。縦割りが全部いけないと言っているのではなく、縦の責任は大事だと思います。党の部会も縦割りなのです。これを横串に差してやる必要があるようなテーマが沢山出てきています。地球温暖化もそうです。安全対策、不況対策、経済対策等政策全般を見るところに居ましたので、そういう意味では、国土交通省族という立場ではなくて、政策全般を見る立場、例えば、骨太の方針を作る時等、副会長として初めから終わりまで参画するのです。税調ですとか色々な分野で国土交通省を割と客観的に見ていました。そういう意味で少し強みかなと思います。
大臣からご指示があった分担として原油対策がありましたが、党の原油対策PTの座長を昨年から務めています。何度も会合を開き、その都度まとめまして、今まで三次に渡る対策を出してきましたが、一番新しいのが6、7月に出したものです。こういったことをやっている中で、国土交通省の担当している分野が結構ありました。今回、私が来て意を強くしているのは、例えば、建設業が苦しいと、これに対しては単品スライドというのが一つ、それから品質確保、こういったことで対応したつもりです。それから離島航路がありました。地方の路線バス等の問題がありましたので、直ちにヒアリングをやり国土交通省にも来てもらい、また国土交通部会長とも相談し、離島振興委員会とも相談をして離島航路対策、地方路線バス対策を担当させていただきました。
それから、高速道路料金の引き下げですが、「引き下げを検討する」との議論が最初あったのですが、それは駄目と、引き下げるんだと、記者会見の時に質問があったのですが、「引き下げを検討、ではないのですか」と聞かれたのですが、敢えて「引き下げ」と書きましたと申し上げた位力を入れてきたつもりですが、実際にやるところは国土交通省でした。いいところに来たなと思いました。何が何でも引き下げる。今、夜間割引を3割から4割引きになっています。頻度割引、大口割引を加えると最大で58%位の割引になると思います。これを更に引き下げるのだと、そしてトラック業者の人達の苦痛に答えるのだというのも今までやってきました。まさに生かせる分野ではと思います。トラックについては3月でしたが、トラック協会の方から陳情があって、党として受けて党全体の会議で議論をし、サーチャージ制を何とか導入しようということで、当時は私の外側にいた国土交通省にサーチャージ制を早くやってくれと言いまして国土交通省は応えてくれました。その入れ物は出来たがこれを本当にどこまで浸透させるのか、こちらでヒアリングをしていますが、全部には行き渡っていません。大手が手を挙げてくれたので、バラバラと入ってきてくれましたが、まだ、全体の4割、5割をカバーするには至っていません。こういったことを更に中小企業まで広げていきたいと思います。また、全般については国土交通省に限りませんが中小企業が多い日本です。建設業、トラック業等中小企業に対する金融セーフティネット保証等をやっていきたい。
あと一つだけ言わせてもらうと、エネルギー環境問題です。この問題は、国土交通省の持っている分野は非常に大きいのですが、今までは外から国土交通省にこういったことを考えて下さいというように、住宅の断熱等を外からお願いしていましたが、今度は中にいる立場ですので、少しは経験を生かせるのかと思っています。住宅の話は省略しますが、国土交通省が今立ち上がったということです。仲間として前へ進むように努力していきたいなと思います。
最後になりますが、私はいままで色々な国際的な仕事をさせて頂きました。国会議員になる前に、ロンドンにある世界原子力協会の会長に日本人で初めてなりました。メダル取ると大騒ぎになりますが、会長になっても一紙も報じてくれませんでしたが、その世界では珍しい話で初めてなりました。そういうこともあって今までに百回以上国際会議に出席をし、仕切ってきたつもりです。そういう意味では国際関係の仕事は国土交通省も観光庁の設立を始め更に増えてくると思いますが、そう言った分野で私がこれまで経験してきたことが何らかのお役に立てるのかなと思っています。以上です。
(問)今お話があったんですが、ちょっと直接の仕事とは関係無いかも知れませんけれども、化石燃料から電気へのシフトということを先程も仰ってまして、電気へのシフトという部分で結局電力を作るのも化石燃料から原子力へということになっていくんでしょうけども、それが果たして地球環境全体にとって温暖化という部分では良いのでしょうけど、原子力発電というのがどんどん増えることについてはどのようなお考えを持っていらっしゃるのかお聞かせ下さい。
(答)これは国土交通省の人間というよりも政治家として答えさせて頂きたいと思います。とても鋭いご質問だと思います。仰る通り、例えば住宅の中で、家の中で、火を燃やさない、そしてヒートポンプを使う、あるいはオール電化を進めていくという選択肢も一つあると思います。その場合の電気は何でできるのか、これを化石燃料でやってたら同じ事でありますから、そこの元の所を非化石燃料に変えていく、つまり電気を非化石でつくる、非化石の王者は当然原子力だと思いますけど、原子力以外も例えば自然再生エネルギー、太陽光とか風力とか、これは使えてもあまり大きな力にはならないのですが、使えるところで積極的に使っていくべきだと思っています。若干国土交通省とリンクしてくるのは、例えば住宅とかビルの上の緑化とか太陽光発電を置くとかそういうことになると、これは国土交通省と関係します。風力というのも色々な所に作りたいのですが、これもやはり国土交通省と相談をしながらの話になると思うので、そことは若干関係すると思います。
それから自動車の燃料については、燃料は100パーセント石油であります。ガソリンにしましても、軽油にしましても、これを何とか石油以外の物に変えていくという点で考えますと、例えば電気自動車も一つの選択であるのだろうと。電気しかないとは決して申し上げません。水素でも良いんですけど。水素を作るのに化石燃料を排出したのではしょうがないと思うので、水素を作るのに自然エネルギーから作るとか、これを原子力で作っていくということです。今東海村でやっております。HTTRと日本では言っております。これを日本としては進めることによって、原子力で水素を作る。そうするとその水素で車を動かせば、これは化石燃料に依存しないで出来ますので、様々な物があると思います。
ご質問の第二点は果たしてエネルギーセキュリティーとか、環境の面では良いけれども原子力には他の問題があるのではないか、本当に原子力にどんどん依存して良いのかという事になります。お答え申し上げますが、あらゆるエネルギーには優れた面、メリットと、もう一つリスクがあります。陰の面があります。
原子力には3つの陰があります。1つは事故が起こったら大変だということ。自動車や飛行機と同じで便利な物ほどリスクが大きいということ。原子力は非常に密度の高い、高密度なエネルギーでこざいますけれども、その反面一度事故が起こると影響が大きい、仰る通りでございます。2つめには核兵器の核拡散のリスクは無いのかということになります。今世界中が原子力で沸き返っております。日本だけは沸き返ってないのですが、私は世界中を回って参りました。世界原子力協会の会長をやっておりましたので、世界中を回って参りましたけど、アメリカ、ヨーロッパ、中国、インド、東南アジア、世界中が原子力で沸き立っております。どんどん作って行こうということです。国民の世論もそうなってきております。そこでそういう時に良いことは良いとして、問題点として、核兵器の拡散にならないか、テロリストに狙われないかという点が、私は心配でございます。核兵器の不拡散を進めて行くということは同時に欠かせないことでありますので、日本政府としても自民党としても基本に置いてありますのは原子力の平和利用の促進であります。3点目のリスクは廃棄物の後始末が出来てないのではないか、とよく反対派の人が仰る事でございます。これは認めます。その通りでございます。以上の3つのリスクがあるからやめるのか、私は3つのリスクは全部克服可能であると思っています。 1つめのリスクについては反応度事故という、ちょっと専門的になりますが反応が止まらなくなるチェルノブイリ型の事故、これが一番恐いことですから、これが原理的に起こらない設計の炉の構造にするというのが日米欧の共通の認識です。例えば軽水炉というのがそうであります。そういう意味では設計思想でまず対応出来る。それから冷却水が抜けてしまうというような冷却水喪失事故、アメリカのスリーマイルのようなもの、これは起こり得ます。このときの対策は緊急に冷却する装置を複数用意することと、最悪の場合でも放射能を核容器の中に閉じ込めることです。アメリカはそれに成功したので実際に被害は出ていません、スリーマイルのことです。これが2つめのリスクです。3つめのリスクは廃棄物の問題です。これについてはトイレ無きマンションと反対派の方は仰ってますが、トイレは出来ております。例えば、フィンランドのオルキルオトで最終処分場が決定しました、着工です。フランスはほぼ決定しました、ビュールです。こういうところで高レベル放射性廃棄物の最終処分場が決まってきているということもまた現実ですので、こういったところの成功物語をよく見ながら日本でもやっていきたい。色々と成功物語を私も調べてきましたが、実物、実体験ができるのが非常に良いということで、これは自民党としてもそれをやりたいということで、また役所の方も認めまして実際に体験出来るようなそういうものを造ろうと言うことで今動いているところです。今日の新聞にはこのことがちょっと書いていましたが、そういうことも体験をして頂いて最終処分場は実現可能なんだということを安全性とともに体験して頂くことが欠かせないと思っています。核兵器、核拡散についてはご存じの通り核不拡散条約を推進していこうと、これをまだ承認していない国の問題があります。その国に対する対応をIAEAとともに進めています。
以 上