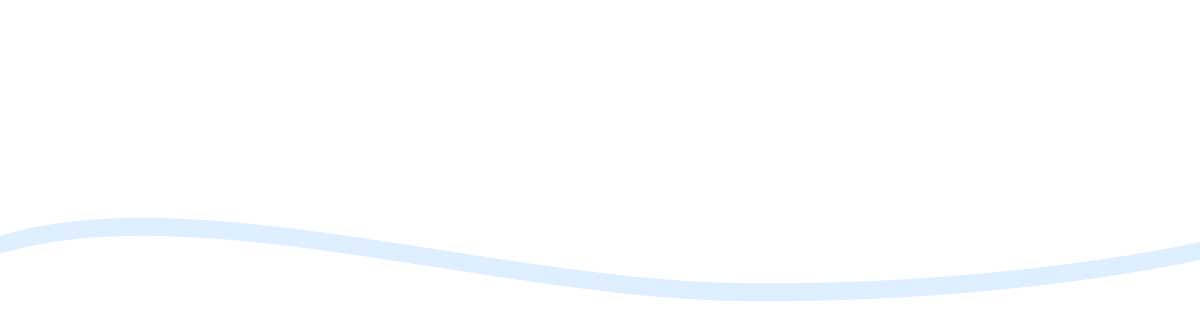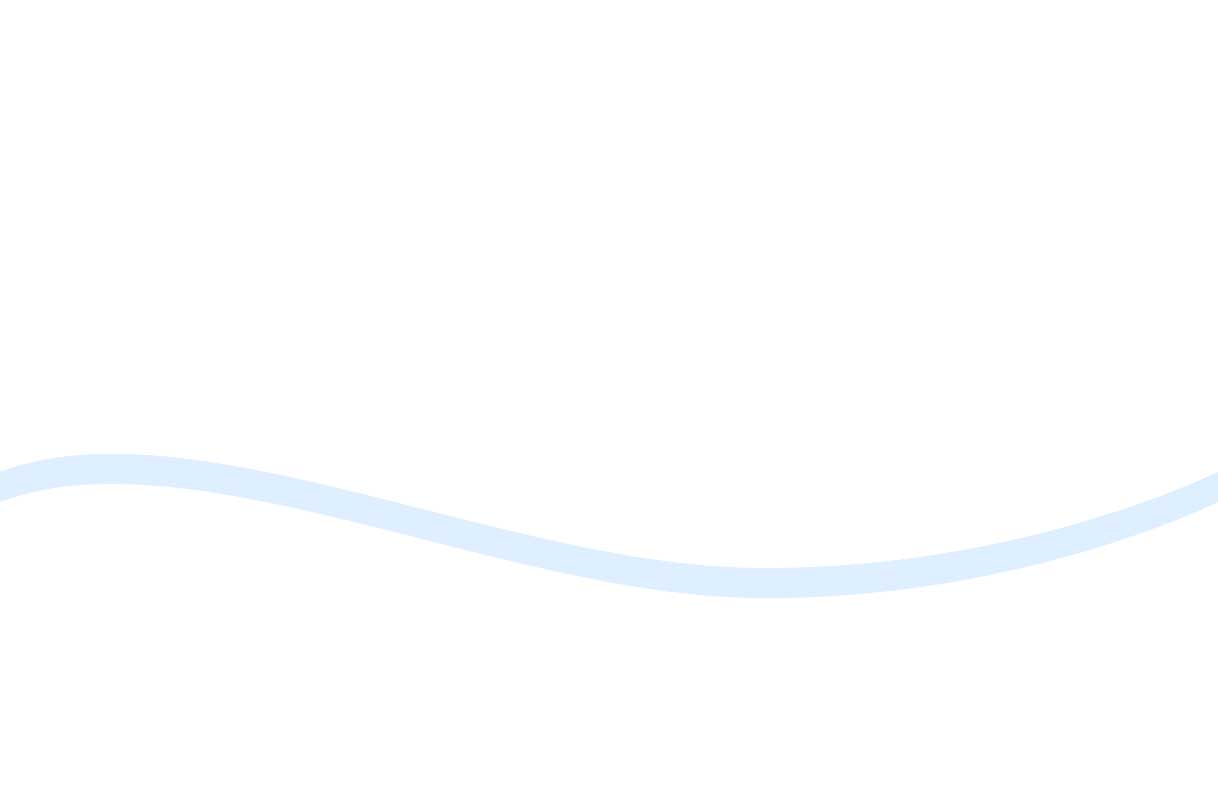資金調達
SDGs
岡山県真庭市
再生利用可能なエネルギー 真庭バイオマス産業杜市
■実施主体:真庭バイオマス産業杜市推進協議会、真庭観光局事業部
◆真庭市は「自治体SDGsモデル事業」に選定された先駆的な自治体
真庭市は岡山県内でもっとも大きな自治体でその8割は森林が占めている。台風や地震といった災害が比較的少なく穏やかな気候に恵まれた同市は国内屈指のヒノキの産地であり木材や木製品産業が盛んだ。
木材を加工する過程でどうしても発生してしまうのが不要な樹皮や未利用の間伐材といった林地残材や産業廃棄物。これらをどうにか活用しようと生み出されたのが木質バイオマスに着目したまちづくりだ。自然環境との調和を重んじる真庭市ではこれらを核として、エネルギー利用産業の観光・学習推進による地域ブランドの向上を目指している。
その取り組みが評価され、2018年(選定初年度)に「自治体SDGsモデル事業」として真庭市が選ばれた。
 地方創生におけるSDGsのモデルとして国からも高く評価されている
地方創生におけるSDGsのモデルとして国からも高く評価されている◆官民の立場を越えた議論が地元の新たなエネルギーを生み出した
スギやヒノキといった住宅用木材の需要は高度経済成長期ピークを迎えたが、1980年代中盤以降建築木材の需要は減り、一方で人件費や経営コストが上がったことで市の産業衰退が懸念された。危機感をもった若手経営者や地元有志が集まり、発足したのがNPO法人「21世紀の真庭塾」である。大学の先生や国・県の職員、先進的な事例をしている会社の社長などをお呼びして2年間で200回に及ぶ勉強会を開催、そこに行政関係者も加わり官民の立場を越えての議論が続けられた。その結果、導き出されたのが木質バイオマスを使った産業都市構想である。
◆エネルギーの地産地消を実現したバイオマス発電
構想を実行に移すにあたり大きな力となったのは、ベンチャー性をもった団体とそれを実行できる人材が揃った民間企業だった。中でも銘建工業は集成材とCLT(木質系材料の一種)において国内シェアナンバーワンでありバイオマス発電のノウハウを持っていたことが大きい。2015年には真庭バイオマス発電所が開設され、バイオマス発電だけで市内の一般家庭の電力自給率100%を超える状態を実現している。発電所で働く人員は全員が地元の人材、燃料に利用する木質バイオマスは勿論地元の調達だ。木材資源安定供給協議会が製材所や山林から木材を購入し山林事業者へ利益還元している。そして一般家庭から出た剪定木も受け入れているため、市民の収入になる一方で貢献意識に対する一助にもなっている。まさにWin-Winの関係だ。
木質バイオマス以外にも生ごみを利用したバイオ液肥の活用にも展開が拡がっていて、真庭市の取り組みにはますますの期待が集まっている。
 一般的家庭の消費電力に換算すると約2万2000世帯分の電力供給ができる
一般的家庭の消費電力に換算すると約2万2000世帯分の電力供給ができる 廃棄されていた木材チップも市を支える立派な木質バイオマスだ
廃棄されていた木材チップも市を支える立派な木質バイオマスだ◆大人気の真庭SDGs・バイオマスツアーで循環型社会を学ぶ
自治体SDGsモデル事業として認定されたということもあり、最先端を行く真庭市には県外から視察申込が殺到している。(一社)真庭観光局では「バイオマス」「SDGs」の取組を進める様々な産業を巻き込んだ展開として、バイオマス利活用やSDGsの取組を学べる真庭SDGs・バイオマスツアーを企画・運営。コースごとに様々な企業、農家等が関わっていてそれぞれに利益が出る仕組みとなっている。
現在では大きく分けて、1日見学を行う「木質バイオマスコース」と「循環農業コース」の2つがある。また、短時間(半日)でも学びたいというニーズを受け、テーマによって細分された「SDGs学習12コース」を商品化。体験コンテンツもあるため企業・学校・市民等に人気が高い。特に学校の教育旅行ではリピート利用もありコロナ禍より目的を「平和学習(広島)」から「SDGs学習」に変更された学校より問い合わせが急増したそうだ。
一方で大規模な学校になると人数規模が大きく、見学企業との受入れ調整や繫忙期のアテンドスタッフ不足など課題もある。地域内で課題を解決する為、登録ガイド制度を開始して市民の方や地域おこし協力隊など現在13名が在籍。地域が一体となり視察者の受入れを進めている。
 市では出前授業を行い地元の子供たちの理解を深める取り組みを推進している。
市では出前授業を行い地元の子供たちの理解を深める取り組みを推進している。 子供たちの収穫体験
子供たちの収穫体験