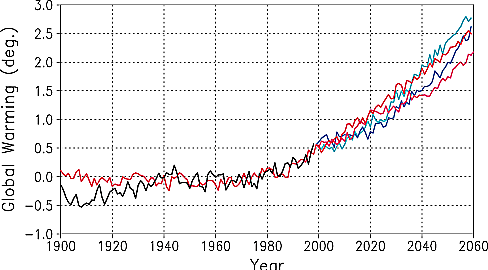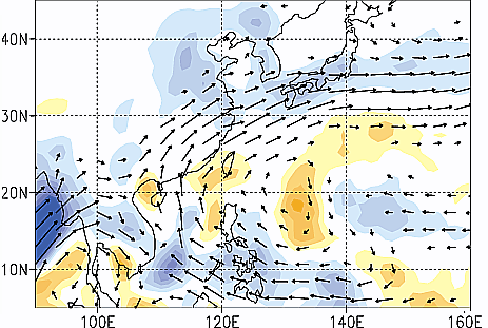�ŋ߂͉Ăɍ����������A�ꏊ�ɂ���Ă͏W�����J�Ɍ�������P�[�X�������Ă���̂ŁA�ُ�C�ۂł͂Ȃ����Ƃ悭������B�������A�Z���Ԃ̃f�[�^�������ċC�ۂɈٕς����������̂悤�ɔ��f���邱�Ƃ͊댯�ł���B�n���̑�C��C�m�̓����́A�����Ĉ��ł͂Ȃ��₦���ω����Ă���B�n����̋C�ہA�����Ă��̒����ԕ��ςƂ��Ă̋C��̌`���ƕϓ��ɂ͕��G�ȗv�f�����ݍ����A�܂��܂��𖾂ł��Ȃ���肪��������c���Ă���B
��ʂɈُ�C�ۂƂ��������A��ʂ�̎g����������Ă���B�ЊQ�������炷�W�����J�̂悤�Ȑ����ŏI���C�x���g���w���ꍇ�ƁA�����ς�ЂƉĂ̕��ϒl�̂悤�ȁu�V��v�ُ̈����ɂ���ꍇ�ł���B��C�A�C�m�Ȃǂ���Ȃ�u�C��V�X�e���v�͎��R�̏�Ԃł���炬�������Ă��邽�߁A���N�����悤�ȕ��N���݂̉Ă����邱�Ƃ͂Ȃ��A�V��͔N���ƂɈقȂ��Ă���B�������A�l���ꐶ�Ɉ�x�o�������o����Ȃ����̂悤�ȋH�Ȍ��ۂ��o������ΎЉ�I�ɂ��e���͑傫���B�����ŁA�����ϒl�Ȃǂ̓��v�ʂ��������ɂ́A�l�̕��ϓI�Ȋ������Ԃł���30�N�Ԃ�1����x�̊m���ŋN����悤�ȋɒ[�Ȓl���ϑ����ꂽ���A�ُ�C�ۂƌĂԂ��Ƃ������B�t�Ɍ����A30�N��1��Ȃ�N�����Ă����������Ȃ��Ƃ������ƂŁA���E�������n���ǂ����ł��̂悤�ȁu�ُ�v�V�N�����Ă���̂��ނ����Ԃł���Ƃ�����B�ЊQ�������炷�悤�ȒZ���̋C�ۏ���܂��A����m���Ŗ��N������̂����R�ȏ�Ԃł���B���̏ꍇ�A�u�ُ�v�Ƃ͂����̔����p�x�⋭�������ϓI�ȓ��v�͈̔͂�����E���邩�ǂ����ɂ���Ĕ��f�����B�Ⴆ�A1���ԍ~���ʂ̍ő�l���ЂƉĂɉ��x���X�V���ꂽ��A�N���ϋC���̍ō��l��10�N�������ēh��ւ���ꂽ�肵�����ɂ́A�C��V�X�e���ɍ����m��ꂴ��ϒ����N�����Ă���Ƃ������Ƃ��^���Ă݂�ׂ��ł���B
�䂪���ɂ����Ė{�i�I�ȋC�ۊϑ����n�܂����̂́A����E���̍�����ł���B������1959�N�A�C�ے��ɃR���s���[�^����������A�����̃x�[�X�ƂȂ����l�\���m��1�n���J�n���ꂽ�B77�N�ɂ͐Î~�C�ۉq���Ђ܂�肪�ł��グ���A88�N�ɂ̓X�[�p�[�R���s���[�^����������āA���Ȃ萸�x�̍������l�\�s����悤�ɂȂ����B�Ƃ͂����A�S�n���I�ɂ͂����������\�N�̊ϑ������A10�N�]��̃X�[�p�[�R���s���[�^�\��o�����l����ƁA�{�i�I�ȁu�ُ�v�C�ۂ̉𖾂́A�܂��܂����ꂩ��ł���Ƃ����Ă悢�B �@
���m�̕���̑����ُ�C�ی����ɂ����āA��r�I�����̐i��ł��錻�ۂ�����B�G���j�[�j�����ۂ�j�[�j�����ۂł���B�G���j�[�j���Ƃ́A���N�Ɉ�x�̊����œ��t�ύX���t�߂��瓌�̐ԓ������m��тŊC�ʐ������オ�錻�ۂ������B�C�ے��́A�ԓ��������m�ɐݒ肵���G���j�[�j���Ď��C��̐������A���N���0.5�x�b�ȏ㍂����Ԃ����N�ȏ㑱���������G���j�[�j�����ۂƒ�`�Â��Ă���B ����A���j�[�j���Ƃ͐ԓ������m�̐������z���G���j�[�j�����ۂƂ͋t�ɂȂ�A���ŒႭ���ō����Ȃ��Ԃ������B�ԓ��������m�̃G���j�[�j���Ď��C��̐��������ς��Ⴍ�A5�����ړ����ϒl��- 0.5�x�b�ȉ��ŁA���ꂪ6�����ȏ㑱�������Ƀ��j�[�j�����ۂ���������B�����̌��ۂ̉𖾂͌��݂��Ȃ�i��ł���A���̉e������M�т̍��X�̓V��͂�����x�̐��x�������ė\������Ă���B ���{�̉ẮA�����m���C���̐��͂Ƃ��̒��S�ʒu�Ɏx�z�����B�����m���C���̈ʒu�ɉe����^����͔̂M�ђn���̊����Ȑω_�Η��̒��S�ʒu�����A�G���j�[�j���ɂȂ�ƁA�ω_�Η��̒��S�͓��{���牓�����ꂽ�M�ё����m�����ɏo����B�t�Ƀ��j�[�j���ɂȂ�ƁA�ω_�Η��̒��S�����{�ɋ߂��t�B���s���t�߂ɏo����B�����ŃG���j�[�j���̎��ƃ��j�[�j���̎��ł́A���{�̉Ă̓V��͑傫���ς���Ă��܂��B�䕗�������̌��ۂƐ[���֘A���Ă���B�䕗�͔M�ѐ������m��ɂ����鐅���̉e���ڎ�B�G���j�[�j���̔N�A�M�ѐ������m��ł͐��[200 m���炢�܂ł̐��������N���Ⴍ�Ȃ�A�C����̃G�l���M�[�����A�����Ă�������ɉ^�Ԑω_�Η�����܂�A�䕗�͔������ɂ����Ȃ�B���������j�[�j���̏ꍇ�́A�M�ѐ������m��ɒg�����C�������܂�ω_�Η������������ɂȂ�̂ŁA�䕗�𑽂�����������v���ɂȂ�B
�G���j�[�j���ɔ����ω_�Η��̕��z�̕ω��́A�������m�ł̑�C�z�̕ω���ʂ��ē��{�ɂ��e����^����B�G���j�[�j�����ɂ́A���N�ɔ�ׂ�Ɠ��{�ɓ쐼��������₷����ԂɂȂ邽�߁A�~�Ȃ�g�~�A�~�J���ɂ͑O�������߂�X���������炷�B���ɔ~�J�������܂�7���̓V��̓G���j�[�j���̉e���������A�W�����J�̊m���������Ȃ�B�~�J�����̏W�����J�́A�~�J�O���Ɏ������쐼�����������ނ��Ƃ�������炳��邪�A�G���j�[�j���������������������ɓ����̂ł���B�~�̏ꍇ�͓쐼�����G�ߕ��i�����X�[���j�m��2�n����߂�����œ����̂ŁA97 � 98�N�̓~�̂悤�ɋɒ[�Ȓg�~�ɂȂ�B ���{�̒n���I�ʒu�͑嗤�Ƒ����m�ɋ��܂�A��������r�I�Ⴂ�ܓx�ɂ���A�W�F�b�g�C���m��3�n���쉺���铌�̒[�ɂ���B���̂��߁A�Ăɂ͔M�тō~��悤�ȃo�P�c���Ђ�����Ԃ����悤�ȒZ���ԍ��J���o�����邱�Ƃ����邵�A���̓V��͊C�̉e�����A�܂��嗤����̉e������B�Ⴆ��N�̉ẮA�������W�����J�Ɍ������A���ɓs�s���ɑ����̔�Q�������炵���B���̎��̑�K�͂ȏ͂���ƁA�M�ѐ������m�̊C�ʐ����̓��j�[�j���̉e���ō����X���ŁA�ω_�Η����N����₷����������Ă����B�t�B���s�������Ɋ����Ȑω_�Η����N����A���{�S�̂������ĂɂȂ�͂��ł��������A�C���h����̃����X�[���̉e�����đΗ��̒��S���k���ɂ���A����ɋ߂Â������߁A�����{����C���A�����{�͍��C���Ƃ������قȋC���z�u�ƂȂ����B��C��̑Η��悩�炽�т��іk�シ��M�ђ�C���������{�𒆐S�ɍ��J�������炵�A�t�ɓ����{�͐��V���������B�傫������A���j�[�j���̉e���Ő������m�őΗ��������������̂����A�����X�[���̉e�����Ă��̔����Ȉʒu���ς���Ă��܂����̂ł���B �G���j�[�j����j�[�j�����ۂ̉e���́A���{�̒����\��̏d�v�ȃt�@�N�^�[��1�ƂȂ��Ă��邪�A����ȊO�̗v�������X�ւ���Ă��邽�߁A�V��ϓ��̉𖾂͓���̂ł���B�W�����J�̂悤�ȍЊQ�������炷�C�ۏ�͂������������̎��������������A��ԓI�ȋK�͂��������B���������āA���̂悤�ȏ�����ǂ̂悤�ɔ������邩�����炩���ߗ\�����邱�Ƃ͓�����A�����̔����ꏊ�̌X���⋭���̓����́A�G���j�[�j������X�[���̂悤�ȁA�������ƕω�����ԃX�P�[�����傫�����ۂɁA������x�K�肳��Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B �@
�ُ�C�ۂ��l���邤���ŁA�G���j�[�j����j�[�j�����ۂƕ���ŁA���ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ɒn�����g��������B�l�Ԃ̎Y�Ɗ����ő����������C���̓�_���Y�f���A�n���ɔM������߂鉷�����ʂɂ���ċC�����グ�Ă���̂ł���B���_���猾���ƁA����A�n���̉��x�͊m���ɏ㏸����B��X�̃V�~�����[�V�����ł́A70�N��ɑS�n�����ςł��悻2�x�b�㏸����Ɨ\������Ă���B2�x�b���炢�Ȃ炻��Ȃɖ�肪�Ȃ��Ǝv���邩���m��Ȃ����A����͒n���S�̂̕��ω��x�ł���B���������ĊC��ł͂�����Ⴍ�Ȃ�A���n�ł͍����Ȃ�B���n�ł��M�ђn�����͖k�ɂ��ɂɋ߂����ܓx�n���������Ȃ�B�ꏊ�ɂ���Ă͔N����5�Ccȏ�ɒB���鏊���o�Ă���B���݂̂Ƃ���A�n�����g���\���̐��x�͂��܂�ǂ��Ȃ��̂ŁA�����@�ւɂ���ċC���̏㏸�ʂ�1 - 3.5�x�b���x�̕�������A�n��I�ȏڍׂƂȂ�Ƃ����ƕs�m��ł���B�Ƃ�����A�e��̗\���͑�܂��ȓ_�ł͈�v���Ă���B�n���̉��x���㏸����ƁA�Ɉ�̕X�̗n���o���ƊC���̖c���ɂ���āA�C�ʂ�70�N��15- 70 cm���x�㏸����B�܂��A���x���オ��Ƌ�C���̐����C�̗ʂ������Ȃ�B���������ĊC�̐����������āA���ꂪ�_�ɂȂ�A���̉_���J���~�点��Ƃ������z�������ɂȂ�B�����C�͓�_���Y�f�ȏ�̉������ʂ������߁A���g�������铭��������B���z�������ɂȂ�ƁA���Ƃ��ƍ~�J�ʂ̑����n��ł͂���ɉJ�ʂ������A�t�Ɋ����n��ł͂���Ɋ������������Ȃ�B�܂��A�ꏊ�ɂ���Ă͍~�J�ʂ������n��ł����������i�ނƂ����悤�ɁA�C�傫���ω�����B �n�����g���͓��{�ւǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ����낤���B�O�q�����悤�ɁA���{�ɂ͔~�J���ɔM�ђn�����玼������C���쐼���ɏ���Ă���ė��邪�A��X�̃V�~�����[�V�����ł́A���̎�������C�̗��ꂪ�A���g���������ɋ��܂�X��������B�������쐼���͏W�����J�̃G�l���M�[���ł��邽�߁A���̕p�x�⋭���̑����X�������O�����B ���̂Ƃ���A�ߋ����\�N�̊ϑ��f�[�^�ɂ��̌X�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���������ĊĎ�����K�v������B�����āA�ُ�C�ۂ�W�����J�̐U�镑���̕ω����܂߂��n�����g���\���̐��x���オ���҂����B
1���N�O�ɂ͑S���n��34 %���߂Ă����X�іʐς��A���݂ł�26 %���x�܂Ō������Ă���Ƃ������Z������B1960�N��ȍ~�A�T�n�������̓���ł͍��������[���ł���B�A�}�]���̐X�єj������ɂȂ��Ă���B���z�����悭�z�����A�ې��͂ɕx�X�т̔j��́A�������E�������������炷�B�X�іʐς̌����͐l�דI�ȗv���ɂ��Ƃ��낪�傫���A����ɂ���ċC�ς���Ă��܂��A���邢�͂��łɕς���Ă��܂��Ă��邱�Ƃ͋^���Ȃ����A���̒��x�ɂ��Ă͂܂��͂����肵�Ȃ������������B�ُ�C�ۂɗ^����e���͌��킸�����Ȃł���B�X�т͋C���ς����邪�A���R�C��̉e�����Ă���B���R���Ԍn�ƋC��̑��ݍ�p�̉𖾂́A�C��ω��̗����Ɨ\���ɂƂ��ďd�v�ł���B ��_���Y�f�����łȂ��A�l�Ԃ̊����͑�C���ɗl�X�ȕ������T���U�炵�Ă���B��C�����̌����ƂȂ闰�_�G�A���]���ƌĂ��u�o�v������1�ł���B���͐o���C��ɑ傫�ȉe����^���Ă��邱�Ƃ��A�ߔN�ɂ킩�ɒ��ڂ��W�߂�悤�ɂȂ����B�G�A���]���͑��z���˂��邽�߁A�n�����g����a�炰������ɓ����͂����Ƃ����̂ł���B���Q�̌������A�����ɒn�����g���̊ɘa�܂Ƃ͔���Ȃ��Ƃł���B�G�A���]���͉_�����o���鎞�̊j�ɂ��Ȃ邵�A��ނɂ���Ă͑��z���˂����z��������̂�����B�l�N���ȊO�̃G�A���]�����܂߂āA���̎��Ԃ̉𖾂��}�s�b�`�Ői��ł���B �l�Ԃ͒n����ɑ����̕�����z���Ă������A�G�l���M�[�I�ɂ����A�厩�R�̈��|�I�ȗ͂̑O�ɂ͂Ȃ��p���Ȃ��Ƃ����̂������ł���B���ɂ��ꂾ���Ȋw�Z�p�����B���Ă��A�܂��䕗�̐i�H��ς��邱�Ƃ���ł��Ȃ��B�������A���R�̒��ɐl�N���̕����𒍓����邱�ƂŁA���R�̉c�݂̃o�����X������Ă��܂��A�{���̃p���[�ł͋N�����Ȃ������悤�ȑ傫�ȋC�����̕ω���U�N�����Ă��܂����B���̈Ӗ��ŁA�l�Ԃ͂��łɑ厩�R�̋t�ɐG���͂������Ă��܂����Ƃ�����B����܂ł̂悤�ɖ����C�Ȑ��Y�����𑱂���킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ����B�����āA�}�炸���N�����Ă��܂����C��̕ω��𐳂����c�����A�Ώ����Ă����K�v���o�Ă����̂ł���B
�@ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@